
1. 歌詞の概要
「Making Plans for Nigel(メイキング・プランズ・フォー・ナイジェル)」は、イギリスのニュー・ウェイヴ/ポストパンク・バンド、XTC(エックス・ティー・シー)が1979年にリリースしたアルバム『Drums and Wires』に収録された代表曲であり、個人の自由と社会の期待との衝突を、鋭利なビートと皮肉な言葉で描いた名作である。
歌詞の主軸は、両親が“ナイジェル”という若者の人生設計を勝手に立ててしまうという設定にある。「ナイジェルは幸せなんだ、だって私たちがそう決めたからね」と語る親たちの声が、まるで管理された社会の口調のように響き渡る。そこに本人の声は存在せず、“他者によって計画された幸福”という不気味さがじわじわと浮かび上がってくる。
この曲は、1970年代末のイギリスにおける社会主義的な労働環境、工業化、そして家庭内における管理主義的価値観の象徴を、一人の無言の若者ナイジェルを通して批判的に描き出している。しかしその描写は怒りではなく、冷静なユーモアとリズムの中に潜む不協和音として提示される。
2. 歌詞のバックグラウンド
XTCは1970年代後半に頭角を現したスウィンドン出身のバンドで、ニュー・ウェイヴの実験性とポップ・センスを併せ持ったユニークな存在である。彼らの3作目となる『Drums and Wires』は、ギタリストのバリー・アンドリュースが脱退し、新たにデイヴ・グレゴリーが加入したことで、より構造的でメロディアスなサウンドへと進化した作品である。
「Making Plans for Nigel」はそのオープニング・トラックにして最も印象的な楽曲であり、ドラマーのテリー・チェンバースによるスネアとフロアタムの重厚なリズムパターンが、まるで産業機械のように反復し、“工場に組み込まれた若者の運命”を象徴するかのような構造になっている。
歌詞は主にコリン・モールディングが手がけており、彼自身が「当時、周囲に“ナイジェル”のような若者が多くいた。何も言えず、ただ他人に従って生きているような存在だった」と語っている。ナイジェルという名は、特定の人物というよりも、当時のイギリス社会が生んだ“声なき世代”の象徴なのである。
3. 歌詞の抜粋と和訳
We’re only making plans for Nigel
僕らはただ、ナイジェルの将来を計画してるだけさWe only want what’s best for him
彼にとって最善のことを願ってるんだWe’re only making plans for Nigel
僕らはただ、ナイジェルの人生設計をしているだけNigel just needs this helping hand
ナイジェルにはちょっと手助けが必要なだけなんだよAnd if young Nigel says he’s happy
もしナイジェルが「幸せだ」と言ったとしてもHe must be happy, he must be happy, he must be happy in his work
それなら彼は幸せなはずさ、幸せなんだよ、仕事の中で幸せになれるんだ
(参照元:Lyrics.com – Making Plans for Nigel)
この繰り返しと断定の口調が、不気味なまでに“善意の押しつけ”を強調しており、反抗の余地のない管理社会の静かな恐怖を描いている。
4. 歌詞の考察
「Making Plans for Nigel」が持つ最大の力は、“語られない主語=ナイジェル本人”の沈黙である。彼自身が何を思い、何を感じているのかは一切語られない。全編が「私たち」が語るナイジェルの話で構成されており、この“本人不在の幸福論”が、作品全体に不穏な緊張感をもたらしている。
「Nigel says he’s happy」という仮定に続く、「He must be happy」という反復は、疑念の打ち消しではなく、疑念そのものの存在を示唆している。つまり、「そう言ってるけど本当はどうなのか?」という問いが、聴く者の頭の中に残るよう設計されているのだ。
また、「British Steel(イギリス鉄鋼業)」に象徴される、工業社会に若者を適合させるシステムの比喩としても機能しており、ナイジェルはまさに**“ギアの一部”として消費される個人の象徴**となっている。その点でこの曲は、戦後から1970年代にかけてのイギリスにおける“階級固定”や“進路の固定化”に対する風刺でもあり、子どもを“社会的商品”として育てようとする保守的価値観への批判でもある。
しかし、この曲は決して怒鳴らない。むしろ冷笑とリズムの中で、淡々と描写することで逆説的な鋭さを生み出している。それが、XTCならではの知的ユーモアとポストパンク的批評性である。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Career Opportunities by The Clash
若者の未来が国家によって操作されることへの怒りを直截に表現したパンク・クラシック。 - Life During Wartime by Talking Heads
都市生活と管理社会の危機感を、ダンサブルなグルーヴで包んだ不穏なポップ。 - Subdivisions by Rush
成長過程で課される選択肢の狭さ、社会のルールへの適応をテーマにしたシンセ・ロック。 - Opportunities (Let’s Make Lots of Money) by Pet Shop Boys
表向きの成功主義と、その裏にある空虚さを皮肉に歌った80年代的社会風刺。 -
Boys Don’t Cry by The Cure
感情を抑圧する社会の期待に屈する若者の内面を、軽快なポップにのせて歌い上げる。
6. “幸せは、誰が決めるのか?”
「Making Plans for Nigel」は、XTCがポップソングの枠を超えて、社会と個人の関係に斬り込んだ先鋭的な作品である。それは一見キャッチーで、シンプルな構造に見えるが、その奥には**“幸福とは誰が決めるのか?”という本質的な問い**が込められている。
この楽曲が時代を超えて響き続けるのは、ナイジェルが今もどこかに存在するからだ。
受験、就職、家族の期待、社会の規範――誰かに“計画”される人生を歩まされるナイジェルたちは、現代にも確かに生きている。
だからこそ、この曲を聴くことは、自分の人生が誰の計画によって動いているのかを再確認する行為でもある。
ナイジェルは言わない。けれど、彼の沈黙は語っている。
「僕の声を、聴いてくれ」と。


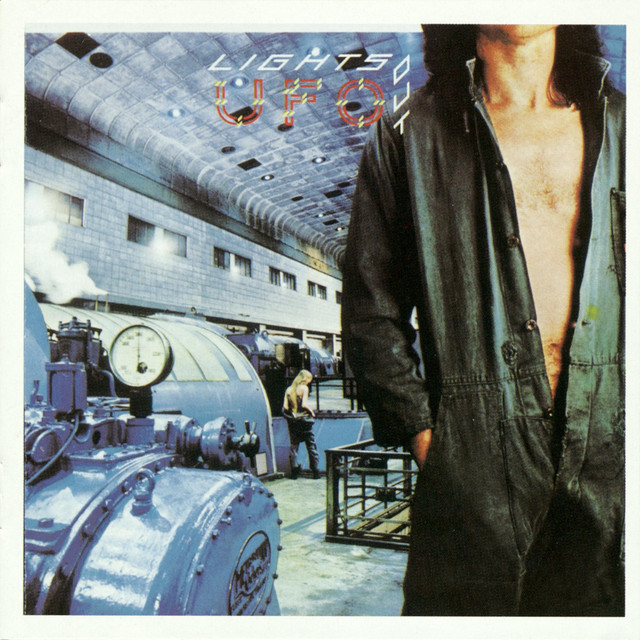
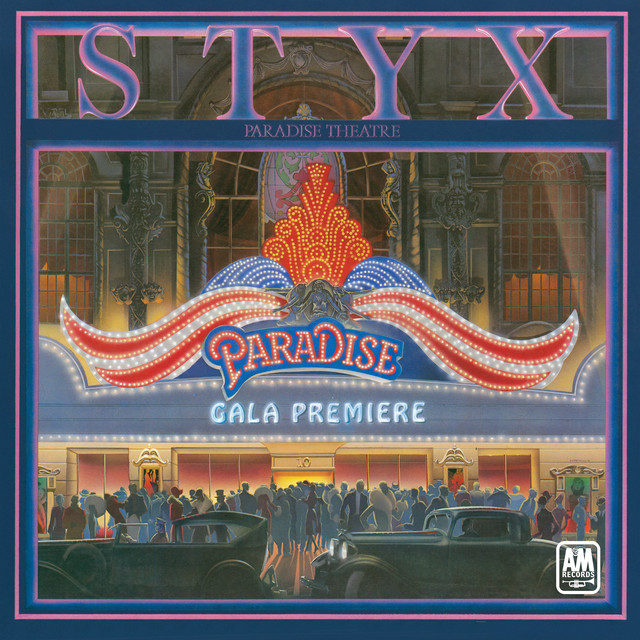
コメント