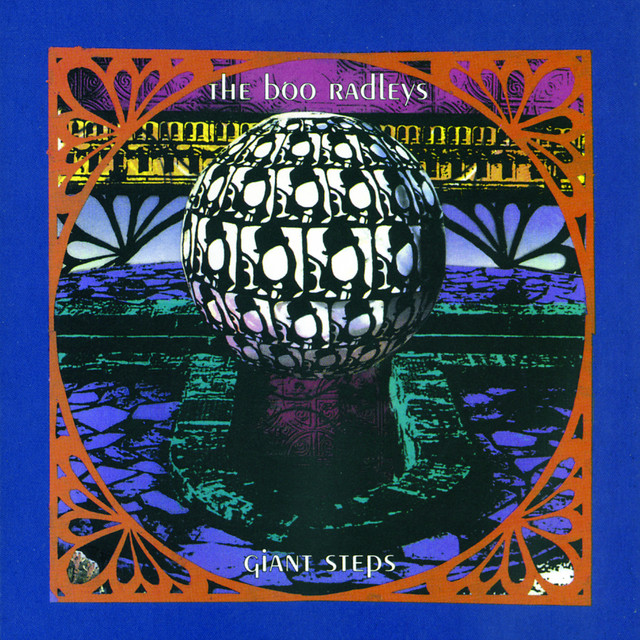
1. 歌詞の概要
「Lazarus(ラザロ)」は、The Boo Radleysが1993年にリリースしたアルバム『Giant Steps』の中核をなす楽曲であり、バンドの創造性と実験精神が最高潮に達した代表的トラックである。曲名にある「Lazarus」とは、聖書に登場する「死から蘇った男」のことであり、この曲もまた「再生」や「変容」を象徴する物語を内包している。
歌詞は、個人的な閉塞感、孤独、憂鬱といった感情を下敷きにしながら、それでも「生まれ変わる」という希望へと向かっていくプロセスを描いている。主人公は何らかの喪失や苦しみを抱え、出口のない日々を過ごしているが、音楽や他者との出会い、あるいは内的変化をきっかけに「蘇る」ような感覚に至る。これは一種の内的カタルシスであり、静かに、だが確実に“再生”へと導かれる語りとなっている。
2. 歌詞のバックグラウンド
「Lazarus」が収録された『Giant Steps』は、The Boo Radleysにとって決定的な転機となる作品であり、1990年代UKインディーシーンにおいても高く評価される一枚である。前作までのシューゲイザー的音像を大きく拡張し、ドリームポップ、レゲエ、ダブ、オーケストラル・ポップ、ジャズなど、多様な音楽要素が混在する本作において、「Lazarus」はその“最初の衝撃”として聴き手を圧倒する。
特筆すべきは、そのサウンド構造。冒頭の静謐なピアノと声のレイヤーが、突如として轟音のギターとダブビートに変貌するというダイナミズムは、まさに90年代初頭の“音の冒険”の象徴と言える。マーティン・キャリルの詞は感情の動線を繊細に描写し、サイモン・ロウのギターはシューゲイズ的な残響とグルーヴ感を共存させている。
当時、この曲はNMEやMelody Makerからも高い評価を受け、Boo Radleysが単なるシューゲイザー・バンドではなく、“ブリットポップ以前の革新者”としての地位を確立するきっかけとなった。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に、楽曲の印象的な一節を和訳とともに紹介する。
I must be losing my mind
きっと、もう自分を見失いかけているんだろうI don’t want to believe it
But it’s happening all the time
信じたくはないけれど
こんなふうに何度も繰り返されるAnd every time I look at you
I see myself again
君を見つめるたびに
もう一人の自分を見る気がするんだLazarus, I’m coming home
ラザロよ、今 俺は帰っていく
※ 歌詞の引用元:Genius – Lazarus by The Boo Radleys
このフレーズは、“喪失の自己”と“再生の自己”が同時に存在しているというパラドックスを示している。自分の中の“死”を認めながら、それでも前に進もうとする――そんな苦しくも美しい再起の物語が、この歌詞には込められている。
4. 歌詞の考察
「Lazarus」は、“再生”をテーマにしながらも、決して一気に明るさへと転じるわけではない。むしろ再生とは、内面の断片を一つひとつ拾い集め、ゆっくりと“かつての自分”と向き合う過程なのだとこの曲は語っている。
タイトルの「Lazarus」は象徴的だ。聖書に登場するラザロは、キリストによって死から蘇った男だが、その奇跡は祝福であると同時に、人間が“生き直す”ことの重みや違和感をも暗示している。The Boo Radleysの「Lazarus」もまた、“死から生への転換”ではなく、“死を受け入れたうえで生きていく”という内面的な物語である。
また、楽曲構造もその変化をなぞっている。前半の静けさは“死”や“眠り”の状態であり、中盤以降に加速するビートやギターの暴発は“蘇生”そのものである。その音の劇的な転調は、ただの演出ではなく、語られない感情の爆発――言葉にできないものを音で描く、というロックの本質を捉えている。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Sometimes by My Bloody Valentine
音響の洪水の中で、繊細な心情が浮かび上がるシューゲイズの金字塔。 - All I Need by Radiohead
欲望と喪失のあいだを彷徨う、感覚の再構築のためのバラード。 - Come to Me by Björk
再生と受容を、母性的な愛の中で描いたエレクトロ・バラード。 - Sing by Blur
光のない都市の中で、孤独と向き合う祈りのようなアンビエント・ポップ。 - Hunted by a Freak by Mogwai
言葉を超えた悲しみと癒しを同時に抱えるポストロックの瞑想。
6. 静けさと轟音のあいだで生まれた名曲:Boo Radleysという“転生”
「Lazarus」は、The Boo Radleysにとって“再発見”の物語である。それは音楽的なスタイルの変化だけでなく、“誰のために音楽を作るのか”という姿勢そのものを問い直す機会だったと言える。
彼らは、この曲によってシューゲイザーの枠を超え、より大きな視野と音楽的挑戦へと歩み始めた。そしてそれは、後の『Wake Up!』でのポップ路線にもつながっていく。だが「Lazarus」にあるのは、“再生の快活さ”ではなく、“再生の痛み”である。
生まれ変わるには、まず一度、何かが死ななければならない。そしてその喪失を真正面から受け入れたとき、初めて“自分自身の声”で歌うことができる。The Boo Radleysは、この曲でそのことを音と詩で見事に描いてみせた。
“Wake Up Boo!”が朝の眩しさを讃える歌だとすれば、「Lazarus」は夜明け前、目を閉じながら何かを乗り越えようとしている人間のための歌である。
沈黙と轟音のあいだで揺れるその姿こそ、まさに“人間らしさ”そのものなのだ。
他にも『Giant Steps』の楽曲を掘り下げてみますか?それともThe Boo Radleysの初期〜解散期までの軌跡を辿ってみますか?


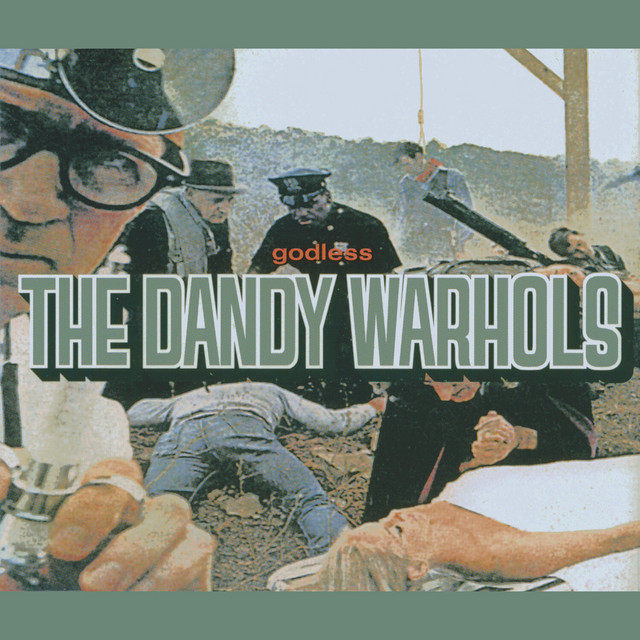
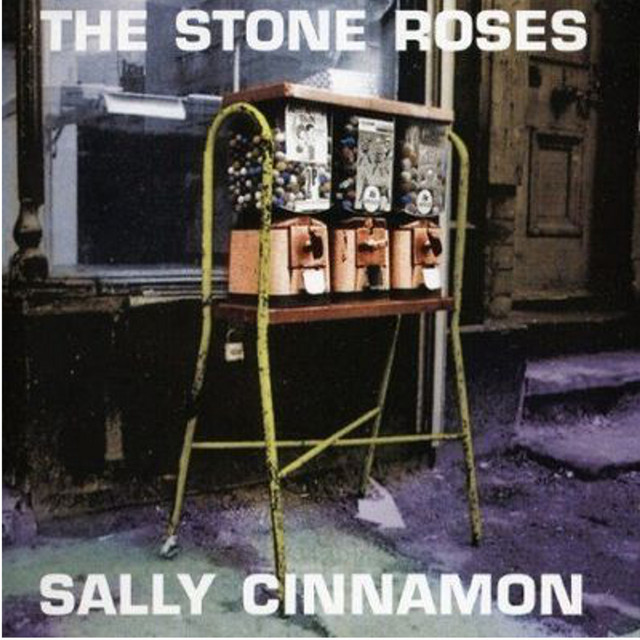
コメント