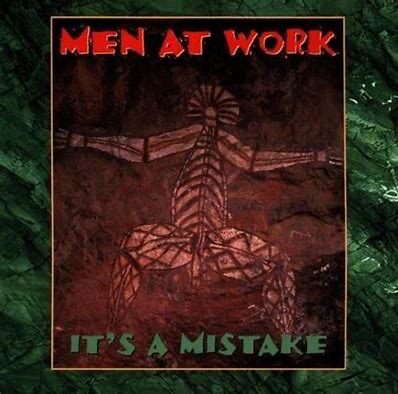
1. 歌詞の概要
Men at Workの「It’s a Mistake」は、1983年にリリースされたセカンドアルバム『Cargo』に収録された楽曲であり、核戦争の恐怖と冷戦時代の緊張感を風刺と共に描いた、極めて時代性の強い楽曲である。前作『Business as Usual』で商業的成功を収めた後、バンドはより社会的かつ政治的なメッセージを含む楽曲へと舵を切っており、「It’s a Mistake」はその代表格とも言える作品である。
この曲は、軍人の視点から描かれており、「間違いだった(It’s a mistake)」という言葉を繰り返すことで、戦争の決定がいかに一瞬の判断ミスや誤解、誤算によって引き起こされるかを皮肉的に示している。また、曲調は軽快で親しみやすいものながら、そのメロディの背後には戦争への不安と虚無が漂っており、「楽しく歌える反戦歌」という非常にユニークな構成を持っている。
2. 歌詞のバックグラウンド
1983年という年は、冷戦の緊張が特に高まっていた時期にあたる。アメリカとソビエト連邦の間での核兵器配備競争が激化し、ヨーロッパ諸国でもその影響が広がっていた。そうした国際情勢の中で生まれた「It’s a Mistake」は、単なるポップソングではなく、政治的風刺と警鐘の意味を持つ作品となっている。
Colin Hay(ボーカル兼ギター)は、当時のインタビューで「この曲は、戦争に対する人間の態度、特にそれがどれほど些細な理由で始まってしまうかに疑問を投げかけている」と語っている。歌詞では、軍上層部の決定がどれほど危ういものかを示すと同時に、一般市民の無力感や混乱も描かれており、ポップなサウンドと重厚なテーマが見事に同居している。
この曲のミュージックビデオも印象的で、兵士たちが子供のようにボードゲームで戦争を始めてしまうというブラックユーモアに満ちた演出が施されており、1980年代のMTV世代にも強い印象を残した。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に「It’s a Mistake」の印象的な歌詞を抜粋し、日本語訳と共に紹介する。引用元は Genius を参照。
Tell us commander, what do you think?
教えてくれ、司令官 あなたはどう考えてる?
We know that you love all that power
あなたが権力を愛していることは知ってるさ
Is it on then, are we on the brink?
始まるのか? 我々は崖っぷちにいるのか?
We should all prepare ourselves for war
我々は戦争に備えるべきなのか?
このパートは、軍上層部に対する皮肉に満ちた問いかけであり、命令を下す側がいかに戦争の現実から乖離しているかを示唆している。「あなたが力を愛しているのは知ってる」といったフレーズには、権力中毒や自己陶酔といった、戦争決定者の傲慢さが表現されている。
It’s a mistake
それは間違いだ
It’s a mistake
それは致命的な判断ミスだ
このコーラスの繰り返しが、曲全体のメッセージの核を成している。淡々と、しかし確信を持って「それは間違いだ」と歌うことで、リスナーに対し、冷静な再考を促している。
After the laughter has died away
笑い声が消え去った後
And all the boys have had their fun
少年たちが楽しんだ後
No surface noise now, not much to say
音もなく、語るべきこともない
We’ve got the bad guys on the run
敵は逃げ出したというけれど
このセクションでは、戦争の“終わった後”の静けさと虚無が描かれている。「勝利」はあっても、そこには歓喜も充足もない。戦争によってもたらされるのは、破壊と空虚だけだという冷ややかな現実が言外に伝わってくる。
(歌詞引用元: Genius)
4. 歌詞の考察
「It’s a Mistake」は、冷戦期の核戦争に対する切実な懸念をテーマにした楽曲でありながら、あくまでポップソングのフォーマットを維持している点において非常にユニークである。そのメロディやリズムは明るく親しみやすいが、その奥にあるメッセージは重く、しかも強い皮肉を含んでいる。
歌詞では軍上層部と一般兵士、さらには民間人の視点が交差し、それぞれが“自分ではどうにもならない状況”に巻き込まれている様子が浮かび上がる。特に「間違いだった」というフレーズが繰り返されることで、戦争が人間の過ちによって容易に引き起こされてしまうという事実への警鐘が鳴らされている。
また、戦争をゲームとして扱うような感覚、つまり「引き金を引くのが簡単すぎる世界」に対する懸念が、この曲には通奏低音として流れている。それは現代におけるドローン戦争や核ボタンの存在とも繋がっており、「It’s a Mistake」が時代を超えて響き続ける理由でもある。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Russians by Sting
冷戦期における核戦争の危機を真正面から歌ったバラード。政治的でありながらも感情に訴える力を持つ。 - 99 Luftballons by Nena
誤解による軍事的緊張と核戦争の勃発というテーマを、ポップなメロディに乗せて描いた1980年代の反戦ソング。 - Two Tribes by Frankie Goes to Hollywood
冷戦をテーマにした攻撃的なサウンドの代表作。核の抑止力に対するアイロニーを音と映像で展開。 - Silent Running by Mike + The Mechanics
近未来の戦争や管理社会を想像させる歌詞と、美しいメロディが融合した楽曲。現代の危機感にも通じる。
6. 軽快なポップの裏にある冷戦の影
「It’s a Mistake」は、表面的には明るく軽快な1980年代のポップソングに聞こえるが、その背後には当時の国際政治や人類の存続に対する深い不安が色濃く刻まれている。Men at Workは、この曲を通じて、政治や戦争のテーマをあくまで日常の延長線上で描き出し、「気づかぬうちに巻き込まれてしまう悲劇」の存在を伝えている。
Colin Hayの知的な歌詞と、バンドの親しみやすいサウンドが合わさることで、この曲は聴きやすさと深さを両立させており、今なお多くのリスナーに支持されている。MTV時代のポップアートとしても、冷戦の記録としても、そして「間違いは誰にでも起こりうる」という普遍的なメッセージとしても、非常に優れた一曲である。
「それは間違いだった」──この一言の重みを、私たちは時代を超えて受け止め続ける必要がある。


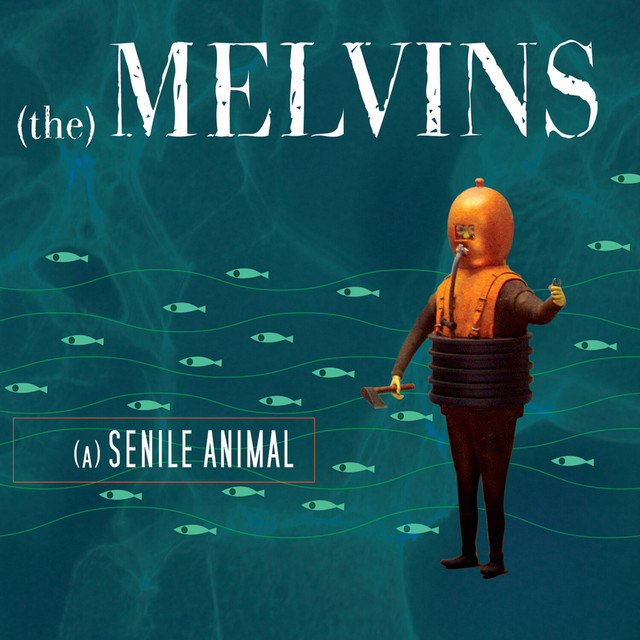
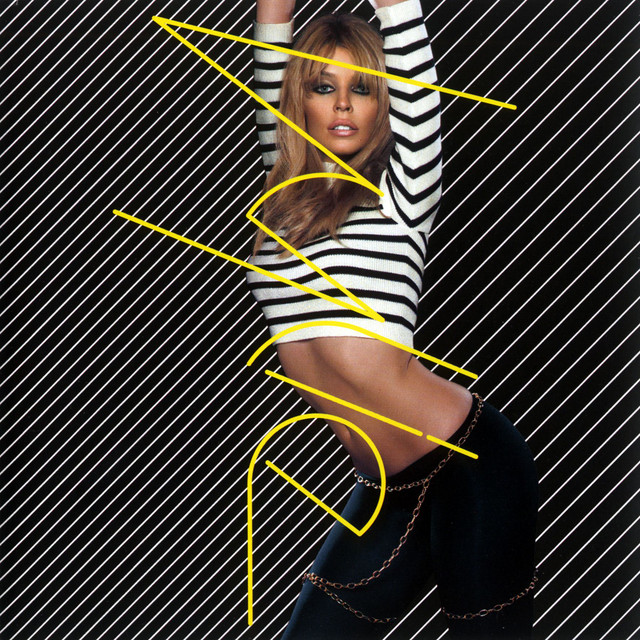
コメント