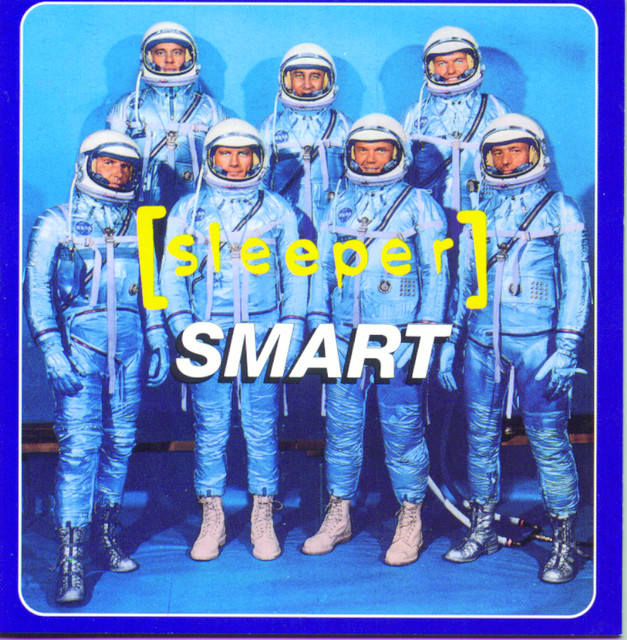
1. 歌詞の概要
「Inbetweener」は、英国のバンドSleeperが1995年にリリースしたデビュー・アルバム『Smart』に収録されている代表的な楽曲であり、彼らのキャリアを決定づけた初期のヒット曲でもある。この曲が描くのは、どこにも属せず、何者にもなりきれない人々――“inbetweeners(インビトウィーナー)”たちの姿である。
“inbetweener”とは直訳すれば「中間の存在」という意味だが、この曲では、人生の選択肢の間に取り残されてしまったような若者たちを指す。夢と現実の狭間、成功と失敗の間、都会と郊外の間、ロマンスと日常の間――そんな“決定的ではない人生”を歩んでいる人々への共感と皮肉が交差するリリックになっている。
そのテーマは、90年代中盤のUK社会、特にミドルクラスの若者たちが感じていたアイデンティティの揺らぎを鋭くとらえており、特にブリットポップの“庶民的なリアル”を反映した代表例としても知られている。
2. 歌詞のバックグラウンド
Sleeperは、ボーカル兼ギタリストのLouise Wener(ルイーズ・ウィナー)を中心に結成されたロンドンの4人組バンドで、ブリットポップ・ムーブメントの中でも数少ない女性主導のロックバンドとして強い存在感を放っていた。彼女のリリックは、ユーモアと辛辣さ、そして現代的な女性視点を併せ持っており、「Inbetweener」でもそのセンスが遺憾なく発揮されている。
曲がリリースされた当時、イギリスではBlurやOasisが人気を二分し、労働者階級と中産階級の文化がメディアを賑わせていたが、「Inbetweener」はそうした**階級対立からも取り残された“なんとなく満たされない人々”**に焦点を当てていた。
それはつまり、ブリットポップの熱狂とは少し距離を置いた場所に立つ、皮肉で、でもどこか親しみやすい視点だったのだ。
また、音楽的には、ジャングリーなギターと甘酸っぱいメロディの組み合わせが特徴的で、The SmithsやBuzzcocks、Elasticaなどからの影響も色濃く感じられる。だがそれ以上にこの曲を特別なものにしているのは、自分の居場所が見つからないという普遍的な孤独感を、明るいサウンドの中に紛れ込ませるセンスである。
3. 歌詞の抜粋と和訳
There’s a strange kind of something
微妙で、説明しづらい“何か”があるのよ
この“strange kind of something”という表現に、言葉にできない空虚さや違和感が凝縮されている。明確な問題はない、でも何かが足りない。そうした感覚に覚えのある人は多いのではないだろうか。
Lives in between what he meant and what he said
彼は「言いたかったこと」と「実際に言ったこと」の間で生きている
この一行は、まさに“Inbetweener”の真髄である。言葉と行動、理想と現実、自分と他人――それらのズレを抱えたまま生きることのリアルな苦味が、淡々としたトーンで綴られている。
He’s the inbetweener
彼は“インビトウィーナー”なの
ここでの“インビトウィーナー”は、単なるあだ名ではない。それは時代の空気に取り残された世代の名前でもあり、アイデンティティの輪郭を持たないまま、曖昧な現在に漂う人間たちの総称として響いてくる。
※歌詞引用元:Genius – Inbetweener Lyrics
4. 歌詞の考察
「Inbetweener」は、一見するとポップで軽やかなギターロックだが、歌詞を紐解いていくと、その奥には存在のあいまいさと、夢を持てない世代の悲哀が隠されている。
この曲に描かれているのは、“失敗”したわけではないが、“成功”とも呼べない人生を歩む人間たちである。進学や就職、結婚や家族、キャリアや自己実現――それらのどれにも積極的になれず、ただ“間”にいるだけの人たち。
だがルイーズ・ウィナーは、そうした人々を断罪するのではなく、愛おしさすら感じさせる目線で描いているのが印象的だ。
また、“inbetweener”という言葉の響きには、どこかノスタルジックな可笑しさと、切なさが同居している。あの頃の自分も、今の自分も、もしかしたら未来の自分も、“何者にもなれなかった人間”かもしれない。だがそれでも、生きている限り、私たちはその“間”で何かを掴もうとするのだ。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Common People by Pulp
中産階級と労働者階級のズレを皮肉と哀愁で描いた、ブリットポップの金字塔。 - Parklife by Blur
ロンドンの平凡な人々の日常をユーモアとリアリズムで描いた都市の肖像。 - Alright by Supergrass
若さと無力さ、楽しさと空虚さの間で揺れる青春賛歌。 -
If… by The Bluetones
理想と現実の狭間で“もしも”を繰り返す、いかにも90年代的な恋愛感情。 -
Statuesque by Sleeper
「Inbetweener」と同じアルバムに収録されており、似たようなテーマと美学を持つ姉妹曲的存在。
6. “何者でもない”という生き方への共感
「Inbetweener」は、ブリットポップの華やかな側面とは違う、もっとも現実的で、日常的な人々に寄り添った名曲である。
音楽が“ヒーロー”や“夢の実現”を歌い上げるとき、Sleeperはむしろ「そんなもの、最初からなかった」という視点に立っていた。
だがそれは諦めではなく、“何者にもならなかった人たちの中にある確かな物語”を見つめる誠実さなのだ。
何者にもなれなくていい。どこにも属さなくていい。
この曲は、そのことを肯定してくれる。そしてその言葉は、今の時代を生きる私たちにとっても、十分すぎるほど優しい。
彼も、彼女も、あなたも、そして私も、もしかすると“inbetweeners”なのかもしれない。
それでも、この不確かな世界で今日を生きることに、意味はきっとあるのだ。


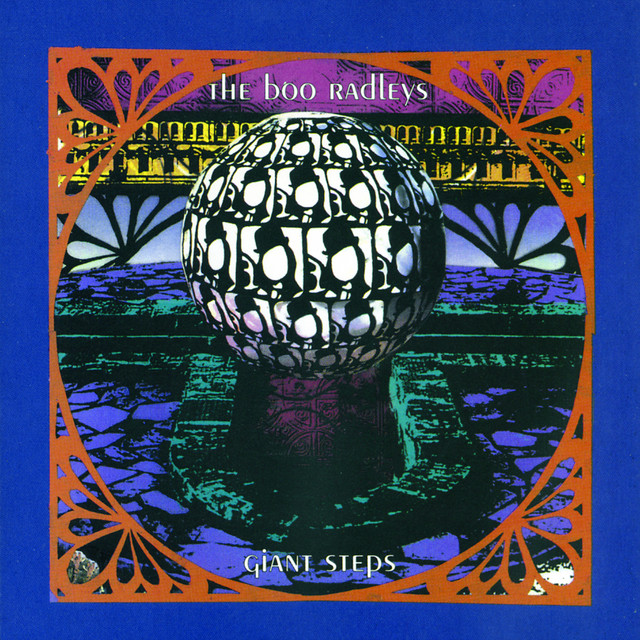

コメント