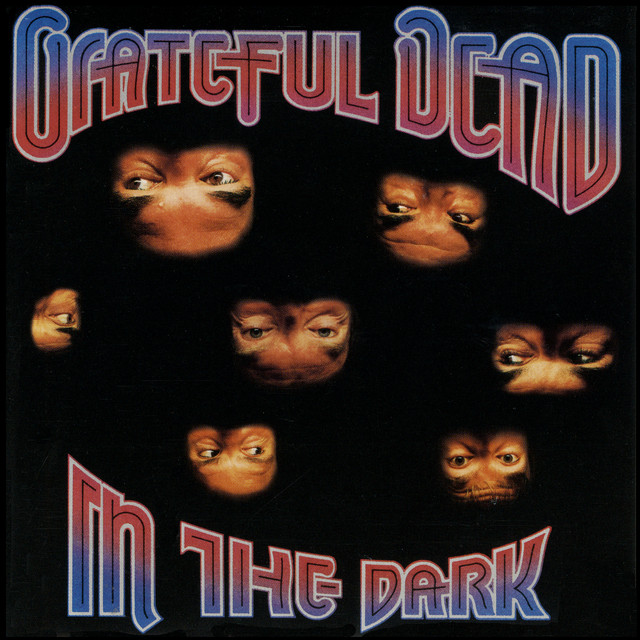
発売日: 1987年7月6日
ジャンル: ロック、アダルト・コンテンポラリー、アメリカーナ
闇のなかで見つけた光——“後期デッド”最大の奇跡と、その静かな到達点
『In the Dark』は、Grateful Deadが1987年に発表した12作目のスタジオ・アルバムであり、
実に7年ぶりの新作としてリリースされた“復活作”にして最大のヒット作である。
1980年代のデッドは、ガルシアの健康問題やドラッグ依存、創作的停滞などの課題を抱えていた。
だがこのアルバムで、彼らはキャリア初のTop10ヒット「Touch of Grey」を放ち、
MTV世代のリスナーにも存在を印象づけることに成功した。
この成功は、ただの“再浮上”ではなく、音楽的にも精神的にも自らを更新した証拠であった。
アルバムのほとんどはライヴ録音スタイルのセッションをスタジオで再現するという手法で録音され、
結果として従来の“ライヴ感”と“スタジオ作品の洗練”が高次元で融合することとなった。
全曲レビュー
1. Touch of Grey
ガルシアのキャリア最大のヒット曲にして、希望とユーモアが混ざり合うデッド流ポップソング。
「I will get by / I will survive(なんとかやっていくさ、生き延びるよ)」というサビは、
80年代の混沌を生きる者すべてに向けた励ましでもある。
ガルシアのヴォーカルには疲れと共に、深い包容力が宿っている。
2. Hell in a Bucket
ボブ・ウィアによる、よりロック色の強いナンバー。
“たとえ地獄に堕ちても、お前と一緒ならかまわない”という開き直ったラヴソング。
デッドにしては珍しいほどの“悪ぶり”が爽快。
3. When Push Comes to Shove
ブレント・マイドランドの鍵盤と、ガルシアの軽快なギターが絡むスウィング気味のミディアムチューン。
曖昧な関係性と妥協を描く歌詞は、日常に潜む哲学を掬い取るような味わい。
4. West L.A. Fadeaway
ファンキーでスモーキーな雰囲気の楽曲。
L.A.の裏路地に生きる者たちへのまなざしが感じられる。
アンダーグラウンドなブルース観と、洗練されたグルーヴが心地よく交錯する。
5. Tons of Steel
マイドランドによる、80年代ロック然としたサウンドとメロディ。
列車事故をメタファーにした歌詞が、愛と破壊の危うさを浮かび上がらせる。
6. Throwing Stones
政治的かつ寓話的なメッセージを込めたナンバー。
“子どもたちは石を投げて遊ぶ/それは戦争のはじまりになる”という反復句が、
現代社会の無自覚な暴力を静かに指摘する。ライヴでは長尺ジャムとして展開。
7. Black Muddy River
アルバムのクロージングにふさわしい、内省的なバラード。
“黒く濁った川を渡る”というイメージは、人生の終わりと浄化の両方を示唆する。
亡くなる直前のガルシアが最後に歌った曲とも言われ、今なお特別な意味を持つ一曲。
総評
『In the Dark』は、Grateful Deadが長い“闇”の時期を経て、ようやく辿り着いた一筋の光のような作品である。
ここで彼らは、過剰なサイケやジャムを封印し、短く凝縮された“歌”としての完成度を追求している。
だがその中にも、彼ららしい即興性、社会へのまなざし、そして何よりユーモアと生への信頼が息づいている。
80年代のデッドは、若い世代から“古いバンド”と見なされていた。
だが『In the Dark』によって、彼らは新しいファン層を獲得し、
その後のフェスカルチャーやジャム・バンドの礎を築くことになる。
そして、このアルバムの真価は、“諦めない”という優しさにある。
グレイトフル・デッドは、生き残った。
闇のなかで音を鳴らし続けた彼らは、その音によって自らを、そして多くの人々を照らしたのだ。
おすすめアルバム
-
『Reflections』 by Jerry Garcia
内省的で穏やかな世界観。『In the Dark』の静けさと重なる部分が多い。 -
『So』 by Peter Gabriel
80年代のポップと深遠なリリックが共存する名作。成熟と実験のバランスが秀逸。 -
『Graceland』 by Paul Simon
時代に寄り添いながらも、自らのスタイルを更新した代表例。 -
『Workingman’s Dead』 by Grateful Dead
リズムより言葉を重視した“歌”の原点。『In the Dark』の系譜をたどるなら必聴。 -
『Time Out of Mind』 by Bob Dylan
老い、死、闇を静かに見つめる音楽として、晩年の境地を共有。


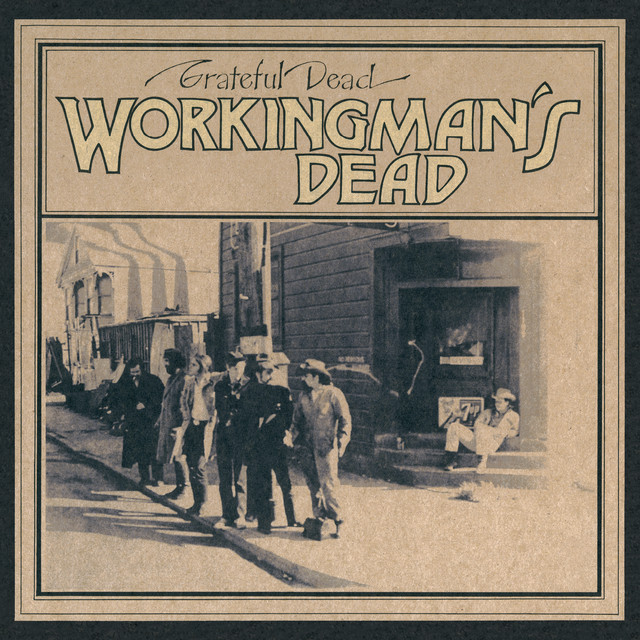
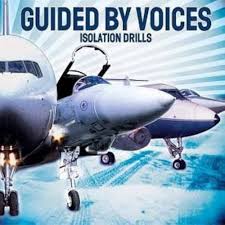
コメント