
発売日: 2010年6月
ジャンル: エレクトロニカ、サイケデリック・ダンス、アンビエント・テクノ
『Further』は、The Chemical Brothersが2010年にリリースした7作目のスタジオ・アルバムであり、彼らのキャリアにおける“もうひとつの転換点”と呼べる作品である。
1990年代の彼らはビッグ・ビートの象徴として、荒削りで爆発的なエネルギーを放ち、2000年代にはポップやロックのゲスト・ボーカルを積極的に迎え入れることで、フェス文化の頂点に立つダンス・デュオとなった。
しかし『Further』でThe Chemical Brothersは、その外向きの華やかさをあえて脱ぎ捨て、サウンドの純度そのものを追求する方向に舵を切った。
この作品ではゲスト・ヴォーカルや有名コラボレーションはほとんど存在せず、代わりに“音そのものが語るアルバム”として、彼らのルーツであるアナログ・シンセ、ブレイクビーツ、そしてトリップ感のあるサイケデリックな音像が中心に据えられているのだ。
制作は、彼らの拠点スタジオであるロンドンの「Rowlands Audio Research」で行われた。
バンドは、かつてのようなシングル志向ではなく、“一枚で一つの映像的体験を作り出す”というコンセプトを採用した。
実際に『Further』は、全編にわたり映像クリエイティブ・チーム「Flat Nose George」と連動しており、各曲には専用のビジュアル作品が制作されている。
そのため、このアルバムは“聴く映画”のような性格を持っており、クラブ・トラックとしてだけでなく、ヘッドフォンでのリスニングにも耐える深度を持っている。
つまり『Further』とは、ケミカル・ブラザーズが自らの“ダンス・ミュージックの文法”を一度解体し、純粋なサウンド体験として再構築した作品なのである。
全曲レビュー
1曲目:Snow
アルバムの幕開けを飾るのは、ミニマルでアンビエントな一曲。
女性ヴォーカルの断片的なサンプリングが浮かび上がり、ゆっくりとシンセ・ドローンが広がっていく。
まるで雪が静かに積もっていくような音の構成で、ここで彼らはすでに“クラブの外側”に立っていることを宣言している。
90年代の暴力的なビートとは真逆の、静けさの中に潜む緊張感が印象的である。
2曲目:Escape Velocity
10分を超える長尺トラック。
イントロのアシッド・シンセがゆっくりと増幅し、次第にリズムが立ち上がっていく構成は、クラブのフロアよりも“意識の中の旅”に近い。
“Escape Velocity(脱出速度)”というタイトルどおり、重力を振り切るようにビートが上昇していく展開は圧巻。
2000年代に積み重ねてきたポップ要素をすべて削ぎ落とし、ダンス・ミュージックのトランス的側面を極限まで引き出した楽曲である。
フェスの巨大スピーカーで体感すれば、もはやロック・バンドのライブと同等のスケールを感じるだろう。
3曲目:Another World
アルバムのハイライトの一つ。
繊細なシンセの揺らめきと、無機質なリズムの上に、幽玄なヴォーカルが漂う。
“Another world, another time”という反復的なフレーズが、まるで夢の中のエコーのように響き、聴く者を没入させる。
ここでは、The Chemical Brothersのサイケデリック志向が極まっており、90年代的な“肉体で踊るビート”から、“意識で浮遊するビート”へと完全にシフトしているのがわかる。
4曲目:Dissolve
トライバルなパーカッションとアシッド・シンセが絡み合う、リチュアル(儀式)的なトラック。
ビートの反復の中にメロディが現れては消え、やがて音が溶けるように広がっていく。
“Dissolve(溶ける)”というタイトルが示すように、曲全体が徐々に形を失い、次第に抽象的になっていく過程そのものが聴かせどころになっている。
ケミカルが“音響芸術”としてのダンス・ミュージックをここまでやったのは、本作が初めてかもしれない。
5曲目:Horse Power
一転して、タイトルどおりのパワフルなトラック。
馬のいななきや疾走音をサンプリングしたようなリズム構成で、重低音のキックがドライヴ感を生み出す。
アルバムの中で最も“肉体的”な瞬間であり、サイケデリックな浮遊感に支配されていた中盤に、明確なスパークを与えている。
ライブでも定番となり、レーザー演出とともに盛り上がるポイントだ。
6曲目:Swoon
本作の象徴的楽曲にして、最もポップなトラック。
繊細なシンセ・リフの反復が、まるで波紋のように広がり、そこに“Just remember to fall in love, there’s nothing else”という囁きが乗る。
静かな多幸感と恍惚を同時に表現しており、アルバム全体の緊張を解く役割も担っている。
後年のライブではアンセム化し、映像と照明が一体化する瞬間に観客が一斉に浮かび上がるような演出が話題を呼んだ。
7曲目:K+D+B
ドラムンベース的なスピード感を持つ曲で、タイトルは「Kick + Drum + Bass」の略。
直訳すれば“ビートの基本三要素”であり、アルバムの中でもっとも直接的なリズム・トラックである。
反復的な構成ながら、音の出入りが非常に繊細で、緊張と解放のバランスが巧み。
フロア仕様のケミカル・ブラザーズが今も生きていることを感じさせる1曲だ。
8曲目:Wonders of the Deep
ラストを飾る美しいアンビエント・トラック。
“深海の奇跡”というタイトルのとおり、低音の波と光の粒のようなシンセが交差し、ゆっくりと意識を沈めていく。
アルバムのサウンド・トリップを締めくくるにふさわしい楽曲で、ここに来てようやくリスナーは“Further(さらに遠くへ)”の意味を実感する。
この終わり方は、90年代的な“爆発”ではなく、2010年代的な“瞑想”である。
総評
『Further』は、The Chemical Brothersが“ポップでフェス映えするバンド”という枠を超えて、改めて“電子音楽家”としての根源的な部分に立ち返った作品である。
『Push the Button』(2005)や『We Are the Night』(2007)での多彩なゲスト構成を経て、彼らはここで“誰かとではなく、自分たちだけでどこまで行けるか”を試している。
その結果として生まれたのは、ビッグ・ビートやエレクトロ・ロックの要素をほとんど排した、純度の高いサイケデリック・ダンス・アルバムだった。
つまりこの作品は、彼らのキャリアの中でもっとも“静かな挑戦”なのである。
アルバムを通して聴くと、まるで一夜のクラブ体験のような構成になっている。
“Snow”で静かに意識が開かれ、“Escape Velocity”でフロアの深層に突入、“Swoon”で歓喜し、“Wonders of the Deep”で夢から覚める――この曲順は、まさにケミカル版『The Dark Side of the Moon』と言っていい。
それほどまでに、構成とサウンド・デザインが緻密に計算されている。
また、アルバム全編が“ビジュアル・アルバム”として設計されており、公式映像と同時再生することで、音と光が一体化するトランス体験を得られる。
2010年代以降のライブ・セットが極めて映像的だったのは、この作品のコンセプトが基盤になっているからだ。
音響面では、彼らが原点回帰したと同時に、デジタル録音技術を極限まで使いこなしている。
アナログ・シンセやサンプラーの温度感と、デジタル・エフェクトの精度が共存しており、単に“昔の音に戻った”のではなく、“今の耳で昔の感覚を再構築した”サウンドになっている。
これは、同時期のUnderworld『Barking』やOrbital再結成期の作品と比べても際立つバランスのよさだ。
一方で、リスナーにわかりやすい“ヒット・ソング”は存在せず、そのことが本作をやや地味に見せる。
だが、数年経って聴き直すと、“Swoon”や“Escape Velocity”が彼らのライブ定番として長く愛されている理由がはっきりする。
それは、このアルバムが一過性の流行ではなく、“体験として残る音”を目指していたからである。
この時期、世界のエレクトロニック・ミュージックはEDM化の波に向かいつつあり、フェスでは派手なドロップと派手な照明が支配的になっていく。
しかしThe Chemical Brothersは、その流れに乗るのではなく、“トランスするための深さ”を選んだ。
つまり『Further』は、2010年代の大衆化するダンス・ミュージックへの静かな抵抗でもあった。
その姿勢は、のちの『Born in the Echoes』(2015)や『No Geography』(2019)にまで引き継がれ、彼らの作品を“踊れる芸術”へと押し上げる礎になっている。
おすすめアルバム(5枚)
- We Are the Night / The Chemical Brothers (2007)
『Further』直前作。ポップと実験のバランスが取れたアルバムで、前後の文脈をつなぐ鍵。 - Dig Your Own Hole / The Chemical Brothers (1997)
ビッグ・ビート期の原点。『Further』のサイケ志向を感じるなら、ここでルーツを確認してほしい。 - The Campfire Headphase / Boards of Canada (2005)
アンビエントとリズムの融合という点で精神的に近い。内向的電子音楽の金字塔。 - Tomorrow’s Harvest / Boards of Canada (2013)
『Further』の“静的トリップ感”をより深く味わいたいならこちらも必聴。 - No Geography / The Chemical Brothers (2019)
『Further』で確立した“音の旅”をさらに拡張した後期代表作。ケミカルの進化形を体験できる。
6. 制作の裏側
『Further』のレコーディングは、ライブを意識したワンテイク感を大切に行われた。
Tom Rowlands と Ed Simons は、コンピュータ上での切り貼りよりも、アナログ・シンセのノブ操作やフェーダーの動きを“演奏”として録音する手法を採用。
このため音のうねり方やフィルターの変化が有機的で、まるで生演奏のようなダイナミクスがある。
また、アートワークや映像制作も同時進行で進められ、“音と映像の関係性”を実験する場として機能していた。
ここから、のちのフェス用巨大スクリーン演出や360°映像ライブへの流れが生まれている。
7. 歌詞の深読みと文化的背景
本作のヴォーカルはほとんどが断片的で、明確なストーリーを語らない。
しかしその断片――“Just remember to fall in love, there’s nothing else”や“Another world, another time”といったフレーズ――は、2000年代後半の閉塞した社会の中で、あえて“内面の解放”を促すメッセージとして機能している。
リーマン・ショック後の不安と、SNS時代の加速の中で、“静かに意識を遠くへ飛ばす”というテーマは、ある意味で瞑想的な抵抗だったのだ。
『Further』は、クラブの快楽を越えて、“都市の中でどう意識を拡張するか”という問いへの答えになっている。
8. ファンや評論家の反応
リリース当時、批評家からは「ケミカルが原点に帰った」「サウンドの深さが再び増した」と高い評価を受けた。
特に『Q Magazine』や『Mojo』では、“彼らの最も統一された作品”と評され、ファンの間でも“聴き込むほどに良くなるアルバム”として長く愛されている。
商業的には前作ほどのセールスには至らなかったが、ライブでの“Escape Velocity”と“Swoon”の評価が高く、ケミカルのステージ演出の進化を決定づけた作品となった。
9. 後続作品とのつながり
『Further』の“音と映像の融合”というコンセプトは、次作『Born in the Echoes』や『No Geography』に直結する。
彼らはこの作品で得た没入感をさらに拡張し、2010年代後半には“音楽と映像の完全同期ライブ”という新しい領域を切り開いていく。
したがって『Further』は、ケミカル後期の創造的方向性を定義した、最も重要な基盤の一枚なのである。
10. ビジュアルとアートワーク
アルバムのアートワークは、淡いブルーと光の粒を基調とした抽象的デザインで、タイトルの“さらに遠くへ”というテーマを視覚的に示している。
ミュージック・ビデオ群も、浮遊感のある自然・宇宙・水のモチーフで統一され、音と完全に呼応している。
ケミカル・ブラザーズがここで確立した“映像と音の共鳴”の美学は、彼らを単なるDJ/トラックメイカーではなく、21世紀の“視覚的作曲家”へと押し上げたのだ。


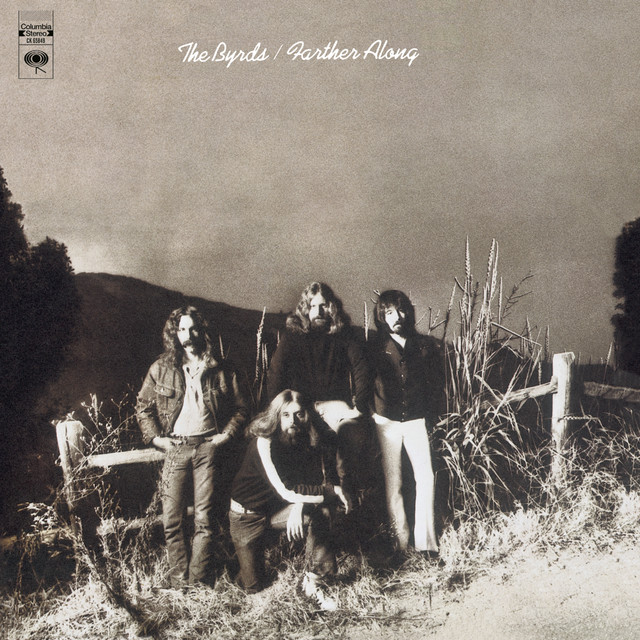

コメント