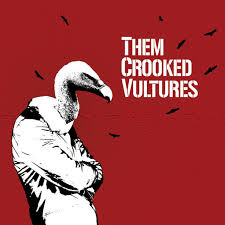
1. 歌詞の概要
『Elephants』は、2009年にリリースされたThem Crooked Vulturesの唯一のスタジオアルバム『Them Crooked Vultures』に収録された楽曲であり、アルバムの中でも最も攻撃的かつダイナミックな構成を持つ一曲である。タイトルの「Elephants(象)」は、その巨大さと重量感を音楽的な比喩として用いており、重厚で押し寄せるようなサウンドの質感を象徴している。
この楽曲は、支配欲、欲望、野性的な衝動といった本能的なテーマを扱っており、歌詞の中にはセクシュアリティや支配関係を想起させる挑発的な言葉が散りばめられている。楽曲の語り手は支配的で、誇示的で、攻撃的なキャラクターとして描かれ、リスナーに対して精神的にも肉体的にも圧倒的な“存在感”を示してくる。
また、『Elephants』は歌詞以上に音の構造に重点が置かれており、複雑で変則的なリズム展開、異様に引き延ばされたブリッジ、そして突如として巻き起こる爆発的な展開が、聴く者を圧倒する。まさにその構成自体が「象」のような大きさ、重さ、そして荒々しさを体現している。
2. 歌詞のバックグラウンド
Them Crooked Vulturesは、Queens of the Stone Ageのジョシュ・オム、Led Zeppelinのジョン・ポール・ジョーンズ、Nirvana/Foo Fightersのデイヴ・グロールという、ロック界の頂点に立つミュージシャン3人によって結成されたスーパーグループである。彼らが集まったことで可能になった音楽的な「暴走」は、既存のロックの枠を超えた新しい表現へと向かっていった。
『Elephants』は、3人の個性が最もぶつかり合い、そして融合した結果として誕生した楽曲であり、スタジオでの即興性が色濃く反映されている。ジョシュの扇情的なヴォーカルとサイケデリックなギターリフ、ジョン・ポール・ジョーンズの重量感のあるベースライン、グロールの肉体的かつアグレッシブなドラムが、絶妙に噛み合う瞬間が次々に訪れる。
歌詞のテーマは、QOTSAでもたびたび描かれてきた性的支配と自己誇張の世界観を引き継いでおり、あえて不快感を覚えるほどのマチズモを前面に出すことで、ロックの原始的な力を再定義しようとする姿勢が見える。
3. 歌詞の抜粋と和訳
Tell me, who’s that writing?
誰が書いてるんだ?
John the Revelator
啓示のヨハネさ
この冒頭のラインは、アメリカのゴスペルソング「John the Revelator」への明確な引用であり、黙示録的な不穏さを前提に物語がスタートする。この「ヨハネ」の登場は、楽曲が単なるセクシュアルな歌でなく、世界の終わりを告げる預言者のような響きを帯びることを意味している。
My generation’s for sale
俺たちの世代は売り物だBeats a steady job
安定した仕事よりはマシさHow much have you got?
お前はどれくらい持ってるんだ?
ここでは、商業主義に飲み込まれた世代の虚無感と、それでもなお享楽を優先するニヒリズムが描かれている。「俺たちの世代は売り物だ」という一節は、音楽産業や政治、社会そのものへの強烈な風刺として響く。
Let it slide
流してしまえYou gotta let it slide
お前は流すしかないDo you wanna ride my soul now?
俺の魂に乗ってみるか?
ここでは、“流されること”がひとつの逃避であると同時に、快楽への飛び込みでもある。魂を乗り物のように扱う比喩は、自己を商品化し、与え、消費させる主体のゆがんだロジックを象徴している。
引用元:Genius – Them Crooked Vultures “Elephants” Lyrics
4. 歌詞の考察
『Elephants』は、単に性的挑発や暴力的マチズモを描いているわけではない。その背後には、「ロックの原始的衝動」と「現代社会の消費主義」の対比が強く打ち出されている。ジョシュ・オムの歌詞は常にアイロニカルであり、ここでも「大きな存在(=象)」として自分を誇示しながら、それがどこか滑稽で、空虚であることを自覚しているように見える。
「魂を乗り物にする」という発想や、「売り物の世代」という表現は、欲望と自己認識が歪んだ社会において、人間がいかにして“商品”に成り下がるのかを暴いている。また、引用された『John the Revelator』によって、この快楽主義的世界が終末的であることもほのめかされ、楽曲全体に黙示録的な影が落とされている。
曲中ではリフのテンポが大きく変化し、ブリッジ部分で一度落ち着いたかと思えば再び爆発する。これはまさに“象が暴れる”ような、制御不能なエネルギーのメタファーであり、理性と衝動、知性と野性のせめぎ合いが音楽そのもので表現されている。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- A Song for the Deaf by Queens of the Stone Age
暴力性とサイケデリックな展開が『Elephants』と共鳴する一曲。無音からの爆発が聴く者を圧倒する。 - Achilles Last Stand by Led Zeppelin
ジョン・ポール・ジョーンズのダイナミズムと長尺構成が炸裂するプログレ寄りの名曲。『Elephants』の構造的複雑さと共通する。 - White Limo by Foo Fighters
デイヴ・グロールによる高速スラッジ系ナンバー。怒りの塊のようなパワーは『Elephants』の衝動とよく似ている。 - Welcome to the Machine by Pink Floyd
社会構造の中で消費される個人をテーマにした、コンセプチュアルなロック。歌詞の思想的な側面が共鳴する。
6. 解体と誇張による“ロックの再構築”
『Elephants』は、Them Crooked Vulturesの音楽的実験の中でも最も過剰で、最も暴力的な形式を取った楽曲である。しかしその過剰さは、単なる騒音ではない。ジョシュ・オムが描くマチズモや快楽主義は、同時にそれをアイロニカルに解体するメタ構造を持っている。つまりこの曲は、ロックが持つ古典的な“男らしさ”や“支配欲”を一度極端に誇張し、それによってその滑稽さや虚しさを露呈させるという構成なのだ。
そのため、『Elephants』はロックの暴走と自己批評が同時に鳴っている奇跡的な一曲であり、今なお破壊力を保ち続ける“知性と衝動の塊”である。
歌詞引用元:Genius – Them Crooked Vultures “Elephants” Lyrics


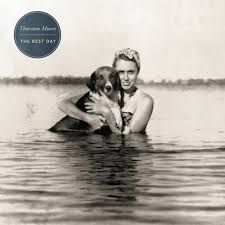

コメント