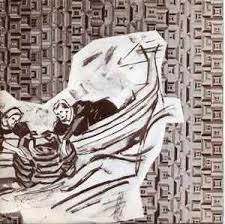
1. 歌詞の概要
「A Gigantic Raft (In the Philippines)」は、It’s Immaterialのデビュー・アルバム『Life’s Hard and Then You Die』(1986年)に収録された楽曲であり、彼らの叙情性とアイロニカルな視点が最も濃密に結実した一曲である。タイトルに冠された「フィリピンにある巨大な筏(いかだ)」というフレーズが示す通り、本作は極めてシュールで寓話的な物語性を持ちつつ、同時に社会的・政治的な暗喩を帯びている。
物語は遠く東南アジアのフィリピンを舞台に、「世界最大のいかだをつくろう」とする試みに関する報道的な描写から始まる。しかし、その背後には植民地主義的視点、欧米社会の消費主義、情報の断片化、そして“誰のための救済か”という普遍的な問いが潜んでいる。歌詞はニュースリポーターのような冷静さを装いつつ、語り手の距離の取り方が逆説的に事態の異様さを際立たせる構成となっている。
この曲は、耳に優しいアレンジと穏やかなボーカルに包まれながら、実は非常に鋭利な批評精神と“寓話”のような象徴性を内包しており、It’s Immaterialというバンドの真骨頂を体現する一曲なのである。
2. 歌詞のバックグラウンド
1980年代のイギリスにおけるニュー・ウェイヴ後期の潮流の中で、It’s Immaterialは一風変わった存在であった。John CampbellとJarvis Whiteheadを中心にしたこのデュオは、単にポップソングを作るのではなく、物語や風景、皮肉や矛盾を織り交ぜて“語る”ことに重きを置いていた。
「A Gigantic Raft」はその最たる例である。フィリピンという遠く離れた地が舞台となっているが、描かれているのは実際の地域性というよりも、“他者の問題を遠巻きに見る西洋人の視点”そのものだ。この曲が風刺しているのは、発展途上国の苦境に対する表層的な“援助”の態度や、メディアが作り出す「善意の劇場」のような構図であり、その語り口には明らかに英国的なアイロニーとシニシズムが込められている。
当時、チャリティブーム(Band AidやLive Aidなど)がイギリスの音楽シーンを席巻しており、それに対する一種の批判とも読める。また、冷戦終盤の地政学的不安や情報の分断された伝達構造も、この楽曲の底流にある重要なテーマであった。
3. 歌詞の抜粋と和訳
(引用元:Genius Lyrics)
A gigantic raft is being built in the Philippines
フィリピンでは、巨大ないかだが建設されている
From an old Japanese freighter sunk in the bay
それは湾に沈んだ古い日本の貨物船から作られている
The people say it’ll carry them away from poverty
人々はそれに乗って貧困から逃れられると言っている
But the tide is wrong, and the wind is not in their favour
だが潮は逆向きで、風も彼らに味方してはいない
この一節には、希望と絶望の二重構造が見事に現れている。貧困からの脱出を夢見る人々の希望、それを象徴する“いかだ”、しかし現実はそれを支えない自然条件——それはまるで、希望を与えるふりをしながら実際には無力な社会制度や国際援助のメタファーのようでもある。
4. 歌詞の考察
「A Gigantic Raft」は、寓話的な語り口を用いながら、極めて現実的な問題——すなわち“救済”と“支配”、“善意”と“無力さ”の交錯を描いている。いかだというイメージは救命装置であると同時に、流されることへの比喩でもあり、それにすがる人々はどこにも辿り着けないかもしれない。
語り手の視点は一貫して“外側”にあり、当事者に寄り添うことはない。この冷たさ、あるいは距離感が逆にリアリティを生む。まるでニュース番組のレポーターのように無感情に伝えられる言葉たちが、聴き手の側に「この状況はおかしいのではないか」という問いを促してくる。It’s Immaterialのこうした“語らないことで語る”手法は、曲全体に強烈な余韻を残していく。
また、「いかだが沈んだ貨物船から作られている」というモチーフには、過去の戦争、アジアと西洋の歴史的断絶、記憶の断片が象徴的に重ねられている。物理的な構造物に見えて、実は記憶の墓標でもあり、それに乗ってどこへ向かうのかも定かではない。その曖昧さこそが、この曲の最も深い部分を構成している。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Shipbuilding by Elvis Costello
戦争と労働、希望と皮肉が織り交ぜられた、英国的叙情の傑作。 - Ghosts by Japan
現実の空虚さと過去の亡霊を繊細に描く、静謐なポストポップ。 - The Boy in the Bubble by Paul Simon
テクノロジーと世界の不均衡を皮肉的に歌ったグローバル視点の楽曲。 - Joan of Arc by Orchestral Manoeuvres in the Dark
歴史的な寓意と現代性を重ねた、ニュー・ウェイヴの名作。 - The Word Girl by Scritti Politti
ポップなサウンドの裏に、言語と表象を巡る鋭い批評性を隠し持つ名曲。
6. “いかだ”が語る、希望と無力のあいだで
「A Gigantic Raft (In the Philippines)」は、その美しく静かなメロディの背後に、社会と個人、歴史と記憶、救済と無力という、極めて重たいテーマを孕んでいる。It’s Immaterialは、この曲で直接的な政治性を排しながらも、その語りの中に深い憂いと批評を込めている。
“巨大ないかだ”とは、もしかすると世界そのもののメタファーなのかもしれない。どこかへ向かおうとしているが、潮流も風もままならず、構造的には沈みかけている——それでも、人々はそこに希望を託さざるを得ない。
本楽曲は、そうした人間の在り方、世界に対する複雑な感情、そして“語りの力”がいかにして現実を照らし出すかを、静かに、しかし強烈に訴えかけてくるのである。これは単なる一曲以上の意味を持つ、ポップ・ミュージックによる現代寓話なのだ。


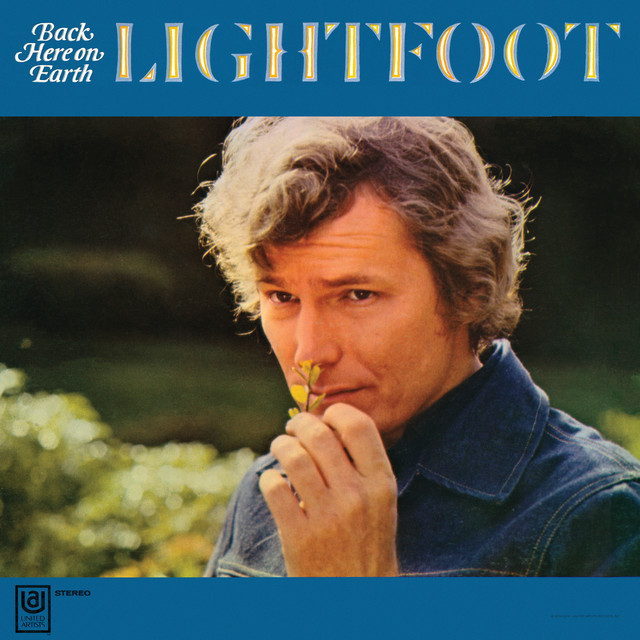

コメント