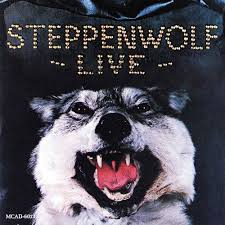
発売日: 1970年4月
ジャンル: サイケデリック・ロック、ブルース・ロック、ハード・ロック
2. 概要
『Steppenwolf Live』は、カナダ/アメリカのロック・バンド Steppenwolf が1970年4月に発表したライブ・アルバムである。
1969年の政治的コンセプト作『Monster』を引っさげたツアーの一環として、1970年1月22日にカリフォルニア州サンタモニカ・シヴィック・オーディトリアムで行われた公演が主な録音源となっており、まさに“Monster期 Steppenwolf”のステージを丸ごとパッケージした作品なのだ。
ステージ上に立っているのは、John Kay(Vo/G)、Larry Byrom(G)、Nick St. Nicholas(B)、Goldy McJohn(Org/Pf)、Jerry Edmonton(Ds)という、60年代末〜70年初頭の“黄金期ラインナップ”である。
プロデュースは引き続き Gabriel Mekler。
『Monster』の重厚な社会批評ロックを、どれだけ生々しくライブで再現できるか――という命題が、このアルバムの背後にはある。
興味深いのは、この作品が“完全なライブ盤”ではないという点である。
「Hey Lawdy Mama」「Corina, Corina」「Twisted」の3曲はスタジオ録音であり、そこに観客ノイズや残響処理を重ねることで、あたかも会場で演奏されたかのように聞かせている。
これはダブル・アルバムとしてのボリュームを確保したいレーベル側の意向であり、バンド自身はあまり歓迎していなかったとも伝えられている。
それでも、『Steppenwolf Live』が単なる“寄せ集め”で終わっていないのは、ライブ音源の核が強烈だからである。
「Sookie, Sookie」「Don’t Step on the Grass, Sam」「Monster」「Draft Resister」「Power Play」といった代表曲群に加え、「Magic Carpet Ride」「The Pusher」「Born to Be Wild」という決定的ナンバーまで、一気に畳みかける構成。
ハモンド・オルガンのうねり、分厚いギター・リフ、Kay のしゃがれ声、そして観客の歓声が一体となり、“60年代末のアメリカン・ロック・ショウ”の臨場感をそのまま伝えてくる。チャート的にも、本作はバンドにとって重要な節目となった。
全米アルバム・チャートで7位、全英15位、オーストラリア16位、ノルウェー9位と各国で好成績を残し、結果としてゴールド・ディスクを獲得。
Steppenwolf にとっては、デビュー作以来となる最後のUSトップ10アルバムとなり、「Hey Lawdy Mama」もシングルとしてトップ40ヒットを記録した。
『Monster』で社会批評に大きく舵を切ったバンドが、そのモードを保ったままライヴ・バンドとしての迫力を証明した作品。
スタジオ曲の混在という“いびつさ”さえも含めて、1969〜70年のSteppenwolfの勢いと矛盾を封じ込めた、“時代の記録”として味わうべき一枚である。
3. 全曲レビュー
1曲目:Sookie, Sookie
Don Covay & Steve Cropper のR&Bナンバーをオープニングに据えた「Sookie, Sookie」。
スタジオ版よりテンポがわずかに上がり、ドラムとベースがタイトに跳ねる。
Goldy McJohn のハモンドが合図のように鳴り、Kay のしゃがれた声が客席を一気に温めていく。
歌詞自体はシンプルなロックンロール的恋愛ソングだが、ライヴでは完全に“ショウのウォームアップ”として機能している。
観客の手拍子が混ざり、コール&レスポンスの気配が漂うことで、リスナーも自然と会場の空気の中に放り込まれるような感覚になる。
2曲目:Don’t Step on the Grass, Sam
続く「Don’t Step on the Grass, Sam」は、『The Second』収録の反ドラッグ・キャンペーン批判ソング。
ここでは6分超のライヴ・バージョンとして演奏され、Kay の語り口とバンドのグルーヴがより鋭くなっている。ウィキペディア+1
“Sam”はアメリカ政府や体制側の象徴であり、草(grass=マリファナ)を踏みつけるのは、若者文化そのものを押さえつけようとする行為の比喩でもある。
ライヴ版では歌詞の皮肉が一段と際立ち、観客の歓声が“体制側へのブーイング”として聞こえてくるのが面白い。
バンドはテンポを微妙に揺らしながら、ブレイクで緊張を高め、サビで一気に爆発させる。
政治的メッセージとライヴの高揚が初めて真正面からぶつかり合う瞬間である。
3曲目:Tighten Up Your Wig
3曲目「Tighten Up Your Wig」は、Junior Wells「Messin’ with the Kid」へのオマージュ/パロディとして作られたブルース・ロック。
ライヴでは、ギターとオルガンの“掛け合い”がより前に出る。
Goldy と Byrom が互いにフレーズを投げ合い、Edmonton のスネアがそこに鋲を打っていくイメージで、終始ごきげんなブルース・ジャムが展開される。
タイトルの“かつらを締め直せ(=頭をしっかりさせろ)”という表現どおり、歌詞はユーモアを交えつつ、聞き手に“目を覚ませ”と促す。
『Monster』ほど重くはないが、ここにもSteppenwolf流の“説教ブルース”の片鱗があるのだと思える。
4曲目:Monster
アルバム中盤の山場のひとつが、9分56秒の「Monster」。
スタジオ版では組曲『Monster / Suicide / America』の一部として展開された楽曲だが、ここではその“モンスター”パートを中心にした形で演奏される。
ライヴ版の特徴は、何より演奏の粗さと勢いである。
オルガンとギターのコードがぶ厚く重なり、ベースが低域を唸らせ、ドラムがロールで煽る。
それを乗りこなすように Kay がアメリカ史と政治を語り続ける様子は、ほとんど“ロック版政治演説”のようであり、そのスリルがそのまま音楽の推進力になっている。
スタジオ版でやや説明的に感じられた歌詞も、観客の前で叫ばれると不思議と血の通った言葉に変わる。
「Monster」は、ライヴという現場を得て初めて、本来の破壊力を取り戻した楽曲なのかもしれない。
5曲目:Draft Resister
「Draft Resister」は、徴兵拒否者をテーマにした『Monster』の重要曲。
ライヴでは3分台というコンパクトな尺の中に、パーカッシヴなビートと鋭いコーラスが凝縮されている。
“ドラフト・カードを燃やした若者”の姿は、当時のライブ会場に実際にいた観客たちと地続きであり、その意味でこの曲はステージとフロアをつなぐ“合言葉”のような役割を担っている。
サビの「Here’s to all the draft resisters」が叫ばれるたびに、喝采と共感のざわめきが広がるのが想像できる。
音の面では、ハモンドの速いランとギターのカッティングが前面に出ており、スタジオ版より攻撃的な印象が強い。
短いが、アルバム全体を象徴するキートラックである。
6曲目:Power Play
「Power Play」は、重いリフとゆったりしたテンポが印象的なブルース・ロック。
ライヴ版では、低音がスタジオ版以上にモコモコと鳴り、会場の空気を震わせるような質量を獲得している。
歌詞は、表向きは民主主義と自由を謳いながら、裏では警察力や官僚機構を使って市民を管理する“権力のゲーム”を描く。
その閉塞感を体現するかのように、バンドはコード進行を執拗に反復しながら、ところどころで爆発的なフィルやソロを差し込む。
アルバム前半の締めくくりとして、政治的モチーフをじっくり煮詰めたような一曲。
ライヴという場で、Steppenwolf がどれだけ“重いテーマ”を真正面から扱っていたかが伝わる瞬間である。
7曲目:Corina, Corina
3面目の入り口を飾る「Corina, Corina」は、古いブルース/R&Bスタンダードのカバー。
ただし本作ではスタジオ録音であり、観客ノイズをかぶせて“ライヴ風”に仕上げられている。
テンポはミディアムで、ギターはクリーン寄りのトーン。
Kay の歌い方もどこか力が抜けていて、アルバム前半の政治性を一度リセットするような柔らかさを持っている。
オリジナルが持つ哀愁やスウィング感を活かしつつ、オルガンが後景でさりげなくコードを支えることで、“Steppenwolf流モダン・ブルース”として聞かせるアレンジになっている。
8曲目:Twisted
続く「Twisted」もスタジオ録音に観客音を加えたトラックで、『Monster』期のバンドのサウンドをよりコンパクトにしたような一曲である。
タイトルどおり、リフはよじれたような半音階を含み、ギターとオルガンが陰鬱なコード進行をなぞる。
歌詞には、社会的な緊張や精神的な追い詰められ感が織り込まれており、“ねじれてしまった世界”というイメージが立ち上がる。
スタジオ録音であることを意識して聴けば、音像のクリアさやオーバーダブの重ね方はライヴ・トラックより整っている。
それでも歓声のフェイクがうまく混ざっているため、アルバム全体の流れはさほど途切れない。
9曲目:From Here to There Eventually
「From Here to There Eventually」は、『Monster』の終曲としても知られるゴスペル寄りロック。
ここでは6分40秒のライヴ・バージョンとして、終盤に向けてじわじわと盛り上がっていく
ヴァース部分は比較的抑えた歌い方で始まり、コーラスが一層ずつ積み上がるようにしてサビに向かっていく。
サビの繰り返しでは、ほとんど教会のコール&レスポンスのような熱を帯び、観客の歓声も合わさって、一種の“集団的カタルシス”が生まれている。
“ここ(現状)からそこ(理想)へ、いつか辿り着きたい”という願いを歌うこの曲は、『Monster』の物語をライヴの場で再確認するような役割を持つ。
アルバムの“内省サイド”を代表するトラックだと言える。
10曲目:Hey Lawdy Mama
10曲目「Hey Lawdy Mama」は、本作からの新曲としてシングル・カットされたスタジオ録音のロック・チューン。
2分台という短さの中に、ドライヴ感あるリフとキャッチーなサビを凝縮した、非常にラジオ・フレンドリーなナンバーである。
アルバムでは「Magic Carpet Ride」へシームレスに繋がるよう編集されており、“MCの挨拶→新曲→代表曲”というライヴらしい高揚の流れをスタジオ録音で再現している。
歌詞は、相手に呼びかけるブルース〜R&B的な定型を踏まえつつ、Steppenwolfらしい荒っぽさとポップさのバランスが光る。
シングルとしてもトップ40入りを果たし、本作を象徴する一曲となった。
11曲目:Magic Carpet Ride
「Magic Carpet Ride」は、言わずと知れた代表曲のライヴ・テイク。
スタジオ版よりわずかにテンポが速く、ギターの刻みも粗さを増している。
特徴的なのは、イントロのサイケデリックなノイズ部分を比較的短く切り上げ、すぐに本編のリフへ雪崩れ込む構成になっていること。
ライヴでは観客の期待値がすでに高いため、“待たせずにすぐ本編へ”という判断なのだろう。
サビの「I like to dream〜」では客席の歌声も重なり、サイケデリックな“魔法のじゅうたんの旅”が、当時の観客にとってどれだけ日常からの逃避の象徴だったかを想像させる。
12曲目:The Pusher
12曲目「The Pusher」は Hoyt Axton 作の反ドラッグ・ソング。
Steppenwolf のヴァージョンはドラマティックな構成で知られるが、ライヴ版ではその“間”の使い方がさらに際立つ。
静かなイントロから、徐々に音量と歪みを増していき、クライマックスで怒涛のシャウトとバンドサウンドが爆発する。
ディーラー(pusher)と単なるユーザーの違いを強調し、“欲望につけ込んで人を破滅させる者”への怒りをぶつける歌詞は、当時のドラッグ文化に対する複雑なスタンスを表している。
観客はこの曲を“反ドラッグ賛歌”として受け取ったのか、“ドラッグの暗い側面を描いた物語”として受け取ったのか。
いずれにせよ、このライヴ・テイクには、倫理的な葛藤とカタルシスが入り混じった凄みがある。
13曲目:Born to Be Wild
ラストはもちろん「Born to Be Wild」。
映画『イージー・ライダー』を経て、“バイカー・アンセム”として完全に定着したこの曲を、バンドは堂々とクローザーに配置している。
イントロのリフが鳴った瞬間に観客が沸き立つ様子が音から伝わり、そこから最後までテンションが落ちない。
テンポはスタジオ版とほぼ同じだが、ギターはより荒れ、ドラムはやや前のめり気味に突っ込んでいく。
歌詞の“heavy metal thunder”というフレーズは、後にヘヴィ・メタルというジャンル名の源のひとつとも言われる有名な一節だが、ここでは単純に“バイクのエンジン音”と“バンドの轟音”が重なる瞬間として響く。
エンジンのように加速し続けるバンドと、叫び続ける観客。
この瞬間があるからこそ、『Steppenwolf Live』は長く愛されるライヴ・アルバムであり続けているのだろう。
4. 総評
『Steppenwolf Live』は、Steppenwolf のキャリアにおいて特別な位置を占める作品である。
それは単に“名曲がたくさん入ったベスト的ライヴ盤”という意味だけではない。
1969年の『Monster』で政治性を大きく前面に押し出したバンドが、そのモードを保持したまま、ライヴ・バンドとしての実力を証明する場になっているからである。
サウンド面を改めて整理すると、本作は以下のような特徴を持つ。
- ハモンド・オルガンとギターの二枚看板
Goldy McJohn のハモンドがローからミッドまでを厚く支え、Larry Byrom のギターがその上でリフとソロを縦横に繰り出す。
この二者のバランスが崩れないことによって、Steppenwolf サウンドはハード・ロックの重量感とサイケデリックな揺らぎを同時に保っている。 - リズム隊のタイトさと“ジャムすぎない”節度
ライブ盤ながら、やたら長尺のジャムにはならず、各曲は比較的コンパクトにまとめられている。
Edmonton のドラミングと St. Nicholas のベースは、曲の骨格を崩さない範囲でフィルとアドリブを回し、聴きやすさとライヴ感のギリギリのバランスを取っている。 - 政治性とロック・エンターテインメントの同居
「Monster」「Draft Resister」「Power Play」「From Here to There Eventually」といった社会批評的楽曲と、「Magic Carpet Ride」「The Pusher」「Born to Be Wild」といった“キラー・チューン”が同じセットの中に並ぶ構成は、当時のSteppenwolfが“メッセージを持つロック・バンド”であると同時に“観客を盛り上げるショウ・アクト”でもあったことを示している。
一方で、このアルバムには“完全なライヴではない”という構造的な歪みも存在する。
スタジオ録音に観客音を被せた「Corina, Corina」「Twisted」「Hey Lawdy Mama」は、制作経緯を知ってしまうと少し複雑な感情を抱かせる部分でもある。
だが、アルバム全体を通して聴けば、それらが流れを致命的に壊しているわけではなく、むしろ“セットリストの間に挟まれたMCや新曲”のような役割を果たしていることも確かである。
同時代のライヴ盤――たとえば The Who『Live at Leeds』や Three Dog Night『Captured Live at the Forum』など――と比べると、『Steppenwolf Live』は演奏そのものの破壊力よりも、“セット全体としての構成”を重視したアルバムであると言える。
骨太なロック・チューンと政治的メッセージ・ソングを緩急をつけて並べ、最後は「Born to Be Wild」で締める――この分かりやすさは、ライヴ盤としての即効性を高めると同時に、“ツアーの一夜をそのまま体験する”感覚を強めている。
バンドのキャリアの観点から見ると、本作はまさに“ピーク時の記録”である。
チャート的にも全米7位・英15位を記録し、ゴールド・ディスクに認定された最後のトップ10アルバム。
この後に続く『Steppenwolf 7』『For Ladies Only』では、ヘヴィさと内省性を保ちながらも、商業的な勢いは徐々に落ちていく。
その意味で『Steppenwolf Live』は、“スタジオ作品の合間に出されたサイド・プロジェクト”ではなく、“第一期Steppenwolfの総決算”と呼ぶべきポジションにあるのだ。
現在の耳で聴き返すとき、このアルバムは二重の意味で興味深い。
ひとつは、ハード・ロック/ヘヴィ・メタルの原型としてのSteppenwolfを、“ライヴ・バンドとして”体感できるという点。
もうひとつは、ベトナム戦争やドラッグ政策など1960年代末の社会問題が、どのようにライブ・ステージ上で語られていたかを、具体的な音として記録しているという点である。
正直に言えば、録音クオリティは現代のライヴ盤と比べると粗い部分もあるし、ミックスもやや中域に寄っている。
しかし、その粗さこそが“会場の空気”を想像させる。
クラブでもアリーナでもない中規模ホールの鳴り方、アンプから直接飛び出すギターの音、PAを通したKayの声――そういったものが、すべて1枚の盤の中に閉じ込められている。
Steppenwolf を知るうえでの“最初の一枚”としては、やはり1st『Steppenwolf』や『The Second』、あるいは『Monster』が推されるかもしれない。
しかし、これらのスタジオ作品を一通り聴いたあとに『Steppenwolf Live』に触れると、“彼らがどんな場でどんな観客と共有されていたのか”が一気に立体的に見えてくる。
そういう意味で、本作はSteppenwolf体験の“第二ステップ”として非常にふさわしいアルバムなのだと思う。
5. おすすめアルバム(5枚)
- Steppenwolf / Steppenwolf (1968)
「Born to Be Wild」「The Pusher」収録のデビュー作。
『Steppenwolf Live』のクライマックスで鳴り響く代表曲が、スタジオではどのような音像だったのかを確認できる原点的アルバム。 - Steppenwolf / The Second (1968)
「Magic Carpet Ride」「Don’t Step on the Grass, Sam」収録。
ライヴ盤でのアグレッシヴな演奏と聴き比べることで、サイケデリックなスタジオ・プロダクションとライヴ・バンドとしての違いがよく分かる。 - Steppenwolf / Monster (1969)
政治的テーマを全面に押し出した問題作。
『Steppenwolf Live』に収められた「Monster」「Draft Resister」「Power Play」「From Here to There Eventually」の“元の姿”を知ることで、ライヴ版の変化や削ぎ落としの妙が見えてくる。 - Steppenwolf / Steppenwolf 7 (1970)
『Steppenwolf Live』と同年にリリースされたスタジオ・アルバム。
ライヴ盤を通してバンドのピークを体験したあと、その勢いをどうスタジオ作品に持ち込んだのかを確かめるのに適した一枚である。 - Three Dog Night / Captured Live at the Forum (1969)
同じくABC/Dunhill所属で、Steppenwolfのツアーに帯同したThree Dog Nightのライヴ盤。
同レーベル/同時期のライヴ録音として聴き比べると、アメリカン・ロック・ショウの“多様なスタイル”が浮かび上がる。
6. 制作の裏側
『Steppenwolf Live』のレコーディングは、1970年1月22日にカリフォルニア州サンタモニカ・シヴィック・オーディトリアムで行われた公演が中心となっている。
この公演は、直前に発表された『Monster』のツアーの一環であり、バンドは政治的な新曲群と既存のヒット曲を織り交ぜたセットを披露していた。
プロデュースは引き続き Gabriel Mekler、エンジニアは Ray Thompson。
彼らはスタジオ録音で培った音作りをライヴ録音にも持ち込み、オルガンとギターが潰れすぎないよう、しかし十分な歪みと迫力を保つバランスを狙っている。
興味深いのは、ダブル・アルバムとして必要な尺を満たすため、いくつかのスタジオ録音が急遽追加された経緯である。
「Hey Lawdy Mama」「Corina, Corina」「Twisted」の3曲はスタジオで録音され、その後ライヴ音源に溶け込むようにイコライジングとディレイ処理を施され、さらに冒頭と末尾に観客ノイズがオーバーダブされた。これらの処理はレーベル側(Dunhill)の判断で行われたとされており、バンド側は必ずしも満足していなかったとも言われる。
しかし結果的に、「Hey Lawdy Mama」はアルバム随一のキャッチーな新曲としてシングル・ヒットし、『Steppenwolf Live』を“ベスト盤以上の何か”へと押し上げる要因にもなった。
また、この作品はベーシスト Nick St. Nicholas が参加した最後のアルバムでもある。
次作『Steppenwolf 7』からは George Biondo が後任として参加し、リズム・セクションのキャラクターも微妙に変化していく。
つまり『Steppenwolf Live』は、サウンド面でもメンバー構成の面でも、“ひとつの時代の終わり”を切り取った記録なのだ。
参考文献
- Wikipedia “Steppenwolf Live”(基本データ、録音日・会場、スタジオ曲の追加経緯、トラックリスト)ウィキペディア
- Steppenwolf Official Store “Steppenwolf Live – CD”(公式トラック一覧、ライヴ盤としての位置づけコメント)Steppenwolf
- Wikipedia “Steppenwolf discography”(ライヴ盤のリリース情報、チャート成績、ゴールド認定)ウィキペディア
- uDiscoverMusic “’Steppenwolf Live’: Rock Heroes Take A Top Ten Album Trip”(チャート推移、最後のUSトップ10作としての位置づけ)uDiscover Music
- 仏語版・伊語版 Wikipediaおよび ClassicRock80 記事(サンタモニカでの録音経緯、スタジオ曲に対する処理、メンバー交代情報など)


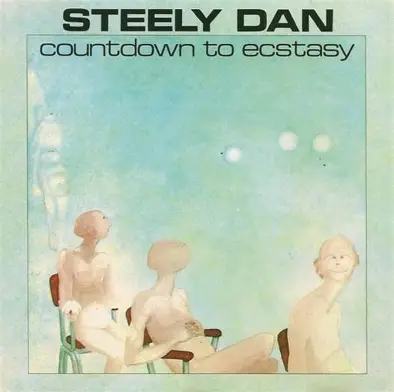

コメント