
発売日: 1979年5月17日
ジャンル: ロック、アート・ロック、ポストパンク
『Wave』は、Patti Smith が1979年に発表したスタジオアルバムである。
本作は、70年代ニューヨークの音楽シーンが混沌としつつも成熟に向かう転換点に位置し、
パンク以降の“言葉とロック”の関係性を改めて問い直す作品として、彼女のキャリアの中でも独特な存在感を放っている。
当時のパティ・スミスは、デビュー以来の詩的で過激なパフォーマンスを続けながらも、
徐々に“ロック・スター”としての立ち位置を受け入れ、より広いリスナーへ向けた表現に踏み出そうとしていた。
その意識の変化が『Wave』には明確に刻まれており、音像はこれまで以上にメロディックで瑞々しい。
プロデューサーにTodd Rundgrenを迎えたことで、サウンドには柔らかい光が差し、
パティの象徴的な反逆性と、よりオープンで清潔なポップ感覚が共存している。
また1979年という時代は、パンク以降のロックが“再構築”されつつあったタイミングであり、
The Clash や Blondie などが世界的評価を確立し、
パンクの衝動は新たなポップ感覚と融合する方向へ進みはじめていた。
『Wave』の優しく空気の軽いトーンは、その時代傾向を反映しているようであり、
同時に、パティ自身がより私的な表現へ移行していく過程を捉えた記録でもある。
本作のテーマには、“別れ”や“祈り”が深く関わっている。
特に、後年の人生の転機へとつながる内面的変化、
そして長らく共に活動してきたPatti Smith Groupの終幕を暗示するかのような静けさが漂う。
『Wave』はヒット作にとどまらず、時代の気配を繊細に映し出す“転換期の証言”として価値を持つアルバムなのである。
全曲レビュー
1曲目:Frederick
アルバムの幕開けとして、澄んだギターと広がりのあるアレンジが印象的である。
パティ特有の祈るような歌唱に、光の差すセンチメントが加わり、
“新しいフェーズ”への入り口を示すように穏やかに立ち上がる。
2曲目:Dancing Barefoot
名曲として語り継がれる理由のひとつは、その神秘的で美しいサウンドだろう。
「it’s an obsession(これは執着)」という象徴的なフレーズから、
愛、信仰、陶酔、献身といったテーマが複雑に交差していく。
アルバム全体の精神性を象徴する核心部分である。
3曲目:Hymn
ミニマルな構成の中で、パティの語りと歌が交互に揺れ動く。
宗教的なモチーフや祈りの言葉が織り込まれ、作品全体の“精神的な地平”を広げる役割を担う。
4曲目:Revenge
バンドサウンドがぐっと前に出る、エネルギーの強い一曲。
怒りや葛藤を内包しながらも、メロディ自体は軽やかで、
アルバムのバランスを保つための“動的な存在”として機能している。
5曲目:Citizen Ship
ポストパンク的なテンションを纏い、社会性のあるメッセージが込められた楽曲。
「市民としての意識」に触れる歌詞は、当時のパティの思想的関心の深さを物語る。
6曲目:Seven Ways of Going
やや実験性が強く、構成も自由度が高い。
語りに近い歌唱と、流動的に変化する楽器のアンサンブルが、
詩の世界観を映し出すように揺らめいている。
7曲目:Broken Flag
静謐ながら強い感情を孕んだ曲で、
“旗”というモチーフが象徴する国家や共同体への視線が読み取れる。
メロディは優しいが、内側にある怒りや悲しみがじんわりと滲む。
8曲目:Wave
タイトル曲であり、アルバムの精神的中心。
亡きローマ教皇に捧げられたともされる祈りのような楽曲で、
語りかけるようなヴォーカルと波のように寄せては返すサウンドが印象的だ。
深い祈念と別れの感触が入り混じる、非常に象徴的な1曲である。
9曲目:Fire of Unknown Origin
未踏の領域への渇望を歌うかのようなエネルギーが宿っている。
後にBlue Öyster Cult が再録し有名になる楽曲の原型であり、
パティの詩とメロディセンスがいかに幅広い影響を生んだかを示す。
総評
『Wave』は、Patti Smith のキャリアの中で“最も静かで、もっとも変化を孕んだ”作品である。
デビュー作『Horses』の荒々しい革新性、続く『Easter』のロック・アイコンとしての自信。
それらと比べると『Wave』は、外へ突き刺さる鋭さではなく、内側へ沈み込む静かな熱を帯びている。
この変化の背景には、パティ自身の人生の転換があった。
活動のペースを落とし、のちに結婚と家庭の時間を優先していく直前の時期であり、
その心境がアルバム全体の柔らかい語り口に反映されている。
“叫ぶパンク詩人”から“祈るように歌う詩人”へ。
その移行がもっとも繊細に捉えられたのが本作なのだ。
サウンドにも特徴がある。
Todd Rundgren のプロダクションは、バンドの粗削りな質感を上手く整え、
透明感のある音像を生み出している。
この時期のアメリカン・ロックが抱えていた“ポップ化の潮流”とも呼応しており、
当時の音楽シーンの気分を非常に上品な形で反映している。
同時代のアーティストと比較すると、例えば
・語りの強さと霊性 → Patti Smith
・ポストパンクの冷たさ → Joy Division
・ポップと芸術性の接続 → Talking Heads
といった“方向性の違い”がわかりやすい。
『Wave』はその中間点に立ちつつ、どれにも属しきらない独自の位置を作り出した。
パンクの残響とポップの清涼感を同時に持つ作品は他にほとんどなく、
まさに“ジャンルの狭間で輝くアルバム”と言える。
本作が現在も聴き継がれる理由は、
何よりその“柔らかさの中に潜む強さ”にある。
怒りや祈り、別れや期待といった複数の感情が、
静かだが強固な芯を持って一本の線につながっている。
時代が変わっても共鳴する普遍性は、この丁寧に磨かれた歌詞とサウンドに宿っているのだ。
おすすめアルバム(5枚)
- Easter / Patti Smith Group
前作であり、より力強いロック性と詩性が共存する作品。 - Horses / Patti Smith
デビュー作にしてパンク前夜を象徴する原点。 - Remain in Light / Talking Heads
アート性とポップ性の融合という点で響き合う。 - Parallel Lines / Blondie
同時期ニューヨークの空気感を共有し、ポップと反逆の同居が魅力。 - Unknown Pleasures / Joy Division
精神的深度やミニマリズムという面で比較して楽しめる。
制作の裏側(任意セクション)
『Wave』は、Todd Rundgren のスタジオで録音されている。
彼は当時、XTC や Meat Loaf など多彩なアーティストを手がけており、
音の透明感やミックスの端正さは完全に彼の手腕によるものだ。
Patti Smith Group のメンバーも、これまでの荒々しさを抑え、
より緻密なアンサンブルを目指したと言われている。
とくにギターの繊細なエフェクト処理や、
ドラムの柔らかなアタックは『Wave』特有の空気感を形作っている。
また、タイトル曲「Wave」の録音時には、
照明を落とした静かな環境でパティがほぼ一発で歌い上げたというエピソードも残っている。
その“祈り”のようなニュアンスは、環境によって生まれたものなのだろう。


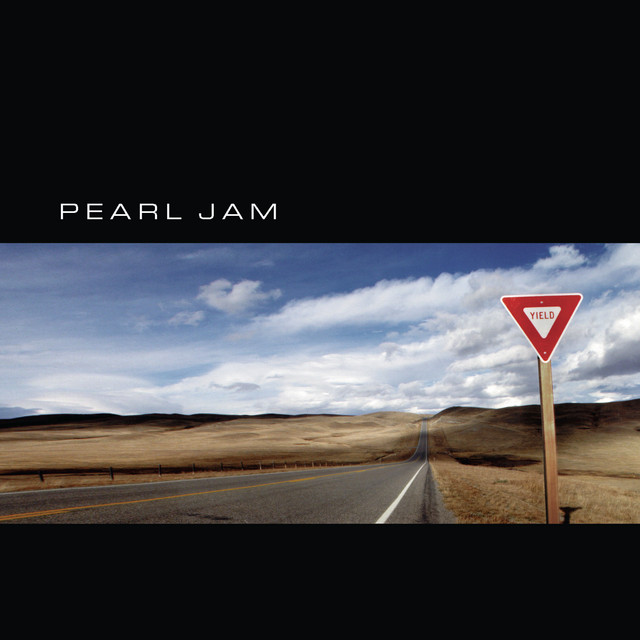
コメント