
発売日: 1983年7月
ジャンル: ポップ・ロック、アダルト・コンテンポラリー、ニューウェイヴ・ポップ
『What Goes Around…』は、The Holliesが1983年にリリースした20作目のスタジオ・アルバムであり、彼らの80年代再始動を告げる重要な作品である。
このアルバムの最大のトピックは、グラハム・ナッシュの16年ぶりの復帰である。
1968年に脱退して以来、Crosby, Stills & Nashで大成功を収めていたナッシュが再び古巣に合流――これはThe Holliesの歴史における象徴的な出来事だった。
その結果、『What Goes Around…』は“再会”と“再生”をテーマにした、バンドの第二幕を飾るアルバムとなった。
制作はロサンゼルスで行われ、サウンド面でも当時のアメリカ的AOR/ソフト・ロックの潮流を強く反映している。
シンセサイザーや電子ドラムが導入され、よりモダンで洗練されたサウンド・デザインを採用。
だが、中心には常にThe Holliesらしい三声ハーモニーが息づいており、60年代から続く彼らの音楽的アイデンティティを見失ってはいない。
このアルバムは、まさに“伝統と現代性の架け橋”なのだ。
全曲レビュー
1曲目:Casualty
エネルギッシュなシンセとドラムマシンで幕を開けるモダンなポップ・ロック。
“時代の犠牲者(Casualty)”というタイトルどおり、80年代的な冷たさと哀愁が交錯する。
クラークとナッシュのヴォーカルが再び重なる瞬間には、往年のHolliesファンにとって感慨深いものがある。
2曲目:Take My Love and Run
軽快なテンポときらめくギターが印象的なシングル曲。
恋愛をテーマにしつつも、“自由と情熱の衝突”を描く内容で、ポップながらも深みを感じさせる。
プロダクションの完成度が高く、MTV世代にも通じる洗練をまとっている。
3曲目:Say You’ll Be Mine
柔らかなシンセとメロディアスなヴォーカルが交錯するミディアム・テンポの楽曲。
60年代後期の叙情性と80年代AORの透明感が見事に融合している。
アラン・クラークの温かい声が、ナッシュのハーモニーと溶け合い、穏やかな再会の雰囲気を作り出す。
4曲目:Something Ain’t Right
ニューウェイヴの影響を感じさせるビートが特徴的。
やや硬質なサウンドだが、サビのハーモニーが入ると一気にThe Holliesらしい柔らかさが戻る。
時代の中で試行錯誤するベテラン・バンドの“前進する姿勢”が伝わってくる一曲だ。
5曲目:If the Lights Go Out
本作のハイライトのひとつ。
ナッシュがCrosby, Stills & Nash時代に書いた楽曲をHollies流にリアレンジしており、シンセの幻想的な響きが美しい。
“もし世界が闇に包まれても、君を見つけられる”という歌詞は、彼らの友情と音楽的絆を象徴している。
6曲目:Stop in the Name of Love
The Supremesの名曲カバー。
大胆なシンセ・ポップ・アレンジで蘇らせ、The Holliesらしいハーモニーを重ねて新しい命を吹き込んでいる。
60年代ソウルの名曲を、80年代の空気の中で再構築した見事な試みだ。
7曲目:Let Her Go Down
ドラマティックなストリングスとコーラスが特徴のバラード。
“彼女を自由にさせてやれ”というテーマは、過去を手放すことを象徴しており、バンド自身の歩みと重なる。
叙情性に満ちたアレンジが、Holliesの成熟した感性を示している。
8曲目:Having a Good Time
明るく開放的なポップ・ソング。
軽やかなグルーヴと陽気なメロディが、アルバム中もっとも“ハーモニーの喜び”を感じさせる。
グラハム・ナッシュの声が特に生き生きと響き、再結成による高揚感をそのまま音にしているようだ。
9曲目:You Gave Me Strength
シンセとアコースティック・ギターが穏やかに共鳴するスピリチュアルなナンバー。
“君が僕に力をくれた”という言葉は、まるでファンや仲間への感謝のように響く。
この曲で聴けるハーモニーは、The Holliesの真価を改めて証明している。
10曲目:Someone Else’s Eyes
ロマンティックなバラードでアルバムを締めくくる。
過去と現在の視点が交錯する詩的な歌詞と、穏やかなメロディが印象的。
80年代の空気をまといながらも、どこか“British Pop”の余韻を残す美しいエンディングである。
総評(約1300字)
『What Goes Around…』は、The Holliesにとって“再生と再会”をテーマにした感動的な節目の作品である。
グラハム・ナッシュの復帰は単なる話題性ではなく、音楽的にも精神的にも大きな意味を持っていた。
60年代に築かれたコーラス・マジックが80年代の新しいサウンドと交わることで、The Holliesは再びその存在価値を証明した。
アルバム全体を通して感じられるのは、“過去にすがらない成熟”である。
彼らは60年代の栄光を懐古するのではなく、それを糧にして現代の音楽へ踏み出している。
たとえば「If the Lights Go Out」や「Let Her Go Down」に漂う哀愁は、単なるノスタルジーではなく、“長く音楽を続けてきた者だけが鳴らせる静かな情熱”の表現だ。
サウンド・プロダクションは、80年代らしいクリーンさとエレクトロニクスが際立つ。
リズム・マシンやシンセサイザーが積極的に導入されながらも、The Hollies特有の温かみは失われていない。
特に、アラン・クラークとグラハム・ナッシュ、テリー・シルヴェスターのハーモニーは驚くほど自然で、まるで時を超えて再び結びついたようだ。
また、選曲と構成には明確なメッセージ性がある。
The Supremesの「Stop in the Name of Love」を含むことで、60年代ポップへの敬意を表しながらも、それを1983年の文脈で再生させる。
“音楽は回り続ける”というタイトルの意味が、まさにこの選曲によって具現化されているのだ。
商業的には大ヒットには至らなかったが、『What Goes Around…』は批評的に高く評価された。
とくに欧州圏では「もしHolliesが80年代にも活動を続けたら」という理想形として再評価されており、後年のリマスターでも音質の良さが際立つ。
最も印象的なのは、そのタイトルの多義性だろう。
“What Goes Around…”(巡りめぐるもの)は、まさに彼らのキャリアそのものを表している。
60年代に始まった音楽の輪が、80年代の今、再び回り始める――その瞬間を、このアルバムは静かに、しかし確かに刻んでいる。
おすすめアルバム(関連・比較)
- A Crazy Steal / The Hollies (1978)
80年代サウンドの萌芽を感じさせる叙情的前作。 - Daylight Again / Crosby, Stills & Nash (1982)
同時期のナッシュ活動との比較で聴くと興味深い。 - Voices / Hall & Oates (1980)
ハーモニーを現代化したポップ・ソウル路線の好例。 - Tug of War / Paul McCartney (1982)
ベテランが80年代に適応した同時代的傑作として対照的。 - Too Low for Zero / Elton John (1983)
同年における英国勢の成熟サウンドとして文脈が近い。


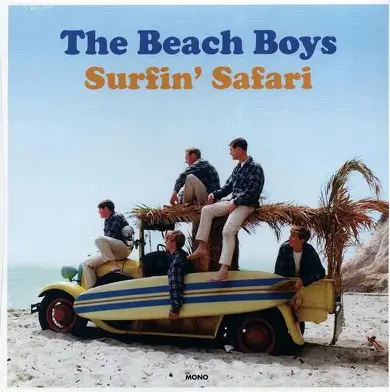

コメント