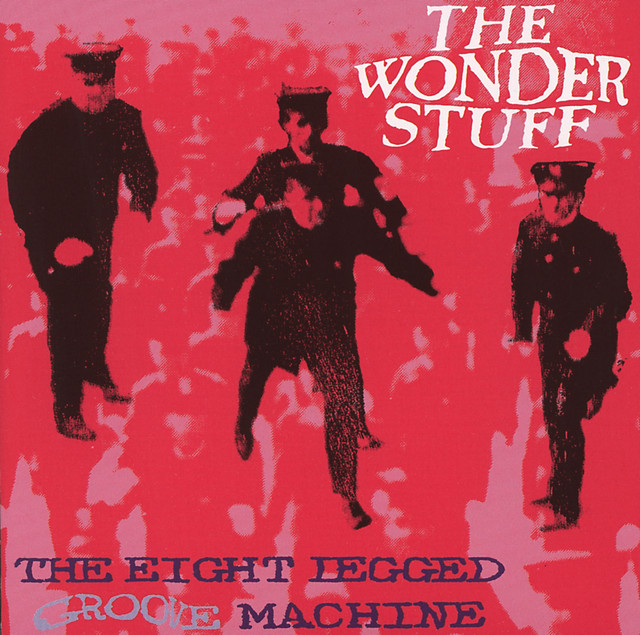
発売日: 1988年5月15日
ジャンル: オルタナティブロック、インディーポップ、マッドチェスター前夜
概要
『The Eight Legged Groove Machine』は、イギリスのインディーロック・バンド、The Wonder Stuffが1988年に発表したデビュー・アルバムであり、80年代末のUKインディーシーンにおいて、パンクの反骨とポップの親しみやすさを絶妙に融合させた作品である。
バンドの中心人物であるMiles Huntの皮肉まじりのボーカルと、アグレッシブかつキャッチーな楽曲構成が際立ち、後に続くブリットポップやマッドチェスターの波に先んじる形で、”楽しさ”と”怒り”のバランス感覚を提示した。
当時のUKロックシーンが持っていた“シリアスで政治的な気質”に対して、本作は明らかに“ユーモアと日常感”を武器にしており、それが大衆的な人気へと繋がった。
その音楽性はBuzzcocksやThe Jamからの影響を受けつつも、より軽妙でウィットに富んだ姿勢が新鮮に映り、NMEやMelody Makerといったメディアでも高評価を受けた。
また、イギリス国内ではインディーチャートで好成績を残し、アルバムの成功をきっかけにメジャーへの躍進も視野に入ることとなった。
全曲レビュー
1. Red Berry Joy Town
オープニングから軽快なギターと跳ねるようなリズムが炸裂。
街の名前を冠したタイトルはどこか皮肉で、幻想と現実の交錯が歌詞に見られる。
バンドの“楽しいけれどちょっとひねくれた”世界観を象徴する一曲。
2. No, For the 13th Time
スピード感あるパンク・ポップナンバーで、反復するフレーズに若者の倦怠と苛立ちがにじむ。
13回目の「ノー」は、感情の飽和点をユーモラスに描いた比喩的な言葉だ。
3. It’s Yer Money I’m After, Baby
本作の代表曲にしてインディーチャートを賑わせた大ヒットシングル。
タイトルの直球な皮肉とキャッチーなサビが魅力で、商業主義への風刺と恋愛の攻防を絶妙に重ねる。
4. Rue the Day
少しテンポを落としたギターポップで、失恋と皮肉が織り交ぜられたリリックが印象的。
パブでの愚痴のような語り口がリアルな共感を呼ぶ。
5. Give, Give, Give Me More, More, More
反復と勢いのあるタイトルがそのまま楽曲のテンションを表している。
消費主義と欲望をテーマにした楽曲だが、重くなりすぎずユーモアで包み込む手腕は見事。
6. Greasy Jacket
中盤のアクセントとなるファンキーで跳ねるリズムが楽しい一曲。
“脂ぎったジャケット”という奇妙なタイトルは、80年代イギリスの若者文化やファッションへの皮肉も含まれているようだ。
7. Fish Waltz
インストゥルメンタルに近い短いトラックで、アルバムの中継ぎ的な存在。
ちょっとした遊び心が垣間見える。
8. Wild Beast
ダイナミックな展開とシャウト気味のボーカルが特徴。
“内なる野獣”というテーマは、自我の解放や欲望のメタファーとして読める。
9. A Wish Away
ポップで軽やかなメロディが際立つ名曲。
“願いを流す”という曖昧で詩的なフレーズに、夢と現実の距離感を感じさせる。
10. Grin
ビートに乗せたユーモアと皮肉の応酬。
笑顔(Grin)は必ずしも幸福ではなく、むしろ社会や人間関係への偽装かもしれないという暗示が込められている。
11. Mother and I
アルバム後半にして、やや内省的な内容が顔を覗かせる。
家族関係を扱いつつも重くなりすぎず、ストーリーテリングとしての巧みさが光る。
12. Some Sad Someone
タイトルの通りメランコリックなギターポップ。
失われた誰かへの想いがこめられたバラード風トラックで、アルバムの緩急に彩りを加える。
13. Ruby Horse
陽気で風変わりな楽曲。
“ルビーの馬”という幻想的なイメージが、子供っぽさとサイケデリアの中間を行き来する。
14. Unbearable
本作のもうひとつの代表曲で、シングルとしても大成功を収めた。
感情の爆発、ユーモア、ラジオ向きのキャッチーさをすべて兼ね備えている。
「I didn’t like you very much when I met you / And now I like you even less」は当時の若者文化に刺さる決定的フレーズとなった。
総評
『The Eight Legged Groove Machine』は、The Wonder Stuffがシーンに現れた瞬間の躍動と、イギリス的なアイロニー、パンク由来のアティチュード、そしてインディーポップ的キャッチーさをすべて詰め込んだ衝撃的なデビュー作である。
このアルバムは、単なる“楽しいロック”ではない。
怒りや虚無、社会への違和感といったネガティブな要素をユーモアとポップの形で包み込む“裏のメッセージ性”が、当時のUKリスナーに強く響いた。
後のBlurやSupergrassにもつながる“皮肉と笑顔のポップ”という英国的ロックの文脈において、本作の果たした役割は決して小さくない。
音楽性としては、ガレージロック、パンク、ギターポップの要素をベースにしつつ、そこに乗るMiles Huntの語り口が独特の色彩を与えている。
その結果として、時に軽薄で、時に深く、常に面白い——そんな唯一無二の空気を纏ったアルバムとなった。
おすすめアルバム
- The Housemartins / London 0 Hull 4
軽妙なインディーポップに社会的視点を持ち込んだ名作。 - Blur / Leisure
皮肉とポップのバランス感覚が近く、ブリットポップ前夜を共有。 - The La’s / The La’s
リバプールらしいメロディセンスとポップの純度が通底する。 - Supergrass / I Should Coco
ユーモアとロックの融合。The Wonder Stuff的な若者感が濃い。 - The Soup Dragons / This Is Our Art
同時代のUKインディーバンドによる、ダンサブルで少し奇妙なポップロック。
歌詞の深読みと文化的背景
Miles Huntのリリックには、一見バカ騒ぎのようでいて、鋭い観察眼と社会への違和感が常に潜んでいる。
「It’s Yer Money I’m After, Baby」は、恋愛を商取引になぞらえたユーモアに満ちた風刺であり、「Unbearable」では感情の鈍麻と対人疲労がシンプルな言葉で語られる。
また、80年代後半のイギリス——サッチャー政権末期の保守化社会の中で、若者たちは一種の無力感を抱えていた。
The Wonder Stuffはその“政治的でない”スタンスのなかに、むしろ時代批評的な力を宿していたのだ。
笑って踊って、でもその奥に“何か変だ”という感覚を残す。
それこそが、『The Eight Legged Groove Machine』の最大の魅力なのかもしれない。


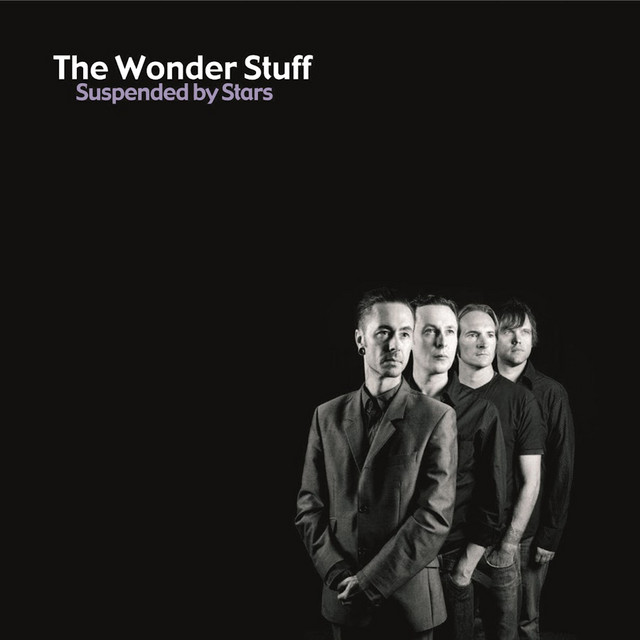
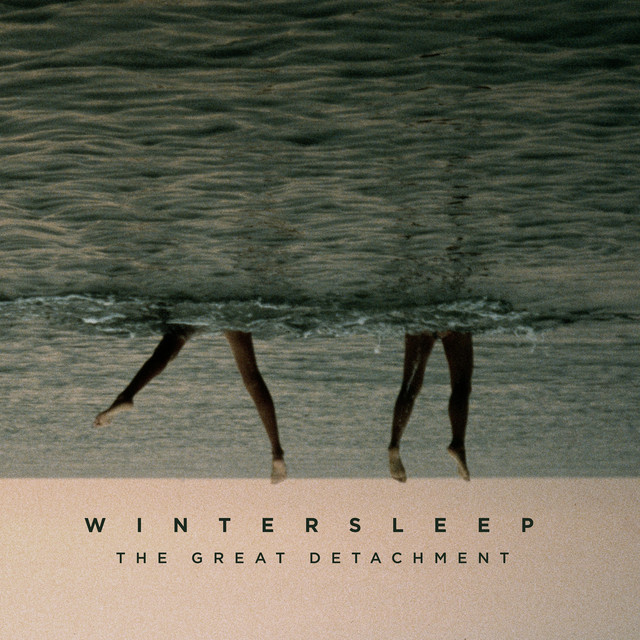
コメント