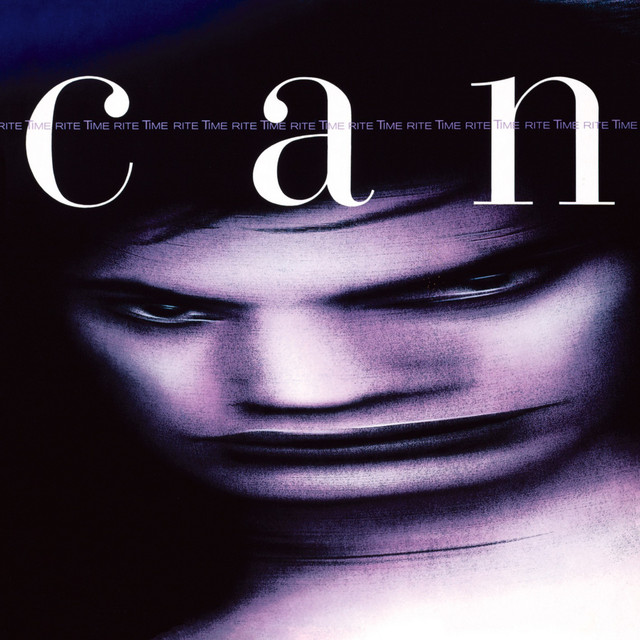
発売日: 1989年10月
ジャンル: クラウトロック、アヴァン・ロック、エクスペリメンタル・ロック
概要
『Rite Time』は、1989年にリリースされたCanの最終スタジオ・アルバムである。
本作最大の特徴は、デビュー期のヴォーカリスト マルコム・ムーニーの電撃復帰であり、彼にとっては1969年の『Monster Movie』以来、約20年ぶりの参加作となる。
この作品は、80年代後半という文脈において、再びCanという装置がどのように音を紡ぐのかを試みた**“静かなる回帰”**である。かつての実験性をそのまま再現するのではなく、**加齢と時間の経過を受け入れた“大人のCan”**として、内省的で瞑想的な音楽が展開されている。
録音は南フランス・ニース近郊、ミヒャエル・カローリ自宅のOuter Space Studioで1986年12月に行われ、1988年にWeilerswistのCan-Studioでミックス、1989年にホルガー・チューカイのラボで編集。プロデュースはミヒャエル・カローリとホルガー・チューカイ。サウンドは明晰で、80年代のテクノロジーを活かしつつ、ムーニーの語り歌い/スポークンに近いヴォーカルが、人間的な体温を前面に押し出している。
本作は、Canという伝説的バンドの**“最終章”にして、静かな別れの挨拶**でもあるのだ。
全曲レビュー
1. On the Beautiful Side of a Romance
開放的なリズムと浮遊感のあるギターが心地よい、再結成の幕開けを飾る一曲。
ムーニーのヴォーカルは“歌”というより詩的な語りで、音との対話が続く。ポストロック的構造の先駆として再評価されるべき楽曲。
2. The Withoutlaw Man
ブルージーなギターが絡む異色作。ロック的語法が強めだが、ムーニーの語り口が「物語性」を付与し、どこか“西部劇を語る語り部”の風情。リズム隊の安定感はさすがで、躍動感が際立つ。
3. Below This Level (Patient’s Song)
ミニマルなベース・ループの上で、ムーニーが低く呟き続ける異様なナンバー。精神世界の深部に踏み込む不穏さは、80年代末にあって逆に新鮮。まさに“内面の音楽”。
4. Movin’ Right Along
軽快なリズムと明るめのコード感が特徴の、珍しく“前向きなCan”。とはいえ、どこか引いた音像が続き、完全にはポップになりきらない。この温度感の曖昧さこそ本作全体のトーンを象徴。
5. Like a New Child
幻想的なギターと微細なシンセが織りなすドリーミーな世界。ここでもムーニーは歌うというより語る。**“音による詩の実践”**が、成熟した形で結実。
6. Hoolah Hoolah
本作で最もファンキーに躍動する曲。ヤキ・リーベツァイトのドラミングが本領を発揮し、ジャム感も随所に。構造は整理されており、**“枠内の自由”**にとどめるストイックさが光る。
7. Give the Drummer Some
その名のとおりドラムが主役。反復と変化が生む催眠効果は『Tago Mago』の系譜にあるともいえる。無意識のグルーヴへと誘う一曲。
8. In the Distance Lies the Future
静謐なインストゥルメンタル。アンビエント的浮遊感と**“余白の美学”**が絶妙で、永遠に終わらない時間を描くような余韻を残す。なお、初出時はCDのみ収録で、のちにアナログ再発で補われた。
総評
『Rite Time』は、Canという存在が10年の沈黙を経て、“再生”ではなく**“再開”を選んだアルバム**である。かつての混沌や暴力性は影を潜め、代わって浮かび上がるのは成熟と沈静、そして言葉にならない対話である。
ムーニーの復帰は単なる懐古ではない。“声”というより“気配”のようにサウンドへ溶け込み、音楽はよりいっそう音と空間の関係へとシフトする。老いではなく、深まりとしてのCan。その美学は静かで深い地平に到達しているのだ。
目立たない一枚だが、その静けさと深度ゆえに、最も耳を澄ませるべきアルバム。“語られなかった時間”を音にするというテーマにおいて、本作はバンドの最終回答なのかもしれない。
おすすめアルバム(5枚)
-
Can – Future Days (1973)
静寂と時間性の極致。『Rite Time』の精神的前身にあたる名作。
-
Talk Talk – Laughing Stock (1991)
ロックの語法を脱構築し、静けさと空間性に至った金字塔。精神性が酷似。
-
David Sylvian – Secrets of the Beehive (1987)
詩的な語りと沈黙の美学。『Rite Time』同様、深い余韻を残す。
-
Holger Czukay – On the Way to the Peak of Normal (1981)
チューカイの幽玄なソロ。『Rite Time』と対照で聴くと発見が多い。
-
Bark Psychosis – Hex (1994)
“ポストロック”の起点とされる傑作。Canが拓いた空間美学を継承。
制作の裏側(Behind the Scenes)
『Rite Time』のセッションは1986年12月、南フランス・ニース近郊のOuter Space Studioで実施。1988年にCan-Studio(ヴァイラーズヴィスト)でミックス、1989年にホルガー・チューカイのラボで編集を経て、1989年後半にリリースされた。再結成の要はマルコム・ムーニーのカムバックで、初期の粗削りな衝動を“静かに成熟させる”というコンセプトが貫かれている。
なお、「In the Distance Lies the Future」は初出時CDのみの収録で、後年のアナログ再発で追補された。
訂正注記(任意で記事末に追記)
【訂正】本文中に“ダモ鈴木の復帰”とありましたが、正しくはマルコム・ムーニーの復帰でした(2025年9月5日修正)。
参考(編集メモ)
-
『Rite Time』は再結成作かつ最終スタジオ作。ヴォーカルはマルコム・ムーニー。
-
録音:1986年12月/Outer Space(南仏ニース近郊)、ミックス:1988年/Can-Studio(独)、編集:1989年/Holger’s Lab。
-
「In the Distance Lies the Future」は初出時CDのみ、2014年のアナログ再発でLPにも収録。
-
なお、ダモ鈴木は本作に参加していない(本人インタビューでも不参加を明言)。




コメント
aiさんにも間違いはあるものです。rite timeにはダモ鈴木は参加しておりません。voはマルコムムーニーです。確認して下さい。
ご指摘ありがとうございます。修正しました。