
発売日: 2011年1月24日
ジャンル: インディー・ロック、パワーポップ、ローファイ
概要
『Cloud Nothings』は、アメリカ・オハイオ州出身のバンド、Cloud Nothingsが2011年にリリースしたセルフタイトルのフル・アルバムである。
この作品は、当時まだ19歳だったフロントマン、**ディラン・バルディ(Dylan Baldi)**のDIY精神が反映された音楽性を一歩進め、より洗練されたサウンドと“バンドとしての統一感”を強調する作品となった。
前作にあたるコンピレーション『Turning On』では、宅録ローファイの魅力と青春の疾走感が高く評価されたが、本作では初めてスタジオでのプロデューサー(Chester Gwazda)との協働により、よりクリアで勢いのあるサウンドを獲得。
その一方で、ティーンエイジャー特有のエネルギー、未成熟な感情、そして一抹の不安定さはしっかりと保持されており、Cloud Nothingsの初期衝動を“形”として封じ込めた作品と言える。
ジャンルとしては、インディー・ロックやパワーポップ、ポスト・パンクを土台としながら、90年代以降のWeezer、The Get Up Kids、Wavves、Jay Reatardらに影響を受けたサウンドが色濃い。
ローファイの美学を持ちつつも、パンキッシュでキャッチー、かつ時折メロウなメロディを聴かせるそのスタイルは、2010年代初頭のUSインディーの象徴のひとつとして機能している。
全曲レビュー
1. Understand at All
オープニングから飛び込んでくるキラキラとしたギターと跳ねるようなビート。
「理解されないこと」への怒りと焦燥を吐き捨てるようなヴォーカルが乗ることで、まさにバンドの出発点を象徴する楽曲となっている。
疾走感とパワーポップの融合が見事。
2. Not Important
軽快なリズムとノイジーなギターの対比が印象的。
自己無価値感というティーンらしいテーマを、甘酸っぱさを帯びたメロディで包み込む構造が、絶妙な感情のバランスを生んでいる。
3. Should Have
リバーブのかかったギターとゆったりめのテンポで始まるが、次第に高揚していく構成。
歌詞には後悔と反省のニュアンスが漂い、Cloud Nothingsの内省的な側面が表れている。
4. Forget You All the Time
エモやポップパンクにも通じる反復メロディが耳に残る名曲。
タイトルの通り、忘れようとしても忘れられない感情が滲み出ており、10代の終わりにある“関係性の断絶”を主題にしている。
5. Nothing’s Wrong
ノイジーなイントロから突入する、非常にエネルギッシュな楽曲。
「間違ってることなんてない」と叫ぶようなトーンが、逆説的に不安定さや迷いを浮かび上がらせる。
まさに“叫ぶことで自我を保つ”ロックの王道。
6. Heartbeat
コンパクトながらもパンチのあるサウンドが展開され、メロディとラウドネスのバランスが絶妙。
心臓の鼓動と恋愛感情を重ねる直喩が、ティーン・ロックの王道感を演出している。
7. Rock
タイトル通り、ベーシックなロックへの愛を込めたような直球トラック。
90年代オルタナティヴ・ロックやグランジの要素も垣間見え、Cloud Nothingsのルーツが垣間見える。
8. You’re Not That Good at Anything
自己嫌悪と怒りの混合物のようなリリックが、疾走するサウンドに乗って炸裂する。
皮肉とユーモアが入り混じった歌詞は、同時代のFIDLARやWavvesとも共通する感覚。
9. Been Through
ややメロウで哀愁漂う一曲。
これまでの疾走感の中に、ふとした“沈黙”が挟まれることで、アルバムに緩急が生まれている。
ティーンの喪失感を静かに描写。
10. On the Radio
アルバムのクロージングにふさわしい、明快でポップなロック・ソング。
ラジオで流れるような自分の音楽、という願望と諦念が交錯する。
セルフタイトルらしい“バンドの自己像”を表したような締めくくり。
総評
『Cloud Nothings』は、バンドのキャリアにおける**“ピュアな原点”であり、10代の感情を生々しいままパッケージングしたアルバムである。
粗削りで、構造もシンプルだが、そこに宿る直情的な美学とDIY精神**こそが、Cloud Nothingsを特別な存在にしている。
この作品では、まだスタジオ・プロダクションの技術やサウンドデザインは発展途上だが、それがむしろ**“親密でリアルな響き”**を生み出しており、聴き手に直接触れるような生々しさがある。
ポップパンク的な要素をインディー・ロックの文脈で再構築したそのアプローチは、同時期のBest CoastやJapandroidsらとも通じる潮流を持つ。
本作はCloud Nothingsの後に続く**『Attack on Memory』(2012年)での劇的な変化の“前夜”**であり、バンドがどのようにしてノイジーで激情的なサウンドへと移行していったのかを知る上でも、極めて重要な一枚である。
おすすめアルバム(5枚)
- Cloud Nothings – Attack on Memory (2012)
次作にして転機。エモ/ポストハードコア的な爆発力を獲得。 - Wavves – King of the Beach (2010)
ローファイ×サーフロックの代表作。Cloud Nothingsと同時代の空気を共有。 - Japandroids – Post-Nothing (2009)
ギターとドラムだけで爆発する青春ロック。Cloud Nothingsの衝動と重なる。 - The Get Up Kids – Something to Write Home About (1999)
エモとポップの理想的な融合。バルディのメロディ感に影響を与えた可能性大。 -
Weezer – Pinkerton (1996)
オルタナ的自意識とメロディの衝突。“やさぐれたポップ”としての原型。
制作の裏側(Behind the Scenes)
このアルバムは、ボルチモアにあるChester Gwazdaの自宅スタジオにて、わずか1週間足らずでレコーディングされたという。
バルディ自身がほとんどの楽器を演奏しつつも、ライヴ感を出すために複数トラックを重ね、ミキシングはあえて“完璧すぎない”仕上がりにしたという。
プロデューサーのGwazdaは、Dan Deaconとの仕事でも知られ、ローファイとハイファイの境界線を崩すような録音哲学を持っており、その美学が本作にも色濃く反映されている。
すべてが音響的に整っていなくても、“その場にしかない瞬間”を記録することが、このアルバムの最大の価値であり、Cloud Nothingsというバンドの初期理念だったのだ。



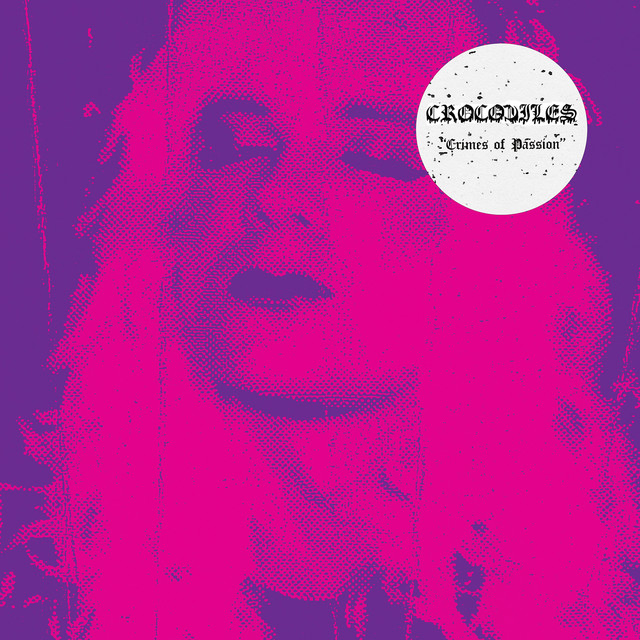
コメント