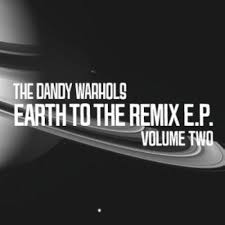
発売日: 2008年11月18日
ジャンル: リミックス、エレクトロニカ、オルタナティブ・ロック、スペース・ディスコ
概要
『…Earth to the Remix EP』は、同年にリリースされたアルバム『Earth to the Dandy Warhols』からの楽曲を中心に再構築したリミックスEPであり、バンドの実験的精神とダンスミュージックへの関心が交差した“音響的再編成”である。
The Dandy Warhols自身が設立した自主レーベル「Beat the World」からリリースされ、インディペンデントな制作環境のもと、“地球から宇宙へ”というテーマをより抽象的かつ感覚的に押し広げた一作となっている。
このEPでは、複数のアーティストによるリミックスが収録されており、エレクトロニカ、IDM、スペース・ディスコ、トリップホップなど、元楽曲にはなかった解釈やリズム処理が施されている。
バンドの音楽を“素材”として見ることのできる作品であり、Dandy Warholsという存在そのものが「ロックとエレクトロの間にある脱構築的存在」であることを改めて印象づける内容である。
全曲レビュー
※以下、代表的なリミックス楽曲を中心に解説。
1. The World Come On (Robert Anthony Remix)
原曲のスロウで浮遊感あるグルーヴを、ビートを強調したスペース・ディスコ風アレンジに変換。
クラブでも映える、反復性と恍惚感のある仕上がり。
2. Mission Control (Tiodo Remix)
緊張感あるインダストリアル風サウンドに再構築。
ロボット的なビートとエフェクト処理が、“コントロール中枢”というテーマを鋭く描き出す。
3. And Then I Dreamt of Yes (Captain Synapse Remix)
原曲のドリーミーな質感を保ちつつ、トリップホップ的なローファイ・リズムで展開。
夜の都市に似合う、内省と陶酔を同居させたリミックス。
4. Wasp in the Lotus (Acid Remix)
アシッド・ハウス風に再構築され、シンセラインとベースの連打がトランス的な陶酔を誘う。
“蓮に潜む蜂”という不穏さが、音の上でも物理的に感じられる。
5. Love Song (Electronic Sunset Mix)
エレクトロニックで温かみのある音像に変化し、原曲のシニカルさがややロマンティックに変容。
日没後の都会の光景が浮かぶようなアレンジ。
総評
『…Earth to the Remix EP』は、The Dandy Warholsというバンドの楽曲がいかに解体・再構築に耐えうる柔軟性と素材力を持っているかを証明する作品である。
オルタナティブ・ロックに分類されがちな彼らの音楽は、実際には構造・美学ともに“ポップの境界線”を滑走する多面的な存在であり、その楽曲を異なる解釈で展開することで、原曲とはまた異なる情景や感情が浮かび上がってくる。
本作は単なるリミックス集ではなく、“音のサイエンス・フィクション”とも言える拡張空間である。
宇宙的というよりはむしろ内宇宙的な旅路として、Dandy Warholsという宇宙船がどこまで飛んでいけるのか、その試験飛行のような作品とも言えるだろう。
おすすめアルバム(リミックス系)
- Radiohead / TKOL RMX 1234567
原曲の複雑さと電子音楽の再構成が共通。音楽の素材的価値を引き出す手法が近い。 - Beck / Guerolito
ベックのアルバム『Guero』の全曲リミックス盤。ジャンルを超えた多様性が魅力。 - Massive Attack / No Protection
トリップホップの名盤『Protection』をMad Professorが全編ダブ化した異色作。 - Nine Inch Nails / Y34RZ3R0R3M1X3D
インダストリアルとエレクトロの間を漂う多様なリミックスの集合体。 - UNKLE / Self Defence (Never Never Land Reconstructed and Bonus Beats)
エレクトロニカ×ロック×映画的サウンドのリコンストラクション。
制作の裏側
このEPは、バンドの自レーベル「Beat the World Records」からの初期配信作品のひとつとして、デジタル配信を中心とした流通戦略の試金石としても機能していた。
制作は主にバンドのポートランド拠点で行われ、一部のリミックスには当時ローカル・シーンで活動していたプロデューサー陣やクラブDJが参加。
また、アートワークやトラックタイトルの表記方法からも、Dandy Warholsらしいカオティックかつ美学的なDIY精神が徹底されている。
このEPを通して、彼らは“音楽そのものを遊ぶ”という姿勢をより開放的に示したのだった。


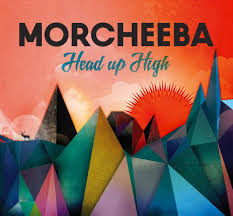
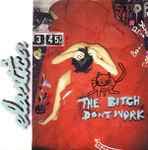
コメント