ロックとジャズ、さらには東洋音楽の要素までをも融合し、1970年代初頭の音楽シーンで鮮烈な衝撃をもたらしたバンド、それがMahavishnu Orchestraである。
鬼才ギタリスト、ジョン・マクラフリンのリーダーシップのもと、複雑なリズムと激しいアンサンブルを自由自在に駆使し、聴く者の耳を一瞬で釘付けにする超絶技巧を披露してきた。
トニー・ウィリアムスのバンドやマイルス・デイヴィスの革新的アルバム群への参加を経て、マクラフリンが確立した独特の音楽観は、ファンクやロック、インド古典音楽、さらにはクラシックの香りまで含み込む懐の深さを持つ。
本稿では、そんなMahavishnu Orchestraの結成背景から代表作、影響関係、そしてその後の展開を丁寧にひも解いてみたい。
結成の経緯と背景
ジョン・マクラフリンはイギリス出身のギタリストであるが、1969年頃より渡米し、ジャズ・ドラマーの巨匠トニー・ウィリアムスが率いるThe Tony Williams Lifetimeや、マイルス・デイヴィスの作品群(『Bitches Brew』や『In a Silent Way』など)に参加し、その名を一気に知らしめた。
特にマイルスのエレクトリック・ジャズ路線は、ロックの大きな音量やエネルギー、電子楽器の可能性を積極的に取り込んだことで当時非常に注目を浴びていた。
このエクスペリメンタルな現場を経験したマクラフリンは、「さらに先鋭的でスピリチュアルなサウンドを生み出すバンドを作りたい」という思いを強く抱くようになる。
やがて彼はヴァイオリン奏者のジェリー・グッドマン、キーボード奏者のヤン・ハマー、ベーシストのリック・ラーアド、ドラマーのビリー・コブハムというメンバーを集め、1971年にMahavishnu Orchestraを結成した。
このメンバーはいずれも技巧派として知られ、ジャズやクラシック、ロックなど多様なルーツを持ち合わせていた。
マクラフリン自身はインド音楽の要素を取り込んだフレージングを志向し、精神的にも東洋思想に傾倒していたことから、バンド名には“偉大なる宇宙の存在”を意味する「マハヴィシュヌ」という言葉を冠することを選んだのである。
音楽性――ジャズ、ロック、そして東洋音楽の融合
Mahavishnu Orchestraの最大の特徴は、ジャズのインプロビゼーションとロックのエネルギッシュなビートを融合した“ジャズ・ロック”や“フュージョン”と呼ばれるスタイルを確立した点にある。
しかしながら、そのサウンドには単なるジャズやロックの枠におさまらない、より広範な要素が染み込んでいる。
まずは、マクラフリンが得意とするインド古典音楽のスケールやリズム概念。
例えば、奇数拍子を多用した複雑なリズム構成や、ラーガ的なメロディ展開は当時のロック・シーンでは斬新であり、強烈な印象を残した。
さらにジェリー・グッドマンのエレクトリック・ヴァイオリンやヤン・ハマーのシンセサイザーが空間的で躍動感のある音色を加え、ビリー・コブハムのパワフルかつ正確無比なドラミングが土台を固めることで、アンサンブルは疾風のごときテンションを維持したまま進行していくのだ。
代表曲とその聴きどころ
初期Mahavishnu Orchestraの代表曲としては、デビューアルバムに収録された「Meeting of the Spirits」や「The Dance of Maya」が挙げられる。
「Meeting of the Spirits」はまさにバンドの名刺代わりともいえる一曲で、冒頭の激烈なギターとヴァイオリンのユニゾンフレーズから一気に聴き手を異次元へ連れ去ってしまう。
また、「The Dance of Maya」はブルース調のリフが不意に奇数拍子へと変化し、さらにリズムとコードがめまぐるしく変容する構成が際立っている。
二作目のスタジオアルバムに収録された「Birds of Fire」も有名で、切れ味鋭いリフに乗せて圧倒的な合奏力とソロ回しが展開される。
どちらの楽曲にも共通するのは、“音の嵐”とも呼べるほどスリリングなインタープレイと、静と動を巧みに織り交ぜたダイナミズムである。
アルバムごとの進化
The Inner Mounting Flame(1971年)
記念すべきデビューアルバムであり、ジャズ・ロック/フュージョンの金字塔として名高い一枚である。
前述の「Meeting of the Spirits」「The Dance of Maya」をはじめ、アルバム全体にわたって超絶技巧と高密度のアンサンブルが貫かれている。
強烈なリフとインド的な旋律が織りなす世界は、当時としては革新的かつ挑発的とすら言え、多くの音楽ファンを熱狂させた。
Birds of Fire(1973年)
前作の勢いをそのままに、さらなるスケールアップを遂げた印象を与えるアルバム。
タイトル曲の「Birds of Fire」や「Sapphire Bullets of Pure Love」など、過剰ともいえるほどのスリリングな演奏が次々に飛び出す。
同時に楽曲構成の緻密さも増し、レコーディング技術の向上も相まってバンドの魅力をダイレクトに伝えてくれる仕上がりとなった。
Between Nothingness & Eternity(1973年)
こちらはライブ盤であり、壮絶なテンションを保つバンドの生々しい姿が収められている。
スタジオ音源では捉えきれない長尺のインプロビゼーションや、観客の熱気を背景にしたメンバー同士のレスポンスが聴きどころ。
まるで嵐の中で踊っているかのような、怒濤のパフォーマンスが詰まっている一枚である。
解散と再編――Apocalypse(1974年)以降
初期ラインナップでの活動は、メンバー間の意見衝突やツアーによる過酷なスケジュールが重なり、1973年に解散へと至る。
しかし、マクラフリンは新メンバーを迎えてバンドを再編し、1974年には名プロデューサーであるジョージ・マーティンと組んで_Apocalypse_を発表。
ここではオーケストラを大胆に導入し、より交響的で深みのあるフュージョンサウンドが展開されている。
以降も編成を変えながら数枚のアルバムをリリースしているが、初期の強烈なインパクトを超える作品は生まれにくかったという評価もある。
影響を受けたアーティストと音楽的背景
リーダーのジョン・マクラフリンが強く影響を受けていたのは、インド古典音楽やタブラ奏者のザキール・フセイン、さらにマイルス・デイヴィスやジョン・コルトレーンといったモダン・ジャズの巨人たちである。
特にコルトレーンのスピリチュアルかつ高密度な演奏や、マイルスのエレクトリック期の実験精神が、マクラフリンの音楽観を大きく形作った。
また、ドラマーのビリー・コブハムはファンクやラテン音楽にも通じており、ジェリー・グッドマンはクラシック教育を受けた上でロックのバンドにも在籍していた。
こうした異なるバックグラウンドの音楽家が集まったことが、Mahavishnu Orchestraの多層的で爆発的なサウンドを生み出す原動力となったのだ。
後世のミュージシャンへの影響
1970年代初頭のフュージョン・シーンには、ウェザー・リポートやリターン・トゥ・フォーエヴァーなど、多くの才能が集結し、それぞれが独自の個性を発揮していた。
その中でもMahavishnu Orchestraの存在は特に鮮烈であり、ジェフ・ベックやカルロス・サンタナなどのギタリストをはじめ、無数のロック/ジャズ系ミュージシャンに強いインスピレーションを与えた。
さらにプログレッシブ・ロックの領域でもキング・クリムゾンやジェネシスなどが、変拍子や高い演奏技術を伴う実験的なアプローチを採り入れる上で、Mahavishnu Orchestraの革新性をひとつのモデルとして意識していたとも言われている。
また、80年代以降のギター・ヒーローと呼ばれる存在(スティーヴ・ヴァイやジョー・サトリアーニなど)も、マクラフリンが見せた超絶技巧や即興性、そしてメロディの運び方に影響を受けたことをしばしば公言している。
ビリー・コブハムのドラミングは、プログレメタルなどのジャンルに通じるパワフルかつ複雑なビートの原型ともいわれ、幅広い音楽シーンに種をまいた結果となった。
オリジナルエピソードと逸話
- バンド結成当時、マクラフリンは自らの精神世界を深めるため瞑想やヨガを実践し、スリランカ出身の思想家スリ・チンモイの教えを熱心に学んでいた。 その影響からか、ライブでも“慈愛”や“瞑想”といった概念を演奏のモチーフとして掲げることが多かったという。
- Mahavishnu Orchestraのリハーサルは異常なほどストイックに行われ、音数の多いリフやメロディをメンバー全員が正確に合わせるため、何時間にもわたって同じフレーズの繰り返し練習が続いたとされる。 これがメンバー間の緊張を生んだ一因でもあった。
- バンド名“Mahavishnu”は、ヒンドゥー教における最高神の一つ“ヴィシュヌ”を示唆する言葉であり、“偉大なるヴィシュヌ”という意味合いを持つ。 マクラフリンがインド音楽を取り込むだけでなく、精神性そのものをサウンドに反映させようとしていた証左でもある。
まとめ
Mahavishnu Orchestraは、ジャズとロックを土台としながらインド古典音楽の神秘やクラシックの重厚さを盛り込み、新たな音楽ジャンルの地平を切り開いたバンドである。
1970年代初頭という時代背景の中で、メンバーそれぞれの類い稀なテクニックを惜しみなく投入し、驚異的なスピード感と緻密なアンサンブルを両立させたのは前人未到の快挙だったといってよい。
解散や再編を繰り返したため、活動期間は決して一枚岩ではなかったが、その遺した作品群は今なおフュージョンやプログレッシブ・ロック、さらにはワールドミュージックのファンに至るまで、多くのリスナーから深いリスペクトを集めている。
まるで激流のように流れる変拍子や、燃え上がるギターとヴァイオリンの掛け合い、そしてビートを突き破っていくドラムのフィル――これらは一度体験すると忘れられない衝撃を刻み込む。
仮に今の耳で聴いても、革新的という言葉では足りないほどのエネルギーを感じられるのがMahavishnu Orchestraの最大の魅力だろう。
その音楽は、時代を超えて新たな表現へと昇華され続ける可能性を秘めている。
結成から半世紀以上が経過した今でも、彼らの作品は音楽史の中で輝き続け、これからも多くの挑戦者たちに刺激を与え続けるに違いないのだ。



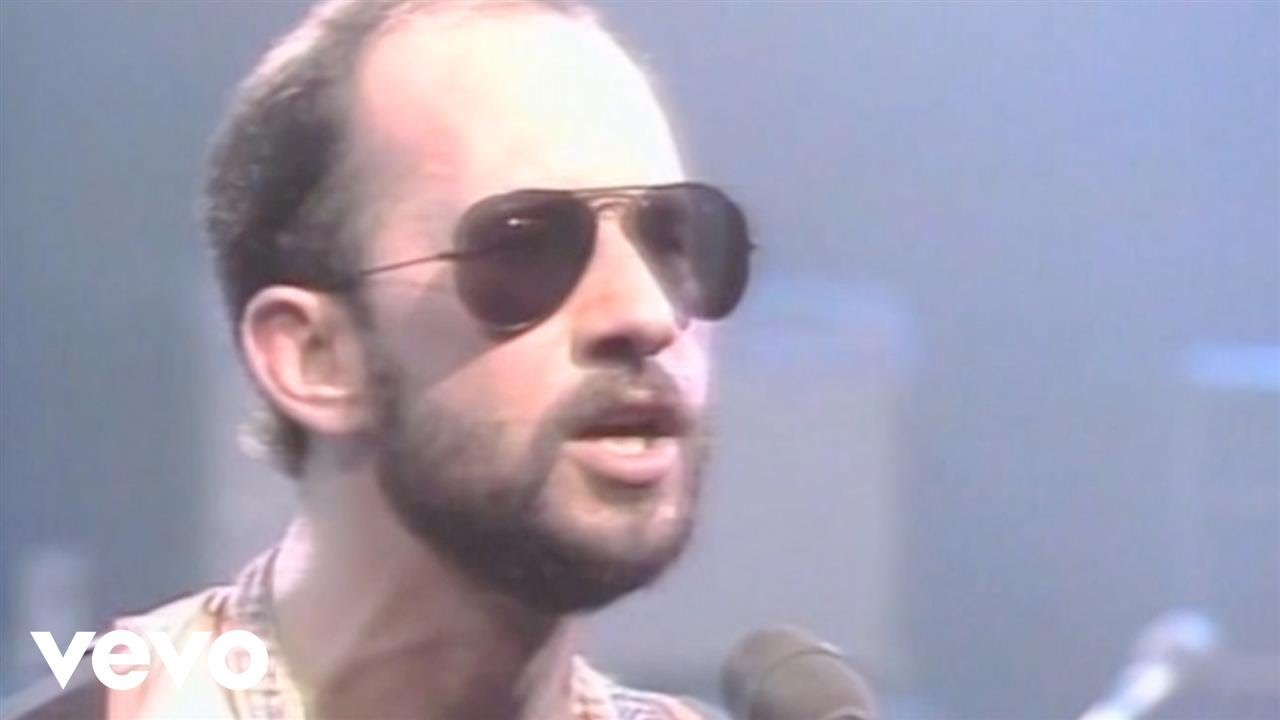

コメント