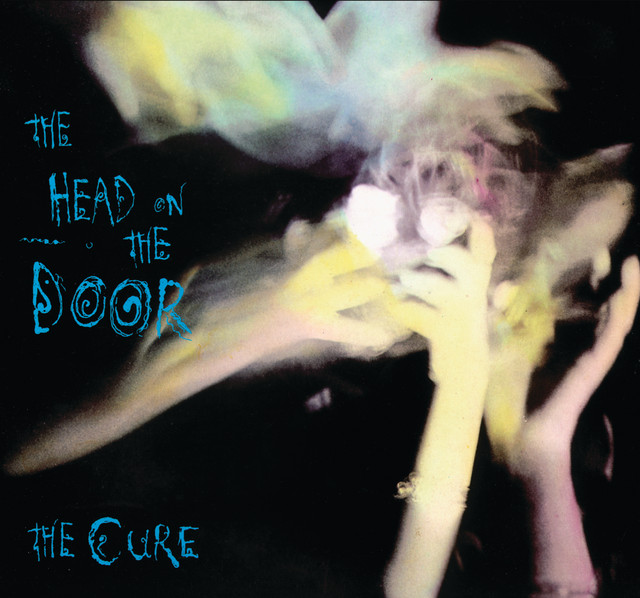
発売日: 1985年8月26日
ジャンル: ポストパンク、ニューウェイヴ、オルタナティヴ・ロック
色彩と混乱のポップ・サイケデリア——“扉の中の頭”が覗いた世界
The Head on the Doorは、The Cureにとって大きな転機となる6作目のスタジオアルバムである。
前作The Topで極度の個人性と実験性を追求したロバート・スミスは、本作で“ポップと混沌”のバランスを取り戻し、より広いリスナー層に訴える作品へと舵を切った。
この作品では、ゴシックな重苦しさだけでなく、ラテン、スペイン民謡、ダンサブルなニューウェイヴ、バロック的メロディといった多彩な要素が混在している。
だが、その多様性は決して雑然とせず、むしろ“精神のカラフルな断片”として統一感を持ち始めている。
タイトルの“扉の上にある頭”という不気味なイメージも、スミスの不安定な精神状態と創作欲のメタファーとして機能しており、
不安定さこそが彼らのポップである、という宣言のようなアルバムだ。
全曲レビュー:
1. In Between Days
アルバムの幕開けにして、キャリアを代表する名曲。
疾走感のあるアコースティック・ギターとシンセが織りなす、カラフルでどこか切ないメロディ。
「君を失ってしまった」と繰り返す歌詞は、明るさの中に確かな痛みを抱えている。
2. Kyoto Song
東洋的なスケール感と変拍子を取り入れた、実験的なナンバー。
夢の中の殺人、血、愛——スミスの内的恐怖が、幻想的な映像として表現されている。
3. The Blood
スペイン風のギターとラテンリズムが特徴的。
情熱的な旋律に反して、歌詞では暴力や裏切りといった暗い感情が語られる。
異国の風景が、むしろ内面の逃避を示しているようだ。
4. Six Different Ways
トイピアノのような音色とワルツ調のリズムが、童話のような不気味さを醸す。
タイトル通り、六通りの物語を同時に語るようなメタ構造をもつ、不思議な一曲。
5. Push
インストゥルメンタルのように長く引き伸ばされたイントロから始まる、ギター中心の爽快なナンバー。
歌詞は抽象的でありながら、若さの焦燥と衝動が滲み出てくる。
6. The Baby Screams
ニューウェイヴ的なビートとシンセが前面に出た、クラブ感のあるアップテンポ曲。
だがタイトルの通り、その高揚感の裏には混乱や苦悩が叫びとして潜んでいる。
7. Close to Me
本作の中でも最もポップでありながら、最も不安定な名曲。
ミュートされたホーン、軽快なリズム、耳元でささやくようなヴォーカルが、強迫観念的な親密さを描き出す。
「君が近すぎて呼吸ができない」と歌うその声は、愛と恐怖の境界にある。
8. A Night Like This
サックスが鳴り響く、80年代のフィルムノワールのようなムードを持つ楽曲。
失った恋と過去の幻影を抱えながら、それでも前に進もうとする哀愁が印象的。
9. Screw
変拍子とファンク的ベースがうねる、実験的でアグレッシブなナンバー。
歪んだエフェクトとラフなアレンジが、“壊れかけた理性”のように響く。
10. Sinking
アルバムのクロージングにふさわしい、沈んでいくようなスロウバラード。
「私は沈んでいる」と繰り返される中で、救いも絶望も提示されないまま曲は終わる。
それでも、その静けさが美しい。
総評:
The Head on the Doorは、The Cureが“暗さ”から“多様性”へと舵を切ったアルバムである。
ポストパンクやゴシックロックの系譜にありながらも、本作ではジャンル横断的なポップ性と音楽的実験が溶け合い、バンドの表現力が一気に開花している。
これは単なるヒットを狙った作品ではなく、カラフルな感情の断片を丁寧に編んだ、ロバート・スミスの脳内日記のようなアルバムだ。
“頭の中の扉”を開いた時、そこに広がるのは狂気ではなく、驚くほど繊細で美しいパレットだった。
The Cureというバンドの可能性が一気に拡張された、歴史的な一枚である。
おすすめアルバム:
-
New Order / Low-Life
ポストパンクとダンスの融合、80年代の光と影。 -
Echo & the Bunnymen / Ocean Rain
耽美でオーケストラルなポストパンクの傑作。 -
XTC / Skylarking
ポップと幻想の同居する、完璧なアートポップ作品。 -
The Smiths / The Queen Is Dead
同時代の英国ロックを代表する、皮肉と哀愁の名盤。 -
The Cure / Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me
本作の延長線上でさらにスケールを拡張した、ジャンル無差別級アルバム。


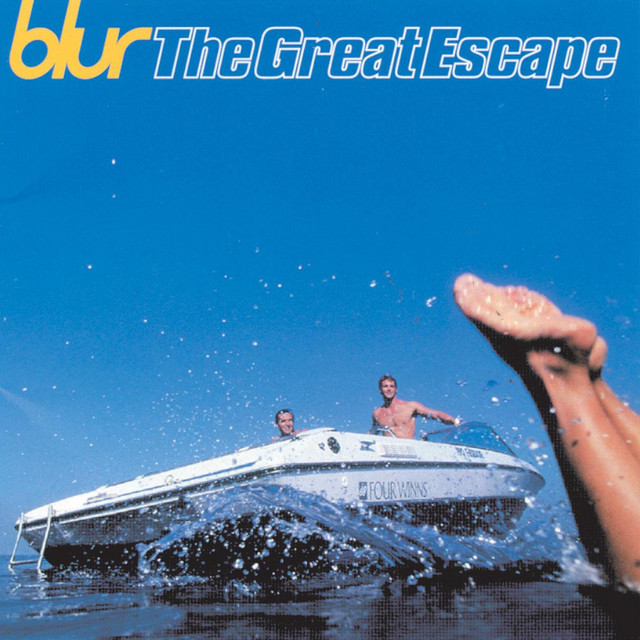
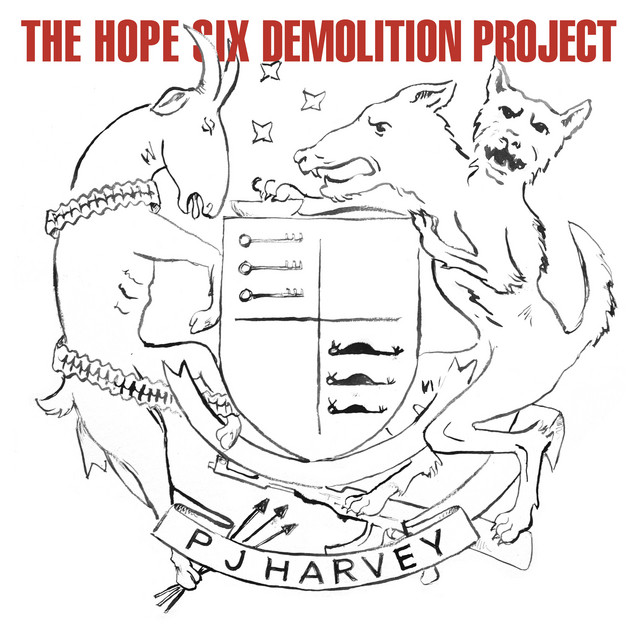
コメント