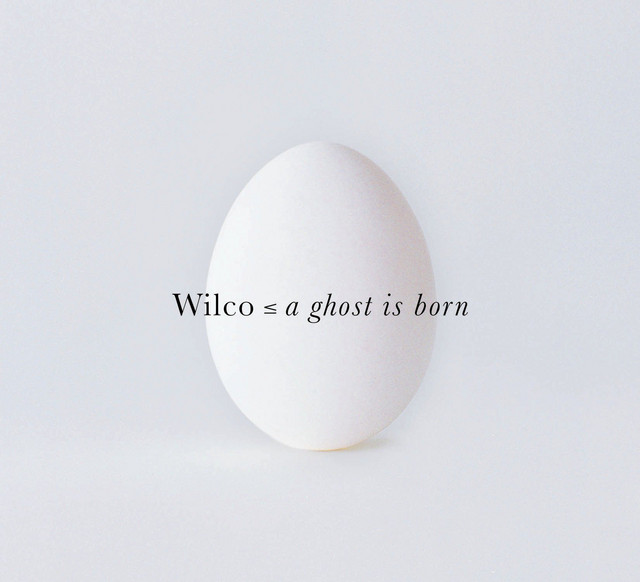
発売日: 2004年6月22日
ジャンル: オルタナティヴ・ロック、アートロック、インディーロック
不安と知性の音響空間——“ゴースト”としての自己をめぐる実存的アルバム
Yankee Hotel Foxtrotという前作で、Wilcoは「実験とポップの融合」という難題を成功させ、00年代オルタナの象徴的存在となった。
その次作として発表された本作A Ghost Is Bornでは、バンドのフロントマンであるジェフ・トゥイーディが、より内面に、より孤独に、そしてより“音”そのものに向き合っている。
このアルバムには、旋律的な親しみやすさと、断続的なノイズ、静寂、不安定さが共存しており、それはまさに“亡霊=ghost”という曖昧で触れがたい存在の比喩でもある。
ジェフ・トゥイーディはリリース直前に薬物依存の治療に入るが、その揺れ動く精神状態と音楽的実験精神は、アルバム全体に張り詰めた空気として染み込んでいる。
ピアノ、ギター、ドローン、ノイズ——そのすべてが「曲」よりも「状態」を描き出すような、極めてモダンでアーティスティックな作品である。
全曲レビュー
1. At Least That’s What You Said
静謐なピアノとヴォーカルで始まり、突如ギターが爆発する冒頭曲。
ジェフの不安と焦燥が、音のダイナミズムで描かれる。
沈黙とノイズのコントラストが象徴的。
2. Hell Is Chrome
クローム(メタリックな光沢)に擬された地獄の誘惑を歌うスロウテンポな曲。
静かに進行するコード進行と、歌詞のメタファーが相まって不穏な美しさを生む。
3. Spiders (Kidsmoke)
10分におよぶ反復とビートの進行。
クラウトロックの影響を思わせる構成で、“Kidsmoke”という曖昧な存在が都市の喧騒を象徴するようでもある。
4. Muzzle of Bees
アコースティック・ギター主体のフォーク風楽曲。
抽象的な歌詞と柔らかな旋律が、日常の隙間にある孤独を浮かび上がらせる。
5. Hummingbird
ビートルズ的なコード進行とポップセンスが光る楽曲。
幻想的なピアノと浮遊感あるメロディが、“ghost”の軽やかさを感じさせる。
6. Handshake Drugs
薬物依存を暗喩する歌詞と、ローリングするリズム。
ポップと狂気が共存し、トゥイーディの自己告白的なリアリズムが刺さる。
7. Wishful Thinking
まるで夢の中の会話のような詩的なリリックと静かなアレンジ。
希望と諦めが交錯するような余白を感じる。
8. Company in My Back
「背後に誰かがいる」という不安感を歌うミニマルな曲。
不協和音と低音が、聴き手の精神にじわじわ染み込む。
9. I’m a Wheel
突如として加速するガレージ的ロックチューン。
自己否定と衝動が疾走感の中に収められており、唯一の“爆発”ともいえる。
10. Theologians
神学者たちへの皮肉を込めたジェフの問いかけ。
軽快なメロディに反して、歌詞の内容は哲学的で挑戦的。
11. Less Than You Think
約15分のうち、後半の10分はドローンと電子ノイズによる持続音。
精神の麻痺や内的沈黙を描いたような、リスナーを試す曲でもある。
12. The Late Greats
皮肉と愛情に満ちたロックンロール風エンディング。
「最高のバンドは知られていない」という逆説的メッセージが、Wilco自身の姿勢を映している。
総評
A Ghost Is Bornは、Wilcoにとっても、00年代ロック全体にとっても、実験と自己開示が極限まで押し進められた野心作である。
ここには“完成されたポップソング”という概念への懐疑と、それでもなお音楽で語ろうとする衝動が共存している。
アルバムタイトルが示す通り、ここで鳴っているのは“生まれたばかりの亡霊”の声であり、それはトゥイーディ自身の心の中に潜むものかもしれない。
その幽かな輪郭を捉えようとすること——それが、このアルバムを聴くという行為なのだ。
おすすめアルバム
-
Yankee Hotel Foxtrot by Wilco
——ポップと実験のバランスが絶妙な前作。Wilcoの転機を刻んだ名盤。 -
Sea Change by Beck
——メロディと虚無感が融合する、ポスト・ブレイクアップの静謐な傑作。 -
Kid A by Radiohead
——ポップの境界線を越えた実験精神と音響世界が共鳴。 -
I Am a Bird Now by Antony and the Johnsons
——静けさの中に叫びが潜む、魂の告白としてのアートポップ。 -
In Rainbows by Radiohead
——内面性と構築美が共存する、聴くほどに深まる音楽体験。



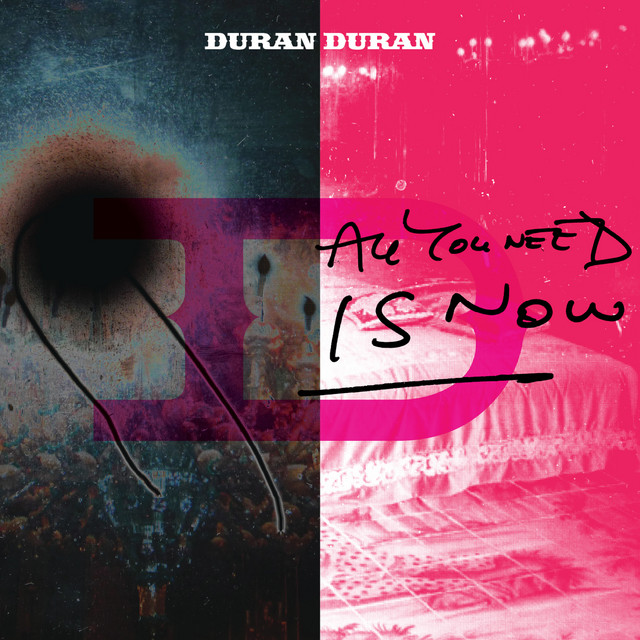
コメント