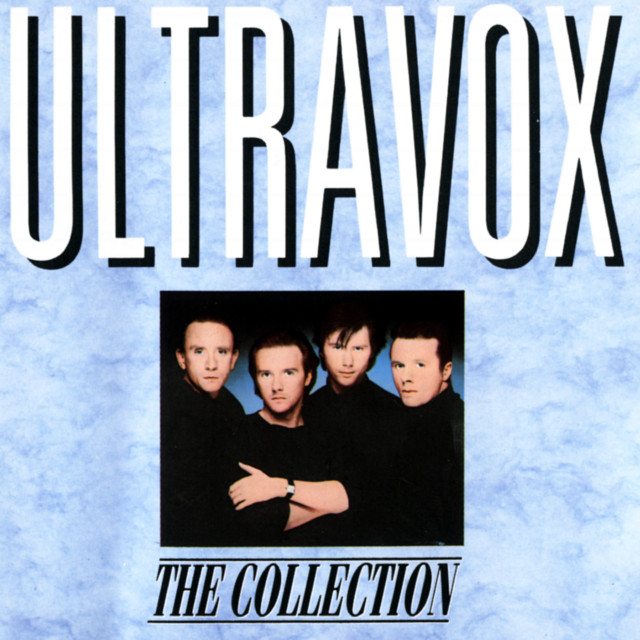
1. 歌詞の概要
Ultravoxの「The Voice」は、1981年にリリースされたアルバム『Rage in Eden』からのシングルであり、Ultravoxの音楽的野心と芸術性を色濃く反映した、象徴性に満ちた作品である。全英シングルチャートでは最高16位を記録し、彼らのシンセ・ポップとニュー・ロマンティックの融合が完成へと向かう重要な楽曲となった。
タイトルの「The Voice(その声)」とは、単なる“音”ではなく、**歴史、権力、信仰、内面の良心といった抽象的概念が発する“声”**として解釈することができる。歌詞は極めて象徴的かつ詩的であり、はっきりとしたストーリーを語るわけではない。しかしその断片的な言葉の連なりからは、命令、鼓舞、あるいは煽動されるような声に人々が従っていく構造が浮かび上がる。
特定の宗教や政治に言及してはいないものの、「その声」はしばしば“力あるもの”が発する威圧的なメッセージであり、人間の理性を超えて群集が動かされていく姿を描いているとも言える。それは、戦争、独裁、メディアといった20世紀の大きな構造と結びついた“集団行動の心理”に関する鋭い洞察でもある。
2. 歌詞のバックグラウンド
1981年にリリースされた『Rage in Eden』は、Ultravoxが『Vienna』の成功を経て、より実験的・抽象的なアプローチに挑戦したアルバムである。「The Voice」はその中心に位置する楽曲であり、ポップソングとしての枠を超え、構造的にもコンセプチュアルな要素を強く持っている。
この時期のUltravoxは、商業的成功と芸術性の狭間で自らのアイデンティティを模索しており、その結果として生まれた『Rage in Eden』は、無機質で冷たいサウンドに、人間的で抒情的なテーマが宿る非常にユニークな作品となった。特に「The Voice」では、ミッジ・ユーロのリードボーカルに加え、荘厳なコーラスと幾層にも重なるシンセサウンドが“声”という抽象概念を音として可視化しようとする意欲が見て取れる。
また、同楽曲のプロデューサーはConny Plank。ドイツのクラウトロック/電子音楽シーンで培われた前衛性と、Ultravoxのヨーロピアンな美意識が融合した結果、ポップとアートの境界を曖昧にする革新的なトラックが誕生した。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に、「The Voice」の印象的な一節を抜粋し、日本語訳とともに紹介する。
And I’m hearing the voice
そして私はその“声”を聞いている
It’s the voice of the silence
それは“沈黙”が発する声
It’s the voice of command
それは“命令”の声
It’s the voice of the past
それは“過去”の声And the voice is the future
その声は、未来でもある
It’s the voice of the one
それは、ただひとつの声
Who will call you to war
あなたを戦争へと駆り立てる声
出典:Genius – Ultravox “The Voice”
4. 歌詞の考察
「The Voice」の歌詞は、断定的な主語や具体的な場面を排除しながらも、「声」という概念にあらゆる象徴性を託している。その“声”は一方的な命令であり、無言の圧力でもあり、過去の記憶であり、未来を決定づけるものでもある。つまり、“声”は権力の隠喩であり、個人を超えて人々を動かしていく支配的構造の象徴なのだ。
「沈黙の声(voice of the silence)」という詩的な表現は、実際には発されていない言葉に従ってしまう群衆心理や、無意識のうちに刷り込まれる社会的メッセージへの警鐘とも読める。そして「戦争へと駆り立てる声(call you to war)」という明示的なフレーズは、その声が決して中立ではなく、破壊と支配を伴うものであることを示唆している。
Ultravoxはこの曲を通じて、「私たちは誰の声に従っているのか?」「その声は、内なる良心か、それとも外からの命令か?」という根源的な問いを投げかけている。それは当時の冷戦下における情報操作や集団行動の問題だけでなく、現代のSNS時代における“アルゴリズムの声”や“群衆の正義”にも通じる普遍的なメッセージとなっている。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Fade to Grey by Visage
無機質なサウンドに込められた存在の希薄さとアイデンティティの問いが、「The Voice」と通じる。 - Being Boiled by The Human League
機械文明と権力構造に対する鋭い批評性を持った、初期シンセ・ポップの傑作。 - Talking Loud and Clear by Orchestral Manoeuvres in the Dark(OMD)
“声”と“沈黙”のあいだを漂う感覚を描いた美しく静謐なエレクトロニック・ラブソング。 - Underpass by John Foxx
都市と声、無名性と存在のテーマを描いたポストモダンなエレクトロ・ポエジー。 -
The Sound of Silence by Simon & Garfunkel
「沈黙が語る声」というテーマの原点的作品。静けさが暴力的なまでに力を持つことを描く。
6. 沈黙が語る「声」——Ultravoxが問いかけた現代の預言
「The Voice」は、Ultravoxのディスコグラフィの中でも最も政治的・哲学的なニュアンスを持った楽曲であり、その音響と構造、詩の力を通じて**“無意識のうちに従ってしまうもの”の恐ろしさ**を浮かび上がらせている。
この曲において“声”とは、宗教でも、国家でも、愛でもない。それはもっと抽象的で、しかし確実に存在する「空気」や「正義」や「流れ」といった名もなき権力である。それに気づかず従ってしまうことこそが、Ultravoxがもっとも危惧した“現代人の姿”であり、その警鐘は今もなお強く響いている。
シンセサイザーの冷たい音像のなかに潜む熱い問いかけ。美しいメロディのなかに忍ばされた鋭利な批評性。「The Voice」は、聴くたびに新しい解釈を誘い、リスナー自身の“声”のありかを探すための鏡となる。Ultravoxはここで、音楽を「問い」に変えることに成功したのである。


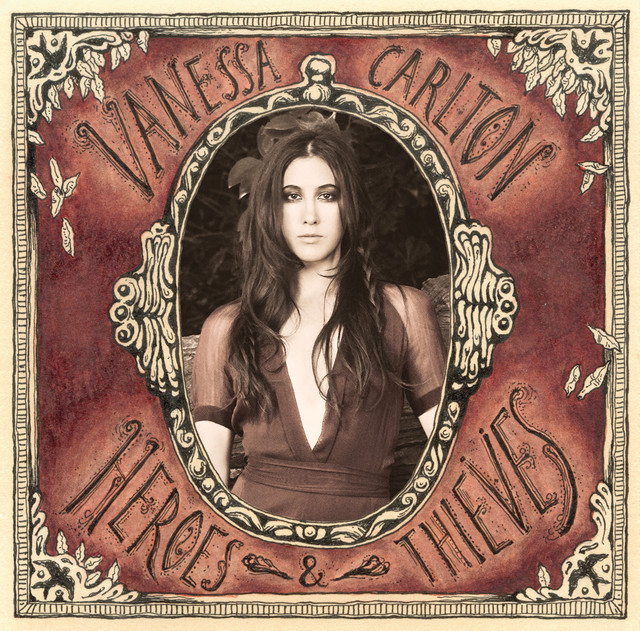
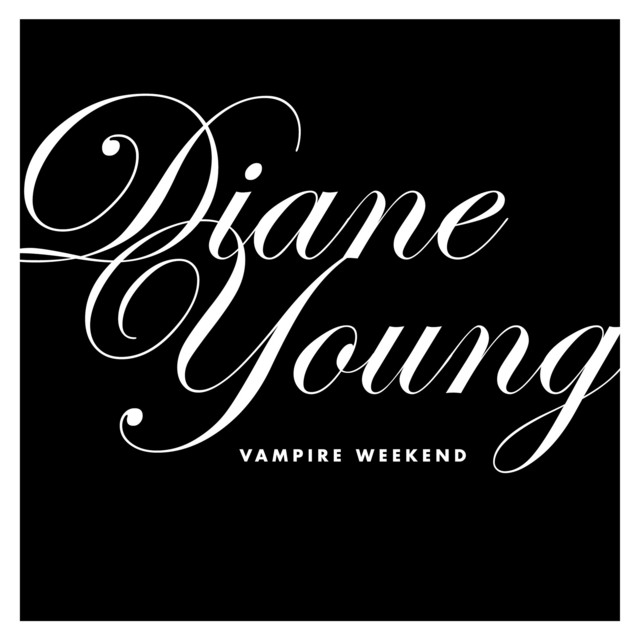
コメント