
1. 歌詞の概要
「Then Came the Last Days of May」は、Blue Öyster Cult(ブルー・オイスター・カルト)のセルフタイトル・デビュー・アルバム『Blue Öyster Cult』(1972年)に収録された楽曲であり、ハードロックやサイケデリック、ブルース、さらにはカントリー的な感触すら漂う異色のバラードである。バンドの激しいイメージとは裏腹に、この曲は静かで内省的な空気をたたえており、その内容は驚くほど現実的で、哀しく、そして衝撃的だ。
楽曲は一人称の語り手が、友人3人の悲劇的な運命を静かに語るストーリーテリング形式で展開する。舞台はアメリカ西部。大学を中退した若者たちが、ドラッグの取引で一攫千金を狙って旅に出るが、最終的には裏切りに遭い、命を落としてしまう――という、実話に基づいた内容が淡々と綴られる。
タイトルの「Then Came the Last Days of May(そして、五月の終わりがやって来た)」は、季節の穏やかな響きとは裏腹に、人生の終焉、青春の終焉、そして無知ゆえの破滅を象徴している。静かなアコースティックギターと囁くようなボーカルによって、この曲はまるで口承のバラッドのように語り継がれるべき物語となっている。
2. 歌詞のバックグラウンド
「Then Came the Last Days of May」は、ギタリストであるBuck Dharma(本名ドナルド・ルーザー)によって書かれた。この曲はフィクションではなく、実際に彼の友人が経験した出来事を基にしており、ドラッグ・カルチャーが若者たちの運命をいかに狂わせるかという現実を描いている。
当時のアメリカでは、1960年代から続いたヒッピー文化や自由な精神が、やがてハードドラッグや犯罪と結びつき、理想から破滅へと変化していく過渡期にあった。Blue Öyster Cultの多くの楽曲が神秘的、オカルティック、哲学的なテーマを取り扱う中で、この「Then Came the Last Days of May」は異彩を放つ、“静かなリアリズム”の結晶である。
この曲はライブでも定番曲として愛され続けており、特にライブバージョンではギターソロが大幅に拡張され、原曲の内省的な空気が、より劇的な情動として演奏に込められていく。Buck Dharmaのギターは、まるで沈黙の中の涙のように、感情の奥底を丁寧に掘り起こす。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に、物語性の強い歌詞の一部を抜粋して紹介する。
Parched land, no desert sand, sun is just a dot
乾いた大地、砂漠ではないが、太陽は小さな点にしか見えないAnd a little bit of water goes a long way ‘cause it’s hot
少しの水でさえ貴重だ、だってあまりに暑いからThree good buddies were laughin’ and smokin’ in the back of a rented Ford
三人の仲間は、レンタカーの後部座席で笑いながら煙をくゆらせていたThey couldn’t know they weren’t going far
彼らは、自分たちの旅がそう遠くには行けないことを知らなかったEach one with the money in his pocket
それぞれがポケットに金を握りしめてAnd each one with the thought: what a funny way
それぞれが心に思っていた――何て馬鹿げたやり方だとTo make a livin’
生きるための手段としては
引用元:Genius Lyrics
4. 歌詞の考察
この曲の核心は、“若者の無知と希望、そして破滅”である。何も知らないままに夢を抱き、世界の仕組みを知らずに危険な取引へと足を踏み入れる三人の若者。その行動は無謀で、無邪気で、そして哀しいほどに現実離れしている。
彼らは未来を信じていた。「ポケットに金を持ち、人生をどうにかするんだ」と。しかしその希望は、“暑さ”と“乾いた大地”という象徴の中で、すでに終わりが予兆されている。
詩の冒頭における「太陽が点でしか見えない」「少しの水も貴重だ」といった描写は、ただの風景ではなく、これから起こる悲劇の比喩でもある。人生のエネルギー源が枯れ、方向感覚を失い、やがて死に辿りつく。
また語り手は、この出来事を“見ていた側”として描かれている。彼は三人の友人の悲劇を回想しており、その語り口は淡々としていながらも、深い悔恨と諦念をにじませている。「彼らは遠くへは行けなかった」という一文には、未来を絶たれた者たちへの鎮魂と、避けられなかった運命への悲しみが込められている。
この曲の偉大さは、そのリアリズムにある。多くのロックソングが“反抗”や“理想”を歌うなかで、「Then Came the Last Days of May」は“現実”を静かに見つめ、語り継ごうとしている。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Down by the River by Neil Young
暴力と喪失をテーマにしたスローな叙情ロックで、静けさのなかに怒りと後悔が溶け込んでいる。 - Needle and the Damage Done by Neil Young
薬物による死を悼むリアリズムに満ちたバラードで、現実を淡々と語る手法が共鳴する。 - Dogs by Pink Floyd
裏切りと社会構造の冷酷さを描いた長編曲で、人生の不可逆的な転落がテーマとして重なる。 - Five Years by David Bowie
終末の予兆を静かに語るバラード。歌詞のストーリーテリングと情感の積層が「May」と似ている。
6. 五月の終わり――青春と死の交差点
「Then Came the Last Days of May」は、Blue Öyster Cultというバンドの表現力の広さを示す重要な一曲である。彼らが得意とする神秘的・宇宙的・象徴的な世界とは異なり、この曲は極めて地に足のついた物語、つまり“私たちにも起こりうる話”を淡々と描いている。
だが、だからこそ怖い。だからこそ美しい。
これは、“夢を信じた若者たち”の鎮魂歌であり、彼らを見送った者たちの悔恨の記録でもある。人生には引き返せない地点がある。知識や経験ではなく、“無知”と“信頼”だけを頼りにした旅の果てに待っていたのは、理不尽で、しかしどこか静かな死だった。
「Then Came the Last Days of May」は、五月のやわらかな光の中に潜む、確かな“終わり”の気配を描いた詩的バラッドである。
それは、青春の影と、無垢ゆえの悲劇を、そっと語り継ぐ歌だ。
そして今もまた、誰かの“最後の五月”が、どこかで静かに始まっているのかもしれない。


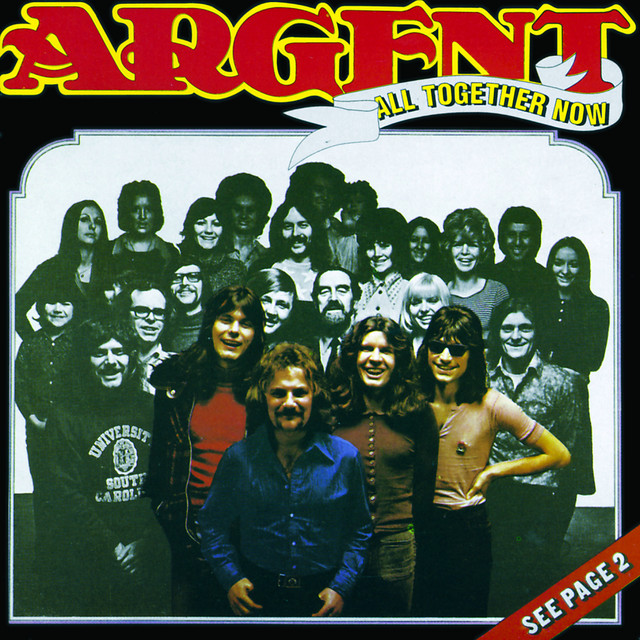
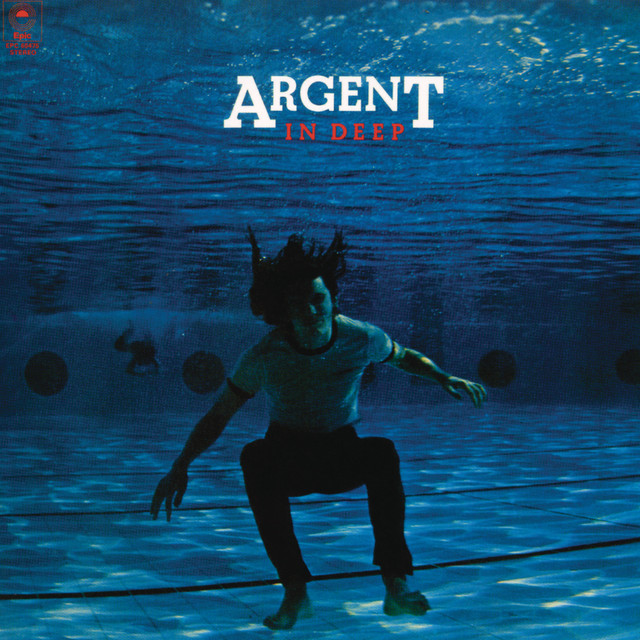
コメント