
1. 歌詞の概要
「The Eton Rifles」は、The Jamが1979年に発表したシングルであり、アルバム『Setting Sons』に収録された社会派ロックの代表作である。歌詞は、イギリスの伝統ある名門校イートン・カレッジ(Eton College)の学生たちを象徴とし、階級社会の不条理と若者の怒りを、鋭い皮肉とともに描いた。
“Rifles”という言葉は、イートン校の予備役軍事訓練部隊「Eton College Rifle Corps」から取られており、エリート教育を受けた若者たちが“模擬戦争”を訓練する姿を通じて、社会の上層と下層の分断を象徴している。一方で語り手は、就職も未来も見えない労働者階級の若者。彼らが不満を抱き、立ち上がろうとするその試みに対して、上流階級の“遊びのような戦い”が冷笑を浴びせる構図が描かれている。
「The Eton Rifles」は、単なるプロテスト・ソングではない。この楽曲の特異性は、“闘うことさえ冷笑される”という、階級社会における不平等の根深さを、痛烈な皮肉として表現している点にある。そしてその皮肉は、怒りを伴いながらも、どこか諦めに近い現実認識として響く。The Jamが社会に対して発したもっとも直接的で、鋭利なナイフのような一曲である。
2. 歌詞のバックグラウンド
「The Eton Rifles」が発表された1979年、イギリスはサッチャー政権の誕生により大きな転換点を迎えていた。労働組合の力が弱まり、社会保障が削減されていく中で、若年層の失業率は急上昇。ポール・ウェラーは、そんな時代の風潮に違和感を覚え、階級社会に対する苛立ちをこの曲に込めた。
イートン・カレッジは、王族や首相、政治家など、イギリスの支配層を多数輩出してきた伝統校であり、そこに通う若者たちは“勝者の人生”を約束されている。一方で、労働者階級の若者たちは、教育も機会も与えられず、現実に押し潰されるばかり。ウェラーはこの差異を“戦い”のメタファーとして使い、イートンの学生たちが軍服を着て模擬訓練をしているのを、比喩的に「階級の戦い」の象徴として描いた。
アイロニーに満ちたこの曲は、後にデヴィッド・キャメロン(イートン出身、元英国首相)が“好きな曲”と公言したことで話題となり、ウェラー自身は「まるで曲を理解していない」と不快感を示したというエピソードも残っている。まさにこの曲の中で描かれた“階級の不理解”が現実の政治家によって再現された格好であり、いまだに社会を刺す鋭さを失っていないことを証明している。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に「The Eton Rifles」の印象的な一節を抜粋し、日本語訳を添えて紹介する。
Thought you’d found a way out / But you never had your sort
逃げ道を見つけたと思ってた——でも君らみたいな奴には、最初からそんなものはなかったYou were working class / And as such, they’ll never understand you
君は労働者階級——そんな君のことを、彼らが理解するわけがないAll that rugby puts hairs on your chest / What chance have you got against a tie and a crest?
ラグビーで男らしくなったって?ネクタイと紋章の前じゃ何の力にもならないよWhat a catalyst you turned out to be / Loaded the guns, then you run off home for your tea
きっかけにはなったけど——銃を構えておいて、結局お茶の時間には家に帰るのかよHello-hurrah, what a nice day / For the Eton Rifles
やあ、こんにちは、なんて素敵な日なんだろう——イートン・ライフルズにとってはね
引用元:Genius Lyrics – The Eton Rifles
4. 歌詞の考察
「The Eton Rifles」の最大の特徴は、怒りを直接的にぶつけるのではなく、冷徹な観察と皮肉という形で表現している点にある。ポール・ウェラーは、自分たち労働者階級の若者が、どれほど勇気を振り絞って“闘おう”としても、それすらも“エリートたちの遊び”として処理されることへの絶望感を、この曲で描き出した。
特に、“Loaded the guns, then you run off home for your tea(銃を構えても、結局お茶の時間には帰ってしまう)”というラインは、階級の上にいる者たちが“戦い”をシミュレーションとして扱うことへの鋭い批判であり、実際に現実と向き合っている者たちとの差異を鮮やかに描き出している。
また、コーラスで繰り返される“Hello-hurrah, what a nice day”という明るいフレーズは、陰鬱な現実との対比によってその皮肉が際立つ。社会の上層に生きる者たちには“良い一日”でも、下層に生きる者にとっては、“その日もまた、生き延びるための戦い”であるという構造的矛盾が、この一節に凝縮されている。
このように「The Eton Rifles」は、感情的なプロテストではなく、構造的な格差を冷静かつ知的に暴き出す社会派ロックの傑作である。歌詞を読み込むごとに、新たな皮肉や痛烈なメッセージが浮かび上がり、まさに“読ませるロック”の真髄が詰まっている。
※歌詞引用元:Genius Lyrics – The Eton Rifles
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Shipbuilding by Elvis Costello
戦争による経済回復の皮肉を描いたバラード。社会構造への視点が近い。 - Common People by Pulp
階級差とその不理解を風刺するブリットポップの代表曲。 - Clampdown by The Clash
権力構造と若者の服従を主題にしたパンク・アンセム。 -
Working Class Hero by John Lennon
個人と社会の摩擦、教育制度の欺瞞を描いたアコースティックな怒り。
6. 皮肉という名の銃弾で、階級社会を撃ち抜いた一曲
「The Eton Rifles」は、ポール・ウェラーが社会に対して向けた、最も鋭く、冷徹で、詩的な視線を持つ楽曲である。ここにはロマンチシズムもヒロイズムもない。ただ、構造的に抑圧されてきた者たちの視点と、上から眺める者たちの断絶が、音楽という武器を通して静かに、しかし確実に突き刺さってくる。
皮肉を知性として使い、怒りを詩として昇華し、それをギターのフィードバックに乗せて放つ——それがThe Jamの「The Eton Rifles」であり、1979年のイギリス社会が生んだ“声なき声”の代弁者だった。
この曲は今なお、“階級”という言葉が意味を持ち続けるすべての国と時代において、強烈なメッセージを放ち続けている。抑圧された側のリアリティを、誰よりもリアルに鳴らしたこの楽曲こそ、The Jamの真骨頂である。


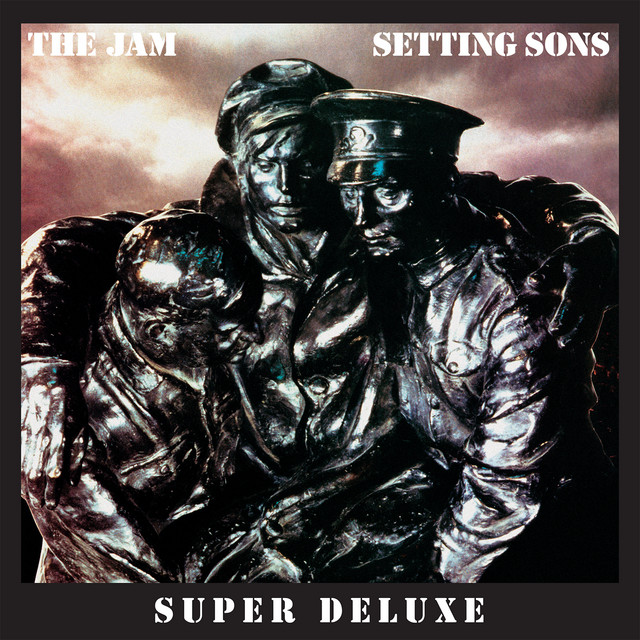
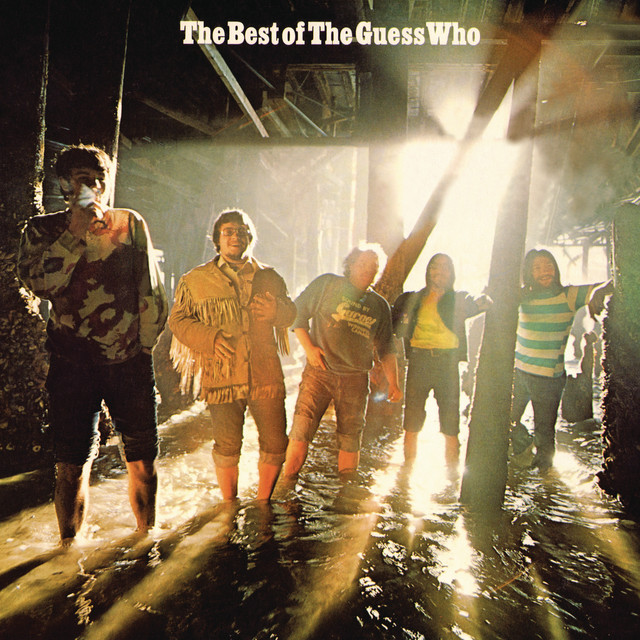
コメント