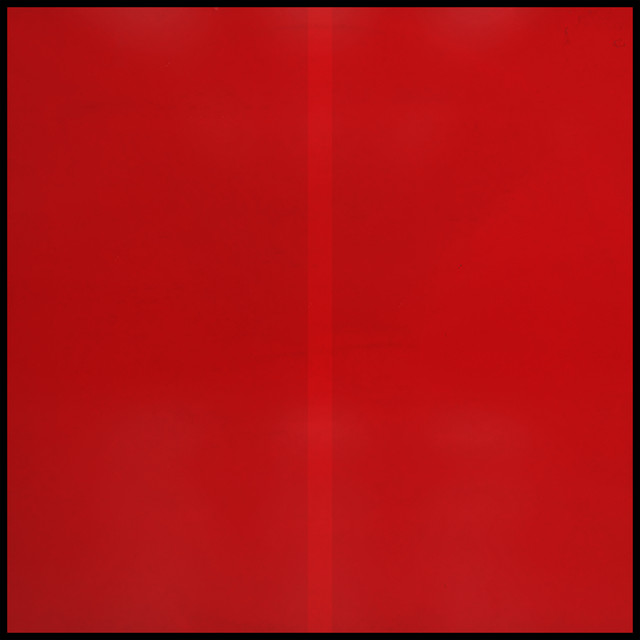
発売日: 2023年8月18日
ジャンル: オルタナティブヒップホップ、ポストパンク、ファンク、エクスペリメンタルポップ
⸻
概要
『STRUGGLER』は、ガーナ出身・オーストラリア育ちのアーティスト Genesis Owusu が2023年に発表した2作目のスタジオ・アルバムであり、混沌の時代における「生存のリズム」と「抵抗の身体性」を圧倒的エネルギーで描いた、現代のアフロ・サイバーパンク的闘争詩である。
前作『Smiling With No Teeth』では「黒い犬=鬱と差別」を象徴的に扱いながら個と社会の断絶を描いたOwusuは、本作でさらに内外の不確かさを深掘りし、“意味がない世界における、意味のない闘い”を肯定するという逆説的なテーマへと踏み込んだ。
アルバム全体を通して登場するのは「ストラグラー=もがき続ける者」という抽象的な存在。
神の不在、無意味なシステム、あらゆる混乱に飲まれながら、それでも踊る、走る、叫ぶ——その“行為”そのものにこそ意味があるというメッセージが、ジャンルを越境するサウンドと共に高らかに鳴らされている。
ファンク、ポストパンク、インダストリアル、ヒップホップが渾然一体となったその音は、理屈ではなく“本能的に抗うこと”を体験させるサウンドトラックとなっている。
⸻
全曲レビュー
1. Leaving the Light
爆発的なイントロ。
「光を残して去る」という不穏なタイトルと反し、ビートは鋭く前のめり。
“死なない者”として世界をさまようような、不滅の旅の始まりを告げる。
2. The Roach
本作の象徴ともいえる楽曲。
「ゴキブリ」は、汚物として扱われる存在でありながらも、どこまでも生き延びる象徴。
Genesisは自らを“roach”になぞらえ、「殺されてもなお這い上がる」と宣言する。
3. See Ya There
テンポを落としたエレクトロニックなR&B。
死や別れのイメージが滲む、静謐で哲学的なトラック。
一時的な内省がアルバムに余白を与える。
4. Freak Boy
不穏なシンセと変拍子が絡むアートパンク寄りの楽曲。
「フリーク=異形」としての自分を肯定しながら、社会の“規範”に笑いを突きつける。
5. Tied Up!
過剰なリズムとファルセットの対比がクセになるダンスチューン。
性的・社会的な束縛を、快楽と共に描き、「縛られながら踊る」ことの矛盾を突く。
6. That’s Life (A Swamp)
人生とは沼——という比喩を文字通り反復する、奇妙なグルーヴの曲。
意味不明であることそのものが、現実の写像として響く構成。
ユーモアと不条理が共存。
7. Balthazar
宗教的な響きを持つタイトルながら、内容は抽象的なレジスタンスの詩。
声が楽器のように使われ、言葉は意味より質感として響く。
聖と俗の交差点にある幻影のような楽曲。
8. Stay Blessed
皮肉に満ちたフレーズを繰り返すゴスペル・ノワール。
「神に見捨てられても、祝福されたふりをする」——その虚無と演技が胸に刺さる。
9. What Comes Will Come
ミニマルなエレクトロ・トラック。
未来への諦観と微かな希望が交錯する、反復の瞑想音楽。
「来るものは来る、それでも自分の足で立つ」という哲学が滲む。
10. Stuck to the Fan
サイケデリックで混沌としたエネルギーの塊。
あらゆる感情が“ファンに吹き飛ばされた”ような状態を音で表現。
ライブ映えするナンバーでもある。
11. See Ya There (Reprise)
3曲目の再演。
より感情がにじみ、亡霊のような浮遊感に包まれる。
アルバム全体を輪にするような構成。
12. Stuggle
エンドクレジットのような小曲。
音数は少なく、タイトルに“Struggle”から“e”が抜けていることで、「もがくこと」自体が“完結しない運動”であることを示唆する。
終わらないストラグルは、リスナーの耳の中に残響として続く。
⸻
総評
『STRUGGLER』は、Genesis Owusu が描く“意味のない世界における意味のある身体性”の探求である。
社会、宗教、自己、愛、死、逃避——あらゆる価値観がバラバラに崩壊する中で、彼は「踊りながらもがく」ことをやめない。
そこには、説教や答えはない。ただ、生きていること自体がレジスタンスなのだという、痛烈で希望的なメッセージがこだましている。
音楽的には前作よりもさらに実験性を増し、プリンス的なファンク、Talking HeadsやDeath Grips的なノイズ・パンク、Kendrick Lamar的な構造批評性など、広範な影響を消化して自分の文法で鳴らしている。
また、アルバム全体が1つの黙示録的な寓話となっており、リスナーは“ストラグラー”としてGenesisと共に暗闇を走る。
その体験は、汗ばみ、息切れし、そして時折泣きそうになる——まさに“生きている”という感覚そのものなのだ。
⸻
おすすめアルバム(5枚)
- Death Grips『The Money Store』
混沌と暴力のエネルギーが音楽化された前衛的ヒップホップの代表作。 - Danny Brown『Atrocity Exhibition』
ジャンルの壊し方と精神的サバイバルという主題の共鳴。 - Prince『Dirty Mind』
性的・政治的挑発をポップに昇華するアプローチの原型。 - Kanye West『Yeezus』
宗教性と破壊衝動、インダストリアルな音像の先駆。 - Young Fathers『White Men Are Black Men Too』
ロック、ヒップホップ、ゴスペルの境界線を越える多面的な音楽性。
⸻
7. 歌詞の深読みと文化的背景
『STRUGGLER』のリリックは、言語による“明確な伝達”というよりは、感情や肉体の“震え”をそのまま音に写したような詩性に満ちている。
「The Roach」は、黒人としての存在やアーティストとしての立ち位置を“ゴキブリ”という最も忌避される象徴で捉え直し、従来のヴィジュアルや美学を打ち壊す強烈なメタファーとなっている。
また「Stay Blessed」や「What Comes Will Come」では、宗教や運命論に対する冷笑的な距離感が描かれ、そこに現代的な信仰の空白が浮かび上がる。
このアルバムでは「抗うことが救いになる」とは一切言っていない。
むしろ、「救われないままでも、踊り続けるしかない」という、絶望と希望の狭間にある“生のグルーヴ”を掴み取る作品なのである。


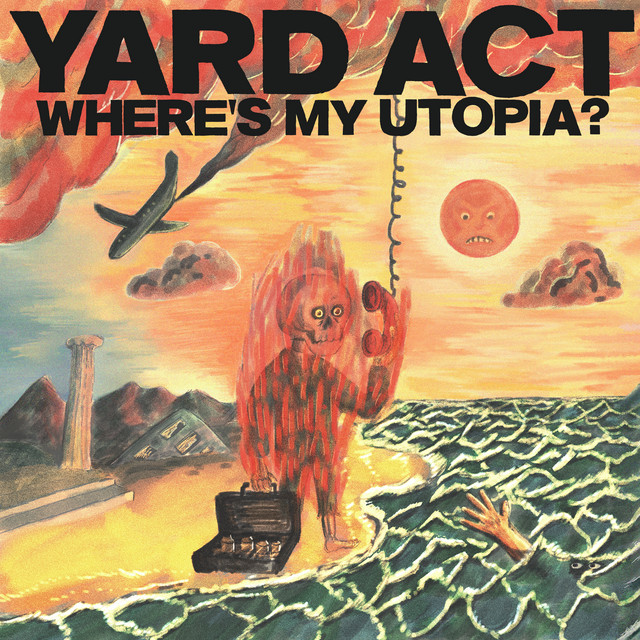

コメント