
発売日: 1977年3月
ジャンル: クラウトロック、ワールドビート、ファンク、エクスペリメンタル・ロック
概要
『Saw Delight』は、Canが1977年にリリースした9作目のスタジオ・アルバムであり、バンドのサウンドがよりリズム志向かつ“地球的”な方向へと進化した作品である。
このアルバムで注目すべきは、元Trafficの**ロズコ・ジー(Rosko Gee)とリーバップ・クワク・バー(Rebop Kwaku Baah)**という2人のアフロ・ジャマイカ系ミュージシャンが新たに参加し、Canのサウンドに“グローバルな血流”を注入したことである。
バンド内部では、この加入によって、ホルガー・シューカイが従来のベース担当から“音響操作”や“電子的処理”へと役割を移行。
そのため、本作は生楽器と電子音響が滑らかに共存するという、後期Canのサウンド的な特徴がより強く現れた作品となっている。
Canはすでに『Flow Motion』でレゲエやダブ、ポップ性への接近を見せていたが、『Saw Delight』ではよりアフリカ、ラテン、ジャズといった多文化的要素が音楽の表層に立ち上がり、まさに“地球規模のセッション”として響いてくる。
同時に、“ポップへの歩み寄り”が加速することで、かつての実験性や混沌からは距離を取り、より整理された構造を持ったアルバムに仕上がっている。
全曲レビュー
1. Don’t Say No
軽やかなリズムと浮遊感あるシンセが交錯する、ミドルテンポのジャム・グルーヴ。
ヴォーカルは抑制されており、むしろバンド全体の“音の会話”が前景化している。
ヤキ・リーベツァイトのドラムが特に有機的で、曲を地面から持ち上げている。
2. Sunshine Day and Night
アフロビート的なベースとカリンバ風のリフが特徴的な、リズミックなトラック。
レゲエやハイライフの影響も感じられ、複数のリズムが交差することで“多層的な躍動”を生み出している。
Canの“グローバル・ビート”への接近を象徴する一曲。
3. Call Me
Canとしては異例のストレートなヴォーカル・ポップ。
ホーン的なシンセとファンキーなギター、明瞭な歌詞が組み合わさり、“聴かせる実験音楽”としての境地を拓いている。
異質なようでいて、実は『Future Days』的な滑らかな感触も内在。
4. Animal Waves
13分を超える本作のハイライト。
長尺ながらも、ビートの揺らぎ、サウンドの浮遊、即興的展開が一体化し、“音楽がどこまでも続いていく”ような感覚を味わわせる。
ホルガーの電子音操作も要所に登場し、Canならではの“無国籍サイケ”が展開される。
5. Fly by Night
ギターのトレモロと反復するメロディが心地よい、アーバンなクロージング・トラック。
ポップでありながら、どこか音が“漂っている”印象を残す。
都市の夜景の中で微睡むような感触で、『Saw Delight』というアルバムの輪郭を穏やかに閉じる。
総評
『Saw Delight』は、Canが1970年代後半という世界的文脈の中で、“音楽の多文化共生”を自らのサウンドに落とし込んだ意欲作である。
ここで聴けるのは、クラウトロックの実験精神を引き継ぎつつ、**世界の音楽文化との対話を試みる“開かれたサイケデリア”**である。
その意味で、このアルバムは“クラウトロック後”のCanを象徴しており、ローカルからグローバルへ、実験から共振へという音楽的変化を体現している。
もちろん、初期の尖った即興性やアブストラクトな構造を求めるリスナーにとっては、やや整いすぎた印象を持つかもしれない。
だが、Canの進化は常に“変化そのもの”であり、『Saw Delight』はその変化を最も色彩豊かに描いた一枚なのだ。
おすすめアルバム(5枚)
- Can – Flow Motion (1976)
本作の前段階にあたる、レゲエやダブの導入を含んだ実験ポップ。 - Talking Heads – Remain in Light (1980)
アフロビートとアート・ロックの融合。『Saw Delight』以降の“ポリリズミックな西洋ロック”の名作。 - Fela Kuti – Expensive Shit (1975)
アフロビートの真髄。Canが取り入れた要素の源流のひとつ。 -
Paul Simon – Graceland (1986)
ワールドミュージックとポップの融合に成功した代表作。Canとは異なる文脈での到達点。 -
Burnt Friedman & Jaki Liebezeit – Secret Rhythms (2002)
Canのドラマー、ヤキ・リーベツァイトが後年追求した“リズムの科学”。『Saw Delight』の発展形。
制作の裏側(Behind the Scenes)
『Saw Delight』制作時、Canの内部では大きな構造変化が起きていた。
ベーシストであり録音・編集の中心でもあったホルガー・シューカイがベースを離れ、ミキシングやエフェクトに集中するようになったのは、本作からである。
この変化により、“演奏者”と“操作者”が分離される構造がCanの中で定着することになる。
また、リーバップの導入によって、Canはそれまでの“ドイツ的冷たさ”から一転して、パーカッションの温かみや空間性をサウンドに導入。
録音は従来のInner Spaceスタジオで行われたが、マルチトラック技術とアナログ・ディレイが駆使され、ミキシング段階での構成力が作品の肝となっている。
このように『Saw Delight』は、Canが“バンドという集団”から、“有機的な音響ユニット”へと脱皮しつつあったことを証明する作品であり、未来のグローバル・グルーヴへの布石でもあったのだ。


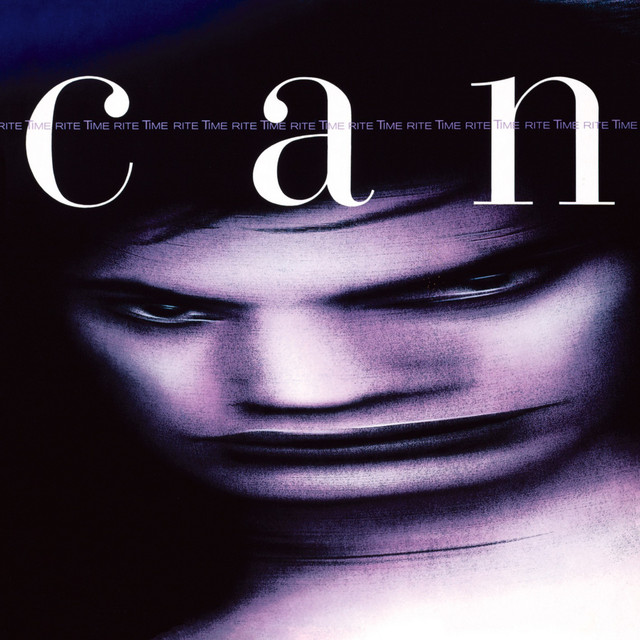
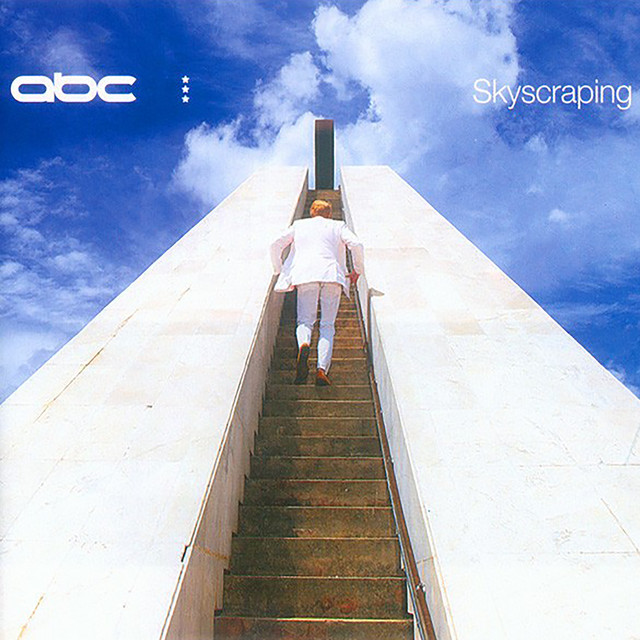
コメント