
発売日: 1978年9月11日
ジャンル: ソウル、ディスコ、ポップ
概要
『Ross』は、Diana Rossが1978年にリリースしたセルフタイトルのアルバムであり、70年代後半の音楽的変遷を象徴するような、ディスコとバラードの二面性を併せ持つ作品である。
本作は、前作『Baby It’s Me』(1977年)で確立された洗練されたアダルト・コンテンポラリー路線の余韻を残しつつ、急速に台頭していたディスコブームへの対応も見せている。
プロデュースはHal Davis、Richard Perry、Gregg Wrightらが担当し、それぞれ異なる手触りの楽曲を提供している。
アルバムの構成は明確に“二層構造”となっており、A面はフロア対応のディスコ/ソウルナンバー、B面はロマンティックで感傷的なバラードが中心。
こうした振れ幅のある構成は、Diana Rossの表現力の広さを強調するだけでなく、1970年代末という時代の混沌をも反映しているようにも思える。
タイトルを再び“Ross”としたことも含め、本作は彼女のアイデンティティを改めて打ち出し直す“リブランディング的作品”としての意味合いも強い。
全曲レビュー
1. Lovin’, Livin’ and Givin’
オープニングを飾るフルスロットルなディスコ・ナンバー。
映画『Thank God It’s Friday』にも使用されたこの曲は、Rossのクラブ向けイメージを確立した一曲。
ストリングスとシンセによる高揚感が、ダンスフロアの熱気を想起させる。
2. What You Gave Me
Ashford & Simpsonによるゴージャスなソウル・ラブソング。
情熱的でありながらエレガントな構成で、Rossの滑らかな歌唱が楽曲を包み込む。
70年代モータウン・サウンドの“美の到達点”のひとつとも言える名曲。
3. Never Say I Don’t Love You
スムースなグルーヴが特徴のアーバン・ソウル。
「愛してると言わなかったとしても、私の行動でわかるでしょ?」という大人の愛の表現が描かれる。
地味ながら味わい深いミッドテンポナンバー。
4. You Were the One
カントリーやアメリカーナの香りも漂うポップ・ソウル。
リズミカルなギターとコーラスが印象的で、Rossの自然体な歌声が親しみやすい。
キャッチーでリラックスしたムードの中に哀愁も漂う佳曲。
5. Reach Out, I’ll Be There
Four Topsの大ヒット曲を再カバー。
ソロとしての再解釈は、より内面的で情感豊か。
壮大なアレンジによって原曲よりもドラマティックな広がりがあり、Rossのヴォーカルが楽曲の核心に新たな命を吹き込む。
6. Sorry Doesn’t Always Make It Right
物悲しさを帯びたバラード。
謝罪の言葉では癒されない心の傷を、静かに、しかし力強く描いている。
彼女の抑えた声が、その痛みを誠実に伝える。
7. Where Did We Go Wrong
ピアノとストリングスを中心にしたメロウな失恋バラード。
別れに至るまでの“沈黙”と“すれ違い”を描写するリリックが詩的で、Rossの語りかけるような歌唱が胸を打つ。
8. To Love Again
アルバムを締めくくる、優美なオーケストラ・バラード。
愛に疲れた人が再び恋に向き合おうとする物語を、Rossはそっと寄り添うように歌い上げる。
Michael Masserによる美麗なメロディが、Dianaの声と調和し、静かな余韻を残す。
総評
『Ross』(1978)は、Diana Rossが“歌手としての多様性”を再提示した作品である。
冒頭のディスコ・ナンバーから、終盤の情感豊かなバラードまで、音楽的なレンジの広さをこれほどまでに自然に行き来できる歌手は稀である。
本作のA面とB面のコントラストは、単なるジャンルの違いというよりも、“夜の熱狂”と“朝の静けさ”のような時間軸の物語性すら感じさせる。
それは言い換えれば、“パフォーマーとしてのRoss”と、“人間としてのRoss”の両面を提示するという構成なのだ。
また、この時期の彼女は映画『The Wiz』への出演も控えており、女優・歌手の両面での活動がピークを迎えていた。
そのこともあり、本作には“演じること”と“語ること”のバランスが絶妙に溶け込んでいる。
キャリアの分岐点に立つ中でリリースされたこのアルバムは、Diana Rossがジャンルや時代の波に適応するだけでなく、それを自分のものにして昇華する“変化の達人”であることを改めて示した作品なのである。
おすすめアルバム(5枚)
- 『The Boss』 / Diana Ross(1979)
本作の直後にリリースされたディスコ路線の傑作で、Ashford & Simpsonによるプロデュースで統一感も抜群。 - 『Love Tracks』 / Gloria Gaynor(1978)
同年に登場したディスコ・クラシック。「I Will Survive」など、女性の自立を歌う内容も通じる。 - 『Tasty』 / Patti LaBelle(1978)
ソウルとディスコのバランス感覚が近く、Rossと同じく多彩な表現力を持つ作品。 - 『A Love Trilogy』 / Donna Summer(1976)
Rossとは異なる方向のディスコ・ディーヴァだが、シンセ主体のダンスサウンドという点で共鳴。 - 『Here, My Dear』 / Marvin Gaye(1978)
同年にモータウンからリリースされた、離婚をテーマにした内省的ソウル。Rossのバラード面との対比が興味深い。
ビジュアルとアートワーク
アルバムのジャケットには、大胆な赤の背景にDiana Rossのシルエットが配され、洗練とエネルギーを同時に表現している。
光沢のあるドレスやポーズはディスコ時代のゴージャスな雰囲気を纏いつつも、どこか控えめで抽象的な印象もあり、アルバム自体の“二面性”と呼応している。
このアートワークは、“Diana Ross=アイコン”としての記号性を押し出すというよりも、“Diana Rossという表現者”としての奥行きを感じさせるものとなっている。
その意味でも『Ross』は、内省と解放を行き来する、1970年代の彼女の肖像画のような作品なのだ。


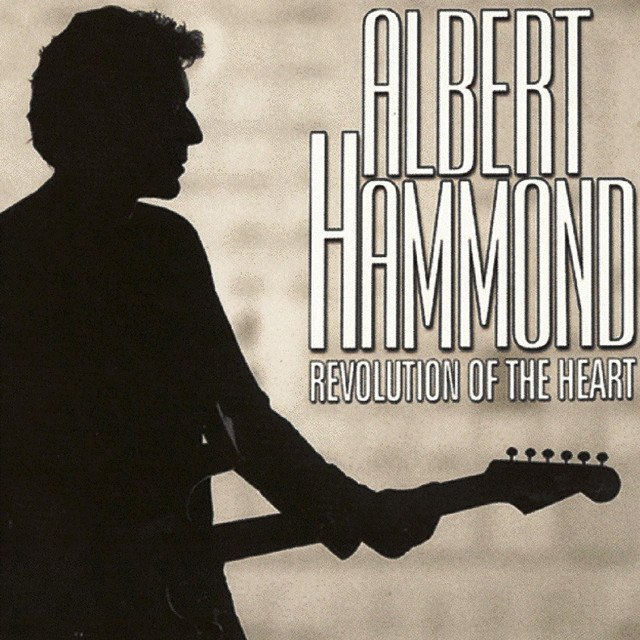

コメント