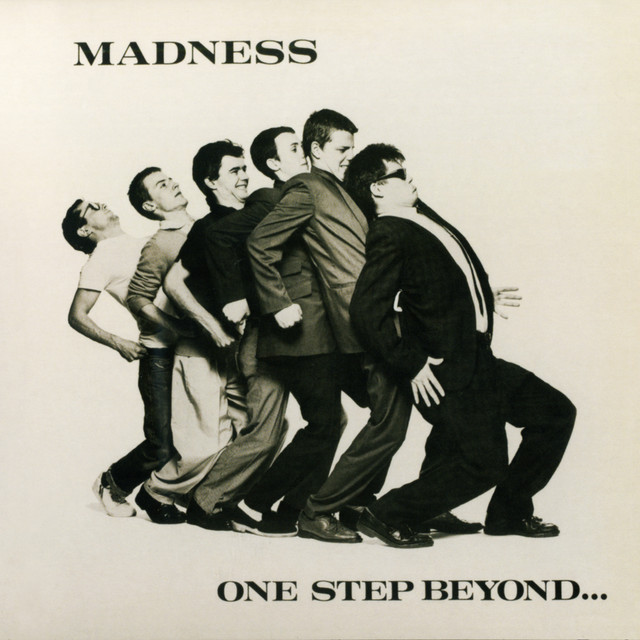
発売日: 1979年10月19日
ジャンル: スカ、2トーン、ポップロック、ニューウェイブ
概要
『One Step Beyond…』は、Madnessが1979年に発表したデビュー・アルバムであり、イギリスにおける2トーン・スカ・リヴァイバルの熱狂を決定づけた作品である。
ノース・ロンドン出身の彼らは、The Specialsらとともに「2トーン・ムーブメント」の中核を担い、
ジャマイカの伝統的スカと英国流のパンク精神、ユーモア、そして**労働者階級の都市文化をミックスした独自のスタイル=“ナットティ・ボーイズ”**を築き上げた。
本作は、その名の通り伝統的スカから“もう一歩先へ”進んだ、新しい音楽とユースカルチャーの宣言として機能している。
プロデュースはClive Langer & Alan Winstanley、録音はわずか数週間で完了。
荒削りながらも爆発的な勢いとコミック性に満ちており、英国チャートでは2位を記録し、以降のキャリアを支える強烈なインパクトを残した。
全曲レビュー
1. One Step Beyond
Prince Busterのカバーにしてアルバムの幕開け。
イントロでのChas Smashの「Hey you, don’t watch that, watch this!」のシャウトがあまりにも有名で、
**この曲はもはや楽曲というより“ムーヴメントそのもの”**として存在する。
無敵のスカ・インストゥルメンタルは、踊ることの解放感とクレイジーな勢いを一瞬で叩き込む。
2. My Girl
シンガーSuggsのややけだるげで人懐っこい歌声が光る名曲。
恋人とのすれ違いをコミカルに、しかしどこか哀愁を帯びて歌い上げる。
2トーン・スカのビートにのせた都市生活の小さな悲喜劇。UKシングルチャートでもヒットした代表曲。
3. Night Boat to Cairo
リズムの急加速とともに始まるインスト風トラック。
エキゾチックなメロディと吹き荒れるサックスが、タイトル通り“カイロへの夜行船”という非現実的トリップを演出する。
途中から歌詞がなくなるのも、Madness流のアナーキーな美学の表れ。
4. Believe Me
ミディアムテンポで展開される、友情と裏切りが交錯するストーリー仕立てのスカ・ナンバー。
ジャジーな鍵盤とトランペットが洒脱で、リズムも踊れるが、歌詞は意外とビター。
5. Land of Hope and Glory
風刺と諧謔が凝縮されたトラック。
英国国歌に準じるタイトルとは裏腹に、現代イギリスの疲弊とユースカルチャーの失望感をパロディ化している。
政治性とエンタメ性の両立が見事。
6. The Prince
バンド結成当初からのアンセムであり、Prince Busterへのトリビュート。
オリジナルのスカを敬愛しながら、自分たちのスタイルに昇華させるMadnessの姿勢が明確に示されている。
エネルギッシュで祝祭的、クラブでも人気の1曲。
7. Tarzan’s Nuts
スカとサーフ・ロックが混ざり合うようなユニークなインストゥルメンタル。
ジャングル的なリズムとコミカルなフレーズが飛び交い、映画音楽とコントの中間のような楽しさを放っている。
バンドの“劇団的”なセンスがよく表れたナンバー。
8. In the Middle of the Night
変質者の妄想をブラック・ユーモアで描くという、際どさと皮肉が入り混じる怪作。
明るいリズムに隠された病的な語り口が、Madnessの“狂気”を象徴している。
パンキッシュかつダークな一面が垣間見える重要曲。
9. Bed and Breakfast Man
短編映画のような展開を持つポップな楽曲。
タイトルは、格安宿泊所に転がり込む浮浪者的な男のことを指し、英国労働者階級のシニカルな風景をポップに描く。
ピアノのリフとコーラスがとにかくキャッチー。
10. Razor Blade Alley
サックスがメロウに鳴り響く、都会の裏路地のようなムード。
歌詞ではナイフと暴力が匂うが、その物騒さを“かわいらしいグルーヴ”に包んでしまうのがMadnessの技である。
陰と陽の絶妙なバランス。
11. Swan Lake
クラシックの「白鳥の湖」をカバーしながら、完全に狂騒的スカに変貌させたとんでもないアレンジ。
チャイコフスキーもびっくりなこの暴挙こそ、Madnessのアイロニーと実験精神を示す好例。
ライヴでは盛り上がり必至の定番曲。
12. Rockin’ in A♭
リズム感のあるポップ・ナンバーで、シンプルながらノリが良く、アルバム終盤を盛り上げる。
歌詞の軽妙さ、コード感のあざとさ含め、“不真面目に真面目な音楽”の完成形。
13. Mummy’s Boy
過保護な母親と息子の関係を茶化したような皮肉な歌。
メロディは爽やかだが、背後にあるのは家庭と自立にまつわる社会風刺。
まるで英国版の落語のようなテンション。
14. Madness
Prince Busterの同名曲のカバーにして、バンド名の由来となった重要曲。
自己言及的なメタ構造も内包しており、自分たちが“狂気”という名の音楽を背負う覚悟を宣言した一曲。
オリジナルへの敬意と現代性が絶妙にブレンドされている。
15. Chipmunks Are Go!
アニメ「チップマンクス」のような高速ヴォーカルをフィーチャーしたユーモア・トラック。
完全なる遊び心の爆発であり、アルバムを“音楽以上の何か”として提示するラストナンバー。
総評
『One Step Beyond…』は、Madnessにとっての出発点であり、イギリスの若者文化と音楽が“真面目な不良”として噴出した記録である。
ただのスカ・リヴァイバルではなく、スカの持つ祝祭性と社会性を、労働者階級の視点とブリティッシュ・ユーモアでリミックスした革新作。
その音楽は、明るくて騒がしくて少し馬鹿げている。
だが、そこには確かな知性と誠実な文化批評があり、“踊ること”が“生きること”に直結するような力強さを感じさせる。
Madnessはこのデビュー作において、すでに**“ロンドンの語り部”としての役割**を果たしていたのだ。
おすすめアルバム(5枚)
-
The Specials – The Specials (1979)
2トーン・ムーブメントの中核をなす政治的かつダンサブルな名盤。 -
The Beat – I Just Can’t Stop It (1980)
同時代のスカ+ニューウェイヴ。メロディとグルーヴが絶妙。 -
Bad Manners – Ska ’n’ B (1980)
Madness同様、ユーモアとスカを融合したパーティ・バンドの代表作。 -
The Selecter – Too Much Pressure (1980)
女性ボーカルが映える、2トーンのもう一つの先鋭。 -
Ian Dury & the Blockheads – New Boots and Panties!! (1977)
音楽的にも精神的にもMadnessの兄貴分的存在。労働者階級の語り部。



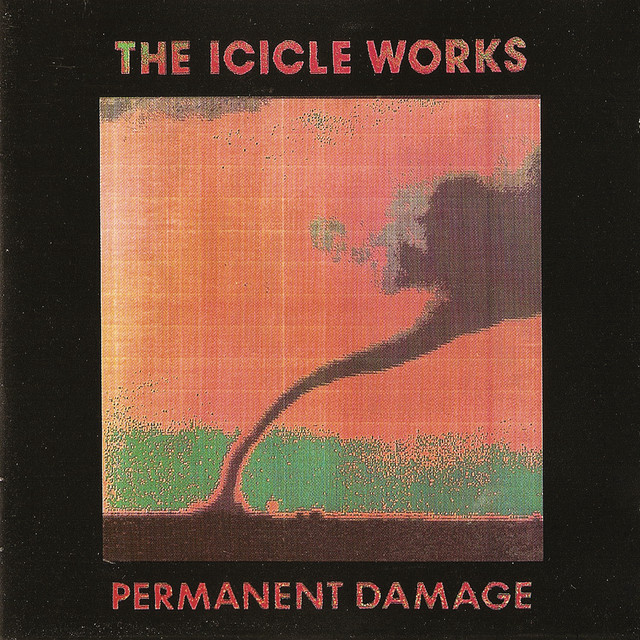
コメント