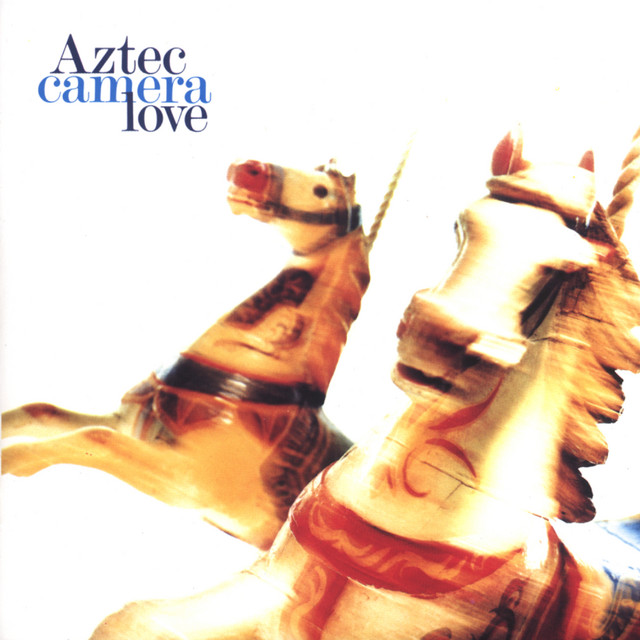
発売日: 1987年11月
ジャンル: ポップ、ブルー・アイド・ソウル、アダルト・コンテンポラリー
概要
『Love』は、Aztec Cameraが1987年に発表した3作目のスタジオ・アルバムであり、彼らにとって最大の商業的成功を収めた作品である。
本作では、より明確にアメリカ市場を意識したポップ路線への転向が図られ、サウンドはこれまでのネオアコ的な繊細さよりも、洗練された都会的ポップスへとシフトしている。
特に全英シングルチャートで3位を記録した「Somewhere in My Heart」のヒットは、Aztec Cameraの名前を広く一般に知らしめた。
だが、そのポップな外面とは裏腹に、ロディ・フレイムのソングライティングは、依然として文学的かつ内省的であり、軽薄なヒット志向とは一線を画す深みを備えている。
制作にはロサンゼルスを拠点とするプロデューサー陣を多数起用し、セッション・ミュージシャンの参加も目立つ。
その結果、楽曲ごとに色彩が異なる一方、アルバム全体としては「愛」というテーマのもとに統一されたロマンティックな空気が貫かれている。
全曲レビュー
1. Deep and Wide and Tall
幕開けを飾るミディアムテンポのポップナンバー。
広がりのあるコーラスとキラキラしたサウンドは、アルバムの都会的な方向性を端的に示している。
「深く、高く、広く」というフレーズが象徴するのは、理想の愛とその難しさ。
2. How Men Are
シンプルなバラードに見えて、内面には男性性への静かな批判と自己反省が込められている。
ロディ・フレイムのボーカルが特に繊細に響く曲であり、彼の叙情性が際立つ。
ソフトな鍵盤とアコースティックギターの絡みが、静かな美を生み出している。
3. Everybody Is a Number One
アップビートで明るい曲調の中に、「誰もが特別」という普遍的なメッセージを込めたポップチューン。
シンセやホーンを用いた派手なアレンジが印象的で、80年代のポジティヴな空気をまとっている。
タイトルの言葉は自己肯定と希望の象徴でもある。
4. More Than a Law
ブルージーでグルーヴィーなアレンジが光る1曲。
愛や正義を「法律以上のもの」として描くリリックは、抽象的ながら感情の強さを感じさせる。
この曲ではギターのプレイが一段とラフでソウルフルな響きを持つ。
5. Somewhere in My Heart
本作の最大のヒット曲であり、Aztec Cameraの代名詞とも言える楽曲。
煌びやかなサウンドと甘く切ないメロディが融合し、ポップスとして完璧なバランスを誇る。
歌詞は一見ロマンチックだが、実際には「本当の愛は心の奥深くにある」という陰影ある内容。
大衆性と芸術性が奇跡的に同居した名曲である。
6. Working in a Goldmine
「金鉱で働く」という比喩を用いた、資本主義社会における生と愛の矛盾を描いた曲。
ファンキーなリズムとキャッチーなメロディが対比的で、ポップの中に苦味が潜む。
職業的成功と感情的な充足の間で揺れる姿がリアルに描かれている。
7. One and One
イントロからR&B的なグルーヴを感じさせる異色作。
愛する者同士が一体になること、しかしそれが決して簡単ではないという現実を繊細に描いている。
多重ボーカルとバックコーラスの使い方が洗練されており、都会的な空気を醸す。
8. Paradise
80年代的な「楽園」幻想をテーマにしたポップソング。
夢のようなアレンジとシンセサイザーが、幻想的な風景を描き出す。
だが、歌詞では楽園が実体ではなく心の中にあるものであることを静かに示しており、理想と現実のギャップが浮き彫りになる。
9. Killermont Street
アルバムの締めくくりにふさわしい、静かで抒情的なピアノ・バラード。
グラスゴーの通りの名前を冠したこの曲は、フレイムの原点を思わせるような、私的でノスタルジックな世界観が広がる。
音数を抑えたアレンジの中で、リリックの美しさが際立つ名曲。
総評
『Love』は、Aztec Cameraが80年代後半のポップスのど真ん中に飛び込みながらも、単なる商業的ヒットに留まらない芸術性と誠実さを保ち続けたアルバムである。
ネオアコの枠を超え、ソウル、ファンク、AORといった多彩な要素を吸収しつつ、ロディ・フレイムの歌心があくまでも核にあることで、どの楽曲も“彼らしさ”を失っていない。
また、「愛」という抽象的なテーマに真正面から向き合いながら、その多面性――甘さ、痛み、理想、現実――を描き切っている点も注目に値する。
音楽的には従来のファンを戸惑わせた側面もあったが、それすらも「変化」への意志と見るべきだろう。
今聴くと、そのサウンドは確かに時代を映してはいるが、決して古びていない。
むしろその誠実なポップセンスと普遍的なリリックは、世代や国境を越えて響く力を今なお保ち続けているのだ。
おすすめアルバム(5枚)
- Tears for Fears / Songs from the Big Chair (1985)
80年代中盤の大衆性と個人的なテーマの共存という点で共通。 - Scritti Politti / Cupid & Psyche 85 (1985)
ポップの中にインテリジェンスを宿す姿勢が似ている。 - Prefab Sprout / From Langley Park to Memphis (1988)
アメリカ志向と文学的歌詞の融合という方向性が重なる。 - Paul Young / The Secret of Association (1985)
ブルー・アイド・ソウル的な歌唱と洗練されたプロダクションが共鳴。 - Style Council / Confessions of a Pop Group (1988)
ソウルとクラシカルな感性を融合し、愛と社会への視点を併せ持つ作品。


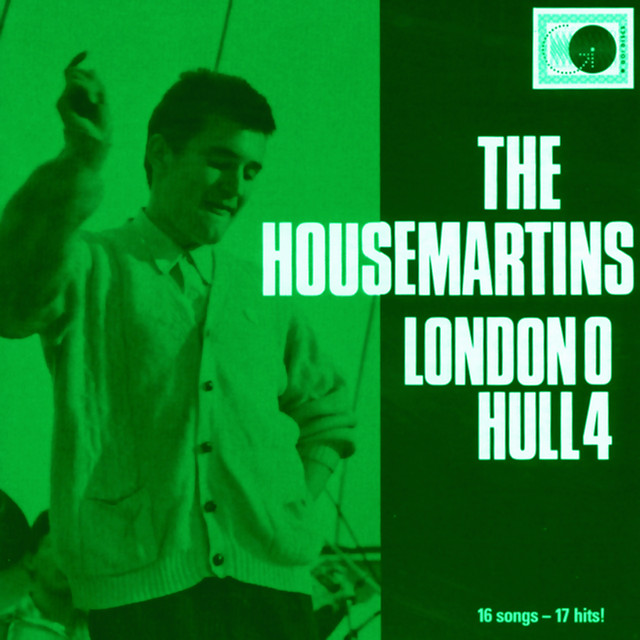
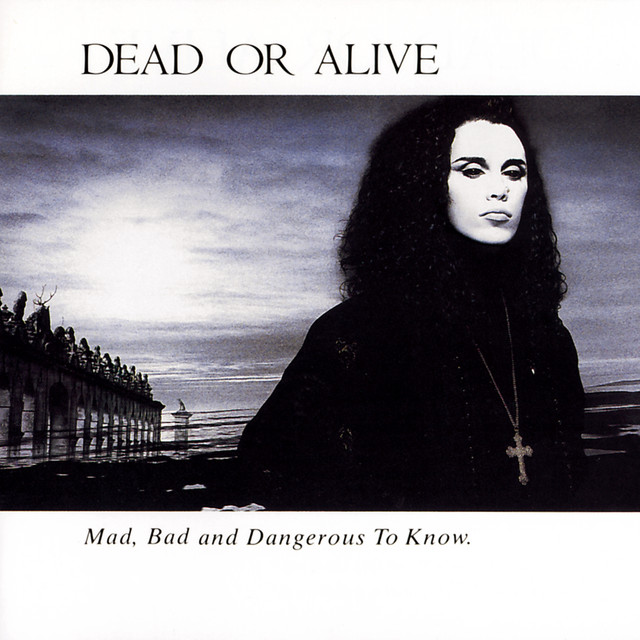
コメント