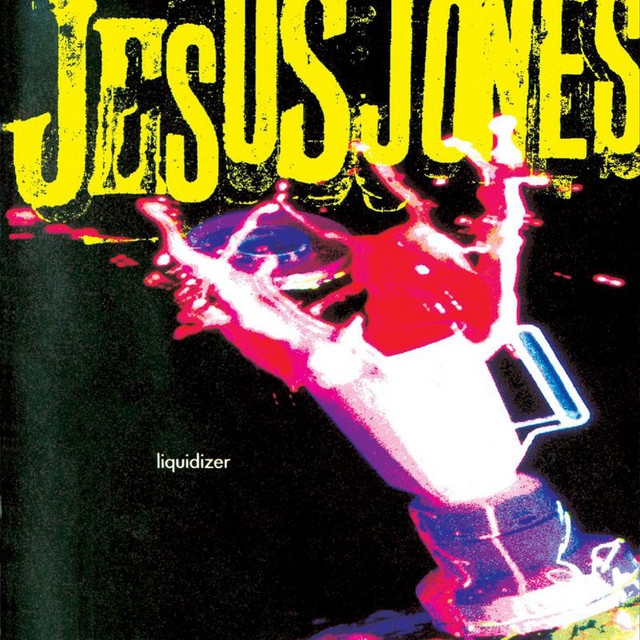
発売日: 1989年10月
ジャンル: オルタナティブ・ダンス、インダストリアル・ロック、サンプル・ポップ
概要
『Liquidizer』は、イギリスのオルタナティブ・ロック・バンド、Jesus Jonesが1989年にリリースしたデビュー・アルバムであり、ロックとダンス、テクノロジーと人間性を融合させた先鋭的作品として注目を集めた。
当時のイギリス音楽シーンでは、“マッドチェスター”や“アシッド・ハウス”といったクラブカルチャーの波が押し寄せており、Jesus Jonesはその流れにロック的な叩きつける衝動とポジティブなエネルギーを接続させた数少ないバンドの一つであった。
バンドの中心人物であるマイク・エドワーズは、サンプラーとギターを武器に、バンドという形態を維持しながらテクノロジーを最大限に導入。
その試みは『Liquidizer』というアルバムタイトルにも象徴されており、ジャンル、思想、文化を一度すべて“ミキサー”にかけて再構築するという姿勢が貫かれている。
全曲レビュー
1. Move Mountains
アルバムの幕開けを飾る、ハードエッジなギターとビートの融合が炸裂する一曲。
「山を動かす」というタイトル通り、自信と前進の決意が力強く込められている。
一聴してJesus Jonesのスタイルを明確に印象づける、スピーディーかつアグレッシブなトラック。
2. Never Enough
短く鋭いポップ・パンチ。
何をやっても満たされない現代人の飢えを歌った楽曲で、消費社会の加速感を音で表現している。
コンパクトな構成に中毒性があり、ライブでも定番となった。
3. The Real World
“現実世界”という直球なテーマを掲げながら、リリックはどこか皮肉で哲学的。
硬質なギター・リフとサンプリングが交差し、情報過多な現代の風景を音でコラージュする。
デジタルとアナログのせめぎ合いが楽曲構造にも反映されている。
4. All the Answers
クエスチョンに対して答えを出すことの不可能性を逆説的に歌う。
ビートが跳ねるように弾み、ヴォーカルのリズムとラップ的な語り口が融合。
知的でありながらダンサブルという、Jesus Jonesならではのスタイルが確立されている。
5. What’s Going On
その名の通り、混沌とした時代の叫びが込められた楽曲。
マーヴィン・ゲイの名曲とは異なるが、同様の“叫び”の系譜に連なる構造。
ギター、ベース、シンセが渾然一体となり、サウンドの密度が高い。
6. Song 13
アルバム中最も実験的なトラックのひとつ。
不穏なサウンドと変則的な展開で、タイトルの“13”が持つ不吉さや予測不能性を増幅させている。
抽象的な構成は、インダストリアルやノイズ・ロックへの接近も感じさせる。
7. Info Freako
Jesus Jonesを語る上で外せない代表曲。
情報中毒(Info Freako)な主人公の姿は、メディア社会に生きる全ての人への風刺である。
スピード感あふれるビートとシャープなギターが炸裂し、当時の音楽番組でもヘビープレイされた。
本作で最もアイコニックかつ中毒性の高い楽曲。
8. Bring It on Down
テンポを落としながらも、重心の低いグルーヴが印象的なナンバー。
攻撃性と内省が混ざり合い、Jesus Jonesの多面的な音楽性を見せつける一曲。
サイケデリックなエフェクト処理もあり、後の“Grebo”的文脈にも接続する。
9. Too Much to Learn
知識や情報に飲まれそうになる焦燥をテーマにした楽曲。
反復的なサビと、詰め込まれた言葉数がリスナーに情報疲れとカタルシスを同時に与える。
その矛盾こそが、Jesus Jonesの美学でもある。
10. What Would You Know
問いかけの連続で進行する、対話的な構造を持つナンバー。
ギターのカッティングとシンセの絡み合いが軽快であり、どこかヒップホップ的でもある。
ジャンルの境界線を意図的に曖昧にした、象徴的な一曲。
11. One for the Money
金と欲望をテーマにした皮肉的ポップ・ロック。
サウンドはキャッチーだが、歌詞の冷ややかさとのコントラストが際立つ。
この時代の若者文化に漂う“シニカルな醒め”を体現するような楽曲。
12. Someone to Blame
クローザーとして完璧な、陰りと決意を併せ持つナンバー。
“誰かのせいにしたい”という感情は、個人の弱さと社会の構造を同時にあぶり出す。
マイク・エドワーズのボーカルが最も切実に響く瞬間でもある。
総評
『Liquidizer』は、Jesus Jonesというバンドの出発点にして、1989年という時代の空気を最もダイナミックに捉えた作品のひとつである。
アナログなバンド編成でありながら、サンプラーとテクノロジーを大胆に導入し、“ロックの未来形”を提示した本作は、後のデジタル・ロックやエレクトロ・パンクの基盤ともなった。
サウンドは終始タイトでエネルギッシュ、リリックは知的で風刺的、そして全体を貫くのは“前のめりな楽観主義”である。
「混沌の中でも走り続けろ」というメッセージは、ポスト冷戦、情報化社会の夜明けにこそ必要とされた精神だったのかもしれない。
クラブ文化、インディーロック、ポップカルチャーに興味を持つすべてのリスナーにとって、『Liquidizer』は今なお新鮮な驚きをもたらす。
おすすめアルバム(5枚)
-
Pop Will Eat Itself – This Is the Day… This Is the Hour… This Is This! (1989)
サンプリングとロックの融合という点で双璧を成す作品。 -
EMF – Schubert Dip (1991)
Jesus Jonesに近い文脈で語られる、90年代初頭の代表的グレボ/ダンス・ロック。 -
The Shamen – En-Tact (1990)
アシッドハウスとポップの融合。クラブカルチャーとロックの交差点。 -
Carter the Unstoppable Sex Machine – 101 Damnations (1990)
政治的リリックと電子音が組み合わさった独特のロック・サウンド。 -
Apollo 440 – Millennium Fever (1994)
テクノロジーとロックの融合をさらに押し進めた、ポストJesus Jones的進化形。



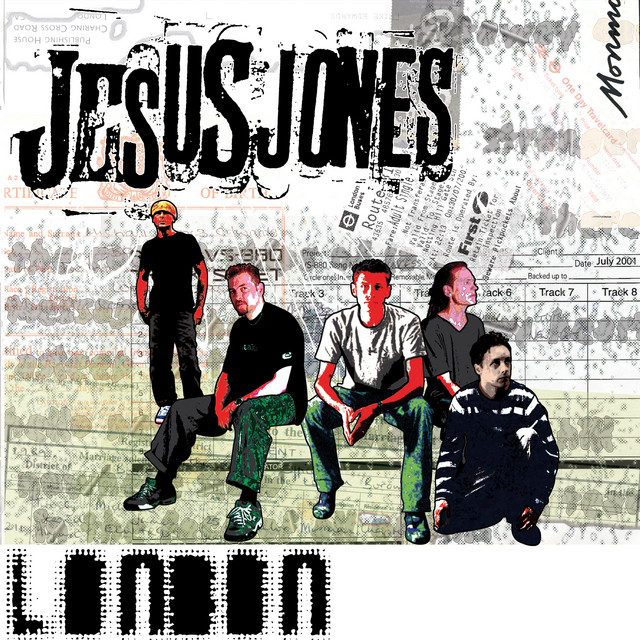
コメント