
発売日: 1998年10月27日
ジャンル: オルタナティブ・ロック、ネオ・サイケデリア、エレクトロニカ、ブリットポップ
概要
『Kingsize』は、The Boo Radleysが1998年に発表した6作目のスタジオ・アルバムにして、活動停止前最後の作品である。
このアルバムは、前作『C’mon Kids』での商業的失速と批評家との緊張関係を経て、ポップ性と実験性のバランスを再び探ろうとした“静かな野心作”である。
一見するとブリットポップ的なキャッチーさを取り戻したようにも見えるが、実際には夢幻的な音響処理、エレクトロニカ的手法、ストリングスの重厚なアレンジなど、さまざまな音楽的要素が統合されている。
つまり、ポップの衣を纏いながら、内実はきわめて内省的で緻密な構築美に満ちた作品なのだ。
マーティン・カーによる楽曲構成は、もはや“ソングライティング”というよりも“サウンドデザイン”に近く、多層的で映像的な音世界が展開される。
ボーカルのシズ・ロウも、かつての若々しいトーンから一転、より叙情的で夢の中の語り部のような存在へと変化している。
『Kingsize』は、時代の流れに抗うことなく、しかし飲み込まれもせず、ポップという形式に託された最後の問いかけとして静かに語りかけてくる一枚である。
全曲レビュー
1. Blue Room in Archway
ストリングスと電子音が溶け合う、サイケデリックなオープナー。
実在するロンドンの地名“アーチウェイ”を舞台に、都市の静けさと孤独を音で描く。
2. The Old Newsstand at Hamilton Square
シンプルなアコースティック・ギターが印象的なノスタルジック・ポップ。
“ハミルトン・スクエアの古い新聞スタンド”という具体的なイメージが、失われた日常と記憶を想起させる。
3. Free Huey
本作のリードシングルであり、最もアグレッシブな一曲。
ブラックパンサー党のヒューイ・ニュートンに捧げたタイトルが示すように、社会的メッセージを内包。
ギターとエレクトロニクスの融合が鮮烈。
4. Monuments for a Dead Century
ゆったりとしたテンポで進行する幻想的なナンバー。
“死にゆく世紀への記念碑”というタイトルからも、20世紀末の憂鬱と内省が滲み出ている。
5. Heaven’s at the Bottom of This Glass
前作『C’mon Kids』にも登場した楽曲のセルフリフレイン。
アルコールの快楽と逃避を詩的に描写し、過去作とのつながりを意識させる。
6. Kingsize
アルバムタイトルを冠した本作の中心的トラック。
壮大なストリングスと中毒性のあるメロディが展開する、文字通り“キングサイズ”のスケール感を持った楽曲。
7. High as Monkeys
軽妙でトリッキーなポップソング。
猿のように“ハイになる”という比喩が、快楽とナンセンスを戯画的に描き出す。
8. Eurostar
ユーロスターに乗って大陸を横断するような、スピード感と旅情に満ちた楽曲。
エレクトロニカ的リズムとサイケデリックなギターが交錯し、仮想的な“音の移動”を実現している。
9. Adieu Clo Clo
1970年代にフランスで活躍したクロード・フランソワ(Clo-Clo)へのオマージュ的トラック。
グルーヴィーなリズムとフレンチ・ポップ的なニュアンスが漂う。
10. Jimmy Webb is God
アメリカの名ソングライター、ジミー・ウェッブに対する賛歌。
“神”と称することで、ソングライティングへの信仰を暗に語るメタ的な一曲。
11. She Is Everywhere
感覚的にはドリーム・ポップの傑作。
“彼女はどこにでもいる”という反復は、記憶や幻影のように聴き手の心をさまよわせる。
12. Comb Your Hair
心地よいメロディラインと淡々とした語り口。
日常の行為(髪をとかす)に込められた時間の感覚と、反復の美しさを描いている。
13. Song from the Blue Room
再び“Blue Room”のモチーフが登場し、アルバム冒頭と呼応する構成。
夢の終わりを告げるような、静かなエピローグ。
総評
『Kingsize』は、The Boo Radleysが最後に提示したポップの理想と、その果てにある沈黙である。
この作品には、『Giant Steps』の実験性や、『Wake Up!』の大衆性、『C’mon Kids』の混沌といった過去のエッセンスが静かに溶け込んでおり、それらがひとつの“終章”として穏やかに統合されている。
華やかではない。だが美しい。
このアルバムに漂うのは、祝祭ではなく、余韻と回想、そして穏やかな別れの感触である。
商業的には成功しなかったが、その静謐さと詩的統合感は、多くの音楽家に影響を与え続けている。
本作のあと、The Boo Radleysは自然な流れの中で活動を停止したが、その終わり方すらも、彼らの音楽性の一部だったように思える。
『Kingsize』は、ポップミュージックという形式を信じ、その限界までも愛したバンドの最後の手紙なのである。
おすすめアルバム
- The High Llamas / Hawaii
ストリングスとビーチボーイズ的構築美。『Kingsize』と共振する知的ポップ。 - The Divine Comedy / Fin de Siècle
同じく1998年にリリースされた20世紀末的叙情を内包する作品。 - Radiohead / Amnesiac
静謐さ、デジタル感、音の空白。『Kingsize』の後継的雰囲気を持つ。 - Badly Drawn Boy / The Hour of Bewilderbeast
メロディとローファイ感、繊細な内省が融合した00年代的継承者。 -
Tindersticks / Curtains
退廃とロマン、夜の音楽としての共通性。
後続作品とのつながり
本作のリリース後、The Boo Radleysは公式に解散を表明。
その後20年以上にわたり沈黙を保ったが、2020年代に入り再始動。
2022年には『Keep on with Falling』をリリースし、まさかの“第2章”をスタートさせた。
『Kingsize』は、最終作でありながら、その後の再出発をも予見していたかのような“静かな余白”を残していた。
それは、すべてが終わった後にもまだ歌が残るということを、証明していたのかもしれない。


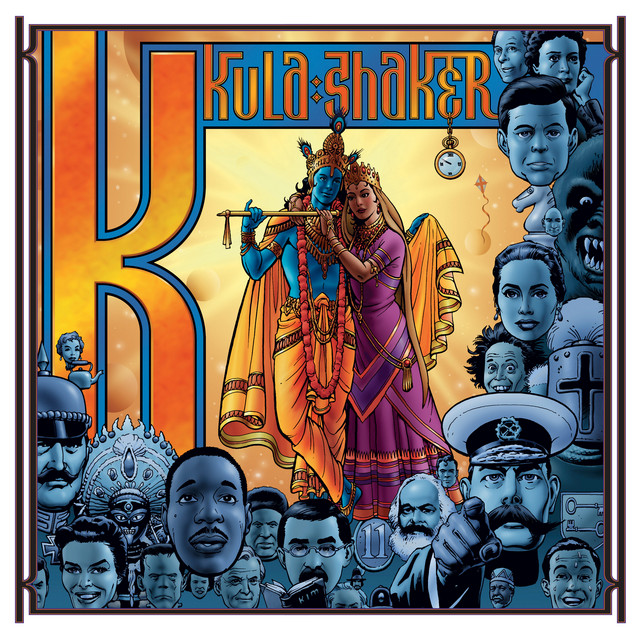
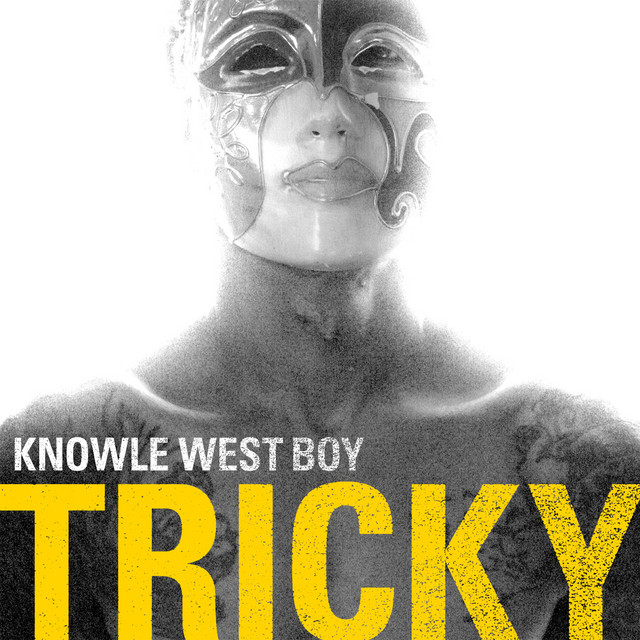
コメント