
1. 歌詞の概要
「(Keep Feeling) Fascination」は、イギリスのエレクトロポップ・バンド、The Human Leagueが1983年にリリースしたシングルであり、彼らの黄金期における代表的楽曲の一つである。この楽曲は、グループの持ち味であるクールなシンセサイザー・サウンドと、ポップで高揚感のあるメロディ、そして多声的なヴォーカル構成が見事に融合した作品で、リスナーに強い印象を与える。
歌詞の中心にあるのは、「Fascination(魅了されること)」というテーマであり、それは恋愛に限らず、人生や人間関係、社会における“新たな可能性”へのときめきや期待を象徴している。“Keep feeling fascination / Passion burning, love so strong”というサビのラインは、内面から燃え上がる情熱や、理屈を超えた引力に引き寄せられる感覚を描いている。
この楽曲は、ポジティブな高揚感に満ちていながらも、The Human Leagueらしい抑制されたエレクトロニクスがその感情を冷静に包み込み、独特のバランスを保っている。つまり、“魅了されていく感覚”を讃える一方で、その過程にはどこか機械的で無機質なリズムがあり、感情の高まりと制御の間で揺れ動く人間の姿が映し出されている。
2. 歌詞のバックグラウンド
「(Keep Feeling) Fascination」は、1983年3月にリリースされ、UKシングルチャートで最高2位、アメリカのBillboard Hot 100でも8位を記録するなど、国際的な成功を収めた作品である。前作『Dare』(1981年)によって世界的な成功を収めたThe Human Leagueにとって、本楽曲はその人気を継続させるための試金石でもあり、見事にそれを達成した。
この曲は当初、単発のシングルとして制作されたもので、オリジナル・アルバムには収録されていない。しかし、その後の編集盤やリイシュー盤には頻繁に収録され、バンドの代表曲のひとつとして定着した。プロデューサーはマーティン・ラッシュント(Martin Rushent)で、彼は『Dare』に続き、バンドの洗練されたエレクトロサウンドを構築する中心人物であった。
歌詞の面でも、本作はThe Human Leagueの他の作品と同様、複数のメンバーがヴォーカルを分担し、会話のように展開していくスタイルが採られている。これは、恋愛における複数の視点や、異なる立場からの“魅了”のあり方を表現するための手法であり、単なるラブソングの枠を超えた広がりを生み出している。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に「(Keep Feeling) Fascination」の印象的な一節を抜粋し、日本語訳を添えて紹介する。
Keep feeling fascination
感じ続けるんだ、その“魅了”をPassion burning / Love so strong
情熱が燃え上がり、愛があまりにも強くなるKeep feeling fascination / Looking, learning / Moving on
惹かれる気持ちを持ち続けよう/見つめ、学び、そして進んでいくIt could almost be a crime
それは、ほとんど“罪”にも近いかもしれないLove’s strange, so real in the dark
愛は奇妙で、闇の中でこそリアルに感じられる
引用元:Genius Lyrics – (Keep Feeling) Fascination
4. 歌詞の考察
この楽曲は、感情や体験への“魅了”という普遍的テーマを通じて、人間が何かに惹かれて生きていく原動力そのものを歌っている。特にサビの「Keep feeling fascination / Looking, learning / Moving on(惹かれながら、見て、学び、進んでいく)」というフレーズは、ただの恋愛にとどまらず、人生全体に通じる姿勢を示している。
「It could almost be a crime(それは、ほとんど罪にも近い)」という表現には、人が何かに強く惹かれてしまうことの危うさや快楽性が込められており、その“抑えがたい引力”を肯定しつつも、一歩踏み外すことへの怖さも滲んでいる。
また、「Love’s strange, so real in the dark(愛は奇妙で、闇の中でこそ本物に感じられる)」というラインでは、愛や魅力の正体が曖昧で掴みがたいものであることが示されている。愛や感情は、明るい場所では整然として見えるかもしれないが、実は暗闇や混沌の中でこそリアルであり、力強く存在しているのだという認識が垣間見える。
シンセポップという機械的なサウンドをベースにしながらも、この曲はむしろ感情の“燃え上がり”をテーマにしている。無機質な音と有機的な感情のせめぎ合いの中で、The Human Leagueは人間の“魅了される力”そのものを讃えているのだ。
※歌詞引用元:Genius Lyrics – (Keep Feeling) Fascination
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Temptation by Heaven 17
欲望と抗えない感情をテーマにしたエレクトロポップ。The Human Leagueとも関係の深いユニット。 - Electricity by Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD)
人間の原動力とテクノロジーを結びつけた初期エレクトロの名曲。 - Everything Counts by Depeche Mode
感情と社会性の狭間を描くシンセポップ。人間の本質を機械的なビートで表現するスタイルが共通。 - Living on the Ceiling by Blancmange
異国的なメロディとシンセの融合。感情の揺れと浮遊感が似ている。
6. “魅了される”ことへの讃歌
「(Keep Feeling) Fascination」は、1980年代のエレクトロポップの中でも、とりわけ“感情”と“機械”の対立を美しく調和させた楽曲である。The Human Leagueは、この曲を通して、人が何かに惹かれること——それが恋愛であれ、知識であれ、夢であれ——の持つポジティブな力を祝福している。
この曲のメッセージは単純だが深い。「感じ続けろ。学び続けろ。そして進め。」というその姿勢は、変化し続ける時代の中で、何かに“魅了される力”こそが人間を動かすエネルギーであるという信念に満ちている。
シンセポップの時代に生まれたこの楽曲は、冷たい電子音の中に、人間の熱を閉じ込めることに成功した。その“熱”こそが、“Fascination”なのである。


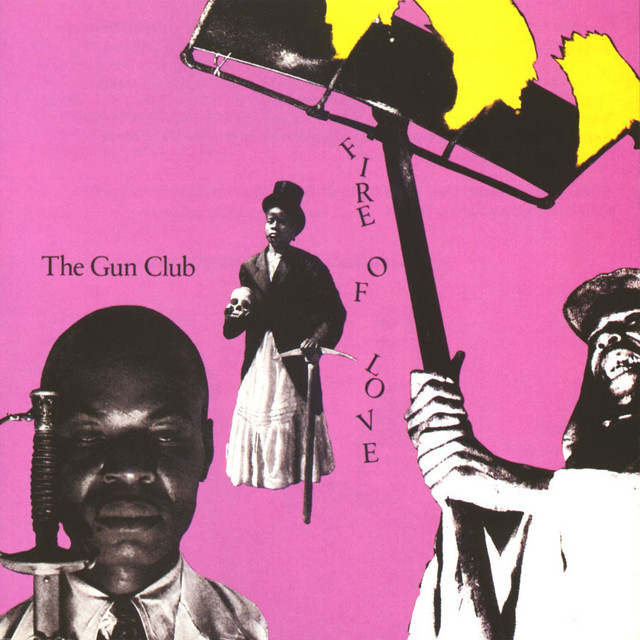
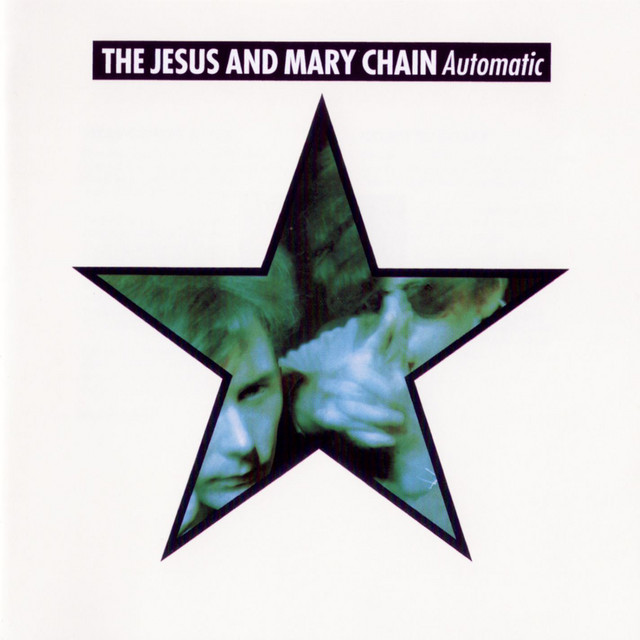
コメント