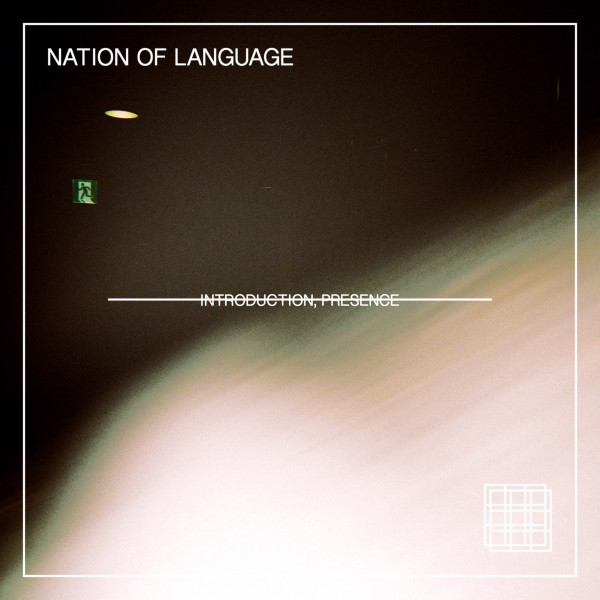
発売日: 2020年5月22日
ジャンル: シンセポップ、ポストパンク、ニューウェーブ
⸻
概要
『Introduction, Presence』は、ブルックリンを拠点に活動するシンセポップ・トリオ、Nation of Languageのデビュー・アルバムであり、1980年代のニューウェーブとポストパンクの美学を現代的な感性で再構築した、驚くほど完成度の高い“懐かしくも新しい”1枚である。
フロントマンのイアン・デグラフ(Ian Devaney)を中心に、Joy DivisionやOrchestral Manoeuvres in the Dark(OMD)、New Orderといったバンドに影響を受けながらも、単なるオマージュにとどまらず、Z世代的な内省や焦燥感をポップに昇華している点が本作の最大の魅力だ。
“Introduction(導入)”という言葉が示すように、本作はNation of Languageの名刺代わりのような役割を果たしつつ、“Presence(存在感)”という単語によって、聴き手の現実に確かに響く“気配”を残す。
それは、ただのレトロな引用ではなく、「現代という不安定な時代を、過去の音で照らす」という極めて現代的な試みなのである。
⸻
全曲レビュー
1. Tournament
ミニマルなシンセと鋭いベースラインで幕を開けるオープナー。
無機質なリズムの中に徐々に熱量が宿り、「戦い(Tournament)」というタイトルが示す緊張と決意が音として伝わる。
2. September Again
本作の代表曲にして、青春の残像と季節感が交差するシンセポップ・アンセム。
「また9月が来たけど、何も変わっていない」——そう呟くようなボーカルに、繰り返される時間への苛立ちと愛着が滲む。
3. On Division St.
タイトルはブルックリンの通り名から。
都市の風景と孤独が織り交ざったこの曲は、無機質な街並みに感情を投影する、まさにニューウェーブ的手法の結晶。
メロディは優しく、どこか心地よい哀しみを伴う。
4. Rush & Fever
エネルギッシュで反復的なリズムが印象的。
「高揚と熱狂」のタイトル通り、感情が制御不能になる瞬間をサウンドで体現しており、ダンスフロアと内面世界が重なる楽曲。
5. The Motorist
機械仕掛けのようなビートと、人間らしさを削ぎ落としたようなボーカル。
車の運転手=人生の運び手というメタファーが、テクノロジーと孤独の時代性を鋭く浮かび上がらせる。
6. Pretty Boy
シンプルなコード進行と切ないメロディラインが印象的な、静かな感傷曲。
“綺麗な顔”という言葉に込められた複雑なアイデンティティと視線の関係性がテーマ。
まるでThe Smithsのような文学的なニュアンスも感じられる。
7. Sacred Tongue
宗教的とも解釈されうるタイトルとリフレインが、神聖さと肉体性のせめぎ合いを象徴。
無数の言葉のなかに“意味”を探し続ける姿勢が現代的であり、詩的でもある。
8. Automobile
再び“移動”をテーマにした、心地よい疾走感を持つトラック。
人生を旅にたとえる比喩が、リズミカルなシンセと共に爽やかに響く。
この曲には、他の曲以上に「風」が吹いている。
9. Friend Machine
SNS時代の“友達”をアイロニカルに描いた名曲。
「僕の親友はマシンの中にいる」というフレーズが刺さる、ポストデジタルな孤独の讃歌。
トランジスタ感あるシンセが印象的で、テーマとの親和性が高い。
10. House in the Country
アルバムの終盤に置かれた、ややノスタルジックで牧歌的な曲。
都会からの逃避、静かな生活への憧れが、柔らかなリズムとともに語られる。
終わりに向かってテンションが穏やかになる構成が心地よい。
11. The Wall & I
ラストを飾るスロウテンポの名曲。
「壁と自分」という抽象的かつ内省的なテーマが、アルバム全体の“存在と不在”を総括する。
ぼんやりとした感情の輪郭が、薄明のように広がっていく終曲。
⸻
総評
『Introduction, Presence』は、Nation of Languageの音楽的ルーツと現代的な感性が完璧に融合した、デビュー作として異例の完成度を誇るアルバムである。
本作の魅力は、単に80年代風のサウンドを復刻しているのではなく、そのサウンドを使って2020年代の精神風景を描き出しているという点にある。
つまりこれは、“懐かしさ”というよりも“違和感の再構築”なのである。
反復するリズム、冷たいシンセ、抑制されたボーカル——それらが描き出すのは、コントロールのきかない世界の中で自分を見失わずにいるための“音楽的防御壁”であり、かつてのJoy DivisionやOMDがそうであったように、孤独を肯定する音楽なのだ。
また、本作のリリースは2020年というパンデミック最中であり、それゆえに「存在の気配=Presence」や「導入=Introduction」といった言葉が、音楽だけでなく、生活そのものと強く結びついて感じられたという時代性も重要である。
⸻
おすすめアルバム(5枚)
- OMD『Architecture & Morality』
クラシカルな構成と現代性が交差するニューウェーブの代表作。 - New Order『Power, Corruption & Lies』
冷静なサウンドと感情の反復が同居する、80sポップの金字塔。 - The Radio Dept.『Clinging to a Scheme』
メランコリックでエレクトロなサウンドと内省的な歌詞の融合。 - Future Islands『Singles』
シンセを駆使しながらも、身体的な感情表現を重視するバンド。 - Interpol『Turn On the Bright Lights』
ポストパンク的な暗さと鋭さを現代化した、重厚なデビュー作。
⸻
7. 歌詞の深読みと文化的背景
Nation of Languageのリリックは、直接的な物語ではなく、感情の輪郭だけを残していくような詩的手法が特徴的である。
「Friend Machine」では、SNSを通じて構築される“関係の幻”が描かれ、「September Again」では時間の反復に対する苛立ちが、「The Wall & I」では壁=遮断と共にある自我の静かな苦悩が、それぞれ抽象的な言葉で示される。
このような言語感覚は、明確なストーリーではなく、“感情の漂流”としてのポップスを可能にしており、それがニューウェーブと現代詩の交差点のような美学を成立させている。
『Introduction, Presence』は、“あるかもしれない感情”を、音と言葉でそっと輪郭づけるアルバムである。


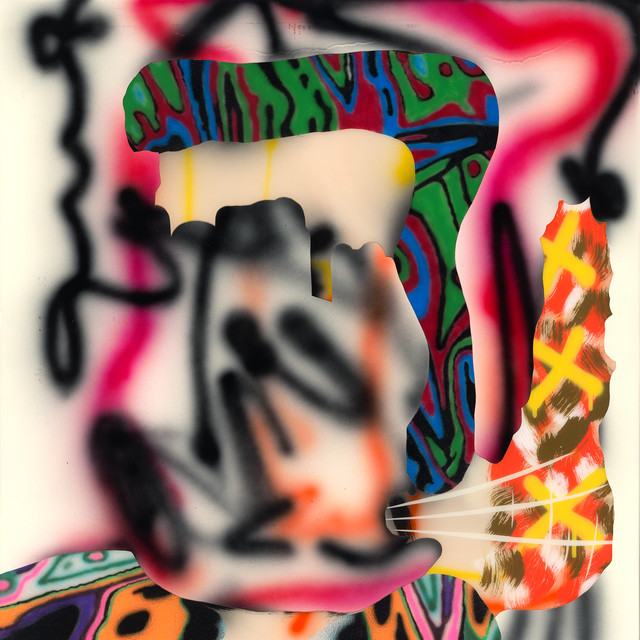

コメント