
発売日: 1997年9月9日
ジャンル: インディー・ロック、オルタナティヴ・ロック
2. 概要
『Indoor Living』は、アメリカ・ノースカロライナ州チャペルヒルのインディー・ロック・バンド、Superchunk が1997年に発表した6作目のスタジオ・アルバムである。
レーベルは彼ら自身が運営する Merge Records。録音はインディアナ州ブルーミントンの Echo Park Studios、ミックスは地元ダーラムの Overdub Lane で行われた。
プロデュースとエンジニアリングを担ったのは、地元ノースカロライナの John Plymale とバンド自身。
前作『Here’s Where the Strings Come In』の“ギター・バンド然としたインディー・ロック”から一歩進み、本作ではピアノ、オルガン、ヴィブラフォンなどを導入し、サウンド・パレットを大きく広げている。
全11曲・約48分。速度と轟音で押し切るというより、ミドルテンポを主体に“余白”を生かした楽曲が多く、Pitchfork は本作を「午後4時のレコード」、つまり“昼と夜のあいだの、少し落ち着かない時間帯”を描いた作品と形容している。
バンド史の文脈で見ると、『Indoor Living』は“成長”や“定住”というテーマと真正面から向き合った一枚である。
Aquarium Drunkard は、本作を“ツアーに明け暮れるバンドが、仕事・生活・大人としての責任と向き合い始めたときの不安に満ちたレコード”と評し、Amazon などの紹介文でも“人が室内(Indoor)に馴致されていく=家に帰り、暮らしを整えていくプロセス”を描いた作品だと説明している。
その一方で、チャート面ではカレッジ系のランキングで上位に入り、US CMJチャートで4位を記録している。
つまり『Indoor Living』は、実験的な音作りとポップ・センスを両立させつつ、当時のインディー・コミュニティの中核としてしっかり受け止められた作品なのだ。
全体のトーンは、前作までの“外へ向かう焦燥”に比べて、明らかに“内側へ沈むざわめき”が強い。
しかしそれは、エネルギーを失ったという意味ではなく、“生活を手に入れながらも、まだ落ち着けない”という現実的な不安の音像化である。
スピードを抑え、そのぶん和音やアレンジの細部に神経を行き届かせることで、Superchunk は“オトナのインディー・ロック”へと移行していくことになる。
3. 全曲レビュー
1曲目:Unbelievable Things
オープニングの「Unbelievable Things」は、アルバム全体のムードを決定づける重要な一曲である。
ギターはクリーン寄りのアルペジオと軽く歪んだコードを行き来し、ピアノとオルガンが背景で揺らめく。
ドラムとベースは前に出すぎず、じわじわと押し寄せるタイプのグルーヴをつくっている。
メロディは抑制されつつもフックがあり、サビで少しだけレンジを持ち上げることで、静かな高揚感を生み出す。
“信じがたいこと(Unbelievable Things)”というタイトルは、青春期の劇的な出来事ではなく、大人になってから目の前に現れる現実――仕事、疲労、関係の変化――に対する驚きのようにも受け取れる。
「On the Mouth」の「Precision Auto」のような即効性の爆発ではなく、じわっと染みてくる序章。
ここで既に、“これは別種類の Superchunk なのだ”という予感が伝わってくる。
2曲目:Burn Last Sunday
「Burn Last Sunday」は、タイトルどおり“先週の日曜日を燃やしてしまえ”という、過ぎ去った時間への決別を思わせる曲である。
テンポは中庸で、ギターは開放弦を生かしたコードを刻み、そこにピアノが点描的に音を置いていく。
サビではコーラスが重なり、わずかにトーンが明るくなるが、全体としてはすっきりしない感情の残り香が漂う。
歌詞は、ダラダラと過ごしてしまった休日、後回しにした決断、言えなかったひと言など、日常の小さな後悔を積み重ねたようなイメージを持つ。
“ではそれを全部燃やして、新しい週を始められるのか?”という問いが、直接言葉にされることなく、音の隙間に滲んでいるようなのだ。
3曲目:Marquee
「Marquee」は、アルバム前半で最も分かりやすくポップな楽曲のひとつ。
ギター・リフはシンプルだが非常に印象的で、サビに向かってスッと伸びるメロディが、Superchunk 的パワー・ポップの系譜をしっかり受け継いでいる。
ドラムはタイトな8ビートで曲を引っ張るが、『On the Mouth』時代ほど前のめりではなく、“飛び跳ねる”というより“歩幅を保って走る”ような感触である。
“Marquee(劇場の看板)”というタイトルは、表に出るもの/目に見えるものへの意識を連想させる。
バンドとしての知名度が上がり、名前がフェスのラインナップや雑誌の紙面に並ぶようになる一方で、当人たちの生活実感は必ずしもスムーズではない――そうしたギャップを暗示しているようにも感じられる。
4曲目:Watery Hands
「Watery Hands」は、本作からシングルとしてもカットされ、コメディアンの David Cross と Janeane Garofalo が出演するMVも制作された、アルバムを代表する一曲である。
イントロのギターは軽快で、ドラムも比較的前のめり、Superchunk らしい疾走感が戻ってきたように感じられる。
しかしメロディやコード進行はどこか切なく、サビでは“水っぽい手”という奇妙なイメージが繰り返される。
“掴みたいのに滑り落ちてしまうもの”“握っても形を保てないもの”としての“Watery Hands”。
それは、安定した生活や、関係性や、自分の中の確信といったものを象徴しているのかもしれない。
明るくふるまうギター・ロックの皮膚の下に、どうしようもない不安が染み込んでいる――そういう意味で、この曲はまさに『Indoor Living』の核心を体現している。
5曲目:Nu Bruises
「Nu Bruises」は、比較的短めでテンポも速く、初期 Superchunk に通じるパンク・エネルギーをまとった曲である。
タイトルは “New Bruises(新しいあざ)” をもじったものと思われ、“古い傷が癒えないうちに、また新しい打撲を負ってしまう”ような日々を連想させる。
ギターは荒々しく刻み、ベースはシンプルなルートを堅実に支え、ドラムはフィルを多用しながらも曲全体の勢いを途切れさせない。
歌詞は断片的ながら、“新しいあざ”という比喩を通じて、日常生活の中で小さく蓄積していく傷や疲労を浮かび上がらせる。
『Indoor Living』が“生活に適応すること”を描いたアルバムだとすれば、この曲はその中でもっともストレートに“痛み”を鳴らした一曲と言える。
6曲目:Every Single Instinct
アルバムの中盤を担う「Every Single Instinct」は、タイトルどおり“あらゆる本能”がテーマになっているような曲である。
テンポはミドルで、ギターはコードを鳴らしながらも、間を意識したフレーズを挟み込む。
かつての“常に前に詰める”アンサンブルから一歩引き、音と音の隙間に緊張が生まれるような構成なのだ。
歌詞では、“直感に従うべきなのか、それとも頭で考えるべきなのか”という、年齢とともに増していく迷いが透けて見える。
若い頃は“本能のまま突っ走ればそれでいい”と信じられたが、生活や仕事、周囲の人々との関係が複雑になっていく中で、そうもいかなくなる――その葛藤がにじんでいる。
サビで一瞬だけ感情が高まり、その後すぐに落ち着く流れも印象的である。
全力で叫び切るのではなく、“飲み込んだまま歌う”という表現を選んでいる点に、本作の成熟がよく表れている。
7曲目:Song for Marion Brown
「Song for Marion Brown」は、そのタイトル通り、フリー・ジャズ/スピリチュアル・ジャズのサックス奏者 Marion Brown へのオマージュとして知られる楽曲である。
サウンドはジャズそのものではないが、コードの動きや音の重ね方に、どこか広がりのある和声感が導入されている。
ギターのトーンも柔らかく、ドラムは細かいシンバルワークで空間を彩る。
Marion Brown の音楽が持っていた、静かなスピリチュアリティや、都市と内面の両方を見つめる視線。
そうした要素を、“Superchunk 的なインディー・ロックのフォーマット”に翻訳したような一曲と言える。
“インドア(Indoor)”な生活の中で、外の世界やジャズの歴史にも耳を傾けている――そんな、バンドの視野の広さも垣間見える瞬間である。
8曲目:The Popular Music
「The Popular Music」は、曲名からして意味深なナンバーだ。
ギターはざらつきつつもコンパクトなリフを繰り返し、ベースとドラムはやや跳ねたグルーヴで曲を前に押し出す。
メロディはキャッチーだが、どこか皮肉を含んだフレージングで、“ポピュラー・ミュージック”という言葉を、そのまま素直に肯定しているとは感じにくい。
歌詞では、ラジオやテレビで流れる“人気の音楽”、チャートやランキング、そうした世界とインディー・バンドとしての自分たちの距離感が、比喩的に語られているように読める。
自分たちも“ある種のポピュラーさ”を獲得しつつ、その構造に完全に取り込まれることへの違和感も抱えている――そうした複雑な立ち位置が反映された曲である。
9曲目:Under Our Feet
「Under Our Feet」は、タイトルどおり“足元にあるもの”を見つめるような楽曲である。
テンポは落ち着いており、ギターはアルペジオを主体にしたアレンジ。
低音域ではベースがじわじわとしたうねりを描き、ドラムは必要最小限のフィルで支える。
歌詞では、床・土・地面といったモチーフが断片的に現れ、目線を遠くではなく“今立っている場所”に向けるよう促してくる。
“バンドのキャリア”“ツアーの移動”といった大きなスケールではなく、暮らしている部屋や街路の細部を見つめる視線が象徴的である。
暮らしの中のささやかな違和感、少しだけズレた家具の位置、部屋の温度――そうしたディテールを通じて、“大人になったインディー・バンドのリアル”が浮かび上がる。
10曲目:European Medicine
「European Medicine」は、タイトルからして海外ツアーや長距離移動の匂いがする一曲だ。
テンポは中速で、ギターは少しダークなコード・ワークを採用し、メロディもどことなく不穏さを帯びている。
“ヨーロッパの薬”というフレーズは、文字通りの薬物かもしれないし、ツアー中に出会うカフェイン、アルコール、夜更かし、あるいは文化そのもののメタファーかもしれない。
ツアー先での時差ボケ、言葉の通じにくさ、非日常と日常の切り替え――そうした“旅の副作用”をまとめて“European Medicine”と呼んでいるようにも感じられる。
『Indoor Living』というタイトルのアルバムにおいて、異国の風景を想起させるこの曲は、“家”と“移動”の緊張関係を浮かび上がらせる重要なピースである。
11曲目:Martinis on the Roof
ラストを飾る「Martinis on the Roof」は、このアルバムの着地点としてきわめて象徴的な曲である。
屋上でのマティーニというシチュエーションは、どこか都会的で、少しだけ疲れた大人の時間を思わせる。
サウンドは静かながら芯があり、ギターとピアノが穏やかな和音を重ね、ドラムはブラシ的なニュアンスも交えつつ控えめにリズムを刻む。
歌詞のトーンは、達観と諦念、そしてわずかな希望が混ざり合ったようなものだ。
劇的なカタルシスではなく、ビルの屋上で夜風に吹かれながら、“今日も何とかやり過ごしたな”と小さく息を吐く瞬間のような終わり方なのだ。
ここまで聴き進めてくると、『Indoor Living』というアルバムが、決して“完璧な大人”を描いているわけではないことが分かる。
むしろ、“まだ不器用なまま大人になってしまった人たち”の揺らぎを、そのまま音楽にした作品なのである。
4. 総評
『Indoor Living』は、Superchunk のディスコグラフィの中で“地味”と形容されることもあるが、実はバンドの成熟と拡張をもっとも繊細な形で結晶させた一枚である。
まずサウンド面での変化が大きい。
Echo Park Studios での録音、John Plymale とバンドによる共同プロデュースのもと、ギター・バンドとしての骨格はそのままに、ピアノ、オルガン、ヴィブラフォン、補助的なパーカッションなどが積極的に導入されている。
『On the Mouth』や『Here’s Where the Strings Come In』に顕著だった“常に前のめりなインディー・パンク”から一歩引き、音と音のあいだに空気を残すことで、楽曲ごとの陰影がより豊かになった。
Pitchfork が“午後4時のレコード”と表現したのも頷ける話で、真昼の勢いと真夜中の内省の中間にある、何とも言えない時間帯を音で掴み取ったような作品なのである。
楽曲面では、「Unbelievable Things」「Burn Last Sunday」「Every Single Instinct」といったミドルテンポ曲が、アルバムの骨格を成している。
そこに「Watery Hands」「Nu Bruises」「The Popular Music」など、昔ながらのスピードとフックを持つ曲が要所要所で挟み込まれ、全体としては緩急のバランスが非常に良い。
特に「Watery Hands」は、MV制作や単独シングル化も含め、“ポップ・ソングとして前面に押し出せる Superchunk”の代表例となった。
一方で「Song for Marion Brown」「European Medicine」「Martinis on the Roof」といった楽曲は、ジャズやツアー生活、都市の夜といったモチーフを通じて、生活感と芸術性を同時に描き出している。
テーマ面で見ると、『Indoor Living』は“ドメスティケーション(家に収まっていくこと)”がキーワードになっている。
Amazon の紹介文が“人間が室内に馴致されていくプロセス”と説明し、Aquarium Drunkard が“バンドが大人としての責任と、ツアー中心の生活との葛藤を抱え始めた作品”と評したように、ここで歌われているのは、単なる恋愛や青春ではない。
仕事、家賃、疲労、健康、都市、ツアー。
そうした非常に現実的な要素が、直接的な歌詞ではなく、部屋・床・薬・日曜日といった比喩的なイメージを通じて描かれていく。
結果として、『Indoor Living』は“インディー・ロックが30代を迎えたときの風景”を巧みに写し取ったレコードになっている。
同時代の作品と比較すると、Radiohead『OK Computer』が巨大なテクノロジー社会の不安を描き、Blur や Pavement がブリットポップ/ローファイの文脈で90年代後半を総括していたのに対して、Superchunk はもっとミクロな視点――“部屋の中の暮らし”――から同じ時代を見つめていたように思える。
そのスタンスは、のちに多くのエモ/インディー・ロック・バンドが“日常の細部”を歌う方向へ向かう流れとも共鳴しており、直接的に引用されることは少なくとも、『Indoor Living』的な“生活スケールのオルタナ”はその後のシーンの基調のひとつになっていく。
評価面では、リリース当初から“成熟した作品”“意欲的な転換点”として語られてきた。
Treble や Pitchfork の再評価レビューは、本作を“バンドの初期の偉大な一連の作品の中で、もっとも気分に左右される・ムーディーな一枚”として位置づけ、“ほとんど歳を取っていないように聞こえる”と書いている。
一方で、ライヴ音源と並べて聴くと、バンド自身は依然として“Slack Motherfucker”を叫んでいた頃と変わらぬ勢いを保っていたこともわかる。
つまり“成長=丸くなる”ではなく、“成長=表現の幅が広がる”という形でキャリアを重ねていった、その最初の大きなステップが『Indoor Living』なのだ。
日本のリスナーにとって、『Indoor Living』は即効性のある名曲揃いの『On the Mouth』や『Foolish』に比べると、少し取っつきにくく感じるかもしれない。
しかし、何度か聴き返すうちに、部屋でひとり過ごす夜や、休日の夕方の少し憂鬱な時間帯に、驚くほどフィットしてくる。
そうなったとき、このアルバムは“派手な代表作”ではなく、“生活のそばに置いておきたい一枚”としての輝きを放ち始めるのである。
5. おすすめアルバム(5枚)
- Here’s Where the Strings Come In / Superchunk(1995)
前作にあたる5作目。
「Hyper Enough」「Detroit Has a Skyline」など、疾走感あふれるギター・ロックと、陰影のあるミドル曲がバランスよく共存するアルバム。
ここから『Indoor Living』への移行を追うことで、Superchunk のサウンドがどのように“室内化”していったかがよく見えてくる。 - Come Pick Me Up / Superchunk(1999)
『Indoor Living』の次作。
プロデューサーに Jim O’Rourke を迎え、ホーンやストリングスなどを大胆に取り入れた、さらに一歩進んだオーケストレーションが特徴。
“生活を見つめるインディー・ロック”という路線を、より豊かなサウンドで押し広げた一枚である。 - Foolish / Superchunk(1994)
『Indoor Living』の少し前、バンド内の関係性の崩壊を背景にした、極めてパーソナルで痛烈な作品。
感情の生々しさは本作以上で、失恋や別れの心理をインディー・ロックのフォーマットで描き切っている。
『Indoor Living』がその後の“大人の生活”を描いたアルバムだとすれば、『Foolish』はその前夜に起きた感情の崩壊を記録した作品と言える。 - OK Computer / Radiohead(1997)
同じ1997年にリリースされた、言わずと知れたオルタナ/アート・ロックの金字塔。
巨大なテクノロジー社会への不安を描いたこの作品と、“部屋の中の生活”を描いた『Indoor Living』を並べて聴くと、
同じ時代を異なるスケールで見つめた二つの視点として、90年代後半の空気が立体的に浮かび上がってくる。 - Clarity / Jimmy Eat World(1999)
エモ/インディー・ロックの名盤として知られる一枚。
内省的な歌詞と緻密なアレンジで、生活や感情の細部をすくい取るスタイルは、『Indoor Living』以降の Superchunk とも共鳴している。
スピードと爆発よりも、ミドルテンポの中で感情を積み上げていく作法を比較して聴くと興味深い。
6. 制作の裏側
『Indoor Living』の制作背景には、バンドのライフスタイルの変化が色濃く影を落としている。
『Here’s Where the Strings Come In』までの Superchunk は、長期ツアーとレコーディングをひたすら繰り返す“走り続けるバンド”だった。
しかし90年代中盤を過ぎる頃には、メンバーがそれぞれ仕事や生活の拠点を持ち始め、音楽活動と日常生活をどう両立させるかが大きなテーマになっていく。
そうした状況の中で、『Indoor Living』のレコーディングはインディアナ州ブルーミントンの Echo Park Studios で行われた。
プロデューサー/エンジニアの John Plymale は、地元ノースカロライナのミュージシャンとも縁が深く、バンドにとって“身内に近い感覚”を持てる存在だったと言われる。
スタジオでは、従来のギター・ベース・ドラムのトリオ+1という編成に、ピアノやオルガン、ヴィブラフォンなどの楽器を加える試みが積極的になされた。
これは単なる“装飾”ではなく、“部屋の中の空気”や“夕方の光”といった情景を音で描くための手段として導入されたものだと言える。
Treble や Pitchfork のレビューが指摘するように、その結果として『Indoor Living』は、バンドにとって最も“ムーディー”で“時刻感覚のある”アルバムになった。
さらに Merge Records という自前レーベルの存在も重要である。
メジャー契約に流れず、自分たちのレーベルからリリースし続けることで、Superchunk は制作スケジュールの自由度やサウンド面での実験性を確保していた。
“インドア”というテーマのアルバムを、外部からの強い商業的プレッシャーを受けずに作れたのは、Merge の自律性あってこそと言ってよいだろう。
2014年にはリマスター盤がリリースされ、当時のマスターテープをもとに音圧と解像度がアップしたヴァージョンが再評価のきっかけとなった。
バンドキャンプでの再発では、同時期のライヴ音源『Clambakes Vol. 8: We’d Like to Thank the Homecoming Committee』もボーナスとして提供され、スタジオ盤とライヴ盤を対で楽しめる形になっている。
こうした一連の再発と回顧記事が示しているのは、Superchunk にとって『Indoor Living』が単なる“過渡期の作品”ではなく、“大人になっていく過程を閉じ込めた重要な記録”として認識されている、という事実である。
9. 後続作品とのつながり
『Indoor Living』ののち、Superchunk は1999年に『Come Pick Me Up』、2001年に『Here’s to Shutting Up』をリリースしていく。
『Come Pick Me Up』では、Jim O’Rourke のプロデュースのもと、ホーンやストリングスを大量に導入し、サウンド・レンジをさらに拡張する。
ここでは『Indoor Living』で試された鍵盤や音色の実験が、よりダイナミックなオーケストレーションへと昇華されており、“インディー・ロック+室内楽的アレンジ”という路線が明確になる。
続く『Here’s to Shutting Up』では、テンポがさらに落ち、アコースティック色やカントリー/フォーク的要素も強まり、“大人のオルタナ”という領域に踏み込んでいく。
Bone Rolling Reviews などの評価では、『Indoor Living』は“初期のポップパンク色と、後期の大人びた内省のちょうど中間に位置するバランスの良い作品”とされており、その橋渡しとしての機能が強調されている。
さらに、2010年代以降の『Majesty Shredding』『I Hate Music』『What a Time to Be Alive』『Wild Loneliness』といった復活〜円熟期の作品を振り返ると、
“速くてラウドなギター曲”と“ミドルテンポで生活感のある曲”という二本柱は、まさに『Indoor Living』の時点で既に形になっていたことが分かる。
つまり、『Indoor Living』は初期のインディー・パンク期と、後期の円熟期のちょうど中間に位置する“ハブ”でありながら、どちらかの影に隠れてしまうには惜しいほどの独自性を持ったアルバムなのだ。
Superchunk の全キャリアを俯瞰したとき、この作品は“人生と音楽のバランスを必死に探っている瞬間”を閉じ込めた、非常に人間くさい記録として、これからも聴き継がれていくだろう。
参考文献
- Wikipedia “Indoor Living”(作品基本情報、録音スタジオ、プロデューサー、リリース年、ラベルほか)
- Merge Records “Indoor Living” 商品ページ(リリース日、トラックリスト、2014年リイシュー情報)
- Pitchfork “Indoor Living Album Review”(アルバムのトーンに関する評価、“午後4時のレコード”という表現)
- Aquarium Drunkard “Unbelievable Things: The Story Of Superchunk’s Indoor Living”(制作背景、テーマ、バンドのライフステージとの関係)
- Superchunk 公式バイオ/ディスコグラフィ(スタジオ・アルバムの流れ、Merge Records の位置づけ、ツアーと制作の変遷)


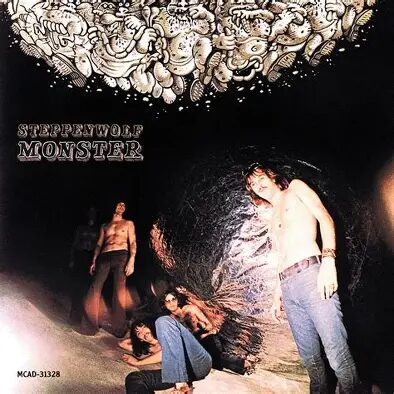
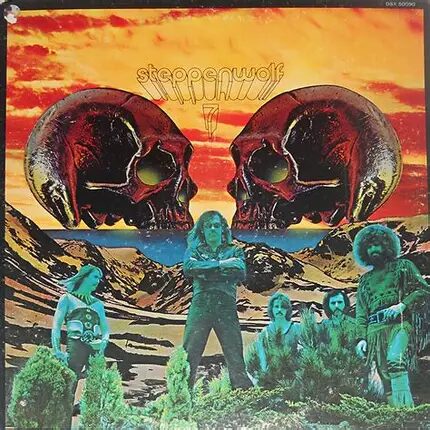
コメント