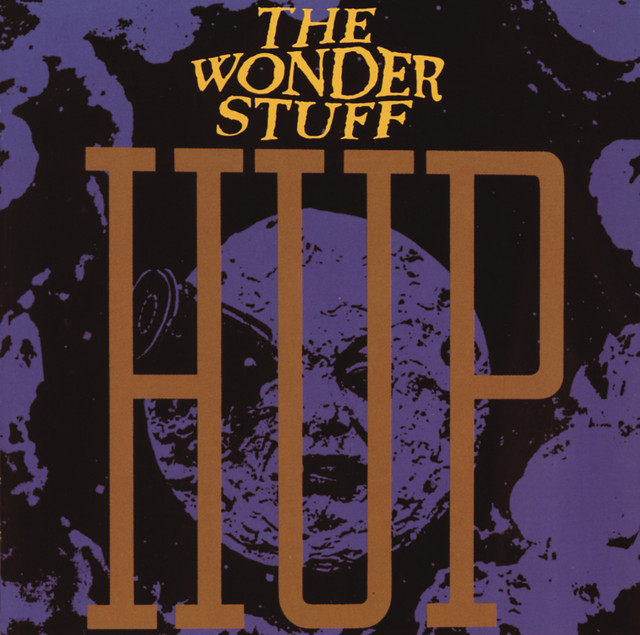
発売日: 1989年10月2日
ジャンル: インディーロック、フォークロック、オルタナティブポップ
概要
『Hup』は、イギリスのインディーロック・バンド、The Wonder Stuffが1989年にリリースした2枚目のスタジオ・アルバムであり、前作『The Eight Legged Groove Machine』の疾走感を継承しながらも、より多彩で深みのあるサウンドとソングライティングを打ち出した傑作である。
リリース当時、The Wonder Stuffはインディーチャートの常連として急成長していたが、『Hup』は彼らを“ジャンル横断的なバンド”として確立させた転換点ともいえる。
フォークやカントリーの要素を大胆に取り入れ、ヴァイオリンやアコーディオンといった楽器が導入されることで、単なるギターロック以上の広がりを獲得している。
一方で、Miles Huntの皮肉とユーモアに満ちたリリック、そして耳に残るキャッチーなメロディは健在。
社会や人間関係への懐疑的な視線を“軽やかな皮肉”として提示するそのスタイルは、同時代のThe SmithsやHousemartinsにも通じながら、よりフェス向けの開放感を持っている。
全曲レビュー
1. 30 Years in the Bathroom
オープニングから炸裂するアグレッシブなギターとヴォーカル。
「30年間トイレにいる」というシュールなタイトルは、自己嫌悪や逃避の比喩とも取れる。
バンドのエネルギーがそのままぶつけられたような衝撃的な一曲。
2. Radio Ass Kiss
軽快でポップなナンバーだが、メディア批判の要素が強い。
ラジオの世界における“おべっか”文化を風刺し、インディーらしい独立精神を感じさせる内容。
3. Them Big Oak Trees
ヴァイオリンが印象的なミッドテンポの楽曲。
“樫の木”という自然の象徴を通して、変わらぬもの・変わるものを対比的に描く。
フォーキーな響きが本作の多様性を象徴している。
4. Can’t Shape Up
疾走感と跳ねるビートが心地よいロック・ナンバー。
タイトルの「うまくやれない」という自嘲的フレーズに、若者の焦燥や社会への適応困難がにじむ。
5. Piece of Sky
シンプルなコード進行と親しみやすいメロディ。
“空のかけら”を求める歌詞は、夢や自由への希求をポップに表現している。
本作のなかでも最も前向きな印象を与える楽曲。
6. Let’s Be Other People
アイデンティティと仮面をテーマにした風刺的な楽曲。
「他の誰かになろう」という提案が、逆に現代社会の自己喪失を浮き彫りにする。
7. Don’t Let Me Down, Gently
アルバム中最も有名な楽曲のひとつで、UKチャートでもヒットした代表曲。
アップテンポでありながら、別れの予感と傷つきたくない気持ちが同居する名バラッド。
ヴァイオリンの旋律が切なさを引き立てる。
8. Cartoon Boyfriend
コミカルで少しサイケデリックなアレンジが印象的なナンバー。
“漫画のような彼氏”という架空の存在に、現実とのギャップや皮肉を込めている。
9. Good Night Though
ややダークなトーンのバラードで、アルバムの静かな中盤を支える一曲。
「それでもおやすみ」と語るMiles Huntの歌声に、疲れた人間の優しさが感じられる。
10. Unfaithful
軽快なテンポの裏に、裏切りと不信をテーマにした毒のある歌詞が展開。
楽しいメロディで深刻なテーマを描くThe Wonder Stuffの真骨頂。
11. Piece of Sky Reprise
5曲目のリプライズ。インスト的で幻想的なアレンジとなっており、アルバム全体にコンセプト的なまとまりを与える。
テーマの回帰が、物語的な余韻を残す。
総評
『Hup』は、The Wonder Stuffが“パンク×ポップ”から“フォーク×ロック×ポストモダン”へと歩みを進めた、音楽的な拡張の記録である。
サウンドのバリエーションは格段に増しながらも、彼らが大切にしてきた“皮肉とウィット”“キャッチーさと懐疑”という二律背反は一貫しており、むしろ強度を増している。
とりわけ「Don’t Let Me Down, Gently」や「Them Big Oak Trees」では、ただの愉快なバンドではない、深い感情とメロディの美学を持った存在としての姿が明確になる。
政治的でも、哲学的でもない、しかし非常に“人間的な知性”に満ちた作品なのである。
この時期のThe Wonder Stuffは、単なるインディーロックの一端ではなく、UKポップ史において確実に“ひとつの異端的クラシック”を形成していたといえる。
おすすめアルバム
- The Levellers / Levelling the Land
フォークとロックの融合という点で『Hup』と共鳴。 - The Waterboys / Fisherman’s Blues
ケルト的なスピリットとロックの結合が近い感触を与える。 - James / Gold Mother
同時代のUKインディーとして、スピリチュアルなテーマ性が響き合う。 - House of Love / The House of Love
より内省的だが、ギターポップとしての美学はThe Wonder Stuffと並走。 - Billy Bragg / Workers Playtime
語り口のユーモアと社会性、そして親密さが共通する。
歌詞の深読みと文化的背景
『Hup』の歌詞には、80年代末のイギリスに蔓延していた“個人主義と幻滅”が底流として存在している。
サッチャー時代の終焉を目前にした時代に、Miles Huntは“怒るでもなく、笑い飛ばす”という知的なスタンスで社会を見つめていた。
「Let’s Be Other People」は自己変容というより“自己から逃げること”への皮肉であり、「Don’t Let Me Down, Gently」は感情を直視できないまま揺れる人間のリアルな弱さを描いている。
The Wonder Stuffのリリックは、決して文学的ではない。
だが、そのぶん日常のスラングや観察眼が鋭く、同時代のリスナーの言葉として“生きていた”のである。
『Hup』は、そんな彼らの言語と音の到達点のひとつといえるだろう。


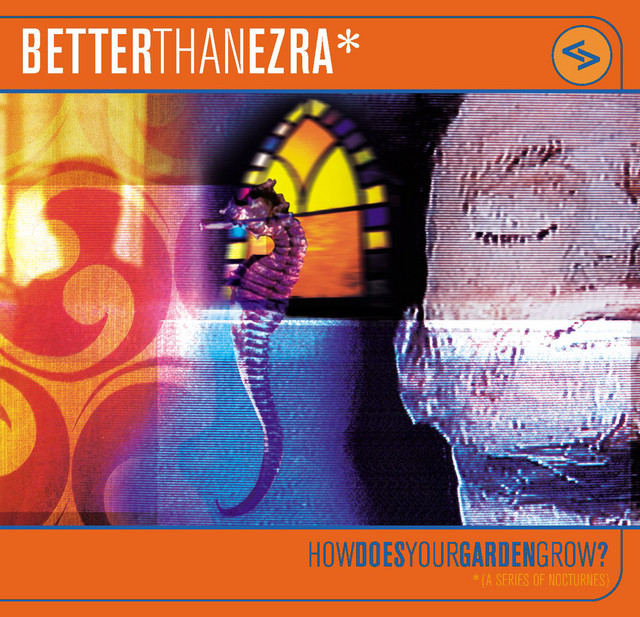

コメント