
1. 歌詞の概要
「Here Comes Your Man」は、Pixiesが1989年にリリースしたセカンド・アルバム『Doolittle』に収録された楽曲であり、バンドの中でも最もポップでキャッチーな楽曲のひとつである。
軽快なアコースティック・ギターのリフと、明るくポップなメロディラインが印象的で、当時のPixiesにおけるノイズや不協和音、シュールなイメージとは一線を画すような仕上がりになっている。そのためファンの間では異色作としても知られているが、その“異質さ”こそが、この曲を特別な存在にしているのだ。
タイトルの「Here Comes Your Man(君の男がやってくる)」という一節は、誰かの恋人やパートナーが到着する場面を描いているようにも受け取れるが、その背後にはより複雑で謎めいたテーマが潜んでいる。明るく響く音像とは裏腹に、歌詞には“地震”や“列車事故”といった不穏なイメージが差し込まれており、Pixiesらしいブラックユーモアとアイロニーが隠されているのである。
2. 歌詞のバックグラウンド
Pixiesは、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、オルタナティヴ・ロックの先駆者としてシーンに大きな影響を与えたバンドである。中でも『Doolittle』はその代表作とされ、サーフロック、ノイズ、パンク、フォークの要素を巧みに織り交ぜたこのアルバムは、後のグランジやインディーロックに多大な影響を与えた。
「Here Comes Your Man」は、実はBlack Francis(本名Charles Thompson)がティーンエイジャーの頃に書いた楽曲で、Pixiesの初期デモ『The Purple Tape』の時点ですでに存在していた楽曲だった。しかし、当時のバンドはこのポップすぎる曲を“恥ずかしい”と感じ、リリースをためらっていたという逸話がある。
それでも結局『Doolittle』の中に収録され、結果としてPixiesにとっての“代表的なヒット曲”となったのは、音楽の流れが変わりつつあった1989年という時代背景を象徴しているようにも思える。アンダーグラウンドのサウンドを持ちながらも、広く聴かれるポップさ——その境界線にある「Here Comes Your Man」は、まさにPixiesというバンドの矛盾と魅力を内包した一曲なのだ。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に印象的な歌詞の一部を抜粋し、和訳を添える。
引用元:Genius Lyrics – Pixies “Here Comes Your Man”
Outside there’s a boxcar waiting
外には貨物列車が待っている
Outside the family stew
外では家族のシチューが煮えている
Out by the fire breathing
火を吹くようにうねる世界の外側で
Outside we wait ‘til face turns blue
外で俺たちは待っている、顔が青くなるまで
I know the nervous walking
あの落ち着かない足取りはよく知ってる
I know the dirty beard hangs
無精髭が垂れてるのも見覚えがある
Out by the boxcar waiting
あの貨物列車のそばで、ずっと待っている姿
Take me away to nowhere plains
俺をどこにも行けない荒野へ連れてってくれ
Here comes your man
ほら、君の男がやってくる
Here comes your man
君の男が
4. 歌詞の考察
一聴すると明るく、まるでラジオヒットを狙ったようなポップソングに聞こえる「Here Comes Your Man」だが、その実、歌詞は不可解なイメージの集合体であり、Pixies特有のアート的皮肉が感じられる。
「boxcar(貨物列車)」という言葉は、米国文化ではホームレスや放浪者を象徴することがあり、ここでは定住せず流浪する者たち、あるいは社会の片隅に追いやられた人々のメタファーとして登場している。また、「地震」や「家が落ちてくる」といったフレーズも、生活の崩壊や予期せぬ災厄を暗示しているように読める。
こうした暗いイメージの中に突然現れる「Here comes your man」というリフレインは、皮肉とユーモアを交えた感情の捻れとして受け取ることができる。恋人の帰還のようでありながら、どこか得体の知れない存在が訪れる気配も孕んでいる。それは死者かもしれないし、運命かもしれない。
この曲は、メロディの快活さと歌詞の陰鬱さという二項対立の上に成立しており、そのギャップが聴く者に奇妙な引力を与えている。軽やかに口ずさめる一方で、その内側には都市の底辺に生きる者たちの孤独や、避けられない運命の重さが忍び寄っているのだ。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- This Monkey’s Gone to Heaven by Pixies
『Doolittle』収録のもうひとつの名曲。環境破壊や宗教観をテーマにしながらもキャッチーな構成を持ち、社会的寓意を詩的に描いている。 - The Man Who Sold the World by David Bowie
歌詞の解釈が多様で、どこか神秘的なポップソング。明るさと陰の同居という点で通じる世界観がある。 - Loser by Beck
90年代オルタナの代表的な一曲。無意味な言葉の羅列とポップなサウンドが奇妙にマッチしており、Pixies的なユーモアとアイロニーが感じられる。 - Under the Bridge by Red Hot Chili Peppers
都市と孤独、個人の疎外をテーマにしたポップロックの名曲。内省的ながら耳に残るメロディが印象的で、「Here Comes Your Man」との共鳴を感じられる。
6. 表と裏の顔を持つポップソング
「Here Comes Your Man」は、その明るさとキャッチーさゆえに、Pixiesの中では“異端”とされた楽曲だった。
しかし今振り返れば、この曲はPixiesというバンドの多面性——狂気と静寂、破壊と親密、前衛と大衆性——を象徴する重要な存在だったように思える。バンドが築き上げたラディカルな音楽性の中にあって、この楽曲はリスナーに対して微笑みかけながら、静かに毒を盛るような、そんな魅力を持っている。
一見“耳障りの良い”楽曲に見せかけて、その内側には荒廃と諦念、そしてどこか空虚な優しさが漂っている。それは、Pixiesが紡ぎ出す音楽が、ただ奇抜である以上に、人間の複雑な感情を掘り下げるものであったことの何よりの証明なのだ。


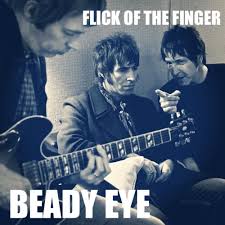

コメント