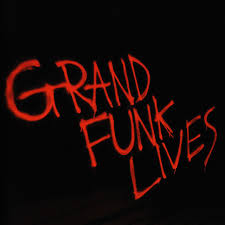
発売日: 1981年7月
ジャンル: ハードロック、AOR、ポップロック
再結成の咆哮、しかし影は深く——“あの頃”を取り戻そうとした男たちの記録
『Grand Funk Lives』は、Grand Funk Railroadが1981年に再結成しリリースした通算12作目のスタジオ・アルバムである。
1976年の『Good Singin’, Good Playin’』を最後に解散していたバンドが、ファーナーとブリュワーを中心に5年ぶりに始動。
だが、ここでの“Grand Funk”は、黄金期とは大きく異なる編成と音楽性をまとっていた。
ベーシストのメル・サッチャーは参加せず、代わりにデニス・バーデンを新たに迎えたトリオ体制。
時代はすでに80年代に突入し、ハードロックはよりメロディアスで洗練された“AOR”的スタイルへと進化していた。
本作でもその流れを受け、シンセサイザーやコーラスワークを導入したサウンドに変化が見られる。
タイトルが宣言するように「グランド・ファンクは生きている」と叫びながら、
その叫びの背景には、かつての栄光との距離、音楽シーンの変化への戸惑いがにじんでいるようにも感じられる。
全曲レビュー
1. Good Times
軽快で爽やかなAOR調のロックナンバー。
「良き時代をもう一度」というメッセージが込められており、再結成の喜びをそのまま音にしたような一曲。
2. Queen Bee
グルーヴィーでファンキーなベースが印象的。
タイトルの“女王蜂”は強い女性像の象徴であり、80年代的な性の主張がテーマに感じられる。
3. Testify
ゴスペルのような力強いコーラスと、ファーナーのソウルフルな歌声が際立つ。
“証言する”という宗教的・精神的テーマが込められた、重厚な一曲。
4. Can’t Be With You Tonight
メロウで哀愁漂うバラード。
再結成バンドならではの「過去の関係」に対する感情の整理が、歌詞にも反映されているようだ。
5. No Reason Why
ハードなギターリフで幕を開ける本格ロックナンバー。
“理由なんてない”という投げやりにも思えるフレーズは、迷いながらも進む心情の表れかもしれない。
6. We Gotta Get Out of This Place
The Animalsの名曲をカバー。
脱出願望と閉塞感を歌った原曲の精神を尊重しつつ、80年代仕様の厚みあるサウンドでリメイクされている。
7. Y.O.U.
ファーナー流のポップ・ロック。
ラブソングではあるが、どこか寂しさと無力感が入り混じる複雑な一曲。
8. Stuck in the Middle
リズミカルな展開と皮肉めいた歌詞が光る、異色の楽曲。
“真ん中で立ち往生している”という比喩は、バンドの立ち位置にも重なる。
9. Greed of Man
人間の欲望と社会問題をテーマにした、シリアスな一曲。
社会への批評性がうかがえる楽曲であり、再結成後のバンドの“真面目な問いかけ”でもある。
総評
『Grand Funk Lives』は、タイトルこそ力強く“生存”を宣言しているが、内容はむしろ迷いと模索に満ちた再出発の記録である。
かつての野獣のようなグランド・ファンクは姿を潜め、ここには時代に適応しようとする大人たちのロックがある。
AOR的なサウンド、ラヴソング中心の構成、そしてカバー曲の挿入は、
新たなリスナーへのアプローチを模索する姿勢であると同時に、
かつてのバンドの“らしさ”とのギャップを感じさせるものでもある。
とはいえ、“Testify”や“We Gotta Get Out of This Place”などに込められた情熱と信念は、
グランド・ファンクが単なる“懐メロ再生産”ではなく、今を生きようとしたバンドであることを証明している。
本作は、時代のうねりの中で自らの居場所を模索した、
再生ではなく再挑戦のアルバムなのである。
おすすめアルバム
-
『Born Again』 by Randy Newman
失意と皮肉をまとった80年代的ロック回帰。再起という点で共鳴。 -
『Raised on Radio』 by Journey
AORとロックの融合。ハードロックバンドの変化を象徴する一枚。 -
『90125』 by Yes
プログレからポップ路線へと大胆に転換した復活アルバム。 -
『King Biscuit Flower Hour Presents Grand Funk Railroad』
80年代のライヴ・エネルギーを記録した音源。再結成後のリアルな姿が垣間見える。 -
『In Through the Out Door』 by Led Zeppelin
終盤の音楽的模索とシンセの導入という点で共通する成熟期の作品。


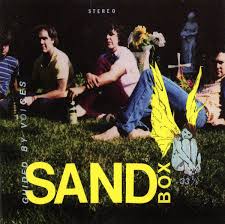
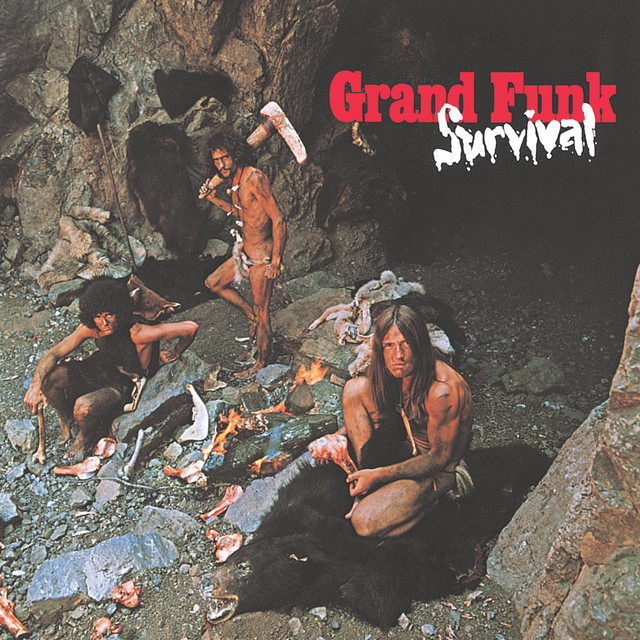
コメント