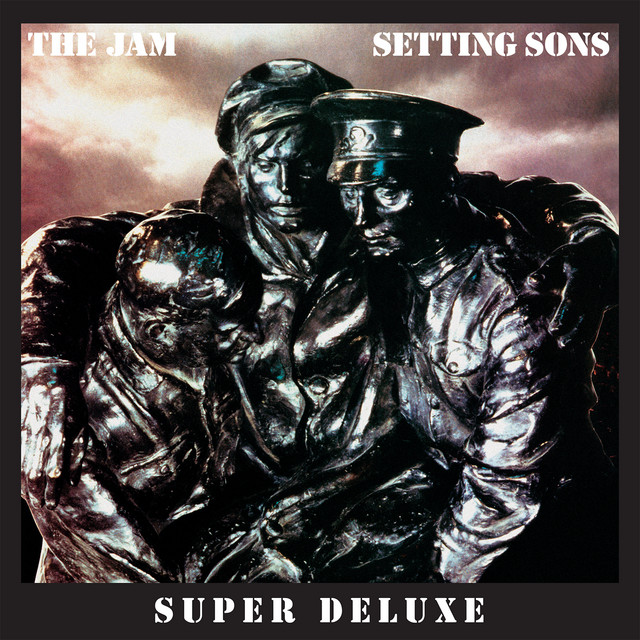
1. 歌詞の概要
「Going Underground」は、イギリスのモッズ・リヴァイヴァルを代表するロックバンド、The Jamが1980年にリリースしたシングルであり、発売初週で全英チャート1位に躍り出た彼らの初のナンバーワン・ヒットである。この曲は、急進的なテンポと攻撃的なギターリフを伴いながら、個人の信念と政治的無関心、そして体制への怒りをぶつけるように展開されていく。
タイトルの「Going Underground(地下に潜る)」は、体制や大衆の流れから距離を置き、“自分の信じるものを守るために表舞台から姿を消す”という象徴的な行為として描かれている。歌詞では、戦争や消費主義への批判、政治への幻滅がストレートに綴られ、ポール・ウェラーの社会に対する不信感と、若者の怒りがそのまま音と言葉に注ぎ込まれている。
一方で、これは単なる“反体制”の叫びではなく、「自分はこういう世界の一部にはなりたくない」という意志の宣言でもある。その態度はときにニヒリズム的でありながらも、誠実で清廉な決意に満ちており、理想主義的なメッセージを衝動的にではなく知的に伝えている点が本曲の特異性である。
2. 歌詞のバックグラウンド
「Going Underground」は、1980年3月にリリースされ、The Jamにとって初の全英1位を記録した記念碑的シングルである。当初は両A面として「Dreams of Children」とのセットで発売されたが、実質的にこの曲がメインとして評価され、大衆の怒りや違和感を代弁するアンセムとして急速に浸透していった。
作詞・作曲はポール・ウェラーによるもので、彼が感じていたサッチャー政権下のイギリス社会への違和感、戦争への懐疑、そして政治やメディアによって形づくられた“偽の選択肢”に対する嫌悪感が色濃く反映されている。特に歌詞中の“braying sheep on my TV screen”という一節には、当時の報道に登場する政治家や軍関係者に対する強烈な皮肉が込められており、単なるラブソングとは一線を画す社会派の視点が貫かれている。
「Going Underground」というフレーズ自体は、1960年代のカウンターカルチャーにも通じる言葉であり、ボブ・ディランやビート詩人たちが用いた“地上からの逃避=真実の追求”の象徴として知られていた。ウェラーはその伝統を受け継ぎつつ、パンク以後の現代社会のリアルに適応させ、よりシャープな言葉とサウンドで再構築した。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に「Going Underground」の印象的な一節を抜粋し、日本語訳を添えて紹介する。
Some people might say my life is in a rut
ある人たちは言うかもしれない——「俺の人生はマンネリだ」ってBut I’m quite happy with what I got
でも俺は、今の自分に満足してるI’m going underground
俺は地下に潜るSo the public gets what the public wants / But I want nothing this society’s got
大衆は、大衆が望むものを手に入れる/でも俺は、この社会が持ってるものなんていらないWe choose to go where we want to go
俺たちは、自分が行きたい場所を選ぶAnd now I’m going underground
だから俺は、地上を捨てて地下に潜るのさ
引用元:Genius Lyrics – Going Underground
4. 歌詞の考察
「Going Underground」の歌詞には、イギリス社会に対する冷静で苛烈な観察と、そこから距離を置こうとする個人の姿勢が濃密に描かれている。“公衆は欲しいものを手に入れる/でも俺はこの社会が持っているものなんて何もいらない”という核心的なフレーズは、まさにこの楽曲のテーマを象徴している。
ここに描かれる“地下に潜る”という行為は、敗北でも逃避でもない。むしろ、それは“多数派に迎合せずに、自分の感性と倫理に従って生きる”という積極的な選択である。戦争や資本主義の空虚さ、世論の操られ方などに対して、ただ怒りを爆発させるのではなく、自分の立場を明確にし、静かに抵抗する。その知的で抑制された“怒りの美学”こそが、ポール・ウェラーの詩的センスを際立たせている。
また、皮肉や風刺を駆使しながらも、語り手は一貫して“自分の価値観を守る”ことを選んでいる。これは80年代初頭のサッチャー政権による新自由主義化、階級格差の拡大、愛国主義の高まりといった政治状況を背景に、若者たちの多くが感じていた“自分の居場所のなさ”を見事に代弁していた。
※歌詞引用元:Genius Lyrics – Going Underground
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Town Called Malice by The Jam
体制への失望と希望の交錯を描いた社会批評ソウル。ポール・ウェラーの鋭い視点が共通。 - Clampdown by The Clash
体制への迎合と反抗を鋭く描いたパンクの名曲。社会と個人の関係性を問うテーマが重なる。 - Shipbuilding by Elvis Costello
戦争による景気回復という皮肉を描いた社会派バラード。深い洞察と優しい怒りが響く。 - Love Will Tear Us Apart by Joy Division
時代の虚無感と内省を描いたニューウェーブの金字塔。疎外感の感触が共鳴する。
6. 反抗は沈黙ではなく、選択のかたちへ
「Going Underground」は、怒りを叫ぶのではなく、怒りを“選択”として提示する。多数派に迎合することなく、自分の倫理に従って生きる姿勢——それこそがこの楽曲の核であり、The Jamというバンドの哲学でもあった。
1980年代という政治的緊張と経済的分断の時代に、The Jamはギターとドラム、そして詩によって、個人の尊厳と自立を描き出した。「Going Underground」はその中でも最も象徴的な楽曲であり、反体制ソングでありながらも、非常に静謐で、美しい余韻を残す。
“地下に潜る”という行為は、単なる逃避ではない。それは、地上の騒がしさに対する拒否であり、本質的な真実を求める行為だ。今日もなお、この曲は、違和感を抱えながら社会に生きるすべての人にとっての“静かな旗”であり続けている。




コメント