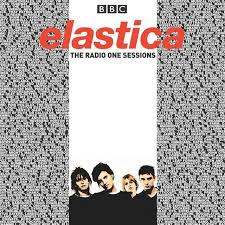
発売日: 2001年10月29日
ジャンル: ポストパンク、ブリットポップ、インディーロック、ローファイ
概要
『Elastica Radio One Sessions』は、イギリスBBCラジオの名物番組「John Peel Show」などで録音されたセッション音源を集めたコンピレーション・アルバムであり、
Elasticaの“スタジオとは異なる、生々しくて衝動的な顔”を切り取ったドキュメントとして極めて貴重な作品である。
収録されているのは、1993年から1999年までのセッション音源。
バンドがブリットポップの台頭を背景に急成長していく時期と、後期の実験的アプローチまでを網羅しており、
Elasticaというバンドの“瞬発力”“未完成性”“ラフさの美学”がむしろ際立つ構成となっている。
スタジオ音源では聴けなかった曲の原型や、後の変化を予感させるプレイ、
またラジオという“即興の場”でこそ映えるミニマルかつ鋭利な演奏は、
ポストパンク/ニューウェイヴ的アティチュードを色濃く宿すライブ・ドキュメントであり、
“完成”ではなく“断片”を愛でるリスナーにこそ響く作品である。
全曲レビュー(抜粋)
1. Annie(Peel Session, 1993)
後に『Elastica』に収録される初期の代表曲。
このセッション版はテンポも粗削りで、バンドの初期衝動そのままのパンク的エネルギーが宿っている。
2. Spastica(Peel Session, 1993)
シンプルなコード進行と鋭いリズム。
病名をパンク化したような挑発的タイトルが、Elasticaの“攻める姿勢”を象徴する。
3. Brighton Rock(Evening Session, 1994)
未発表曲の中でも人気の高いトラック。
ギターのリフが延々とループし、脱構築的な展開がバンドの実験的側面を垣間見せる。
4. Vaseline(Peel Session, 1994)
スタジオ版以上に速く、鋭い演奏。
ノイズと性的メタファーが交錯する様が、ライブの“剥き出しの美学”として昇華されている。
5. I Wanna Be a King of Orient-Ah(Peel Session, 1994)
未発表トラック。タイトルは東方三博士への皮肉な言及か。
宗教的イメージとアナーキーなサウンドの交錯がユニークな一曲。
6. Never Here(Evening Session, 1995)
『Elastica』収録曲の別バージョン。
より内省的でスロウなアレンジが施され、消失と不在というテーマがより強調されている。
7. KB(Evening Session, 1999)
『The Menace』収録版よりもラフで即興的。
この時期のElasticaがよりノイジーでローファイな美学に向かっていたことを示す資料的価値が高い音源。
8. Generator(Peel Session, 1999)
機械的なリズムが強調され、インダストリアル寄りのミニマルサウンドが前面に出ている。
ブリットポップからの決別を感じさせる一曲。
総評
『Elastica Radio One Sessions』は、Elasticaというバンドの本質が、実は“スタジオの完璧さ”ではなく“現場の衝動”にあったことを証明する音源集である。
短くて鋭くて、完成されていない。
しかしその断片の一つひとつが、90年代UKインディーの“瞬間の美学”を象徴するナイフのような存在感を放っている。
とりわけ、Peel Sessionの音源は彼女たちのパンク的出自やDIYスピリットを浮き彫りにし、
一方で後期のセッションには、解体されていくポップの断面と再構築の可能性が詰まっている。
これはElasticaの“裏名盤”であり、同時に彼女たちがなぜ特別だったかを再認識させてくれる記録である。
おすすめアルバム
- The Slits / Cut
女性によるポストパンクの原点的作品。セッション的ラフさと攻撃性が共通。 - The Fall / The Peel Sessions
ポストパンクにおける即興性と断片美の頂点。 - Wire / Document and Eyewitness
完成形を拒否したライブの記録。Elasticaとの精神的親和性が高い。 - Yeah Yeah Yeahs / Is Is EP
スタジオ音源とは異なるラフさと衝動が詰まったミニアルバム。 - Lush / Gala
セッション/EP集でありながら、全盛期の感覚を詰め込んだ作品としての魅力を持つ。
歌詞の深読みと文化的背景
本作に収められた歌詞の多くは、短いフレーズと皮肉、性や孤独にまつわる直接的表現で構成されており、
“語りすぎないことで力を持つ”ミニマルなパンク詩としての側面を強く持っている。
「Annie」や「Spastica」では、逸脱や拒絶を“遊び”として捉えるジェンダー批評的要素が、
「Never Here」や「KB」では、喪失感と自己解体の美学が透けて見える。
スタジオではなくラジオ、編集ではなく即興。
この作品は、“語ることがすでに行為になる”という、Elasticaらしい“音と言葉のアクション”の記録なのである。



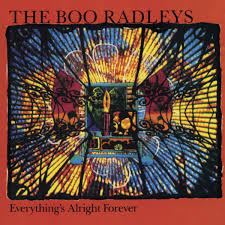
コメント