
発売日: 1979年7月**
ジャンル: クラウトロック、エクスペリメンタル・ロック、アートロック
自己を名乗るという行為の終着点——終焉と転生の間に揺れる“後期Can”の肖像
『Can(1979)』は、同バンドのセルフタイトル作品にして、初期の創造的爆発から10年を経た後期Canの“自己定義の最終形”と位置づけられる。
しばしば「Inner Space」とも呼ばれる本作は、オリジナル・メンバーであるホルガー・シューカイ脱退後、バンドが新たな局面を模索しながら生まれたアルバムである。
タイトルをバンド名と同一にすることで、一周回ってCanとは何かを問い直すメタ的な構成がうかがえるが、
その実、音楽的には従来のアヴァンギャルドさが後退し、よりコンパクトで構造的な“曲”としての楽曲が増えたのが特徴である。
これは、ある種のポストパンク的整合性への接近でもあり、Canというバンドが時代と共に変化しようとした“柔軟さ”と“終焉の兆し”が同居している。
全曲レビュー
1. All Gates Open
8分超のオープニングは、Canらしい持続的グルーヴとミニマルな展開美が健在の長尺トラック。
細やかなギターと浮遊するシンセがレイヤーを重ねながら、徐々に視界が開けていくような印象を与える。
本作では数少ない、“昔のCan”の残響をまとった楽曲。
2. Safe
タイトなリズムとポップなヴォーカルが交差する、1979年らしいポストパンク風アートロック。
フックのあるメロディラインと、淡白ながら不安定なビートが、時代との接点を感じさせる。
メンバーたちの“次の段階”を模索する試行錯誤のようにも聞こえる。
3. Sunday Jam
ゆったりとしたリズムに身を任せるような、レイドバックしたインストゥルメンタル。
ジャムバンド的な展開だが、Can特有の無意識的反復が静かに息づいている。
“日曜午後の無為”を音で表現したかのような感触。
4. Sodom
強めのビートと、やや攻撃的なギターが印象的なトラック。
宗教的ニュアンスのあるタイトルが象徴するように、どこか不穏でダークなムードが支配する。
Canにしては珍しく、重力感のあるサウンドに仕上がっている。
5. A Spectacle
最も異色な楽曲。シンセのポップな音色と、ソリッドなビートが交差するポストクラウト的ナンバー。
後のニューウェーブ/エレクトロ・ポップへの接続点とも感じられる。
タイトル通り、“見世物”のような派手さと奇妙さが同居する。
6. E.F.S. No. 99 (“Can Can”)
“Ethnological Forgery Series”の最終番号にして、かの有名な“カンカン踊り”のモチーフを大胆に引用したユーモラスな一曲。
ファンキーなビートとともに遊び心が全開で、Canの“実験=戯れ”という本質が最後の最後に顔を出す。
“CanがCanをやる”というセルフパロディとも解釈できる。
総評
『Can(1979)』は、ひとつの時代の終わりと、Canという名の“現象”が自己解体を始めた瞬間の記録である。
アルバム全体に漂うのは、初期の爆発的創造力を経た後の、落ち着きと空虚、そしてある種の“諦念”のようなもの。
だがそれはネガティブなものではなく、むしろ成熟した音楽家たちが、“音楽”という形そのものを静かに見つめ直した結果とも言える。
かつては音の混沌そのものであったCanは、ここで“形”を得る。
それは音楽史におけるCanの最後の風景であり、最初の自己言及だった。
おすすめアルバム
-
Wire『Chairs Missing』
ポストパンクと実験性の融合。『Safe』『Sodom』に通じる美学。 -
Brian Eno『Taking Tiger Mountain (By Strategy)』
構築されたポップと脱構築的サウンドの狭間を歩む知的作品。 -
Holger Czukay『Movies』
Can脱退後に発表されたホルガーの代表作。より自由なカットアップ精神が感じられる。 -
David Sylvian『Brilliant Trees』
静謐で内省的なアートロック。後期Canの空気感を受け継ぐ。


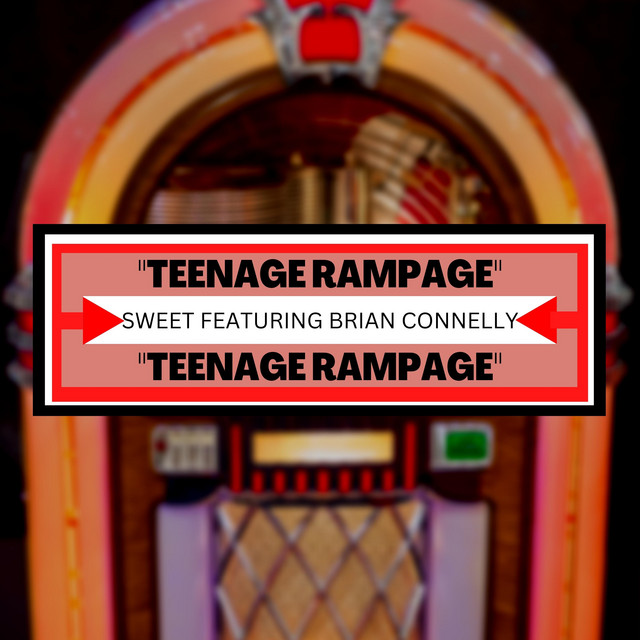
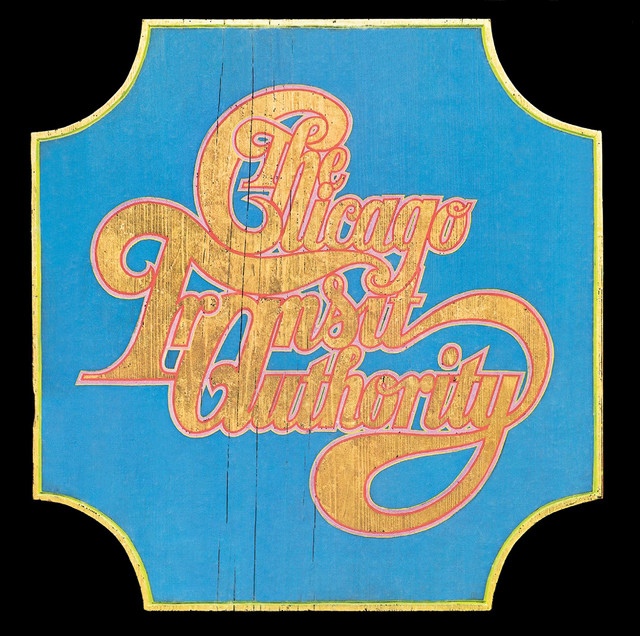
コメント