
発売日: 1979年11月
ジャンル: クラウトロック、アート・ロック、エクスペリメンタル・ロック
概要
『Can』(通称『Inner Space』)は、1979年にリリースされたCanの11作目のスタジオ・アルバムであり、バンド名を冠した唯一の作品であると同時に、彼らの“公式な終焉”を告げるような、総括的かつ散漫な印象を与える作品でもある。
この時期、ホルガー・シューカイは完全に脱退しており、ロズコ・ジーとリーバップ・クワク・バーも不在。
残ったのはオリジナルメンバーのイルミン・シュミット、マイケル・カローリ、ヤキ・リーベツァイトの3人であり、Canはこのアルバムにおいて初めて**“トリオ編成”としての音楽的可能性**を探ることとなった。
前作『Out of Reach』での評価不振を受けて、本作では一応の“回帰”が試みられている。
すなわち、かつての実験性やアブストラクトな雰囲気を意識的に取り戻そうとしながらも、どこか“再現としてのCan”という印象が強く、スタイルのパロディ化や過去作のエコーが随所に見られる。
一方で、「Aspectacle」や「All Gates Open」といった楽曲には、まだCanの本質——“空間の構築”“時間の変容”——が微かに息づいており、本作が完全な終焉ではなく、最晩年のバンドが持つ“諦念と成熟”の産物であることが分かる。
全曲レビュー
1. All Gates Open
8分を超えるオープニングトラック。
ダブの影響を感じさせるベースラインと、ぼんやりと漂うシンセ、反復される語句が、まるで過去のCanの亡霊のように浮かび上がる。
音の隙間と構築感は健在だが、どこか“幻影としてのCan”のようにも聴こえる。
2. Safe
よりコンパクトな曲構成で、メロディも明確。
ファンク的リズムと空間処理されたギターが心地よく、耳に残る一曲。
Canとしてはややストレートだが、後期作品の中ではバランスの取れた佳曲。
3. Sunday Jam
タイトル通り、リラックスした空気感のジャム・ナンバー。
モータリックなグルーヴはなく、どこか“日曜の午後のセッション”のような、脱力と親密さに包まれている。
音の密度は薄いが、それが逆に余白を生んでいる。
4. Sodom
サイケデリックなギターとドラムがせめぎ合う、陰鬱かつ重厚な一曲。
Canの“暗部”が久々に戻ってきたような印象で、70年代初期の『Tago Mago』期の残響を感じる。
5. A Spectacle
本作のハイライトとも言える、ポストパンク的な推進力を持つトラック。
シンプルなビートに乗せて反復されるギターとシンセが強烈な没入感を生む。
Canというよりも、まるでThis HeatやWireの未発表曲を聴いているような感触。
6. E.F.S. No. 99
Ethnological Forgery Seriesの終盤ナンバー。
架空民族音楽の模倣というより、ノイズと即興の断片が交錯する抽象的スケッチ。
Canの“余白”や“編集的美学”が辛うじて息づいている。
7. Ping Pong
タイトルどおりのチクタクとした電子音のやり取りが楽しい短編トラック。
軽妙なセンスとサウンド遊戯に満ちており、実験性とユーモアの融合が小気味よい。
8. Can Be
アルバムのクロージング曲。
穏やかなグルーヴの中で、かすかに再構築されたCanの残響が漂う。
“Canであり続けること”への問いかけを含んだタイトルが象徴的である。
総評
『Can(Inner Space)』は、バンド名を冠しながらも、その実体は**“Canという存在の影をなぞる”音の記録である。
ホルガーもダモもおらず、ジャム中心でも編集的でもない。
だが、そこには確かに“残されたものたちによる、過去との対話”**があり、衰えや変化を引き受けながらも、最後まで“音楽の中で生きようとする意志”が存在している。
音のキレ、アイデアの鮮度、サウンドの先進性において、かつての名作群には及ばない。
だが、むしろその不完全さ、不安定さのなかに、“生き延びる音楽”としてのCanの姿を見出すこともできる。
それは、どこかポストパンクの冷ややかさ、ニューウェイブのミニマリズムを先取りしており、むしろ1979年という時代の“気配”を敏感に反映した作品でもあるのだ。
総じて、『Can』は**“最晩年のバンドが見せた、正直な終末”**であり、決して派手ではないが、静かな深みを湛えたアルバムとして聴く価値がある。
おすすめアルバム(5枚)
- Can – Future Days (1973)
Canのアンビエント的側面の頂点。静寂と流動の美学を再確認したいなら必聴。 - This Heat – Deceit (1981)
実験性とポストパンクが融合した異端作。『Can』の音像に近い冷ややかさを持つ。 - Wire – Chairs Missing (1978)
簡潔な構造と前衛性のバランス。Can後期のミニマルな実験性との共鳴がある。 - Brian Eno – Before and After Science (1977)
ロックとアンビエントの間で揺れる“音楽の余白”を丁寧に描いた作品。 - Holger Czukay – Movies (1979)
元メンバーによるソロ作。編集とユーモアに満ちた“もう一つのCan”として聴ける。
制作の裏側(Behind the Scenes)
本作は、Inner Spaceスタジオでの最終録音作品でもあり、**Canの自律的な制作体制の“終章”**を象徴している。
録音は1978年から1979年にかけて行われ、もはや“バンド”というより“コレクティブ”のような即興集団として活動していた。
特にヤキ・リーベツァイトのドラミングは本作でも際立っており、彼の無限ループのようなビートがアルバムの構造を辛うじて支えている。
また、マイケル・カローリのギターはかつてよりもメロディアスかつ抑制的で、Canのサウンドに“終わりの美”を持ち込んでいるようにも思える。
最も注目すべきは、本作のリリースをもってCanの“オリジナル活動期”が終了したという事実である。
1989年には一度再結成が行われるが、それ以前の最後の“正規アルバム”として、本作は静かなる終幕の書なのである。


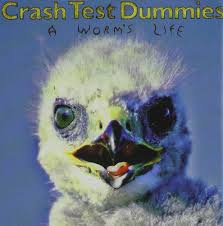

コメント