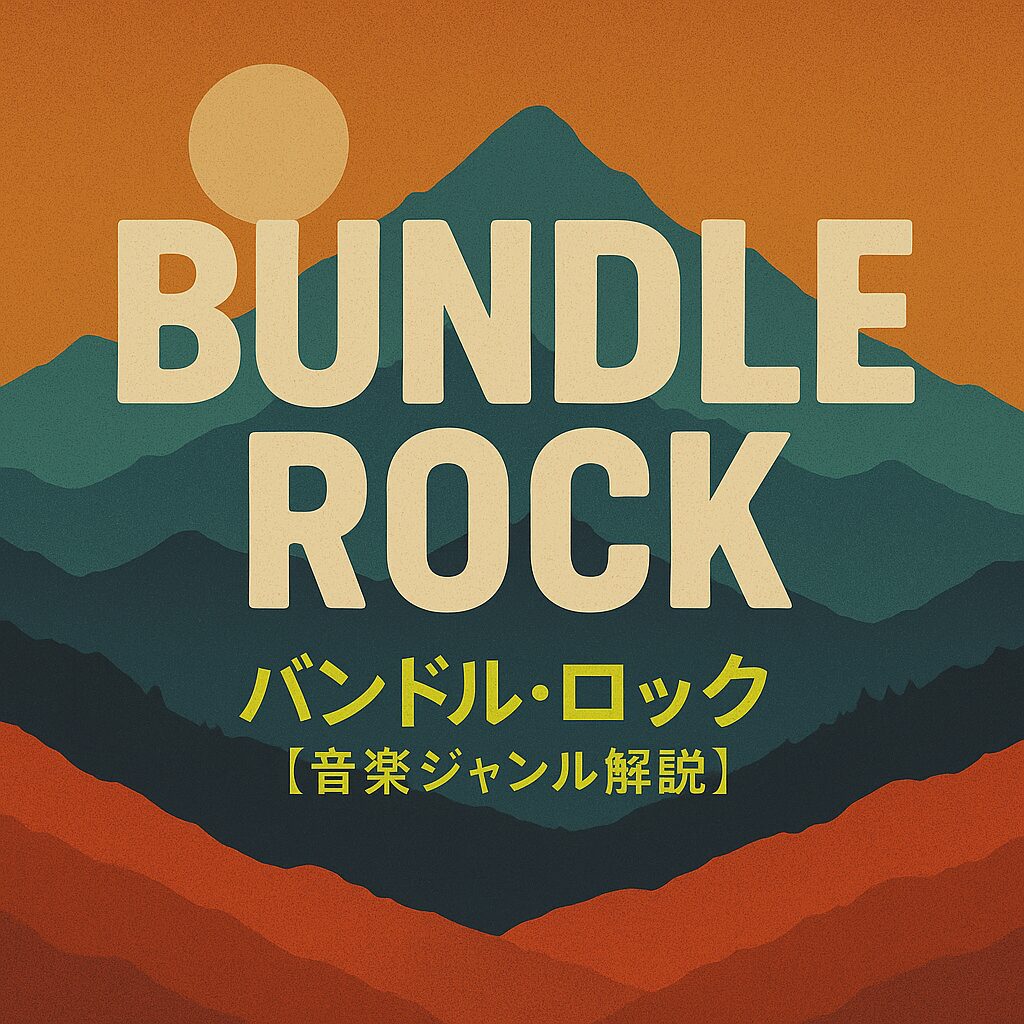
概要
バンドル・ロック(Bundle Rock)という言葉は、一般的な音楽ジャンル名としては現在確立されたものではなく、
主要な音楽メディアや評論の中でも標準化された定義や系譜を持っていない造語的な表現である可能性が高い。
ただし、「バンドル(bundle)」という単語の意味――複数の要素を“ひとまとめ”にしたもの――を踏まえると、
複数ジャンルを組み合わせた折衷的/ハイブリッド型のロックを指す比喩的な用法として理解されるケースがあるかもしれない。
その場合、バンドル・ロックとは:
- オルタナティヴ・ロック
-
ミクスチャー・ロック
-
ポスト・ジャンル的音楽(ジャンルレス)
-
クロスオーバー/フュージョン的ロック
といった**複数のジャンルを内包し、ひとつのスタイルに還元できない“雑食型ロック”**を指す表現と考えられる。
推測される背景と使われ方
1. マーケティング用語としての「バンドル」
SpotifyやApple Musicなどの**ストリーミング時代における“プレイリスト文化”において、
多様なジャンルの楽曲を“バンドル(セット)”して楽しむ発想が浸透しており、
その影響で音楽ジャンルにも“いろいろ混ざっていて決まった呼び名のないロック”**を「バンドル・ロック」と呼びたくなる感覚が生まれたのかもしれない。
2. ジャンル混交が進んだ2020年代以降の音楽傾向
現代では、多くのバンドがポップ/パンク/ヒップホップ/シンセウェイヴ/エモ/R&B/ハイパーポップなどの要素を自在にミックスしている。
このような動きに対して、「バンドル・ロック」という呼称がインディー文脈やSNS発信の中で自然発生的に生まれた可能性がある。
音楽的な特徴(仮定的)
あくまで仮のジャンル名として「バンドル・ロック」を定義するならば、次のような音楽的特徴を想定できる:
- 複数ジャンルを自由に横断(ジャンルの“束”)
- 例:エモ+ドリームポップ+ラップ+ギター・ロック
- プレイリスト向けの耳なじみのよさとトレンド感を持つ
-
ヴォーカルスタイルが多様:歌唱、ラップ、オートチューン加工など
-
打ち込みビートと生演奏の融合(デジロック寄り)
-
Z世代的感性=ジャンル無視、感覚優先
想定されるアーティスト(イメージ)
もし「バンドル・ロック」という言葉が現在の実態に即した造語ジャンルであるなら、以下のようなアーティストが該当するかもしれない:
- 100 gecs:ハイパーポップとスクリーモ、ラップ、ノイズのミックス
-
King Princess:インディーロック+R&B+エレクトロ
-
Jean Dawson:ヒップホップとエモ・ロックの混交
-
Yves Tumor:サイケロックとインダストリアル、ソウルを横断
-
beabadoobee(近年):90sグランジ、ドリームポップ、Y2K感覚の合体
-
The 1975:時代ごとのサウンドを自在に組み合わせるポップ・ロックの象徴
関連ジャンル
-
オルタナティヴ・ロック:ジャンル定義を意図的に曖昧にした表現。
-
ミクスチャー・ロック/ラップ・ロック:多要素をブレンドした90年代以降の先駆的スタイル。
-
ポスト・ジャンル:Spotify以降の“ジャンル無効化”の現代思想。
-
エモ・ラップ/ハイパーポップ:感情とデジタルを統合する新潮流。
まとめ
「バンドル・ロック」という言葉に現時点で明確な定義は存在しないが、
もし使われているとすれば、それは“ロック的要素をベースにしながら複数ジャンルを抱え込む音楽”を、
プレイリスト時代的な視点で柔らかく言い換えた造語的表現だと考えられる。
ロックは、もはや“ひとつの音楽”ではなく、無数のスタイルの束(バンドル)になった――
その事実こそが、「バンドル・ロック」という言葉の本質なのかもしれない。


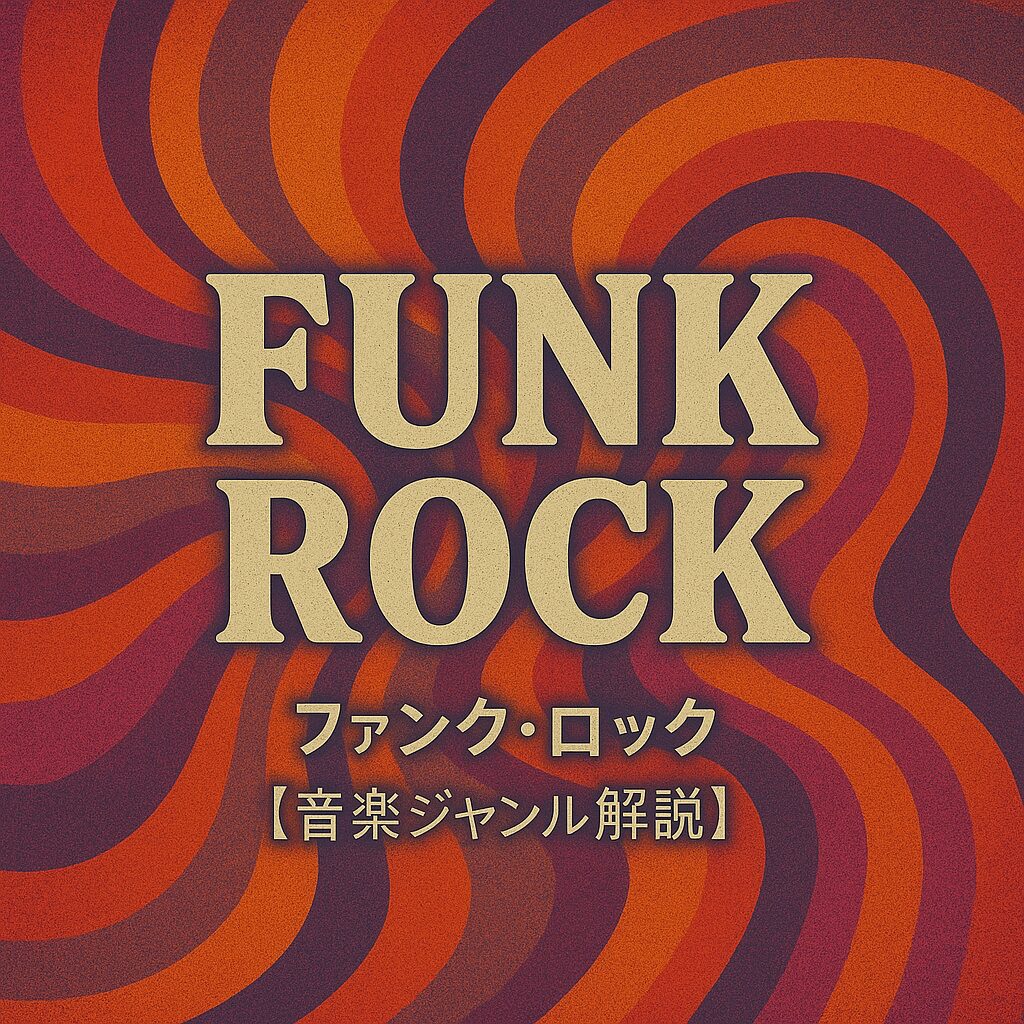

コメント