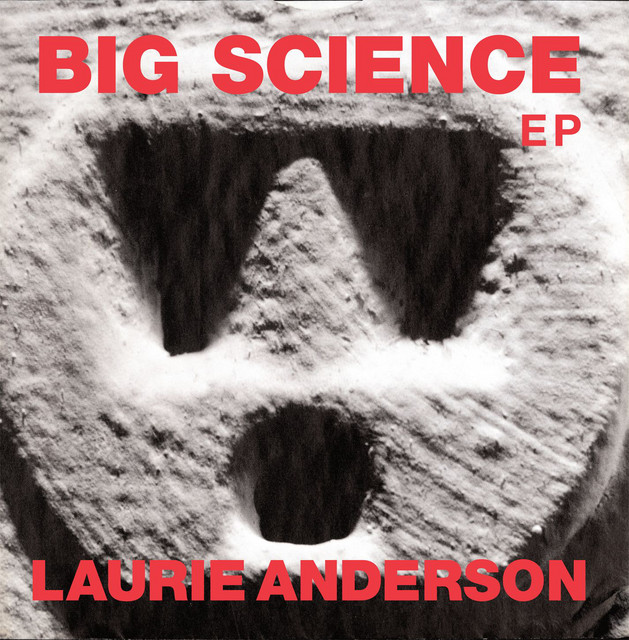
1. 歌詞の概要
“Big Science“は、アメリカの前衛アーティスト、**Laurie Anderson(ローリー・アンダーソン)**のデビューアルバム『Big Science』(1982年)のタイトル・トラックであり、その中核を成すコンセプト曲でもあります。ミニマルなエレクトロニクスと、冷静で淡々とした語り口を基調とした本作は、近代アメリカ社会の科学信仰、監視、暴力性、ユーモア、そして空虚さを詩的かつ皮肉たっぷりに描き出しています。
歌詞の中で語られるのは、アメリカの広大なハイウェイを走る風景、カウボーイ、警告音、政府の介入、人工音声、そして「大いなる科学(Big Science)」という抽象的な存在。これらはすべて、制御されすぎた社会、過剰に管理された現代文明への冷笑的観察として組み合わされています。
アンダーソンは「Big Science」という言葉を、国家規模で展開されるプロジェクト=科学とテクノロジーによる巨大な制度を指すだけでなく、それによって失われる人間の感情や自由、神秘性といったものを浮き彫りにするための装置として用いています。
2. 歌詞のバックグラウンド
この曲が含まれるアルバム『Big Science』は、アンダーソンが1980〜81年にかけて発表した8時間に及ぶライブ・パフォーマンス『United States Live』からの抜粋として構成されています。そのパフォーマンスは音楽、映像、語り、パフォーマンスアート、テクノロジーを融合させたポストモダン・オペラとでも呼ぶべき内容でした。
“Big Science”の歌詞は、広大なアメリカの風景と、それを支配する不可視の権力や構造を描写しており、レイモンド・チャンドラー風の冷静な語り口でテクノロジーと暴力、宗教的なイメージ、そして皮肉なユーモアが展開されていきます。
アルバムは先行シングル「O Superman」の成功によって大きな注目を浴び、当時の実験音楽としては異例の商業的ヒットを記録しました。”Big Science”という楽曲も、その中で静かなる怒りと不安、そして笑いを湛えた哲学的詩編として評価されています。
3. 歌詞の抜粋と和訳
Lyrics:
Get ready for Big Science.
和訳:
「備えなさい。“大いなる科学”の時代に。」
Lyrics:
I think we should put some mountains here.
Otherwise, what are the characters going to fall off of?
和訳:
「この辺りに山を置いた方がいいと思うの。
でないと、キャラクターたちが落ちる場所がないでしょ?」
Lyrics:
Put your hand over your heart.
Yes. Put your hand over your heart.
和訳:
「心臓に手を当てて。そう、心臓に。」
Lyrics:
America: you have the right to remain silent.
和訳:
「アメリカよ:黙秘する権利がある。」
Lyrics:
These are the things I whisper to my satellites.
和訳:
「これが、私が衛星にささやいていること。」
(※歌詞引用元:Genius Lyrics)
語りの随所に現れるこのようなフレーズは、無意味なようでいて、現代社会における構造的な権力と情報の非対称性を浮かび上がらせる非常に高度なアイロニーとして機能しています。
4. 歌詞の考察
“Big Science”は、冷静な声で語られるディストピア的現実を通じて、私たちが無自覚に受け入れている現代社会の仕組みを炙り出します。
✔️ 科学と権力の融合
「Big Science」は、本来人間の幸福や進歩のためにあるはずの科学が、いつしか国家や企業による制御と監視の手段になっていることを暗示しています。「衛星にささやく」「黙秘権」などの語彙は、軍事・警察・通信といった制度的権力を象徴しており、テクノロジーがどこまで人間性に介入できるかを問いかけているのです。
✔️ 自然と人工のねじれた関係
「ここに山を置いたらどう?」というフレーズには、風景すらも作られた虚構である可能性を示唆しています。つまり、我々の住む「現実」が、物語のように誰かによって設計された舞台であるという感覚。それはまさにポストモダンの空虚と超現実の中間地点です。
✔️ ユーモアと恐怖の共存
アンダーソンの特徴でもある、不気味な笑いとアイロニカルな間はこの曲でも顕著で、何気ない語り口がじわじわと不安を掻き立てていきます。それは、笑っているうちに何かが始まってしまう社会の仕組みそのものを映す鏡でもあります。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- “O Superman” by Laurie Anderson
→ テクノロジーと権力への批評を声と電子音で表現した象徴的な楽曲。 - “Discipline” by Throbbing Gristle
→ システムと人間の関係性をノイズと繰り返しで突き詰めた作品。 - “The Jezebel Spirit” by Brian Eno & David Byrne
→ 断片的な音声サンプルとアフロビートで構成された実験的トラック。 - “Close to the Edit” by Art of Noise
→ メディアの解体と再構成をポップに仕上げた80年代アート・ポップの傑作。 - “United States Live” by Laurie Anderson(全体)
→ 本曲のコンセプト全体像を知る上で必聴のパフォーマンス作品。
6. 『Big Science』の特筆すべき点:テクノロジー詩学と社会批評の融合
“Big Science”は、以下のような要素を絶妙に融合させることで、音楽作品の枠を越えたメディアアート的な体験を提供しています。
- 🔍 科学と管理社会に対する鋭い批評性
- 📡 電子音と語りを融合した知覚的コラージュ
- 🧠 ポストモダン文学のような空白と断絶を活かしたリリック構成
- 🗺 アメリカという国土と幻想の「風景」を再解釈するアート的視点
結論
“Big Science“は、Laurie Andersonのキャリアを通じて最も深い問題意識と芸術性が結晶した作品のひとつです。科学、国家、個人、風景、そして言語──それらが複雑に絡み合いながら進行するこの曲は、聴き手にただ「聴く」のではなく、感じ、解釈し、問い直すことを求めます。
あなたが今いる場所は、誰がつくったものですか?
あなたの使っている言葉は、どこから来たのですか?
そして、Big Scienceにあなたはどう備えていますか?
この問いは、1982年に放たれたまま、今なお私たちの耳に突き刺さる未来からのメッセージです。

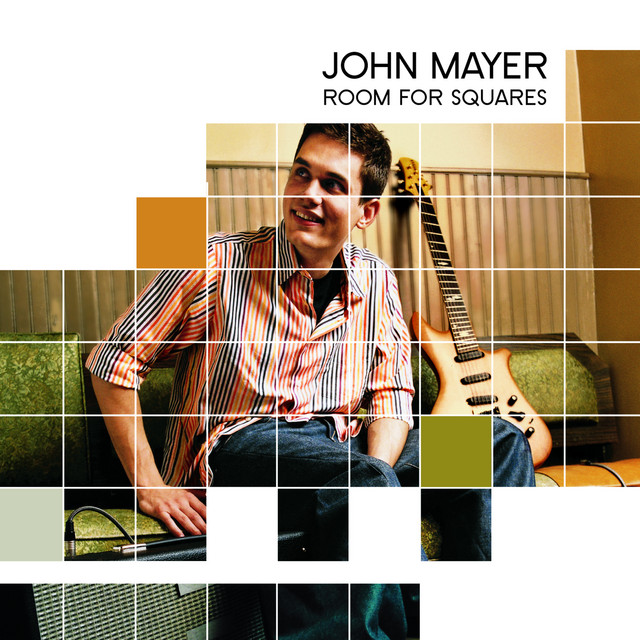
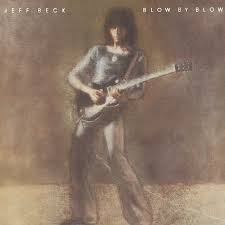
コメント