
1. 歌詞の概要
「Ashes to Ashes(アッシズ・トゥ・アッシズ)」は、カナダのインディーロックバンド Parlor Greens による2023年の楽曲であり、死生観と再生、記憶と忘却をテーマにした、バンド屈指の最も陰影深く、魂に訴えかける一曲である。
タイトルの「Ashes to Ashes」は、英語の葬送の祈祷文「ashes to ashes, dust to dust(灰は灰に、塵は塵に)」から引用されたもので、死と朽ちること、そしてその先にある精神的な循環を象徴している。
この曲では、過去の痛みや喪失、そしてそれらを乗り越えていく人間の営みが、静謐なメロディと詩的なリリックによって丁寧に綴られている。
愛する人との別れ、終わった関係、あるいは自分自身のある部分の“死”——
「Ashes to Ashes」は、そうした“形のない喪失”を見つめ直すための、音による追悼のような作品だ。
2. 歌詞のバックグラウンド
Parlor Greensはこれまでも「Lovestruck」や「Outside Looking In」といった楽曲で、個人的な孤独や感情の揺らぎを詩的に描いてきたバンドだが、「Ashes to Ashes」ではそれがさらに深化し、時間や生死といったより本質的なテーマへと踏み込んでいる。
この楽曲の構想は、バンドメンバーがそれぞれ身近な人の死を経験した時期に生まれたもので、作詞を担当したジェイミー・クレインは、「これは喪失に対する弔辞ではなく、“残された者がどう生きるか”を描いた歌だ」と語っている。
録音はほとんど深夜に行われ、あえてノイズの多いテープを使い、音の中に“時間の経過”や“崩れかけた記憶の断片”のような質感を持たせたという。全体として非常に繊細でミニマルなアレンジが施されており、沈黙すらも楽曲の一部となるような、張り詰めた空気感が漂っている。
3. 歌詞の抜粋と和訳
“Ashes to ashes, we fade into light”
「灰は灰に、そして僕らは光の中に消えていく」“The names we whispered now lost in the wind”
「ささやかれた名前たちは、いま風の中で消えていった」“I keep your shadow pressed in my palm / It slips through like time”
「君の影を手のひらに押し込めたけれど、それは時のように指の間をこぼれていく」“We live, we leave, we burn, we bloom again”
「生きて、去って、燃えて、そしてまた花開く」
このように、歌詞は死や消失を恐れずに受け止めながら、それでも**「その先に続いていくもの」を信じる、静かな信仰のような言葉**で構成されている。
4. 歌詞の考察
「Ashes to Ashes」は、単なる“悲しい歌”ではない。むしろそれは、終わりの中にある始まり、別れの中にある再会、静寂の中にある言葉といった、“逆説的な生”を描いた作品である。
「灰は灰に」というフレーズは、キリスト教的な埋葬の言葉として知られているが、ここでは宗教的な意味合いよりも、“物質が再び循環していく”という自然の摂理としての死を象徴している。
特に「We live, we leave, we burn, we bloom again(生きて、去って、燃えて、また咲く)」という一節には、死=終わりではなく、生=繰り返しであるという思想が込められており、それはParlor Greensが音楽で語ってきた“曖昧な感情”と深くつながっている。
また、ギターの残響やささやくようなボーカルが作り出す音像には、記憶と感情の“揺らぎ”がそのまま音に定着している。
リスナーはこの楽曲を聴くことで、自分の中にある失われたものたちと、ひととき穏やかに対話できるような、そんな時間を得ることができる。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- “Re: Stacks” by Bon Iver
静けさと感情が交差する、再生の瞬間を描いたインディー・フォークの名曲。 - “No Distance Left to Run” by Blur
愛と別れの感情を沈黙で語るようなバラード。音の余白に感情がにじむ。 - “Elephant Gun” by Beirut
死や別離を祝祭のように描く、パレードのような弔い歌。 - “Holocene” by Bon Iver
自分のちっぽけさと宇宙的な存在感を同時に見つめる、圧倒的な叙情。 - “Into My Arms” by Nick Cave & the Bad Seeds
宗教と愛と死をテーマにした、切実で個人的な祈りのようなラブソング。
6. 音楽が祈りになる瞬間——“灰”のなかに咲く花
「Ashes to Ashes」は、Parlor Greensが放つ**もっとも深く、もっとも静かな“音楽という祈り”**である。
この楽曲は死を描いているが、恐れをあおるものではない。むしろそれは、何かが終わるということは、必ず何かが始まるということなのだと優しく語りかけてくる。
“灰”になっても残るもの。それは、声や肌ではなく、記憶や名前や手のひらの温度かもしれない。
Parlor Greensはその繊細な感覚を、音の粒子に乗せて丁寧に、まるで燭台に火を灯すようにして提示している。
この曲を聴くとき、あなたはきっと、自分の中にあった忘れられた影や、遠くに失った誰かの輪郭をそっと思い出すだろう。
それは悲しみではなく、
“何かがそこにあった”ことを思い出す、やさしい風のような瞬間である。
そしてその風が吹いたあと、灰の中から、小さな花が咲き始めるかもしれない。



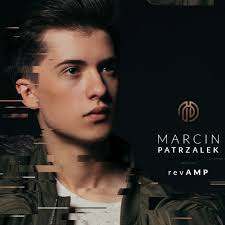
コメント