
発売日: 1991年10月30日
ジャンル: インディー・ロック、パワー・ポップ、ポスト・ハードコア
2. 概要
『No Pocky for Kitty』は、アメリカ・ノースカロライナ州チャペルヒル出身のバンド Superchunk が1991年に発表した2作目のスタジオ・アルバムである。
レーベルは当時のインディー・アイコン的存在であった Matador Records。
録音は1991年4月21〜23日のわずか3日間、シカゴのChicago Recording Companyにて、Steve Albini のエンジニアリングによって一気に行われた。
ライナーには “Produced with eyes closed by Laura, who sat in the right chair.” と記されており、プロデューサーの名義はベーシストの Laura Ballance になっている。
しかし実際には、録音とミックスの現場を仕切っていたのは Albini であり、彼はクレジットをことさらに求めないやり方を貫いていた。
バンドの布陣は、Mac McCaughan(Vo/Gt)、Jim Wilbur(Gt)、Laura Ballance(Ba)、Chuck Garrison(Dr)という4人。
前作『Superchunk』で提示された、パンクのスピード感とポップなフックを併せ持つギター・ロックは、本作でよりタイトかつ大きな音像へと拡張される。
Merge Records は後年のリイシューに際して、このアルバムを “Steve Albiniプロデュースによって、チャペルヒルの“キッズ”を地図に載せた作品” と形容している。
タイトルに含まれる “Pocky” は言うまでもなく日本のお菓子・ポッキーのこと。
インディー・ロックの文脈に日本のスナックが唐突に現れる、その軽やかなアイロニーも含めて、90年代オルタナ文化の雑食性を象徴する一枚と言える。
サウンド面では、Albini らしい“生々しくてデカい”ドラムとギターが際立つ。
NHPR は、Albini の仕事を振り返る記事の中で、『No Pocky for Kitty』において彼が“バンドのラフな才能をそのままに、ポゴ・ダンス向きのサウンドを研ぎ澄まし、ブレないエネルギーを大きく、フォーカスの合った力強さに変えた”と評している。
つまり本作は、ガレージ的な荒さを残しつつも、コード感やハーモニー、フックを整理することで、インディー・ロックとパワー・ポップの理想的な交差点を生み出したアルバムなのだ。
批評面でも、本作はSuperchunkの代表作のひとつとして位置づけられている。
Trouser Press は “忘れがたいフック” と Mac の “不透明だが妙に説得力のある歌詞表現” を評価し、Paste は “若い多幸感と冷静な経験値が交差する地点を捉えた作品” と書いている。
Nirvana『Nevermind』と同じ1991年にリリースされたという時代性も象徴的である。
メジャーのグランジが世界を席巻していくその裏側で、Superchunkはインディー・サイドから“もうひとつの90年代ロック”の形を提示していた。
3. 全曲レビュー
1曲目:Skip Steps 1 & 3
アルバムの幕開けを飾るのは、代表曲のひとつに数えられる「Skip Steps 1 & 3」。
いきなり歪んだギターが全開で鳴り、タムを多用したドラムが前のめりに転げ込んでくる。
コード進行自体はシンプルだが、リズムの微妙な突っ込み方と、ユニゾン気味の2本ギターが作る“塊感”によって、とにかく音がデカく感じられる。
歌詞はタイトルどおり、“ステップ1と3を飛ばしてしまう”ような、段取りをすっ飛ばしてしまう衝動や焦燥をイメージさせる。
10代/20代前半特有の“早回しで生きてしまう感じ”が、抽象的な言葉と疾走するバンド・サウンドに織り込まれているのだ。
Albini の録音はここで早くも本領発揮で、特にスネアの“バシッ”という立ち上がり方と、ベースのローエンドが印象的である。
インディー・ロックでありながら、ハードコア並みの物理的なパンチを持つオープニングなのだ。
2曲目:Seed Toss
2曲目「Seed Toss」は、アルバムの中でも最もポップな部類に入る楽曲で、日本のインディー・ファンからの支持も厚い。
イントロのギター・リフは、パンクのスピード感を保ちつつも、メロディアスなラインがしっかりと仕込まれている。
サビではコーラスが重なり、“叫び”というより“歌っている”印象が強い。
歌詞に出てくる “Seed Toss(種を投げる)” という比喩は、関係性の見通しのなさや、“とりあえず投げてみるしかない”若さの行動原理を象徴しているようにも読める。
終盤、ギターがオクターブで同じフレーズを繰り返すパートは、本作全体でも白眉のカタルシスであり、ライヴでも映える構成だ。
3曲目:Cast Iron
「Cast Iron」は、タイトルどおり“鋳鉄”のように重く粘りのあるギターが特徴的な1曲である。
テンポは少し抑えめで、リフも他曲よりダークな響きが強い。
アルバムの中では、よりエモーショナルで陰影のある側面を担う楽曲だと言えるだろう。
メロディは意外なほど抒情的で、サビに向かうにつれてボーカルのレンジが少しずつ上がっていく。
ギターも、コードをかき鳴らすだけでなく、ところどころで単音フレーズを差し込むことで、曲にうねりを与えている。
歌詞は明確なストーリーではなく、断片的なイメージが積み重ねられるタイプだが、“重くて壊れないもの”と“脆く崩れそうな心情”の対比が感じられる。
インディー・ロック〜エモの系譜から見ても、後続バンドに与えた影響は小さくないトラックである。
4曲目:Tower
「Tower」は、ややシンコペーションの効いたギター・リフと、跳ねるようなビートが印象的なナンバー。
アルバムの前半にして、もっとも“ポップ・パンク寄り”と言える曲かもしれない。
サビのコード進行は非常にキャッチーで、メロディも一聴して耳に残る。
歌詞に出てくる“塔”は、到達すべき場所なのか、閉じ込める構造物なのか、その解釈は聴き手に委ねられている。
しかし、音の感触としては、閉塞を突破していくような高揚感の方が強く、ライヴで一体感を生み出すタイプの曲だと想像できる。
Albini のミックスはここでも、ボーカルを必要以上に前に出さず、バンドがひと固まりになって迫ってくるような音像を作っている。
この“ヴォーカルも含めたアンサンブル”というバランス感覚が、本作の魅力を支えているのだ。
5曲目:Punch Me Harder
タイトルからしてすでに勢いしかない「Punch Me Harder」。
2分強のショート・チューンであり、ハードコアとポップ・パンクのちょうど中間地点のようなスピード感を持つ。
イントロではギターとドラムがほぼ同時に飛び込み、そのままほとんどブレイクなしで突っ走る。
サビではコーラスがシンプルなフレーズを繰り返し、観客が一緒に叫べるような構成になっている。
“もっと強く殴れ”というフレーズは、自己破壊的な衝動というより、“どうせなら徹底的にやってしまえ”という若さの開き直りにも聞こえる。
歌詞のディテールは抽象的だが、そのぶん、聴き手が自分の感情を投影しやすい曲でもある。
6曲目:Sprung a Leak
A面ラストを飾る「Sprung a Leak」は、アルバム前半の中では最もエモーショナルでメロディ重視の楽曲である。
タイトルの “Sprung a Leak(どこかに穴が空いて漏れ出した)” というイメージは、自分の中から何かが溢れて止まらない感覚と重なる。
ギターはオープン・コードを生かした鳴らし方で、アルバムの中では比較的“抜けの良い”サウンドを聴かせる。
サビではボーカル・ラインが少しだけ長く伸び、そこにコーラスがハモりを加えることで、短いながらも大きな感情の波が生まれている。
A面を締めくくるにふさわしい、ささやかなクライマックスなのだ。
7曲目:30 Xtra
B面頭の「30 Xtra」は、短くタイトな構成の中にフックを詰め込んだ佳曲。
スネアの連打とともに始まり、ギターがオクターブ・リフを刻む。
テンポは速めだが、メロディ自体はどこか切なさを孕んでおり、その落差がSuperchunkらしい。
“30 extra”というフレーズは、具体的には何かの数値(時間、距離、年齢)を指しているようにも、単に“余分な何か”を表しているようにも取れる。
いずれにせよ、“過剰であること”が若さの証であり、それがそのままロックの燃料になっている、という感覚が伝わってくる。
8曲目:Tie a Rope to the Back of the Bus
「Tie a Rope to the Back of the Bus」は、タイトルからして物騒で不穏だが、実際のサウンドは驚くほどキャッチーである。
ギターは軽やかなカッティングとパワーコードを行き来し、ドラムはかなりタイトな8ビートを刻む。
サビではメロディが一段階持ち上がり、コーラスが重なって一気に開けた印象になる。
歌詞の “バスの後ろにロープを結びつける” というイメージは、何かに引きずられていく感覚や、止めたくても止まらない状況の比喩のように聞こえる。
しかし曲のテンション自体はどこか楽しげで、そのギャップが90年代インディー的ユーモアにも通じている。
9曲目:Press
「Press」は、ややハードコア寄りのスピードと、シンプルなコール&レスポンス的フックが光る1曲。
イントロからほぼノンストップで突っ走り、ブレイクも短い。
ギター・リフはミニマルだが、曲に必要な推進力は十分にある。
“Press”という言葉は、物理的な“押しつぶす力”と、“メディア”の両方を想起させる。
歌詞は抽象的だが、外部からのプレッシャーと、それに対する反発心が入り混じったようなトーンを感じさせる。
10曲目:Sidewalk
「Sidewalk」は、アルバム終盤の中で最も“歌もの”に近い印象を与える楽曲である。
イントロのギターは、コードを刻む合間に短いフレーズを挟み、街角のざわめきのような空気感を作り出す。
ドラムは比較的抑えめで、ボーカルとメロディの輪郭がよく見えるミックスになっている。
“歩道”というタイトルは、道路の中心ではなく、その脇を歩く感覚――メインストリームから半歩外れた場所を歩くインディー・バンドのスタンスとも重なる。
歌詞のディテールは普遍的でありながら、どこかチャペルヒルというローカルな街の風景を思わせる描写も含んでいるように感じられる。
11曲目:Creek
「Creek」は、1分40秒足らずのショート・チューン。
ほぼパンクのテンポで走り抜けるが、その中にきちんとドラマが収められている。
“小川”を意味するタイトルどおり、歌詞には水辺のイメージが散りばめられている。
ノスタルジックな場所や、そこに結びついた記憶が、スナップショットのように浮かんでは消える。
音像としては、ドラムの生々しさとベースのうねりが強く、Albini録音の“バンドを一発で閉じ込める”哲学がよく現れている曲でもある。
12曲目:Throwing Things
ラストを飾る「Throwing Things」は、アルバムの中で最も構成が練られた楽曲であり、エンディングにふさわしいスケール感を持つ。
イントロはやや抑えめのギターとボーカルで始まり、徐々にドラムとベースが厚みを増していく。
サビではメロディが大きく開き、ギターもオクターブやアルペジオを織り交ぜて、感情の振れ幅を広げていく。
タイトルの“物を投げつける”という行為は、衝動的な怒りやフラストレーションの象徴であると同時に、手放すこと、距離を取ることの比喩にもなっている。
青春期の行き場のないエネルギーが、破壊的でありながらどこか切ない光を放っているのだ。
アルバム全体を聴き終えたとき、“短いけれど、確かな旅をした”という感覚が残るのは、この曲の構成力によるところが大きい。
4. 総評
『No Pocky for Kitty』は、Superchunk にとって決定的な一枚であると同時に、90年代アメリカン・インディー・ロックの重要なマイルストーンでもある。
まずキャリアの中での位置づけを整理しよう。
デビュー作『Superchunk』は、パンク寄りの荒々しさと名曲「Slack Motherfucker」で注目を集めたが、音像の面ではまだローカルなインディー・バンドの域を出ていなかった。
そこから1年で届いた『No Pocky for Kitty』では、ソングライティングの骨格はそのままに、サウンドが大きくアップデートされている。
Steve Albini の録音は、ギターとドラムのアタックを前面に押し出しつつも、バンドのダイナミクスをそのまま封じ込めることに成功している。
NHPR は、Albini の“仕事”を象徴する作品のひとつとして本作を挙げ、“ラフなエネルギーを殺さずに、より大きく、焦点の合った力へ変換した”と評価している。
曲の書き方も、この時点ですでに非常に洗練されている。
Trouser Press が指摘するように、本作の楽曲はどれも“忘れがたいフック”を持ち、Mac McCaughan の歌詞は“抽象的でありながら、なぜか強く迫ってくる”質感を持つ。
「Skip Steps 1 & 3」「Seed Toss」「Cast Iron」「Tower」あたりの流れは、パンク由来のスピードと、パワー・ポップ的なメロディ感が高いレベルで両立しており、まさに“インディー・ロックのお手本”と呼べる。
一方で「Sprung a Leak」「Another’s Lifetime」に通じるようなエモーショナルな側面は、のちのエモ/インディー・エモ世代への先駆けとしても聴き取れる。
同時代のバンドと比較すると、その独自性がよりはっきりしてくる。
Pavement がローファイとシニカルなユーモアで時代を象徴し、Dinosaur Jr. がギター・ソロとヘヴィさを押し出し、Nirvana がメジャーからオルタナの爆発を起こしたとすれば、Superchunk は“インディーの側からポップさを押し上げたバンド”だった。
『No Pocky for Kitty』には、グランジ的な暗さや、ポスト・パンクの硬質さよりも、“楽しくてちょっと切ない”感覚が強く刻まれている。
これは、後年 Merge Records を通じて多くのインディー・バンドを世に送り出すことになる、彼らのポップ・センスの源流とも言える。
社会的・文化的な文脈で見ると、このアルバムがリリースされた1991年は、まさにオルタナティヴ・ロックがメインストリームへ流れ込む転換点である。
Nevermind が全世界を席巻する一方で、SuperchunkはチャペルヒルからDIYなネットワークを通じてツアーを行い、インディー・コミュニティと密接に結ばれたまま活動していた。
ある論考は、『No Pocky for Kitty』を“90年代オルタナ文化を理解するためのもう一つの基準点”として位置づけ、Nevermind の文化的インパクトを否定するのではなく、インディー側の重要作として並列させている。
トータルで33分強というコンパクトさも含めて、本作は“アルバム単位で一気に聴く”ことを前提としたロック・レコードである。
起伏はありつつもダレる瞬間が少なく、ラスト「Throwing Things」まで一気に駆け抜ける構成は、ライヴ・セットにもそのまま持ち込めそうな完成度を持っている。
AllMusic や各種レビュー・サイトでは、“全曲が良いが決定的な1〜2曲に欠ける”とする意見もあるが、むしろそれは“アルバム全体の質が均一に高い”ことの裏返しでもある。
今日の耳で聴くと、『No Pocky for Kitty』は非常に“今っぽく”響く。
ローファイすぎず、過剰にプロダクションを盛るわけでもないギター・ロック。
シンプルなコードとメロディに、少しひねくれた歌詞と疾走感を組み合わせるスタイルは、21世紀のインディー・ロックのテンプレートにもなっている。
日本のリスナーにとっては、タイトルの“Pocky”や、その後のMerge作品群を通して感じる“親しみやすいインディー感”も相まって、どこか距離の近いアルバムに思えるだろう。
90年代USインディーの空気を体感したいとき、あるいはギター・バンドの原点を掘り下げたいときに、何度も戻ってきたくなる作品なのである。
5. おすすめアルバム(5枚)
- Superchunk / Superchunk(1990)
バンドのデビュー作。
「Slack Motherfucker」を含む、より粗削りでパンク寄りのサウンドが楽しめる。
『No Pocky for Kitty』との連続で聴くと、ソングライティングと音像の進化がはっきりと見えてくる。 - Superchunk / On the Mouth(1993)
次作となる3rdアルバム。
よりエモーショナルな楽曲と、少しだけ大人びたメロディが増え、90年代中期インディーの空気を先取りしている。
『No Pocky for Kitty』の勢いと、『On the Mouth』の成熟を対比するのも面白い。 - Archers of Loaf / Icky Mettle(1993)
同じくノースカロライナ勢によるインディー・ロック名盤。
ざらついたギターと奇妙なメロディ感、“ひねくれたポップ”という点でSuperchunkと通じる部分が多く、チャペルヒル〜周辺シーンの空気を別角度から味わえる。 - Dinosaur Jr. / Green Mind(1991)
同じ91年にリリースされたギター・ロックの重要作。
Superchunk よりもルーズでソロ重視だが、“インディーからメジャーへ”という時代の揺らぎを感じさせるという意味で、セットで聴くと90年代初頭のスケール感が伝わる。 - Pavement / Crooked Rain, Crooked Rain(1994)
西海岸オルタナ/インディー側の決定的名盤。
ローファイとポップ・ソングライティングの融合という点では Superchunk と近いが、より斜に構えたユーモアが強い。
東海岸チャペルヒル vs 西海岸ストックトンという構図で聴き比べると、90年代インディー・ロックの多様さが見えてくる。
6. 制作の裏側
『No Pocky for Kitty』の制作で特筆すべきは、やはりそのスピード感である。
バンドの証言によれば、シカゴでの録音は “3晩(18時〜翌6時)で録ってミックスまで仕上げた” という。
日中は友人のアパートの床で眠り、夜になるとスタジオに入って一気に録る――という生活を3日間続けたというのだから、そのままアルバムのテンションに直結していると言ってよい。
スタジオは Chicago Recording Company(CRC)。
Albini はここで、ドラムを大きめの部屋に配置し、ルームマイクを多用しながらも、各パートの分離をしっかり確保する手法を取っている。
彼の哲学は一貫して“バンドが鳴らしている音を、そのまま、できるだけ忠実に記録すること”にあり、過剰なコンプやリバーブを避け、演奏そのもののダイナミクスを信頼する。
『No Pocky for Kitty』の“デカいのに抜けの良い”サウンドは、この哲学とSuperchunkの演奏力が噛み合った結果なのだ。
興味深いのは、ライナー・クレジットで Albini の名がほとんど前面に出てこない点である。
“Produced with eyes closed by Laura” という一文は、バンド内部のユーモアであると同時に、“誰か一人のプロデューサーの手柄にしない”という、当時のインディー・シーン特有の価値観も反映しているように思える。
本作は当初 Matador Records からリリースされ、90年代後半に Merge Records によってリマスター再発されている。
Merge はもともと Mac と Laura が立ち上げたレーベルであり、自分たちの作品を自分たちのレーベルから出し直すという動きも、きわめてインディー的なセルフ・マネジメントのかたちと言える。
日本では、Time Bomb Records や国内ディストロを通じたLP/CDの限定リイシューが行われており、“USチャペルヒルのエモ/パンクバンド”として紹介されることも多い。
「3日間で録られたAlbini録音」「Nevermindと同年作」「ポップでパンクな名盤」といったキャッチが付され、90年代インディー好きの間でロングセラーとなっているのだ。
参考文献
- Wikipedia “No Pocky for Kitty”(アルバム基本情報、制作時期、トラックリスト、批評)
- Merge Records “No Pocky for Kitty / Superchunk”(リイシュー情報、レーベルによる紹介文)
- Guitar.com “The Genius of… No Pocky for Kitty by Superchunk”(クレジット、メンバー構成、音作りの分析)
- MAGNET Magazine “MAGNET Classics: Superchunk’s ‘No Pocky For Kitty’”(録音日程、シカゴでのセッション背景)
- NHPR “8 Tracks: What was the Steve Albini sound?”(Albini によるサウンドの特徴と本作での役割)
- Historifans “Nirvana, Superchunk’s No Pocky for Kitty, and 1990s alternative music culture”(90年代オルタナカルチャーにおける位置づけ)
- Time Bomb Records / LIKE A FOOL RECORDS 商品解説(国内盤リイシュー情報、日本語による紹介)



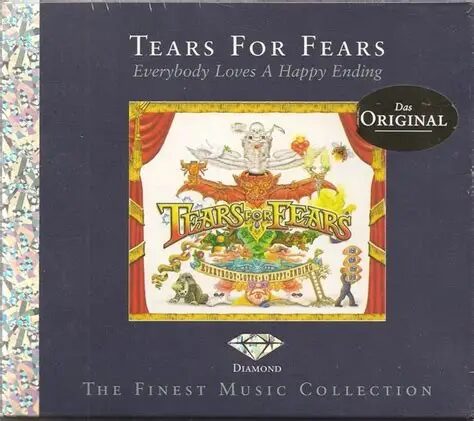
コメント