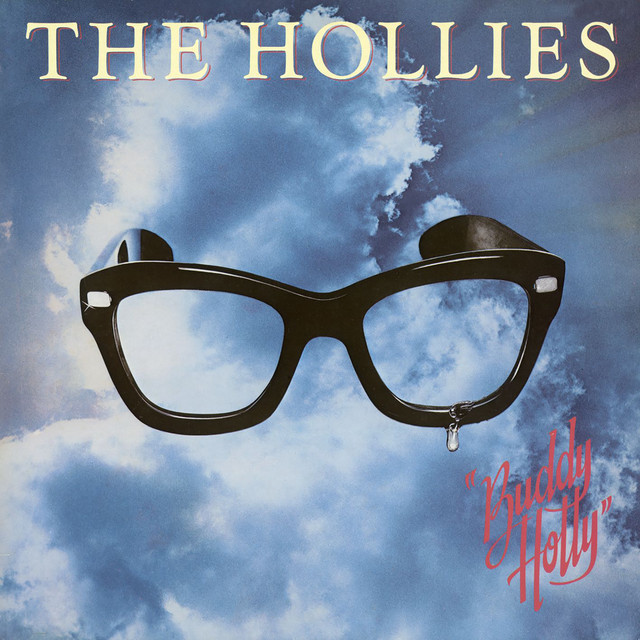
発売日: 1980年2月
ジャンル: ロックンロール、オールディーズ、ポップ・ロック
『Buddy Holly』は、The Holliesが1980年に発表したトリビュート・アルバムであり、タイトルの通り“ロックンロールの父”バディ・ホリーへのオマージュとして制作された作品である。
彼らのバンド名自体が“Buddy Holly & The Crickets”に由来していることはよく知られており、このアルバムは長年の敬意を正式に形にしたものだ。
つまり本作は、The Holliesにとって単なるカバー集ではなく、自らのルーツへの巡礼でもある。
1980年という時期は、パンクとニューウェイヴの勢いが衰え始め、音楽界が次の方向性を模索していた過渡期だった。
The Holliesはその中で、原点回帰的な姿勢を取り、“どんな時代でも歌そのものが輝きを持つ”という信念を示した。
ロックンロール黎明期への敬意と、自らの音楽的成熟が交わる――それが『Buddy Holly』という作品の本質なのだ。
全曲レビュー
1曲目:Peggy Sue
軽快なビートとリズム・ギターが心地よく、The Hollies流のハーモニーが加わることで原曲よりも華やかな印象に。
アラン・クラークの伸びやかな声がホリーの純粋さを引き継ぎつつ、より洗練された響きをもたらしている。
冒頭から“このアルバムは単なる再現ではない”という姿勢が伝わってくる。
2曲目:Words of Love
透明感のあるハーモニーが光る美しいカバー。
Buddy Hollyの繊細な感情表現を、The Holliesは精密なコーラスで再構築している。
静けさの中に温かさが宿る、まさに二組の“声の職人”による対話のような楽曲である。
3曲目:That’ll Be the Day
原曲のスウィング感を生かしながら、より厚みのあるバンド・サウンドにアップデート。
ギターとドラムが強調され、70年代後期のHolliesらしいソフト・ロック的な質感が加わる。
軽快さと懐かしさが絶妙に共存する。
4曲目:Heartbeat
アメリカン・ロックンロールの黄金時代をそのまま再現したような明るいナンバー。
リズムセクションのグルーヴが滑らかで、The Holliesの安定した演奏力が際立つ。
シンプルな構成ながら、聴く者に自然と笑顔をもたらす。
5曲目:Raining in My Heart
Buddy Holly晩年の名バラードを、Hollies流に繊細に再解釈。
ストリングスとアコースティック・ギターが加わり、より叙情的で洗練されたアレンジへと昇華している。
アラン・クラークの深い声が、原曲の寂寥感を優しく包み込む。
6曲目:It Doesn’t Matter Anymore
ポール・アンカ作曲によるホリーの死後リリース曲を、The Holliesは軽やかにカバー。
リズムの揺らぎが心地よく、まるで人生を微笑んで受け入れるような余裕が漂う。
“どんな悲しみも音楽で癒せる”というメッセージが滲み出ている。
7曲目:Rave On
オリジナルの疾走感をそのままに、The Holliesらしいコーラスと分厚いサウンドで再構築。
ロックンロールの衝動を現代的に鳴らすことに成功しており、ライブ感も強い。
Holliesの原点=バンドとしての喜びが最も明確に表れたトラックだ。
8曲目:Well… All Right
リズムを少し落とし、グルーヴィーにアレンジ。
原曲のシンプルさを保ちつつ、ブルース的な深みを加えている。
彼らがバディ・ホリーを“模倣”ではなく“継承”していることを感じさせる。
9曲目:True Love Ways
アルバムの感動的なハイライト。
オーケストレーションを背景に、アラン・クラークが穏やかに愛を歌う。
オリジナルの純粋なロマンスをそのまま引き継ぎながらも、より成熟した情感を湛えたカバーである。
ラストに近づくにつれ、The Holliesの“長年の感謝”が音に滲み出るようだ。
10曲目:Learning the Game
アルバムを締めくくるにふさわしい、静かな別れの曲。
“人生とは学ぶことの連続だ”というホリーの哲学が、穏やかに、しかし確かな希望とともに響く。
このエンディングには、“音楽の灯を次の世代へ繋ぐ”というメッセージが感じられる。
総評
『Buddy Holly』は、The Holliesにとって“ルーツの証明”であり、“音楽の原点回帰”である。
彼らはこのアルバムで、キャリアの出発点にある憧れ――Buddy Hollyへの敬意を、全身で鳴らしている。
単なるカバー集ではなく、まるで“師への手紙”のような誠実なトリビュートだ。
60年代初頭、マンチェスターで活動を始めたThe Holliesは、ビートルズと並んで“Buddy Holly直系”の英国グループとして知られていた。
軽快なビート、クリアなギター・サウンド、ハーモニーを中心に据えた楽曲構成――それらはすべてホリーから受け継いだ要素であり、このアルバムではその原型に立ち返りながら、20年後の自分たちの音で再構築している。
つまり『Buddy Holly』は、懐古ではなく“再解釈”なのだ。
サウンド面では、The Hollies後期特有の滑らかさが特徴的で、AOR的なアレンジとロックンロールの初期衝動が共存している。
「Rave On」や「Peggy Sue」ではリズム・セクションの厚みが増し、よりモダンなグルーヴを獲得。
一方で「True Love Ways」や「Raining in My Heart」では、ストリングスを効果的に使い、原曲にはなかった情感の深さを引き出している。
この“懐かしさと新しさの共存”こそ、Hollies流の敬意表現である。
アラン・クラークのヴォーカルも見事だ。
彼はホリーの声を真似るのではなく、自らの成熟した声で“ホリーの精神”を歌っている。
そこにあるのは模倣ではなく継承――まさに「音楽が人から人へ伝わる奇跡」の体現である。
また、テリー・シルヴェスターとトニー・ヒックスのコーラスも安定しており、The Holliesが築き上げたハーモニー文化の粋がここに結実している。
商業的には大ヒットには至らなかったが、このアルバムが放つ温もりは時を超える。
“ロックの始まり”と“円熟の果て”が一本の線で繋がったような感覚を与え、聴くたびに音楽の普遍性を再確認させる。
The Holliesが20年を経てなお、音楽に対して真摯であったこと――それがこの作品最大の価値である。
『Buddy Holly』は、過去への感謝と、未来への継承が同居した美しいアルバムだ。
そしてその“穏やかな誇り”こそ、The Holliesというバンドの本質そのものなのだ。
おすすめアルバム(関連・比較)
- Not Fade Away: The Complete Studio Recordings / Buddy Holly (1959)
原曲を網羅する決定版。The Hollies版との聴き比べで魅力が際立つ。 - Rock’n’Roll Music / The Beatles (1976)
英国勢によるロックンロール回帰の好例。 - Get Happy!! / Elvis Costello (1980)
同時代に“原点回帰”を試みた別系譜の作品として比較的文脈。 - A Crazy Steal / The Hollies (1978)
本作直前の円熟作。彼らの“穏やかな時代”を理解するうえで必聴。 - Cliff Richard / Rock’n’Roll Juvenile (1979)
同世代アーティストによるロック回帰作として、共鳴するスピリットを感じられる。




コメント