
発売日: 2007年10月24日
ジャンル: ポップ、アダルト・コンテンポラリー、ポップ・ロック
『Unbreakable』は、Backstreet Boysが2007年に発表した7枚目のスタジオ・アルバムであり、グループとして初めてケヴィン・リチャードソンを欠いた4人編成での作品である。
前作『Never Gone』(2005)でのロック寄りアプローチを受け継ぎながらも、本作ではさらに穏やかで成熟したアダルト・ポップ路線を打ち出し、“永続するグループ”としての在り方を提示した。
アルバムタイトル「Unbreakable(壊れない)」が象徴するように、本作のテーマは“結束と継続”である。
メンバー脱退という試練を経ながらも、彼らは決して解体せず、再び“声の重なり”を信じる道を選んだ。
そのため、サウンドは過剰な実験性よりも「安定感」「温かみ」「落ち着いた感情の表現」に重点が置かれている。
90年代の煌びやかなポップでもなく、2000年代初頭のロック的力強さでもない――その中間にある、成熟した男性グループの静かな自信がここにはあるのだ。
3. 全曲レビュー
1曲目:Everything But Mine
開幕を飾るこの曲は、ややメランコリックな電子音と軽やかなビートで、アルバム全体の方向性を端的に示している。
タイトルの“Everything But Mine(僕のもの以外すべて)”が暗示するように、掴みきれない恋や不安定な心情を、繊細なヴォーカルワークで描く。
前作よりも電子的な質感が強まり、モダンR&Bのエッセンスを控えめに取り入れている。
2曲目:Incomplete(※本作収録ではなく前作との連続性を示唆)
本作には収録されていないが、『Unbreakable』の冒頭では『Never Gone』から続く静謐なトーンを引き継いでおり、グループの再生物語が延長線上にあることが感じられる。
2曲目:Inconsolable
リードシングルとして発表された珠玉のバラード。
ピアノを中心としたクラシカルなアレンジと壮大なサビが特徴で、彼らの“声の重なり”を最大限に生かしている。
歌詞は、愛を失った喪失感と、それでも前を向こうとする希望が織り交ざっており、90年代の彼らを想起させる感傷性が戻ってきたようでもある。
3曲目:Something That I Already Know
ブライアンとハウイーの柔らかな高音が際立つ、ミディアム・テンポのバラード。
別れを悟りながらも認めたくない心情を、静かに語りかけるように歌っている。
アルバムの中心に位置する、非常に成熟したトラックである。
4曲目:Helpless When She Smiles
壮大なストリングスが広がる、映画のサウンドトラックのようなバラード。
この楽曲のドラマ性は、かつての「I Want It That Way」や「Shape of My Heart」を思わせる。
サビでの4人の声の重なりが美しく、まさに“Backstreet Boysの原点回帰”を感じさせる一曲だ。
5曲目:Any Other Way
テンポを上げて、爽やかなポップ感を取り戻す楽曲。
軽快なギターとドラムのリズムが心地よく、前半のしっとりした流れに空気を通すような存在である。
歌詞は「他の道を選ぶことはできなかった」という後悔と誇りを同時に描いており、アルバム全体の再生テーマとリンクしている。
6曲目:One in a Million
モータウン風のグルーヴを持つアップテンポ・ナンバー。
“君は百万に一人の存在”というロマンチックなフレーズを、軽やかに歌う。
90年代のポップ・ソウルの香りを残しつつ、2000年代的な洗練さを加えた構成が心地よい。
7曲目:Panic
電子音を強調したアレンジが印象的なダンス・トラック。
前半のバラード群とは異なり、Bsbのポップ・アイコンとしての側面を思い出させる。
特にニックのボーカルが主導し、若さと勢いを保ちながらも落ち着いたトーンでまとまっている。
8曲目:You Can Let Go
アコースティック・ギターの響きが柔らかい、アルバム中でも特に優しい一曲。
「もう手放してもいいよ」というメッセージは、別れの痛みを肯定的に受け止める姿勢を示しており、本作の成熟を象徴している。
9曲目:Trouble Is
穏やかなR&Bテイストの中に少しだけブルースの香りを混ぜた曲。
夜の静けさを感じさせる構成で、Bsbが“都会的な哀愁”を表現する力を身につけたことを示している。
10曲目:Treat Me Right
ブライアンの伸びやかな高音がリードする、軽快でポジティブな楽曲。
“正しく僕を扱ってくれ”というストレートなメッセージを明るく歌うことで、アルバム後半に明るい風を吹き込む。
11曲目:Love Will Keep You Up All Night
愛に溺れ、眠れない夜を描いた大人の恋愛ソング。
ボーカルの抑揚が美しく、過剰にドラマチックにならない点に円熟を感じる。
ストリングスとギターの絡みが絶妙で、サウンドの完成度が非常に高い。
12曲目:Unmistakable
イントロのピアノから漂うノスタルジーが印象的。
別れた恋人への複雑な感情を、繊細なボーカルで紡いでいる。
“あの時の愛は間違いなく本物だった”という確信が、アルバム全体の“壊れない心”のテーマと響き合う。
13曲目:Unsuspecting Sunday Afternoon
アルバムのクロージングを飾る楽曲であり、Bsbのハーモニーがもっとも美しく響く。
穏やかな日曜の午後というタイトルながら、そこにあるのは“静かな再生”の物語である。
前作『Never Gone』の余韻を受け継ぎつつも、ここではより温かく、希望を感じさせるラストになっている。
4. 総評(約1300文字)
『Unbreakable』は、Backstreet Boysのキャリアにおける“安定と再構築”を示した作品である。
ケヴィン不在という現実はグループにとって大きな変化だったが、その穴を「声の配置の再編」で補い、4人でもなお“Backstreet Boysらしさ”を保つことに成功している。
サウンドの方向性は、前作『Never Gone』のロック的アプローチをやや後退させ、より滑らかで内省的なアダルト・ポップへと移行している。
これは2000年代後半の音楽シーン――ColdplayやSnow Patrol、OneRepublicといった落ち着いたメロディ志向のバンドが支持されていた時代背景とも合致している。
『Unbreakable』の洗練されたサウンドは、そうしたトレンドを踏まえつつも、グループ固有の“温もりある声の重なり”を軸に再構築されているのだ。
本作の大きな美点は「派手さを削ぎ落とした誠実さ」にある。
過去のように巨大ヒットを狙うのではなく、“聴き続けられる音楽”を志向している点が、アーティストとしての成熟を物語る。
また、歌詞の多くが“過去の痛みを受け入れ、前を向く”というテーマで統一されており、失恋や喪失を単なる悲しみとしてではなく、成長の一部として描いている。
この点で『Unbreakable』は単なるポップ・アルバムではなく、“人生の中での再生”を描いた作品として聴ける。
特筆すべきは、4人編成になったことで生まれたバランスの良さである。
ブライアンの清らかな声、AJのソウルフルな深み、ハウイーの繊細さ、ニックの軽やかさが、互いに補い合う。
それぞれの声が前に出すぎず、調和を保ちながら物語を紡ぐことで、“欠けても壊れない”というタイトルの意味が、音そのものから伝わってくる。
制作面では、プロデューサーにDan Muckala、Billy Mann、そして元N SyncのJC Chasezらが関与し、ポップとアダルト・コンテンポラリーの中間を狙った音作りがなされている。
リッチなプロダクションながら過剰な装飾はなく、ボーカルの美しさを中心に据えたミキシングは、Bsbの真骨頂を丁寧に引き出している。
その意味で、『Unbreakable』は“成熟したBsb”の理想形と呼ぶにふさわしい。
リリース当時、前作ほどの話題性はなかったが、時間が経つにつれ“落ち着いた名盤”として再評価が進んでいる。
ティーン時代に彼らを聴いた世代が大人になり、自分たちの生活と重ね合わせながら聴けるようになった今、このアルバムの真価が見えてきた。
“ポップ・アイドル”という枠を超え、アーティストとしての尊厳と継続を体現した一枚――それが『Unbreakable』なのだ。
5. おすすめアルバム(5枚)
- Never Gone / Backstreet Boys (2005)
サウンド面での前作。バンドサウンド導入の第一歩を踏み出した重要作。 - This Is Us / Backstreet Boys (2009)
次作で再びダンス・ポップを再構築。電子的アプローチへの回帰が見られる。 - Songs About Jane / Maroon 5 (2002)
アダルト・ポップとロックのバランス感が似ており、『Unbreakable』の流れを理解する上で参考になる。 - The Script / The Script (2008)
同時代のメロディ志向ポップ・バンド。『Unbreakable』の落ち着いたトーンと共鳴する。 - Lifehouse / Lifehouse (2007)
感情を抑えたロック・バラード群が、Bsbの本作と同様の成熟感を持つ。
6. 歌詞の深読みと文化的背景
『Unbreakable』の歌詞群には、喪失と再生というテーマが貫かれている。
たとえば“Inconsolable”では「君を失って、何も慰めにならない」と歌いながらも、その絶望を静かに受け入れている。
これは、2000年代後半の世界的なムード――9.11以降の喪失感、そして癒しを求める文化――とも通じており、単なる恋愛ソングの域を超えた普遍性を持っている。
また、ケヴィンの脱退を経てもなお“Unbreakable(壊れない)”と名乗ったことには、グループそのものの哲学が表れている。
もはや若さや外見ではなく、“声”と“信頼関係”こそが彼らの武器であることを、このタイトルは静かに語っているのだ。
7. ファンや評論家の反応
当時の批評家は、“無理に若返らず、自然体で成熟を描いたアルバム”として好意的に受け止めた。
一方で、一部ファンからは「ケヴィン不在の寂しさ」も指摘されたが、ライブでの安定したパフォーマンスや4人の結束力がそれを補って余りあるものだった。
日本では“静かな名盤”としての人気が高く、『Inconsolable』はFMラジオでも長期にわたりオンエアされた。
結論:
『Unbreakable』は、Backstreet Boysが“時代に流されず、自分たちの形を守る”ことに成功したアルバムである。
それは、ボーイ・グループという枠を超えた“継続の美学”を体現した、静かなるマイルストーンなのだ。


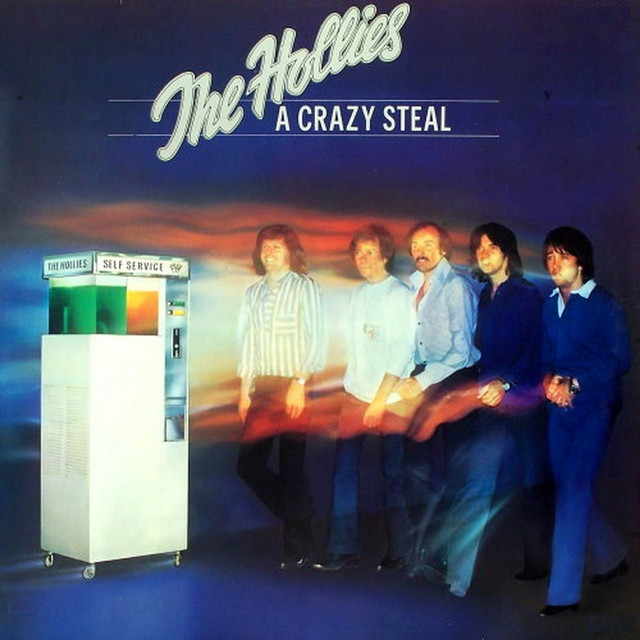
コメント