
発売日: 2019年11月22日
ジャンル: オルタナティブロック、インディーロック、ブリットポップ回帰
概要
『Better Being Lucky』は、イギリスのインディーロック・バンド、The Wonder Stuffが2019年に発表した10枚目のスタジオ・アルバムであり、結成35周年という節目を迎えた彼らが“今なお鋭く、なおかつ肩の力を抜いたロック”を提示した、いわば“第二の安定期”ともいえる作品である。
タイトルの「運が良い方がマシさ」という言葉は、かつてのような怒りや皮肉を薄めた代わりに、“経験と諦観を経た今の等身大の感覚”としてリアルに響く。
アルバム全体を通じて、過去の自己と現代の混沌、そしてその中でなお続ける音楽活動への静かな覚悟と皮肉まじりの愛情が浮かび上がってくる。
音楽的には、デビュー作からのメンバーであるMalc Treeceの復帰が話題となり、ギター・サウンドが再び前景化。
バンド本来のパンキッシュでダンサブルな側面が蘇りつつも、フィドルやアコースティック要素も引き続き活かされ、初期の衝動と後期の叙情性が巧みにブレンドされている。
全曲レビュー
1. Feet to the Flames
開幕を告げるストレートなロックナンバー。
“火の中に足を踏み入れる”という強烈な比喩が、日常に潜む葛藤と戦いを象徴する。
リフの力強さとヴォーカルの熱量が健在。
2. Lay Down Your Cards
“カードを伏せろ”というタイトルが示すように、勝負や駆け引きの終焉、あるいは自己開示の瞬間をテーマにしたミッドテンポ曲。
アコースティックとフィドルの絡みが心地よい。
3. Don’t Anyone Dare Give a Damn
皮肉に満ちたタイトルをそのまま突き進むパンキッシュな一曲。
「誰も気にするな」という投げやりの裏に、強烈なメッセージ性と逆説的な感情がある。
ライブ映え必至のアグレッシブな仕上がり。
4. No Thieves Among Us
社会的信頼と裏切りをテーマにした、重層的なロックナンバー。
リズムセクションが際立ち、緊張感あるサウンドが持続する。
「俺たちの中に泥棒はいない」というフレーズが、逆説的に疑心暗鬼を浮かび上がらせる。
5. Better Being Lucky
アルバムタイトル曲であり、キャッチーなサビと軽やかなアレンジが耳に残る。
「努力より運さ」と言い切るような歌詞には、達観と皮肉、そしてある種の優しさが滲む。
6. Bound
中盤の感情曲線を担うバラード的トラック。
“縛られている”というモチーフを恋愛、社会、内面といった多層的な意味で捉えるリリックが秀逸。
7. It’s the Little Things
「小さなことが大事なんだ」と繰り返すメッセージ性の強いポップロック。
身近な日常に潜む意味を見つけ出そうとする視点が、バンドの成熟を物語る。
8. When All of This Is Over
仮定法的に“これが終わったら”を描くメランコリックな楽曲。
現代社会の閉塞感を受け止めつつ、希望の火を消さずに持ち続ける意志が感じられる。
9. The Guy with the Gift
物語的な構成を持つトラック。
“才能を持った男”という題材を通じて、承認欲求や芸術と大衆性の対立が読み取れる。
アレンジも劇的で印象的。
10. Let’s Not Pretend
「もう誤魔化すのはやめよう」という言葉が、年齢とともに獲得された誠実さを象徴する。
バンドの姿勢がストレートに表れた名曲。
11. Map & Direction
アルバムのラストを飾る、人生の道しるべをテーマにした穏やかなナンバー。
フィドルの旋律とアコースティックギターが柔らかく包み込むように響き、希望と余韻を残して幕を閉じる。
総評
『Better Being Lucky』は、The Wonder Stuffが“続けること”そのものの価値を、再確認するように作り上げたアルバムである。
30年を超えるキャリアを持つバンドにとって、“鋭くあること”と“しなやかであること”のバランスは難しいが、本作ではその両立が見事に成し遂げられている。
特にタイトル曲をはじめ、全体に漂う“諦観と肯定の同居”は、かつて怒りや皮肉を炸裂させていた若き日からの成長を感じさせる。
だが同時に、その鋭さの源泉は今も失われていない。
むしろ、削ぎ落とされた音とストレートな言葉のなかにこそ、“バンドであり続けるという誇り”が宿っている。
ベスト盤ではなく、新曲だけでこの完成度。
それこそが、The Wonder Stuffというバンドの“今”を最も雄弁に物語っている。
おすすめアルバム
- James / Living in Extraordinary Times
同じくベテランUKバンドによる、時代批評と個人の叫びを融合した傑作。 - Paul Weller / True Meanings
過去の自分と折り合いをつけるような深いフォーク的サウンドが共鳴。 - Manic Street Preachers / Resistance Is Futile
経験値を活かしながらも熱を失わないロックの姿勢に通じる。 - The Bluetones / A New Athens
再結成後に放った大人のギターポップ。知的で柔らかいエネルギーが共通する。 -
Levellers / Peace
フォークパンクを軸にしつつ、社会との対話を続ける長寿バンドの姿。
歌詞の深読みと文化的背景
『Better Being Lucky』の歌詞は、ポスト・ブリグジット、ポスト真実、SNS疲労といった2010年代末のイギリス社会に向けた、静かな反応として読むことができる。
「Don’t Anyone Dare Give a Damn」では、無関心社会への怒りと皮肉が、「When All of This Is Over」では、現在を耐え抜いた先にある可能性が語られている。
Miles Huntは、かつてより饒舌ではない。
だが、その一語一語はより深く、より確かに聴き手の胸に残る。
それは“叫ぶ時代”を経た者にしか描けない、真実の重みを持っている。
『Better Being Lucky』は、祝祭ではない。
だが、地に足がついた“生のロック”として、確かに希望を灯している。



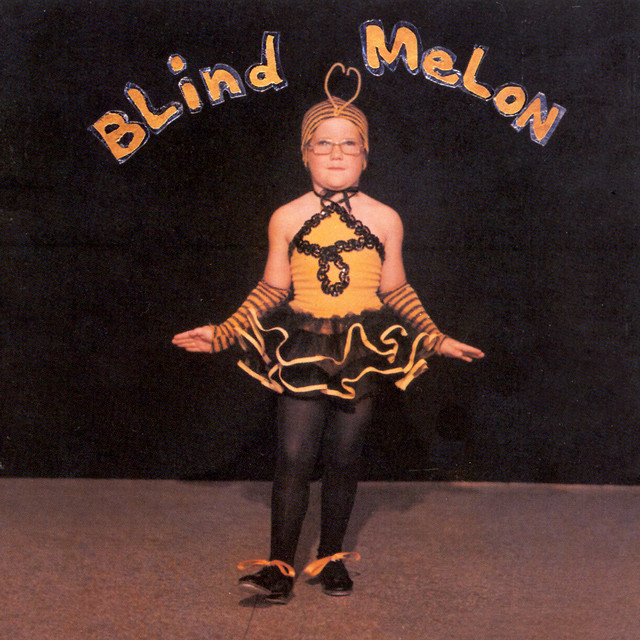
コメント