
発売日: 1996年9月30日
ジャンル: ネオ・サイケデリア、オルタナティブ・ロック、ノイズ・ポップ、エレクトロニカ
- 概要
- 全曲レビュー
- 1. C’mon Kids
- 2. Meltin’s Worm
- 3. Melodies for the Deaf (Colours for the Blind)
- 4. Get On the Bus
- 5. Everything Is Sorrow
- 6. Bullfrog Green
- 7. Heaven’s at the Bottom of This Glass
- 8. What’s in the Box? (See Whatcha Got)
- 9. Four Saints
- 10. New Brighton Promenade
- 11. Bloke in a Dress
- 12. Wake Up Boo! (Music for Astronauts)
- 総評
- おすすめアルバム
- ファンや評論家の反応
概要
『C’mon Kids』は、The Boo Radleysが1996年にリリースした5作目のスタジオ・アルバムであり、前作『Wake Up!』で獲得したブリットポップ的成功からあえて逸脱しようとする挑戦的かつ反逆的な作品である。
1995年の『Wake Up!』は「Wake Up Boo!」の大ヒットによってチャート1位を獲得し、The Boo Radleysを一躍“陽性なブリットポップバンド”として広く知らしめた。
しかしそのイメージは、彼ら本来の音楽的実験精神とは乖離していた。
マーティン・カー(Gt)は「『Wake Up!』のせいでティーン向けバンドのように思われた」と語り、本作はそのイメージを破壊するべく制作された。
結果として『C’mon Kids』は、ノイズ、エレクトロニクス、コラージュ、ビートルズ的サイケ、ジャズ、ドラムンベース的リズムなど、90年代中期のあらゆる音楽的要素を混在させた“混沌の万華鏡”となっている。
売上的には前作から大きく後退し、世間の期待とは裏腹に“裏切り作”と評されたが、今日ではバンドの芸術的ピークとして高く評価されるようになっている。
そのタイトル「C’mon Kids」は、ファンに向けて“目を覚ませ”と呼びかけるメタ的メッセージであり、ポップとノイズ、快楽と違和の狭間で揺れ動く、深く挑戦的な作品なのである。
全曲レビュー
1. C’mon Kids
冒頭から炸裂するノイズとビート、異様なテンション。
“子どもたちよ、目を覚ませ”という呼びかけは、リスナーへの直接的な挑戦状のように響く。
カオスとメロディの境界線を疾走する。
2. Meltin’s Worm
変拍子とサイケデリックなギターが渦巻く、実験色の濃い一曲。
“溶ける虫”という不条理なタイトルも象徴的で、不定形な世界観を作り出している。
3. Melodies for the Deaf (Colours for the Blind)
タイトルからして逆説的で、聴こえない者へのメロディ、見えない者への色。
音楽が知覚の限界を超えて働きかけるという、非常に詩的なコンセプトの楽曲である。
4. Get On the Bus
短くポップでありながら、突飛な展開を持つ一曲。
“バスに乗れ”という呼びかけは、リスナーをこのカオスの旅へ誘う比喩でもある。
5. Everything Is Sorrow
一転してメランコリックで内省的な楽曲。
タイトル通り“すべては悲しみでできている”という諦念を湛えた、静かな核。
6. Bullfrog Green
ビートルズ的なメロディラインにノイズと変則リズムが加わった異色曲。
“カエルの緑”というタイトルも童話的で、現実と幻覚の中間にあるような不思議な感触。
7. Heaven’s at the Bottom of This Glass
ジャズ的コード進行と酩酊感あるボーカル。
アルコールのグラスの底にある“天国”は、快楽と破滅の紙一重を示す象徴的表現。
8. What’s in the Box? (See Whatcha Got)
唯一シングルカットされたアップテンポなギターロック。
エネルギッシュな展開とシンプルな構成で、アルバム中もっとも外向きな楽曲。
9. Four Saints
テンポを落とし、幻想的な音像が広がるドリーミーな一曲。
宗教的なイメージを想起させるが、どこか逸脱とアイロニーが漂っている。
10. New Brighton Promenade
淡いノスタルジーが香るインストゥルメンタル調の楽曲。
タイトルの“プロムナード(遊歩道)”という言葉から、過去への回帰と緩やかな歩みが感じられる。
11. Bloke in a Dress
タイトルの挑発性がそのまま楽曲の精神を表している。
ジェンダーや社会的規範を逆撫でするような内容で、音楽的にも異様な緊張感を持つ。
12. Wake Up Boo! (Music for Astronauts)
前作の代表曲のタイトルを冠した“影”のようなトラック。
“宇宙飛行士のための音楽”という副題は、現実からの距離を象徴し、前作の陽性イメージをメタ的に再解釈している。
総評
『C’mon Kids』は、The Boo Radleysにとって最も勇敢で、最も誤解された作品である。
ブリットポップの頂点であった『Wake Up!』からわずか1年後、バンドは商業的成功ではなく創作の自由と誠実さを選んだ。
その結果生まれたこのアルバムは、ポップ、ノイズ、エレクトロニクス、フォーク、ジャズ、実験音楽が複雑に交錯するカオティックでありながら精緻な音の迷宮となった。
確かに、リスナーを選ぶ作品である。
だがその混沌の中には、“音楽とは何か”、“ポップとは何か”という問いへの答えの断片がいくつも埋まっている。
とりわけ90年代後半以降のポスト・ロック、IDM、エクスペリメンタルなインディー・ポップの流れを先取りしていた点で、本作の先見性は驚くべきものがある。
『C’mon Kids』は、ポップと芸術性の均衡を極限まで揺さぶった異端の傑作であり、聴く者に問いを投げかけ続ける、挑発と詩情の塊である。
おすすめアルバム
- Primal Scream / Vanishing Point
ジャンル横断的な実験性と音響操作が『C’mon Kids』と共振する。 - Radiohead / OK Computer
ポップとテクノロジーの衝突、社会的不安、構成の大胆さ。時代の双璧とも言える。 - The Beta Band / Hot Shots II
コラージュ的構成とポップの解体・再構築において非常に近い。 - Stereolab / Dots and Loops
ポストモダンで知的、電子音と60sポップの融合。『C’mon Kids』的アプローチの別解。 - Super Furry Animals / Guerrilla
サイケ、エレクトロ、ロックのごった煮感。遊び心と芸術性の両立が特徴。
ファンや評論家の反応
リリース当時、『C’mon Kids』は前作とのあまりの乖離により、多くのリスナーから戸惑いと落胆を持って迎えられた。
チャート成績も振るわず、商業的には「失敗作」とされていた。
しかし、時を経るごとにその革新性と大胆さが再評価され、現在では「The Boo Radleysが最も真摯に音楽と向き合った瞬間」として多くの批評家から賞賛を受けている。
音楽性だけでなく、リスナーとの関係すら問い直すようなこの作品は、今なお挑戦的で、そして美しい。


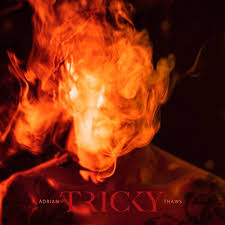
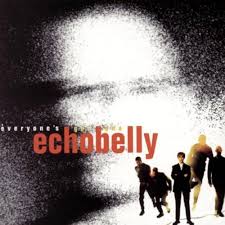
コメント