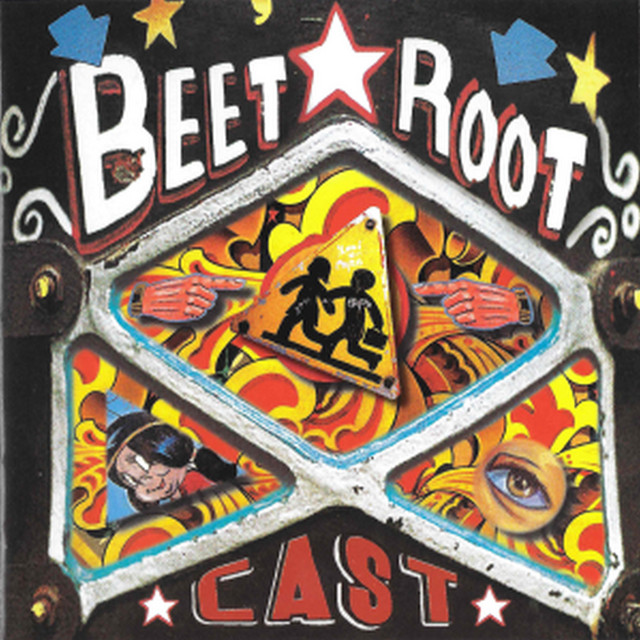
発売日: 2001年7月30日
ジャンル: オルタナティヴ・ロック、ファンク・ロック、サイケデリック・ポップ
概要
『Beetroot』は、Castが2001年に発表した4枚目のスタジオ・アルバムであり、
彼らのキャリアにおいて最も実験的かつ賛否両論を巻き起こした異色作である。
90年代のブリットポップ・ムーブメントの終焉とともに、
ジョン・パワー率いるCastも転機を迎えていた。
それまでのギター中心のロックンロールとは一線を画し、
本作ではファンク、ソウル、ブラス、アフロビート、サイケデリックといった異なるジャンルを大胆に取り入れた、
ある意味で「解体」と「再構築」のアルバムとなっている。
タイトルの「Beetroot(ビートルート=赤かぶ)」は、
血や根っこ、土着的なものを象徴しつつ、ユーモラスで謎めいた語感が、本作の内容と不思議に呼応している。
商業的には失敗に終わり、チャートでも振るわなかったが、
Castというバンドの“殻を破ろうとした精神性”を如実に映した記録であるとも言える。
全曲レビュー
1. Desert Drought
不穏なイントロとグルーヴィなベースラインが印象的なオープニング。
砂漠の干ばつ=精神的枯渇を描くかのような実験的ファンクロック。
2. Alien
前作『Magic Hour』に収録された曲の再録。
よりビートが強調されたアレンジになっており、疎外感と混沌がサイケデリックに浮き彫りになる。
3. Kingdoms and Crowns
荘厳なストリングスとパーカッションが融合した、幻想的な一曲。
“王国と王冠”は、自己の内なる支配と幻想を象徴するメタファーとなっている。
4. Giving It All Away
タイトル通り“すべてを手放す”ことを歌うソウルフルなナンバー。
ブラスが入り、カーティス・メイフィールド的なスピリチュアル・ソウルを思わせる。
5. Hold On
従来のCastらしさに最も近い、直球のギターポップ。
サウンドは明快ながら、“つかまっていろ”という言葉ににじむ危機感と再出発の兆しが感じられる。
6. Dancin’ on the Flames
ファンク+ラテン的なリズムが炸裂する、ダンサブルなトラック。
“炎の上で踊る”という表現は、絶望と快楽の同時性を表すメタファーとしてユニーク。
7. Get on You
肉体性とスピリチュアルな高揚を併せ持つ、異色のポップファンク。
ジョン・パワーのヴォーカルが珍しくブルージーなニュアンスを見せる。
8. Universal Love
アルバムの中核となるスピリチュアル・ラブソング。
タイトル通り、“普遍的な愛”という抽象的で壮大なテーマを、グルーヴィなリズムで軽やかに包み込む。
9. High Wire
“綱渡り”のような不安定な状況をテーマにしたアーバン・ソウル。
本作の方向性を象徴する一曲で、バンドの試行錯誤が最も感じられる。
10. I Never Wanna Lose You
内省的なラストトラック。
原点回帰とも言えるアコースティックなサウンドが、過剰な装飾の後の静けさと誠実さを取り戻すように響く。
総評
『Beetroot』は、Castが築き上げてきたギターロックの王道像を一度“捨てる”ことで、
新しい音楽的地平を模索しようとした野心作である。
ただしその試みは、必ずしも成功したとは言いがたく、
従来のファンからは「らしくない」「何を目指しているのか分からない」といった批判も多く寄せられた。
しかし一方で、ブリットポップ終焉後の音楽シーンにおいて、ジャンルや様式を超えた“越境性”を提示したアルバムでもある。
ジョン・パワーは、音楽的・精神的な解放を求めてこの作品を作ったが、
結果的には“迷い”や“模索”そのものが、アルバムの核心になっている。
『Beetroot』は、派手な成功も明快な答えもないが、
バンドの限界と可能性が同時に浮かび上がる、特異な“転換点の記録”として再評価に値する。
おすすめアルバム
- Primal Scream / Give Out But Don’t Give Up
ロックからファンクへと舵を切った“転換作”としての共通点。 - The Stone Roses / Second Coming
前作との落差、過剰な期待、そして実験精神という文脈で共鳴。 - Supergrass / Road to Rouen
ポップロックから脱却し、内省と実験に踏み出したバンドの姿勢が類似。 - Paul Weller / Heavy Soul
ソウル/ファンクへの傾倒とUKロックの融合。 -
Lenny Kravitz / Circus
ファンクやソウルの文法を現代的なロックに再編成した好例。
歌詞の深読みと文化的背景
『Beetroot』における歌詞は、明確なストーリーテリングよりも、
抽象的かつ感覚的なイメージが多く、リズムや響きの中に意味を託した詩的断片として存在している。
“Universal Love”や“Kingdoms and Crowns”のように、
抽象的な愛や支配、精神世界への言及が増えており、
それは“新しいスピリチュアルの言葉を探している過程”とも捉えられる。
“Beat Mama”や“Free Me”といった明快なスローガンを用いた過去作とは異なり、
ここでは言葉も音も流動的で、解釈をリスナーに委ねる“脱中心的”な構造を取っている。
こうした手法は、2001年という“ブリットポップ後の文化的空白”を反映したものであり、
迷い、模索、問い直しがそのまま作品の詩学になっている。
『Beetroot』は、そうした“未完成な美学”をあえて提示することで、
終わりの先を見つめる意志の萌芽を記録した、静かな異端作なのである。



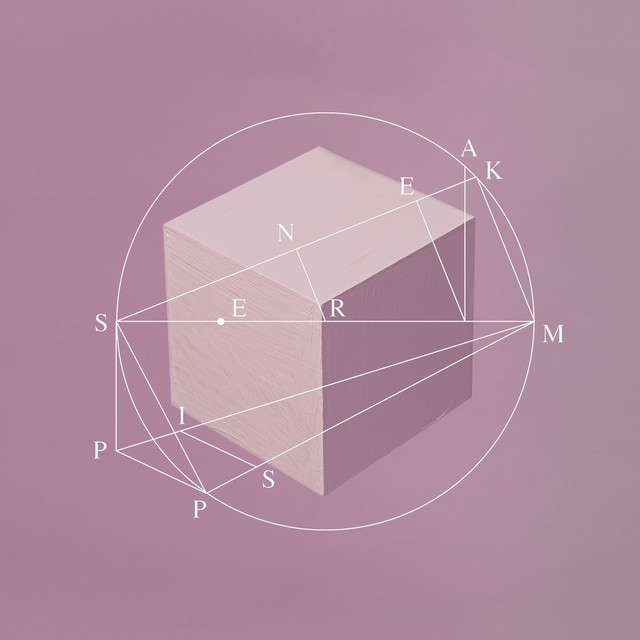
コメント