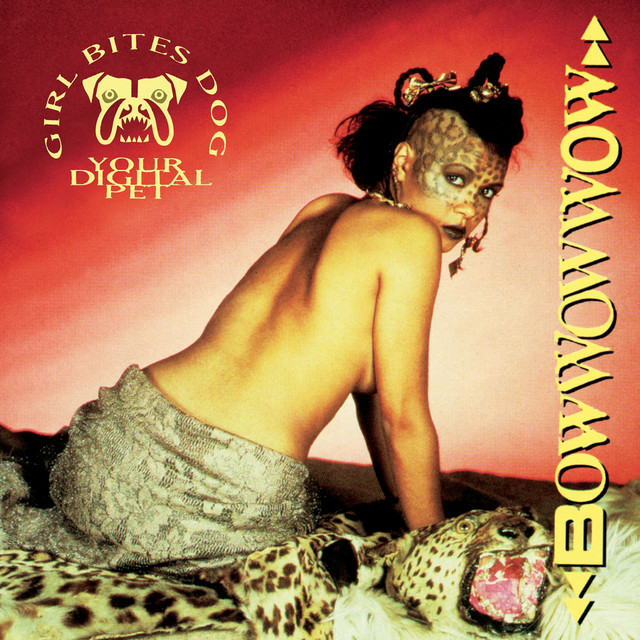
1. 歌詞の概要
「C30 C60 C90 Go」は、Bow Wow Wowが1980年にデビュー・シングルとして発表した楽曲であり、ニューウェーブ/ポストパンク・シーンの中でもとりわけ異彩を放つ、“音楽産業への挑発”そのものである。曲名の「C30」「C60」「C90」とは、当時一般的だったカセットテープの種類(録音時間に応じた長さ)を指しており、タイトルからしてすでに「レコードよりカセットのほうが自由で楽しい」というメッセージが込められている。
歌詞では、好きな曲をテープに録音して“自分のミックス”として楽しむ若者たちの姿が描かれ、当時のイギリス社会におけるパイレーツ・ラジオやホーム・タップ文化への肯定的なまなざしが強く打ち出されている。加えて、“レコード会社”や“著作権”といった音楽業界の権威に対して、堂々と反旗を翻す内容となっており、その反骨精神はBow Wow Wowのキャリア全体を貫くスタンスとして確立された。
とりわけ特徴的なのは、この曲がまさに「ミュージック・カセットテープ」としてのみリリースされた点である。当時のEMIから発売されたC30カセットは、片面に「C30 C60 C90 Go」の音源、もう片面は空白となっており、聴く者が自ら音楽を録音できる“参加型メディア”として販売された。これは明確に音楽業界の商業主義に対する反逆であり、ポップミュージックにおける「消費者=リスナー」が主体になる可能性を提示した先駆的な試みであった。
2. 歌詞のバックグラウンド
Bow Wow Wowは、当時のロック・シーンにおけるプロデューサー的狂人マルコム・マクラーレン(元セックス・ピストルズのマネージャー)が仕掛けたプロジェクト型バンドとして誕生した。バンドには、アダム・アントのバックメンバーだったドラマーのデイヴ・バーバリー、ギタリストのマシュー・アシュマン、ベーシストのリー・ゲイツ、そしてヴォーカリストとして抜擢されたのが、まだ13歳だったアナベラ・ルーウィンである。
「C30 C60 C90 Go」は、彼らが音楽的にも概念的にも“反体制”を明示するために作られた一曲であり、特に“著作権”という概念に対して、消費者=若者の側から異議を唱えたという点で画期的だった。
当時イギリスでは、カセットテープによる私的録音が「音楽の窃盗」としてメディアに非難されており、音楽業界とリスナーの間に摩擦が生まれていた。その中で、Bow Wow Wowはむしろ「録音して何が悪い? 自分の好きな音楽を、自分で楽しめばいい」と開き直り、ミュージシャン側から「自由な複製」を支持する異例の立場を取った。
その結果、「C30 C60 C90 Go」は、BBCでは“音楽の盗用を奨励する”という理由で放送禁止となりながらも、カセット世代の若者たちの強い支持を受け、カウンターカルチャー的アイコンとしての地位を確立していった。
3. 歌詞の抜粋と和訳
以下に、この曲の象徴的なラインを抜粋し、その和訳を添える。
Off the radio I get constant flow
→ ラジオからは、ひっきりなしに音楽が流れてくるHit it, pause it, record and play
→ 再生、ポーズ、録音――ボタンを押すだけ!Turn it, rewind it, fast forward, stop
→ 巻き戻し、早送り、ストップ――すべて私の自由C30, C60, C90, go!
→ C30、C60、C90、さあ始めよう!Now I got a new way to move
→ これで私は、新しいやり方を手に入れたの
引用元:Genius Lyrics – Bow Wow Wow “C30 C60 C90 Go”
この反復的でリズミカルな歌詞は、カセットテープの操作感そのものを“ビート”として捉えており、テクノロジーと身体性が交差する独特の美学が宿っている。
4. 歌詞の考察
「C30 C60 C90 Go」は、そのキャッチーさやポップさに反して、非常にラディカルな主張を秘めた曲である。
最大の特徴は、“音楽を聴く=受け取る”という一方通行の構造を拒絶し、“音楽を自分のものにする”という行為を積極的に肯定している点にある。それは、ポストパンクやニューウェーブが共通して持っていた“自己表現”への欲望を、より日常的・実践的なレベルで提示したという点で画期的だった。
さらにこの曲は、テープ操作という具体的な身体行為をメタファーとして用いることで、音楽との“関わり方”自体がすでに創造的であるという考えを打ち出している。アナベラのボーカルは、まだ10代とは思えないほどの自信と自由を帯びており、それが歌詞の“アクション”とぴったり重なって、聴く者に「音楽はもっと自由でいい」と訴えてくる。
また、マルコム・マクラーレンの意図もここに明確である。彼は、音楽を“権威”から解き放ち、カセットやファッション、消費行動といった“非・音楽的なモノ”と再結合させることで、まったく新しい音楽文化の地平を作り出そうとしていた。その思想は、「C30 C60 C90 Go」に凝縮されており、この楽曲は単なる“曲”を超えた“宣言”だったのだ。
5. この曲が好きな人におすすめの曲
- Antmusic by Adam and the Ants
ポストパンクのダンスビートとアフリカン・パーカッションが融合した反主流派アンセム。 - Money by Flying Lizards
既存の価値観や商業主義への痛烈な皮肉を、機械的ボーカルで表現したニューウェーブの異端。 - Pop Muzik by M
音楽の消費と大量生産を主題に据えた、テクノポップ黎明期のメタ・ポップソング。 - Being Boiled by The Human League
テクノロジーと倫理の対立を歌った、シンセポップ以前の思想的パンク。 -
Video Killed the Radio Star by The Buggles
メディアの変化とその影響をポップに描いた、時代の変革期を象徴する名曲。
6. “複製の自由”と音楽の民主化
「C30 C60 C90 Go」は、音楽を取り巻くメディア環境が急速に変化していた1980年という時代を、鋭く、しかも遊び心たっぷりに切り取った記録である。
この曲は、カセットテープという技術がもたらした“音楽の私物化”を称揚し、従来の音楽流通や著作権観念に一石を投じた。そのメッセージは、今日のストリーミングやYouTube、プレイリスト文化にまでつながる「個人が選び、構成し、共有する音楽体験」の先駆けである。
だからこそ、「C30 C60 C90 Go」は今聴いてもまったく古びない。むしろ、今日の私たちが抱える“音楽と所有”“デジタルと創造性”といった問いを、40年以上前にポップでラジカルな形で提示していたという点で、この曲は今なお“未来の音楽”なのである。


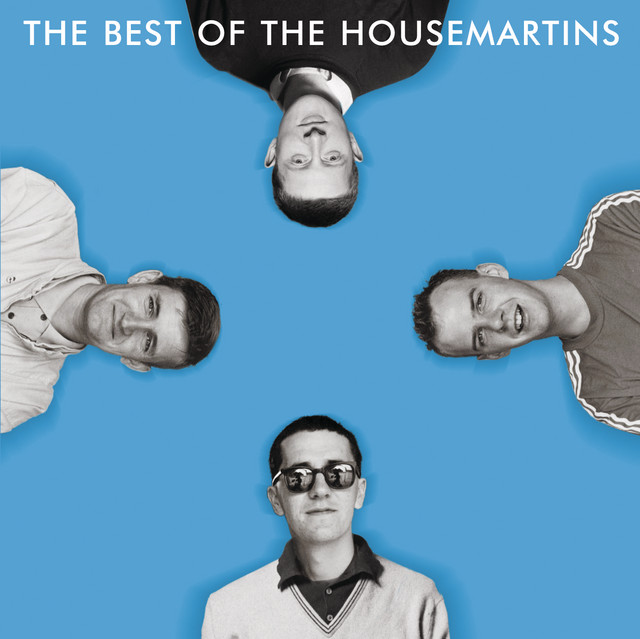
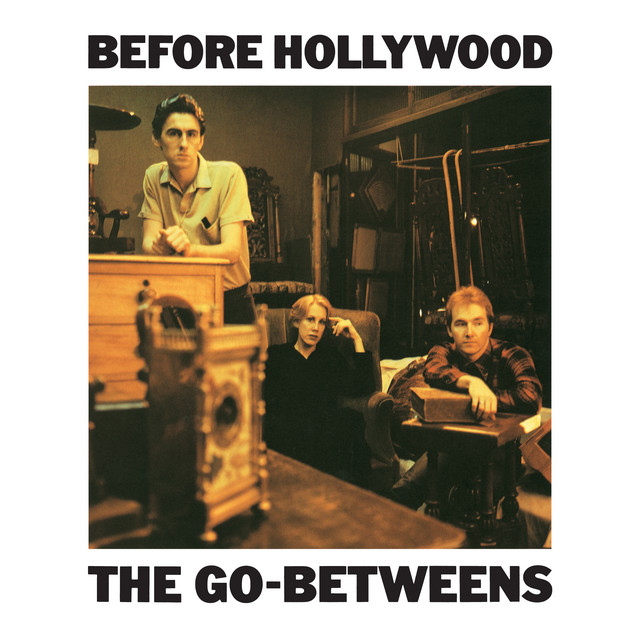
コメント