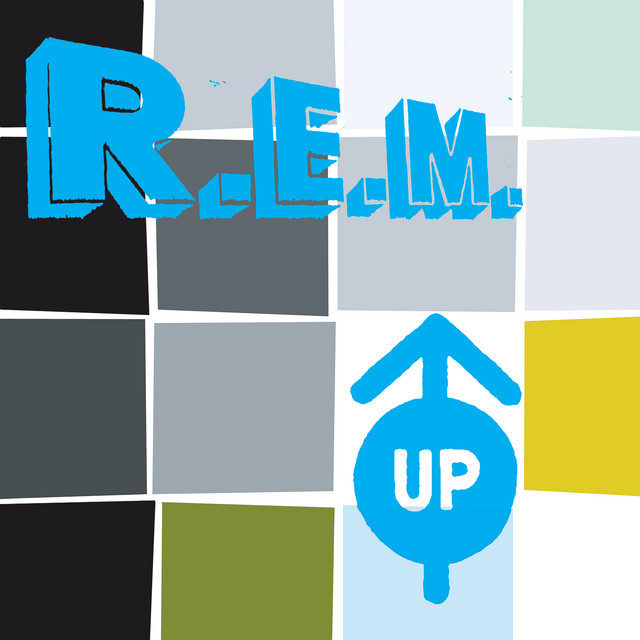
発売日: 1998年10月26日
ジャンル: エレクトロニカ、ドリームポップ、アートロック、オルタナティヴロック
概要
『Up』は、R.E.M.が1998年に発表した11作目のスタジオ・アルバムであり、**ドラマーであり共同創作の中心でもあったビル・ベリー脱退後、初のアルバムとして制作された“再構築の記録”**である。
1996年の『New Adventures in Hi-Fi』をもって、黄金期の4人編成に終止符を打ったR.E.M.は、その喪失をきっかけに、
ロックバンドの定義そのものを問い直す方向へと大きく舵を切る。
その結果、『Up』ではドラムレス、あるいはプログラミングやループを多用した楽曲が中心となり、従来のギターバンド的フォーマットからの脱却と、電子音楽/アンビエント的手法の導入が顕著となった。
ブライアン・イーノ的ミニマリズムや、ビーチ・ボーイズの『Pet Sounds』を想起させるハーモニー構築も随所に見られ、
このアルバムは“ポップ”を再定義する静かで野心的な挑戦である。
その一方で、歌詞は極めて内省的かつ繊細で、喪失、孤独、再生、自己対話といったテーマがアルバム全体を貫いている。
『Up』とは、決して“上昇”の意ではなく、“静かに目を開ける”ための運動なのである。
全曲レビュー
1. Airportman
シンセパッドと微細なエフェクトによる、静謐でアンビエントな導入曲。
歌詞は抽象的かつミニマルで、“移動”と“無名性”の感覚を漂わせる。
この曲がR.E.M.の新章を明確に告げている。
2. Lotus
トレモロギターと浮遊感のあるアレンジが特徴。
「I ate the lotus…」というフレーズは、ギリシャ神話の忘却の果実“ロータス”を引用し、無意識や快楽主義への沈潜を暗示する。
セクシュアルかつ催眠的。
3. Suspicion
柔らかなエレクトリックピアノと、スタイプの抑制されたヴォーカルが光るナンバー。
恋愛における不安と自己投影が静かに描かれる。
透明感と曇りガラスのような距離感が共存。
4. Hope
レナード・コーエンの「Suzanne」のコード進行を引用した、詩的かつマシンライクな反復による楽曲。
“神の不在”を前提としながら希望を探すという、終末思想的な問いかけを含む。
5. At My Most Beautiful
ビーチ・ボーイズ風のハーモニーと、クラシックなラブソングの形式を持った名曲。
“君の電話を待ってる”という一節が、時代遅れな純粋さとして逆に胸を打つ。
本作の中では最も親しみやすく、再出発のための優しい核となっている。
6. The Apologist
“謝り続ける人”というアイロニカルな主人公を描いた曲。
ピアノの反復とドラマティックな展開が、内面の揺らぎと後悔を浮かび上がらせる。
7. Sad Professor
アコースティック・ギターとスタイプの素の声だけで構成された、詩的な弧の楽曲。
アルバムの中でもとくに剥き出しの感情が見える。
**“教えることはできても、自分ではうまく生きられない”**という孤独。
8. You’re in the Air
エフェクトがかったギターと音響処理されたボーカルで進行する、ドリームポップ的トラック。
“空気の中に君がいる”という表現が、過去の恋人か、幻覚か、曖昧な記憶かを漂わせる。
9. Walk Unafraid
繰り返されるコードとドラムマシンに乗せて、“恐れずに歩け”と語りかけるアンセム。
このアルバム中で最も希望的なメッセージソングであり、**“壊れた後に進む者たちへの応援歌”**となっている。
10. Why Not Smile
ウクレレとピアノ、マリンバによるミニマルな編成。
笑えなくなった人へ、淡く励ますような言葉を送る。
癒しと諦めのあいだにある、祈りにも似た音楽。
11. Daysleeper
シングルカットされた、夜勤労働者(=デイスリーパー)の哀愁を描いた楽曲。
“正常な社会”からこぼれ落ちた存在への共感と、眠れぬ現代人の心象風景が交差する。
12. Diminished / I’m Not Over You
前半は輪唱のような静かなナンバー、後半は隠しトラック的な弾き語りの“自傷的ラブソング”。
感情が壊れ、表現すら迷子になるような、断片的で美しい崩壊の記録。
13. Parakeet
タイトルはインコだが、内容はペットを通じた支配/自由/逃避の寓話。
オルガンとループの重なりが、囚われた希望のような質感を持つ。
14. Falls to Climb
終幕にふさわしい静謐なバラード。
宗教的な語彙と抽象的な詩で、“また昇るべき崖”を描く。
再起する勇気と終わりの受容が、ゆっくりと深く響く。
総評
『Up』は、R.E.M.というバンドが“ドラムの抜けた穴”を埋めるのではなく、その穴に静かに耳を澄ませた作品である。
それは単なる“音楽的方向転換”ではなく、“失ったものをどう受け入れ、そこからどのように美を築くか”という倫理的な問いかけでもある。
多くの曲が内省的かつミニマルな構成でありながら、そこには決して自己陶酔的なナルシシズムではなく、
“曖昧さ”“弱さ”“未完成さ”を肯定する視線がある。
ポスト・ビル・ベリー時代のR.E.M.は、ここで初めて“生き延びる”という作業を音楽として描いたのだ。
リリース当時は賛否を巻き起こし、商業的には前作までほどの成功を収めなかったが、
のちに“静かな傑作”として再評価され、現在ではR.E.M.後期の核心作として語られている。
おすすめアルバム(5枚)
- Radiohead / Kid A
ロックバンドの解体と再構築という意味で、構造的な近似がある。 - Brian Eno / Another Green World
音の間と余白を重んじる美学、アンビエントとポップの融合という点で共振。 - The Beach Boys / Pet Sounds
『At My Most Beautiful』の源泉でもある、ロマンティックな構築美。 - Nick Drake / Pink Moon
繊細で私的な歌が、静かに時代を突き刺すフォークの傑作。 -
Sparklehorse / It’s a Wonderful Life
音響処理と内面性、夢幻と現実の狭間を行き交う世界観が近い。
ビジュアルとアートワーク
アルバムジャケットは、シンプルな“UP”の文字が回転するような視覚処理で構成されている。
上下の判別があいまいで、見る者に“どちらが上か”を問うような意匠。
これは本作のテーマ──喪失と再生、アイデンティティの揺らぎをそのまま視覚化している。
『Up』は、音楽という“日記”の中に、沈黙とやさしさ、傷跡と再起の兆しが交錯する、極めて静かな革命の記録である。


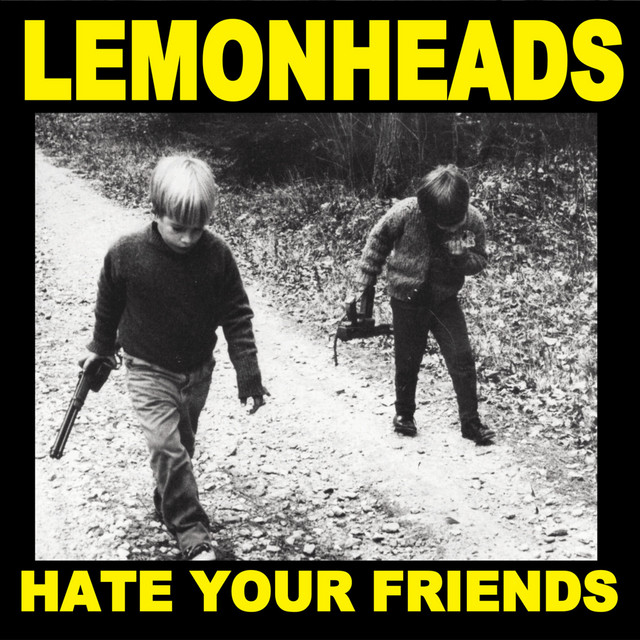

コメント