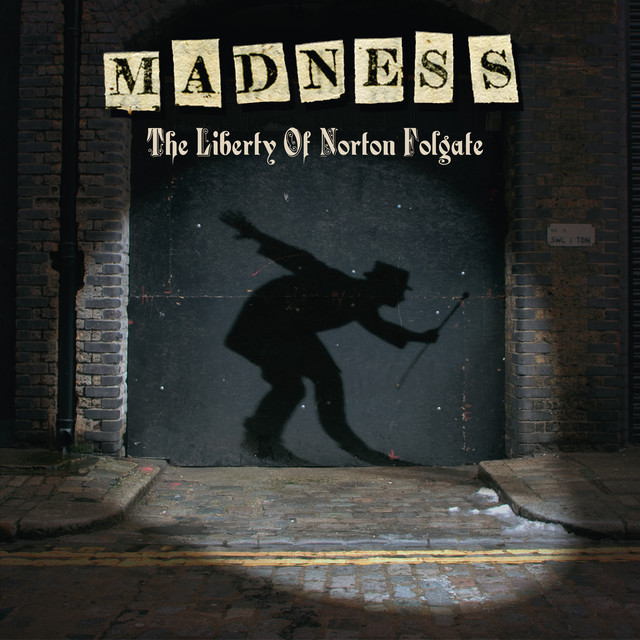
発売日: 2009年5月18日
ジャンル: シアトリカル・ポップ、ブリティッシュ・ポップ、2トーン、音楽ホール、サイケデリック・ポップ
概要
『The Liberty of Norton Folgate』は、Madnessが2009年に発表した通算9作目のスタジオ・アルバムであり、
バンド史上最高傑作のひとつと称される、“ロンドン”そのものを音楽化した叙事詩的作品である。
前作『Wonderful』(1999年)から10年。
バンドは再び7人編成で活動を本格化し、**「音楽ホールと2トーンの精神性を持ったシアトリカル・ポップ・アンサンブル」**として円熟の境地へと突入。
アルバムタイトルにもなっている“Norton Folgate”とは、ロンドン東部スピタルフィールズに実在した、自治特権を有する古い区域の名称。
この歴史と地理に着想を得た本作は、都市の記憶と個人の人生が交錯する、ブリティッシュ・ポップの集大成とも言える大作である。
演奏は精緻かつ多彩。リリックは詩的で映画的。
かつてのスカやコメディのイメージを超えた、“語り部としてのMadness”が最も豊かに開花した作品なのだ。
全曲レビュー
1. Overture
まるでミュージカルの開幕のようなインストゥルメンタル。
アルバム全体のモチーフとなるメロディやリズムが次々と登場し、これから始まる“都市の物語”の序章としての機能を果たす。
スウィングジャズ、スカ、クラシカルなアレンジまでが一堂に会する壮麗なイントロダクション。
2. We Are London
アルバム冒頭の歌ものトラック。
パブロック調のギターリフと力強いコーラスに乗せて、ロンドンの多様性とカオスを讃える。
「俺たちはロンドンなんだ」というメッセージは、排外的ナショナリズムではなく、
“共生する都市”への賛歌として響く。
3. Sugar and Spice
ミッドテンポでメロディアスなポップソング。
青春時代の恋愛とその後を振り返るような歌詞が切なくも美しく、
“時間の流れ”がテーマの中心に据えられている。
ストリングスとピアノの絡みが、感情の起伏を繊細に表現。
4. Forever Young
タイトルの“永遠の若さ”は、皮肉でもあり祈りでもある。
ミディアムテンポのスカ・リズムと美しいメロディに乗せて、年齢を重ねても変わらない“心の若さ”を優しく歌い上げる。
老いと希望の両方を受け入れる、マチュアなメッセージソング。
5. Dust Devil
ダンスビートを取り入れた躍動的な一曲。
“塵の悪魔”というタイトル通り、街をさまよう人間の焦燥感や逃避願望が、パーカッシブなアレンジに表出している。
MVではスーツ姿で踊る男女が印象的で、混沌と秩序の間で揺れる都市民の肖像が浮かび上がる。
6. Rainbows
淡く夢見がちなコード進行と、空想的な歌詞が融合したサイケポップ的トラック。
虹=希望と記憶のメタファーとして使われており、過去に置いてきた色彩を、今ふたたび取り戻そうとするような、優しくも切実な楽曲。
7. That Close
ジャジーな雰囲気の中で、かつて近しかった人との距離感を回想するメロウなポップナンバー。
甘すぎず苦すぎず、まるで英国版のスティーリー・ダンのような円熟のポップセンスが光る。
Suggsの歌唱も物語を語るようなトーンで、ナレーション的な趣がある。
8. MKII
オルガンがリードする、コミカルかつ軽快なナンバー。
MKII(マーク2)とは英国車などの型番で、古き良き時代と今との落差をユーモラスに描く。
笑いながらもどこか寂しい、Madnessらしいノスタルジック・ポップ。
9. On the Town (feat. Rhoda Dakar)
スペシャルズで知られるRhoda Dakarをゲストに迎えた、男女のデュエットが映えるスカ・ナンバー。
リズムは軽やかでも、歌詞は孤独と欲望、すれ違いを描く大人のラブソング。
掛け合いの妙と、メロディの鮮やかさが抜群。
10. Bingo
カジノやビンゴゲームを題材にした、都市の喧騒と退屈のメタファーとしての風刺ソング。
中毒性あるループとブラスアレンジが印象的で、
音楽ホール的ユーモアの現代版といえる内容。
11. Idiot Child
都市に生きる“逸脱した存在”=愚かな子供たちを、憐れみと理解の両方をもって描く社会的バラード。
テンポは遅く、言葉も少なめだが、音の重ね方と間に込められた感情が深い。
Madnessの“観察者としての優しさ”がよく表れている。
12. Africa
マーチのようなビートに乗せて、かつての帝国主義や文化的投影を皮肉る内容。
音楽的にはレゲエやアフロ・ビートへのリスペクトも感じられるが、
それをあえて“白人のイギリス人”が演奏することで、植民地主義とポップカルチャーの交差点を照らしている。
13. The Liberty of Norton Folgate
本作の頂点にして、10分を超える壮大な組曲的タイトルトラック。
ロンドン東部の歴史、移民、階級、多文化性、都市の変化をすべて飲み込むようなスケールで、
Madnessが「ロンドンの語り部」であることを決定的に証明した金字塔的作品である。
バロック・ポップ、スカ、レチタティーヴォ、ミュージカル──すべてを統合したこの曲は、**バンドのキャリア全体を総括する“叙事詩”**といえる。
総評
『The Liberty of Norton Folgate』は、Madnessが“過去”ではなく“今”を語るバンドであることを決定づけたアルバムであり、
かつての2トーンやスカの熱狂からは遠く離れながらも、その精神=庶民への共感と都市生活への洞察はより深く、成熟し、詩的に進化している。
それはただの回顧ではない。
歴史と記憶、哀愁とユーモアをたずさえて歩く、ロンドンという都市の歩行者たちの音楽なのだ。
この作品でMadnessは、もう一度その名の通り“狂気”の街に、優しさと知性をもって帰還した。
そして私たちに、街を、時間を、人々を「語る」という行為の美しさと意味を、改めて思い出させてくれる。
おすすめアルバム(5枚)
-
The Kinks – Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire) (1969)
都市と階級、個人史を描いた英国ポップの古典。Madnessのルーツと並ぶ思想性あり。 -
Blur – Parklife (1994)
ロンドンと庶民の視点から描かれる日常の讃歌。Madnessの後継的傑作。 -
The Divine Comedy – Victory for the Comic Muse (2006)
音楽ホールと文学的叙情を融合した知的ポップ。『Norton Folgate』との構造的親和性が高い。 -
XTC – Apple Venus Volume 1 (1999)
ブリティッシュ・ポップの叙情性と構築美の頂点。同時代的洗練を共有。 -
Ray Davies – Working Man’s Café (2007)
都市の片隅に生きる人々を見つめる視線と、それを支える円熟のポップ感覚。Madnessと同じ道を歩む語り部の作品。


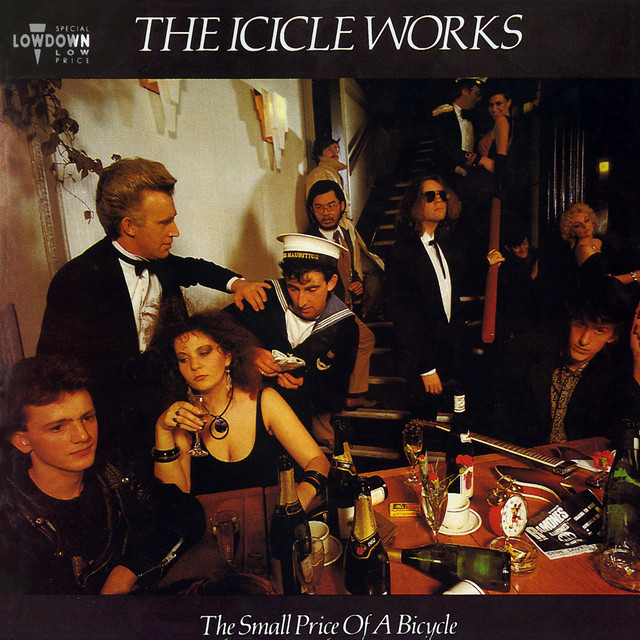
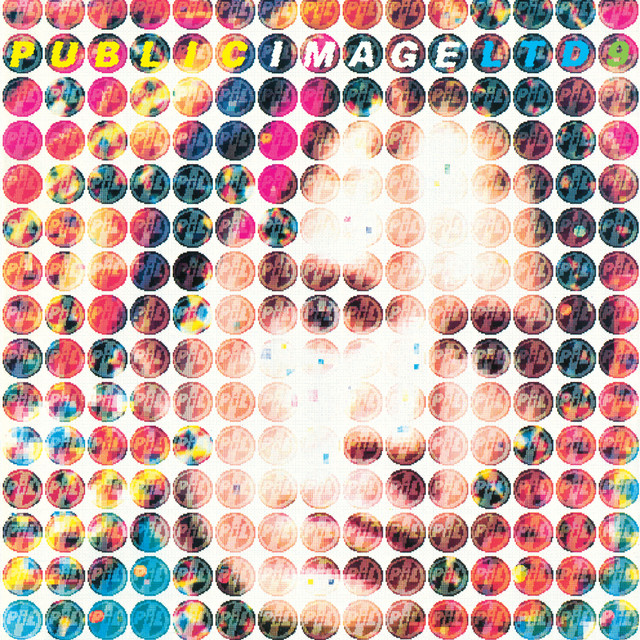
コメント